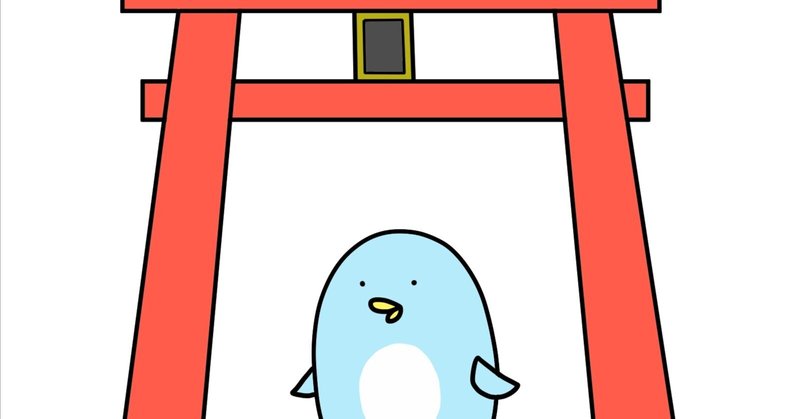
【歴史のない日本伝統11】国家神道(新興宗教)
右翼は低偏差値であったり歴史を知らないのに「日本の伝統が大事だ」とすぐに云う。しかし右翼が強調する伝統や歴史観などウソだらけで伝統性など乏しいものばかりだ。
今回は国家神道の歴史のなさを説明する。
国家神道とは長州(=山口)起源の新興宗教であった。
本来の日本の神道とは自然を崇拝して生活の安寧を願うものであって国家統一イデオロギーではない。
地域ごとに多様な信仰体系が存在していた。
地域の自然環境と人々の生活に根差した緩い多神教だった。政治イデオロギーを国民に押し付けるようなものではなかった。
日本古来の神道をオウム真理教のような天皇真理教にすり替えて
日本を神聖国家と位置付けて国民を威圧して動員して動乱をくり返して多くの人々を戦死させたのが国家神道である。
国家神道のルーツは平田派国学や後期水戸学、津和野派国学など一枚岩とはいえないが幕末の長州のテロ活動(=尊王攘夷運動)によって明治維新後の国家神道の国教化が実現した事は確かである。
国家神道とは新興宗教であってそれまでの日本の歴史には全く連続性がないものである。
1863年(文久3年)7月に長州の神官の青山上総介、天野小太郎、世良孫槌ら5名が「神衹道建白書」を長州藩政府に提出した。神仏を分離して国家と一体になった神衹所の設置を訴えたのだ。
こうして廃仏毀釈運動に繋がる。神道を国家と一体化させた社会革命を目指した。
この革命構想が明治維新後の1869年(明治2年)に天皇家の祭祀を司る神衹宦を太政官の上に置き立法権と行政権の分立を認めないという祭政一致の国家神道原理体制となっていった。
こうして赤松小三郎などが構想していた近代憲法(=天皇象徴制)とは程遠い大日本帝国憲法(=天皇元首制)が国の体制になっていった。
長州藩が押し付けた大日本帝国憲法以前の憲法構想は戦後の日本国憲法に近く伝統に連なっていた。
長州の神官たちによる国家改造計画の最初の具体的活動が1864年(元治元年)5月25日に山口明倫館で斎行された楠公祭(=楠木正成再興)であった。参加者は吉田松陰、村田清風、来原良蔵や無名の庶民であった。16名の長州志士たちが招魂されたのだ。
主に天皇のために死にさえすれば身分の分け隔てなく皆が平等に招魂され神となって祀られるという革新的な新興宗教だった。これが後年の靖国神社と繋がっていく。昭和前半までの大日本帝国の中核テーゼがこれである。
楠公祭は北朝末裔の孝明天皇(121代目)の否定を意図する国家転覆神事だったと云われている。
吉田松陰の過激な意志を継承した楠公主義者たちは北朝体制を根底から否定する国家改造論者になっていったのだ。
楠公祭に扇動された長州家老の福原越後や国司信濃らは京都に進撃をして孝明天皇を拉致しようとした。京都御所を武力で襲撃をして禁門の変を引き起こしている。
京都御所を襲撃して天皇を拉致しようとした連中が天皇を神格化して日本を神国としたのだ。
また招魂という儀式は古来の神道に存在しない。本来の日本の神道にあるのは祟りを恐れる鎮魂だけである。
陰陽道においては招魂という儀式はあったが生きている人間が衰弱した時に生気を回復するものだった。死者の魂を招き寄せるという招魂ではない。
招魂は中国の道教や朝鮮儒教の儀式に存在したものだ。ゆえに長州は排外主義を唱えながら朝鮮と活発に国禁の密貿易を行っており朝鮮文化の影響を強く受けたという説が濃厚である。
南北朝や安土桃山の武将を再興したり神社を新たに創建したり皇国史観をでっちあげたり廃仏毀釈を行い寺社を封じ込めたり武士道という革新概念を流布させたのは日本の歴史に通じるものではなかった。それは他の諸藩出身者を黙らせ長州志士たちの動乱や統治を正統化する事を近代化とするためだった。
(結論)
国家神道は長州藩が普及させた新興宗教である。長州藩が近代日本を構築すると同時に国内の治安を悪化させた。
天皇を中心としたクニづくりとは歴史に通じるものではなく長州神社体制確立でしかなかった。
招魂というのは日本古来の伝統ではなく中国の道教や朝鮮儒教の儀式であった。大日本帝国的な尊王自己犠牲美徳ロジックは1864年の楠公祭に長州志士らによって作られた。現代の新興宗教でもある靖国神社にこの招魂と長州中心主義は継承されている。
■参考文献
『赤松小三郎ともう一つの明治維新』関良基 作品社
学習教材(数百円)に使います。
