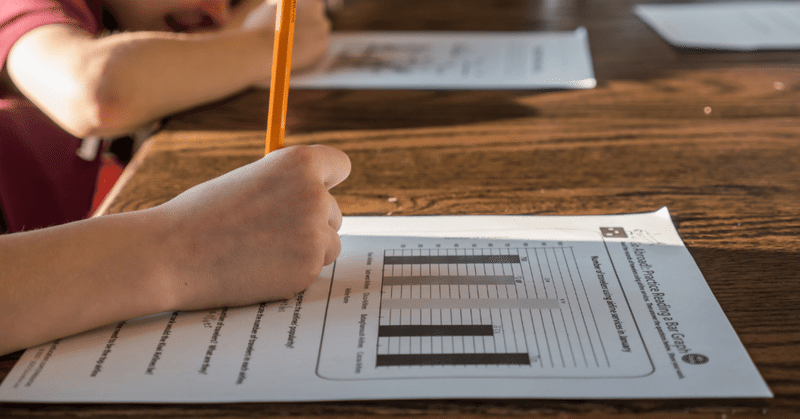
なぜ、ベテランの先生方の授業はあんなに、、、
勉強って、なにが楽しいんですかね?
多分、知識の一般化が楽しいのだと思います。
ある特定の場面にしか使えない知識がありますよね。算数で言うと、「21-7の計算をするときは、まず21を20と1に分けて、20の塊を先に処理することで計算しやすくなるー」といったものです。
社会で言うと、「豊臣秀吉は農民出身にも関わらず関白まで上り詰め、最後は朝鮮半島まで手中に収めようとした。」といったものです。
これらの知識を「転移しない知識」と呼ぶことにします。
逆にあらゆる場面で応用できる知識がありますよね。算数で言うと、「何十何ー何の計算をする時は、まず何十何を何十と何に分けて、何十の塊を先に処理することで計算しやすくなるー」といったものです。
社会で言うと、「身分を何段階か登った人は欲望に限りがなくなり、更にを求める傾向にある」といったものです。
これらの知識を「転移する知識」と呼ぶことにします。
そして、「転移しない知識」が「転移する知識」に変化する瞬間を「知識の一般化」と呼ぶことにします。
この「知識の一般化」が行われたとき、「勉強面白っ!」って感じるのではないかと思うのです。
僕は子供たちに勉強を好きになってほしいという思いがあります。勉強するこそが人生を豊かにし、自分を人生の主人公にしてくれると考えているからです。
ですが僕は、、、面白みのない「転移しない知識」の押し付けに終始してしまってます。これじゃあ子どもが勉強を嫌いになってしまいます。
例えば、今週行った算数の授業。それこそ、「何十何ー何の計算をする時は、まず何十何を何十と何に分けて、何十の塊を先に処理することで計算しやすくなるー」という「転移する知識」の獲得を狙いとする授業でした。
その獲得をするために「21-7の計算をするときは、まず21を20と1に分けて、20の塊を先に処理することで計算しやすくなるー」という「転移しない知識」を教える必要がありました。
これを教えました。ひとまずこの「転移しない知識」の獲得は児童のほとんどができました。
そして、似たような例題「43-9(だったっけ?)」の問題を解くように言いました。すると、半分くらいの児童がさっき教えたやり方で計算を説明できないのです。
子どもの中で、「転移しない知識」が「転移する知識」になっていないのです。つまり一般化が行われていないのです。
僕はこの授業を大反省しました。反省を言語化し、対策も言語化しました。そしてここで洞察が生まれます。
「一般化を促すには、児童がそのやり方の良さに気づくことが必要だ」
「そのためにできる教師の働きかけは、『なぜ?』という質問を生み出すことだ!」
僕はこの反省をもとに授業をしてみました。
🧑🏫「33-7」のやり方を説明してください。
👦「まずは33を30と3に分けます」
🧑🏫「ちょっと待って。ここまでで何か質問ある人いませんか?」
👦「なぜ、30と3に分けたのですか?」
👦「確かに!!別に31と2でもいいのにね!」
🧑🏫「あー。なるほど、、、。この質問に答えられる人いますか?」
👦「30という塊を先に作ることで、計算がしやすくなります。」
🧑🏫「計算しやすくなる?」
👦「30ー7を先にできるから簡単です。あとは、3を足すだけです」
🧑🏫「今言ってくれたことをもう一回言える人ー」
というような流れになりました。
子どもが「なぜ?」と言いたくなるシチュエーションをつくり、そこからこのやり方の良さを考える流れになりました。
このような流れの授業であれば、前よりは知識の一般化が進んだのではないでしょうか。その表出として子どもがとても楽しそうでした。
「楽しいだけの授業じゃダメだ」
よく言われることです。そりゃそうです。わからないとどちらにせよ子どもは勉強を嫌いになります。
ただ楽しさがない、「わかるだけの授業」も同じくらいダメだと思うのです。
学びの深化のためには知識の一般化が必要です。知識の一般化がされた表出として楽しそうな子どもの姿が表れるのではないでしょうか。つまり、知識の一般化が進む授業ができれば、絶対に子供は楽しいはずです。
「わかるだけの授業」というのは「転移しない知識」をただ分かりやすく教えているだけの授業であり、そこからは深い学びは生まれません。何より、、、子どもが勉強が嫌いになってしまいます。
だから、「わかるだけの授業」も「楽しいだけの授業」と同じくらいダメだと思います。
僕はこの二つを行ったり来たりです😢
先生になって3年でようやく気付きました。なぜベテランの先生方の授業を受けている子どもたちがあんなに楽しいそうなのか。
それはギャグが面白いとか、脱線トークが面白いとかそんなことじゃありません。
知識を一般化させる技術に長けているからです。
ふふ。僕の中でもこの記事を通して知識の一般化が行われました。
「A先生の授業を受けている子供は楽しそう」
「B先生の授業を受けている子供は楽しそう」
「C先生の授業を受けている子供は楽しそう」
という個別の「転移しない知識」が、
「面白い授業をする先生は知識を一般化させる技術に長けている」
という「転移する知識」に一般化されました。
だから今すごく楽しいです😊
学ぶって、勉強って、楽しいですね✨✨
余談です。「わかるだけの授業じゃダメ」という話をさっきしましたが、実際中・高では結構仕方ないところもあるような気がするんですよね。
学習内容が膨大すぎるし、一つ一つの知識を深ぼっていたらとても内容を教えきれません。
僕自身高校の時は「転移しない知識」をひたすら詰め込むことをしていました。だから勉強は全く楽しくなかったです。
でも、それらの細々とした「転移しない知識」が今になって「転移する知識」を作るための材料になっています。
だから、賢くなろうと思うなら、面白くないけど「転移しない知識」を詰め込むことは必須になってくるのでしょうね。
ただし、あまりにも「わかるだけの授業」一辺倒でも子どもは勉強自体を嫌いになってしまうというジレンマ、、、。
授業って本当に難しいです、、、💦
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
