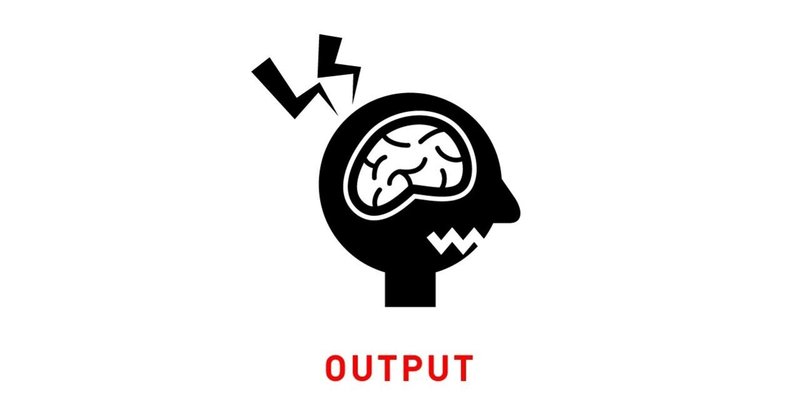
「頭のゴミ」を捨てれば、脳は一瞬で目覚める!
少し前に読んだ本ですが、最近内容を見返す事があったので、ついでにnoteの記事にもしてアウトプットし直しておきます
※こちら質より量・速度を優先して投稿いるので、誤字脱字、回りくどい文章…など、至らぬ点多々あると思いますが、ご了承くださいませm(_ _)m
頭の中モヤモヤしてますか?→しまくってます!
読んだきっかけは、頭の中がモヤモヤしてることが、それなりに多いタイミングだったからです。
というか割とモヤモヤしながら常に過ごしているから…です。
読む前に、どんな内容なのか目次をサラ〜っと見たのですが、割と目標達成のための思考法が書いてある部分があり、「俺のモヤモヤもたしかに目標に向かって何かをしてるつもりなのに、上手く行ってないのが原因にも感じる…」〜という事が読んだ理由にあります。
それでは3つほど気になった部分をピックアップします。
ホメオスタシス
自分の見ている世界は、自分の脳が重要だと判断したものだけで成り立っており、脳は昨日までの自分が重要だと判断していたものを今日も重要だと判断する〜という事らしいです。
そして、安定した状態を保つために、思考的に現状を維持しようとするのは理にかなっており、そうした機能をホメオスタシスと言います。
生体を安定した恒常的状態に保とうとする「恒常性維持機能」 とも言えるらしいです。
「自分を変えたい」「変わりたい」と思っても変われないのは、「変わりたい」と言いながらも、これまでの自分を手放そうとしないからです。
なぜ手放そうとしないかといえば、これまで通り過ごす方が楽で、変えることが本当は面倒くさいからです。つまり現状維持のホメオスタシスが働いているから。
ちなみに、このいつもの自分と変わらない、「ラクでいられる範囲」のことを コンフォート・ゾーン と呼びます。
「変わりたい」と願い、「オレは変われる」といくら口で言っても、すでにできあがっているコンフォート・ゾーンからはずれないように、ホメオスタシスが思考と行動を制限するらしいです。
これ自体への対応策をどうこうする、という事よりも、脳科学的に人間はそういう思考に自然となる〜という事実が、逆に「そう思う事自体は悪いことではなく、自然な事なんだ〜」と捉えられることで、なんだか自分を責めずに楽な気持ちになれました。
エフィカシー
自分の能力に対する自己評価のことを「エフィカシー」と言います。
「自分には行動力と発想力がある!」という高いエフィカシーを持つのと、「自分には行動力も発想力もない」という低いエフィカシーを持つのとでは、実際には同じ能力でも、パフォーマンスに大きな差が出てしまいます。
頭のモヤモヤは、言語でできているらしく、自分自身も、自分に対して日々、刷り込みを行ない、モヤモヤを量産しているらしいです。
私たちは 1 日におよそ100回、自分を定義する言葉を口にしたり、心の中で発したりしていると言われています。「オレは人見知りだからなあ」「オレは口下手だからなあ」「オレは体力ないもんなあ」「アタシはおおざっぱな性格だから」…といった具合に。
ただ、失敗体験を何度も思い出したり、上手くいかなかった理由に「どーせ俺は…」と考えるネガティブ思考は全く価値がないので、絶対にしないほうが良いらしいです。
失敗したときに、「しまった!」「最悪!」「自分がダメだから失敗したんだ」と思わず、ただ「自分らしくないな」と思えばいいらしいです。
自分の評価を下げる相手は自分自身で、ネガティブな自己対話が、自分の頭のゴミを増やし、自分の夢を潰すことになるそうです。
よく自分も駄目な部分を把握しておらず、それが仕事上の評価を下げる原因となり、反省したりすることがあります。
ただ、それを理解反省し、修正していく〜の流れは正解ですが、それ以上のネガティブ感情はさっさと捨てていくことで、エフィカシーを高く保つようにやっていこうと思います。
ゴールは必ず現状の外に設定
自分がラクでいられる範囲「コンフォート・ゾーン」という話を先に出しましたが、なにか目標を設定するときはコンフォート・ゾーンの外にゴールを設置する事が重要になってきます。
というか、自己成長のために何かに励むとしたら、自然とそういう事なっていくのだと思います。
ゴールをコンフォート・ゾーンから外して設定すると、「本来あるべき姿」と「今の自分」にギャップが生まれてきます。
例えば俳優を目指す会社員がいたとします。
「俳優として活躍している自分」のイメージの臨場感が強くなると、我慢しながら会社員をしている自分という物理的現実世界との間にギャップが生まれます。これを「認知的不協和」と呼びます。自分は映画の撮影現場にいるはずなのに、会社でパソコンを叩いているなら、脳はその認知的不協和を解消しようと働きはじめます
脳は臨場感が高い方を「現実の自分」として選び、その自分に合わせてコンフォート・ゾーンが移動し始めるらしいのです。
ゴール設定
↓
高い臨場感で新しいコンフォート・ゾーンをイメージ
↓
ホメオスタシスが変化
↓
現状のコンフォート・ゾーンに代わり、新しいコンフォート・ゾーンがホメオスタシスに選ばれる
自然とゴールへ向かう思考へなっていく〜の流れです。
ゴールに対しての高い臨場感を持つことが、重要になってきます。
高い臨場感にはエフィカシーの存在が重要です。「どうせ俺は…」と思っているうちは臨場感をイメージ出来ません。
よく自分も何かを頑張っている時に、途中でエフィカシーが低くなり、「まぁ俺には荷が重い目標だったか…」なんて思いはじめ、途中で終わる、、、もしくは三日坊主ではないけど、「上手くいかなくて、モチベーションが保てず辞めた…」なんて結果になることがあります。
エフィカシーを保って、ゴールに対して高い臨場感を持つ!
忘れずに毎日を過ごしたいですし、周りの人が挫折しそうになっていたら、エフィカシーを高く持ってもらえるような助言なんかできると良いのだろうな〜と思いました。
…他にも色々書いてある本ですが、「ホメオスタシス」「コンフォート・ゾーン」「エフィカシー」という横文字3つの関係性が記憶には焼き付いています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
