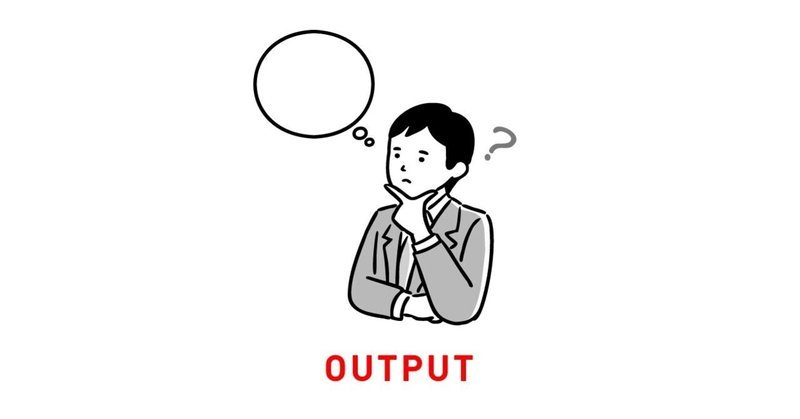
問題解決能力を高めたい @Schoo
先日も似たような記事を書きましたが、今年は問題解決能力に注力しております。瞬発思考という本を読んだのがそのきっかけです。いつもお世話になっているSchooの授業で「朝Schoo」という出社前に見てもらう事を前提にしたものがあり、7月が問題解決特集だったので、ざっと4回分を見てみました。その中での気づきをアウトプットします。
※こちら質より量・速度を優先しているので、誤字脱字、回りくどい文章…など、至らぬ点多々あると思いますが、ご了承くださいませm(_ _)m
朝Schooはこちら
瞬発思考に組み込めそうなものと、そうでないもの
色々同時には行えないので、今練習中の瞬発思考に組み合わせて活用できるものをピックアップしたいな〜と思って受講をしまいた。
瞬発思考についての記事はこちら
全4回のうち、前半の2回井尻 淳先生の授業は割とベーシックな問題解決思考についての内容だったので、結構嬉役立ちそうでした。
・【実践】問題解決の思考:前編「問題の分析」
・【実践】問題解決の思考:後編「解決策の立案」
後半の2回は少し方向性が違う問題解決思考だったので、ちょっと流して見てしまいました。。。
・問題解決の「企画脳」的アプローチ
・生産性を向上させる問題解決
問題解決のプロセス・ポイントは大体同じ
以前記事にした瞬発思考でも、今回のSchooで受けた井尻 淳先生の【実践】問題解決思考でも、概ねのプロセスやポイントは同じでした。
まず大事なのはとにかく問題に対して、経験・知識などで解決策を当てはめてはいけない。まずはフラットに分析するという事。
当てはめ思考、HOW思考などというやつですね。
そして問題の状況把握→分析→対策という順序を必ず守るという事。
また問題自体を見直す事も必要であればする。
実は別の問題が引き金になっているケースもあるので
現状把握・原因解明パートの深堀り
瞬発思考では現状把握・問題定義・原因究明というパートが、今回Schooの授業では大きく「分析」というパートにまとまっていました。
分析パートでは、主にロジックツリーを利用して問題を分析していきます。ただ、そのスタートはまずは2つのカテゴリーにザックリ分けて展開するというもので、そこまで難しい事を実践するという印象は受けませんでした。ただ、とどのつまりロジカルシンキングのMECEを活用するに近いので、切り口が重要になり、意外と求められているもののハードルは高いのかもな…と感じました。
例:体重増加問題=接種・代謝にまずは分類
現状把握で細かな課題、キーワードを拾い、それをロジックツリーに当てはめていくという形で瞬発思考の原因究明パートで役立てそうでした。
対策はいくつか出た案から選択
瞬発思考側で若干曖昧に感じたのは対策についての説明でした。問題に対しての対策は当然ですがいくつか出てくるものがあります。これについての説明が瞬発思考ではあまりされていない印象がありました。
対して井尻 淳先生のSchoo授業では、その中で出た対策案をマトリクスにあてはめて、選定するというパートがありました。
「やりやすさ・効果の高さ」の2軸で考える形です。
丁寧にやる=時間がかかる
瞬発思考と今回Schooで受けた井尻 淳先生の授業を比べて思ったのは、どれだけ丁寧にやるか〜の差です。
井尻 淳先生のフローでは、丁寧にやると、原因究明・分析でロジックツリー、対策の立案にロジックツリー、対策案の決定にマトリクス〜と、パートごとにフレームワークを使用します。瞬発思考側ではフレームワークに溺れないように、あえてそういう型にはめる形にはしていません。
仕事で活かすようにするには正確性も大事ですが、スピード感も必要です。細かい問題に対しては即座に対策を打ってしまえばいいですが、それ以上の少し考察が必要なものに対して、どの程度丁寧に行うかが懸案かな…と思いました。
思考に慣れてくれば精度もスピードも上がりますが、慣れないうちはどちらを優先して実行するか悩みます。
ただ、どちらかというと質より量を優先してPDCAの回転を上げる。速度を優先する方が有効〜という事を、最近受けたSchooの講義や、本などでは書かれてる傾向があるので、とりあえず丁寧さよりも速度感を持って取り組んでいこうと思います。
井尻 淳先生の授業・キーワードあれこれ
その他気になった所、キーワードになったのは以下の点です。
●早く解決したいからさっさと対策を打ってはいけない(思いつきでコレだ!とか)
●考えたくない、楽したいから、ネットや本の情報をそのまま実行してしまう
●対策を打ってる状態への安心・満足感だけで、目的を見失ってはいけない
●とにかく最初は問題の内容をザックリ切り分ける
分けるは解る〜というロジカルシンキング的思考
●細かい問題をどんどんピックアップするのも間違いではないが、それは思考的には逆順になるので、まずは順序どおりに考える
●とりあえず対策を打ってることに満足して、実際に効果の高いものなのか〜という有効性の検証を見失ってないか
●対策の吟味で終わってしまわないように
第3・4回の内容
ちょっと流してみてしまったので、雑ですが印象に残った点を羅列します。
第三回 問題解決の「企画脳」的アプローチ
この授業は問題を解決するというよりも、アイデアを形にするうえでの課題解決をどうするか〜というものでした。
深刻な顔で問題解決はできない
イヤイヤ取り組んでも、なかなか問題解決しずらい。
本音で取り組めるかどうかが重要。
第四回 生産性を向上させる問題解決
生産性を高める=いかにスムーズに仕事進めるかという内容でした。
生産性を高める方法
・仕事を減らす
・効率を高める
この2つしか方法はない
でも効率性をあげるのは結構難しい。
なので、仕事を減らす!に注力する。
…売上アップよりも経費削減の方が確実で手っ取り早いに近い印象ですね。
4つの軸を元に減らすを検討
取り除く・結合する・順序を変更する・簡素化する
毎度雑ですが、今回はこんな感じです。
問題解決能力、、、自分に対しても(メンタル弱いんで…)、仕事に対しても高めたいです!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
