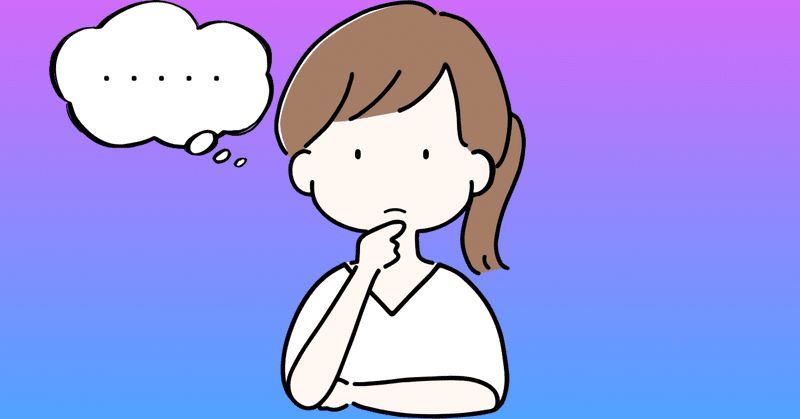
「できると信じる」は、使い方に注意が必要かもしれない
「できる」と信じて進むことは大事なこと。
だけど、この言葉は注意が必要。
「できると信じる」と言ってしまうと、微妙に意味が違ってくると思う。
まあ、この言葉を使う人・聞く人によって、その意味が変わることも大いにあると思うけれど。
本当は、「できると信じたい」と思ってはいない? と聞いてみたくなることがある。
「できると信じよう」でも同じ。
「信じたい」も「信じよう」も、実はその時点では「信じきれていない」ということだから。信じているなら、この言葉は遣う必要がない。
(相手に対して自分の気持ちを伝える場合は別の話で)
もしかしたら、どこかで聞いたフレーズをそのまま受け止めて同じように使っているだけかもしれないけれど。
或いは、難しい局面にあって、それに立ち向かうため気持ちを強く持つために、敢えて使っているのかもしれないけれど。
自分の望みを「できると信じる」と何度も繰り返したら、「信じきれていない」状態が深く心に刻まれてしまうのでは? と思ってしまうのだ。
そして自分の気持ちにちゃんと添っている言葉か?
” 信じる ” を省いて「できる」と繰り返しても、気持ちと言葉の間に距離があったら、実現までに時間がかかってしまわないか?
例えば、周りを気にして咄嗟に言っただけだったり、本心では「できればいいなと思うけれど、自分にはそこまでは無理なんじゃ?」と思っていたりということはない? と聞いてみたい。
一方で、まだ方法はわからないけれど、望む方向へ進んでいきたいという場合に、「少しずつでもできそうなこと・効果のありそうなことをやっていく」と言葉にすることは、気持ちを整えていく助けにもなるのではないかと思う。
言霊という言葉があるように、一つ一つの言葉には深い意味と大きな力があると思っている。
だから、意味やニュアンスといったものは、きちんと使い分けたいとも、その力を借りたいとも思うのだ。
***
少し前、ある計画を練っていた頃に。
それは期限が決まっていたのに、あまりにも事が進まず『これは間に合わないかもしれない』という事態に陥った。
思えば、初めに作業の段取りを考えていた時点で読みが甘かった。
そのことに気づかないまま、最初の作業があまりにもスムーズに進んだ為、慢心し、油断してしまった。
更に、途中でこの方向で本当にいいのかと迷いまでも生じてしまい、しばらく作業が止まった。
その後、初めに考えていた時より必要な作業がいくつもあることに気づき、それぞれかなりの時間がかかることもわかった。
それまで作業していたことと、この後必要な作業を比べて、寒気がした。
『じゃあ、諦める?』とどこかから聞こえた気がした。
「嫌だ!」と脳内で強く反応した。
駄駄をこねる子どものようだったけれど。
その途端、諦めるという選択肢は、私の中から消えた。
それ以降、進捗状況を確認するなどは最小限に留め、作業することに集中した。この状況でどう進めるか、何が必要かを考えた。
不思議なことに、間に合わないかもと再び感じることはなかった。
ここは諦める、代わりにこちらに重点を置く、など代替案 (?) を自分でも驚くほどあれこれ思いついた。
結果、なんとか期限までに間に合わせることができた。
数々の問題点が残ったままではあったけれど、ともかくできるだけのことはしたし、何より「諦めなかった」という事実が私には大きかった。
だからといって、意志の力で迷いをねじ伏せた、なんて感じは全くしない。
諦めたくないと強く意識したことで、望む気持ちに対して、( それを打ち消そうとする ) 何かが反論することを止めたような感じだった。
「本当はどうしたいのか?」と私の迷いを見透かして、どちらに決めるかを見定めるため待っていて、定まった後には、あちこちに散らばったエネルギーを集め、手伝ってくれた、そんな気がした。
一部の人を除いて、ほとんどの人は迷ったり試行錯誤しながら進んでいくものだろうと思う。
だから常にいくつかの選択肢を念頭に置きながら進むのではないかと。
それぞれの段階で選択肢の中から一つを選び、次の段階でまた選択を繰り返すのだと。
やりたいことを決めるも良し、嫌なことをやめるも良し、どちらの方向であれ、見定めて、言葉をそれに添わせ続けることが「できる」への「初めの一歩」になるのかもしれない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

