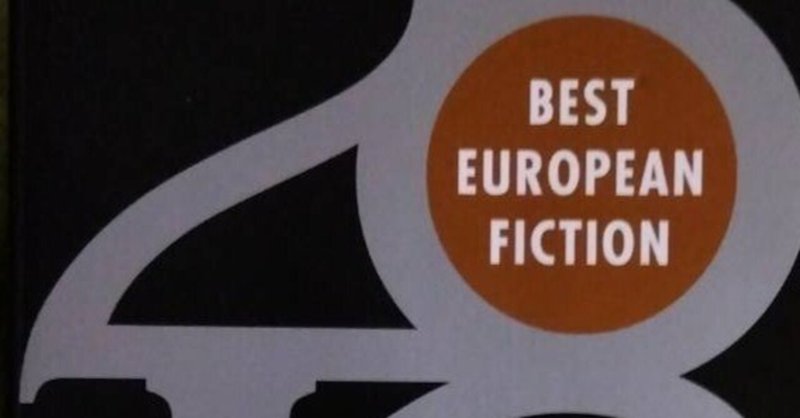
リトアニア文学:イエヴァ・トレイキーテ
今回紹介するのは、"Best European Fiction 2013"に収録されている短篇である。出版はドーキー・アーカイブ社、現代マケドニア短編小説コレクションを出した出版社としておなじみである。2010年から2019年まで続いたこのアンソロジーは、その年のヨーロッパ各国から生み出された選りすぐりの短編が英訳されて集められている。ヨーロッパ文学の今を知ることができ、外国文学好きには垂涎ものである。文字通りヨーロッパ各国、アルバニアやマケドニア、クロアチア、ボスニアなどバルカン諸国や、北欧に中欧、アルメニアやジョージアなどコーカサスも含むばかりか、嬉しいのはリヒテンシュタインという超小国の文学まで扱っているところである。このアンソロジーに出会うまでリヒテンシュタイン文学なんて聞いたことがなかった。どうしても大国文学に押されがちな小国文学を、余すところなく汲み取ろうとする強い意志と大いなる寛大さが伝わってくる。こんなアンソロジー、滅多にないので非常に貴重だが、2019年で途絶えてしまっているのが遺憾でならない。日本の片隅から復刊を切に望んでいる。
ドーキー・アーカイブ社に対しては称賛と感謝の言葉が尽きないが、さて賛辞はこれくらいにして、紹介に移るとしよう。
リトアニア出身の作家イエヴァ・トレイキーテ Ieva Toleikytė は1989年生まれの若手作家である。デンマーク語の翻訳家でもあり、北欧研究を専門とし、かつてヴィリニュス大学でデンマーク語と北欧文学、文学理論を教えていた。作家としてデビューしたのは20歳の頃、作品は"Mustard House"という短編小説集であった。
"Best European Fiction 2013"に収められている彼女の短編、”The Eye of the Maples” (2011年) は透き通っていて悲しく、美しい。「楓の眼」とは、なんとも不思議なタイトルである。
どこか民話のようで、この作品を読んでいると自分が幼少期に世界の民話を探求していたころの記憶がよみがえる。幻想的な情景が絵画のように立ち現れてくるのが、この物語の魅力だと思う。
この短篇のテーマとなるのは、「クレイヴィン病」という肌が青くなる架空の病である。この病に侵された子供たちのための治療所で過ごした短い日々を、大人になった主人公カスパラスは回想する。
少年だった頃のカスパラスが3週間だけ過ごした、町の外れにある豊かな自然に囲まれた美しい治療所、そこで出会った子供たち、彼らと交わした言葉、奇妙で謎めいたしきたり―これらが作者の美しく静かな筆致によって織りなされている。
カスパラスが治療所に来たのは9歳になる前だった。そこには39人のほぼ同じ年頃の子供たちが暮らしていた。その中で11歳のブロンドの少女だけは、何事にも動じず無関心でいるので、カスパラスは彼女に話しかけた。すると彼女は「楓の眼」の話をしてくれたのだ。
ある日僕は彼女に、どうして何も恐れないのかと尋ねてみた。
彼女は言った。「楓の眼に入ったことがあるから。それ以来なにも怖くないの」
・・・
「君が僕をそこに連れて行ってくれるのかな?」
「私が?いいえ、できないわ。リーダーが連れて行ってくれるわ、あなたが行けると彼が判断したらね。でもその時にはもう行きたくなくなるでしょうね」
「きっと行きたくなるよ!」僕は彼女に自分が臆病者だと思わせてはおけなかった。
「みんなそう言うのよ」
この謎めいた非日常のような実態が、少しずつ分かりかけてくる。どうやらリーダーと呼ばれる14歳の少年が、夜中になると子供たちを引き連れて森に行くそうだ。カスパラスが来た最初の夜、ルームメイトが足音を殺して部屋を出て行く気配を感じたことで、そう察せられた。目を開けて待っていると、戻ってきた彼と眼があった。彼は体をぶるぶる震わせ、顔は蒼白だった。
ついにカスパラスは「楓の眼」に対面する時を得た。
満天の星空の下、淡い月明かりのなか深く黒い森をひたすら進む。黄色い楓の樹々に囲まれていたのは、黒々とした水―それは湖でもなく池でもない―「眼」としか形容できないものだった。
カスパラスはリーダーに命じられる。この中に飛び込み、「眼」の底にある砂を取ってこい、と。
とっさに彼は恐怖に囚われる。きっと寒いだろうし、どれくらい深いか分からないから溺れるかもしれない。だがリーダーは容赦せず、カスパラスは意を決して飛び込む。「眼」は思ったよりかなり深く、まるで底なしだった。どれだけ行っても底に手がつかず、息がだんだん苦しくなり死の恐怖が彼をとらえる。
彼は息継ぎをするためやっと水面に出た。本当は底なんて無いのに、リーダーは騙したのかもしれない―彼はリーダーに怒りをぶつけるが、リーダーはそっけなく言い放つ。「一晩に、一人が飛び込むんだ」。
***
治療所では薬として、紅茶のような色をした飲み物が一日に3回与えられていた。だが親友のルームメイトはあるとき、大興奮しながらカスパラスに打ち明けた。薬と言って出される茶色い飲み物は、本当は「楓の眼」の水で、薬などではないのだと。僕たちは騙されていたんだ!彼らは窒息しそうになるほど笑い転げる。
騒いだ罰として、親友は「眼」に入るようリーダーに命じられた。カスパラスはリーダーにやめさせるよう叫びたかった。だがもし逆らえば、自分が飛び込まなければならないかもしれない。それは苦しいし、怖い。おぼれて死ぬかもしれない。親友を助けたい気持ちと臆病、無力感がせめぎ合う。
結局、親友はカスパラスにさよならを告げ、「眼」に飛び込んだ。1秒、2秒と時間を数えるが、5分経っても彼は上がってこなかった。もう戻ってくることはないだろうと観念した他の子どもたちは、そろそろと部屋に帰っていった。親友を失った怒りで泣き叫ぶカスパラスをただ一人残して。
翌日の朝、カスパラスが目を覚まして窓の外を見ると、昨日まではなかった場所に楓の樹木があり、その枝には親友が裸で座っていた。「「眼」の底には岩しかないんだ!」と言ってカスパラスに無邪気に笑いかけていた。彼の肌は真っ白で、青い斑点が一つ残らず消えていた。彼だけでなくすべての子供たちの肌から青い斑点が消えていた。子供たちの親は、奇跡が起きたのだと涙した。
治療所で過ごした日から何年経っても、その頃の思い出が鮮明に思い出される。だがそれはあまりにも夢のようで、そんな出来事は本当にあったのだろうかと思うときもある。
夜中の2時になるとふと目が覚める。まるで「楓の眼」に招かれているかのように。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
