
アルバニア人ディアスポラによる、フィンランド語で書かれたアルバニアBL文学
My Cat Yugoslavia Pajtim Statovci
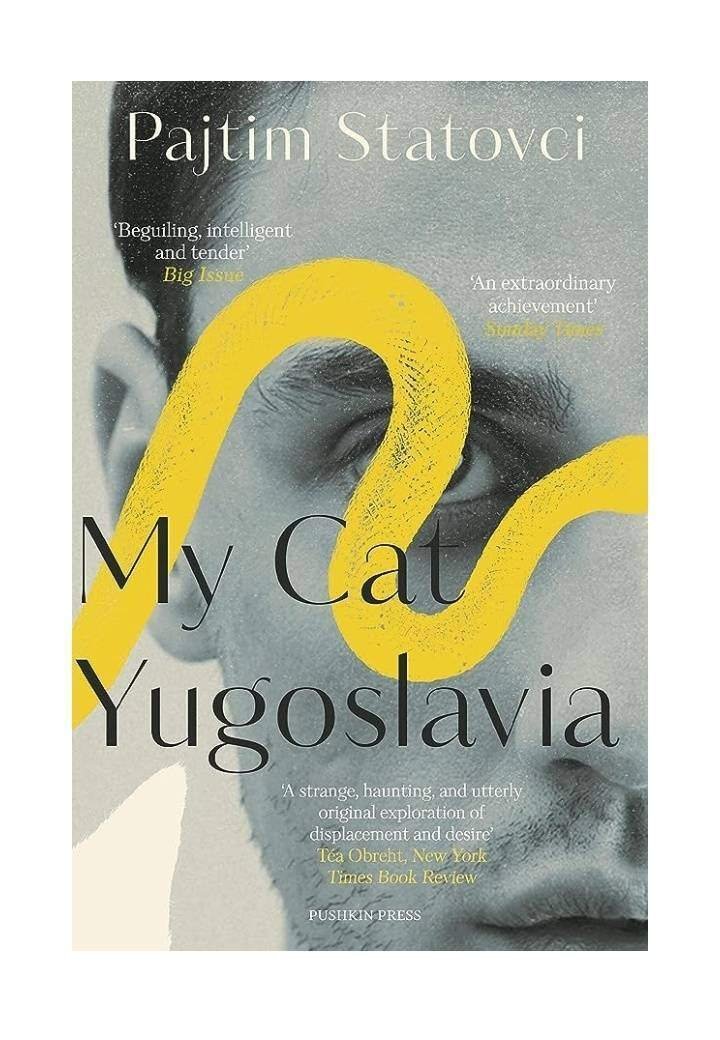
My Cat Yugoslavia(原題:Kissani Jugoslavia)は、コソヴォ出身のアルバニア人作家、パイティム・スタトヴツィ(Pajtim Statovci)による処女作である(2014年刊行)。アルバニア人の両親のもと1990年に生まれた著者は、2歳のときにボスニア紛争が勃発したおり一家でフィンランドに逃れた。スタトヴツィの作品はこれまでに3作を数え、どれもフィンランド語で執筆されている。当作の翻訳は今のところ英訳のみで、2017年に出版された。日本ではおそらくまったく知られていない作家である。
この作品は著者のそうしたこれまでの経緯をなぞるような、自伝的な内容となっている。主人公のゲイの青年ベキムと、彼の母親エミネの物語が交互に語られてゆく。故郷を追われ、移民として生きることの二重の苦しみが痛切に描かれている。彼らは差別や偏見に苦しめられるだけでなく、それが次第に内面化して自身に向かう矢となり、いつも誰かに責められるのではないか、何か突然の事故に巻き込まれるのではないかと、神経症的な強迫観念に自分を追い込んでしまう。
読み進めていくと、登場人物が抱く暗澹たる濃霧のような閉塞感が伝わってくる。暗闇のどこに手を伸ばしても何もつかめず、どこにも進むことができないかのような、現状を打破するいっさいの選択肢が奪われ、なす術もなくぬかるみのような現状にとどまっているしかないという、もどかしい無力感と気怠い諦念に支配されていく。
母親エミネの物語は1980年代から始まっている。当時のコソヴォ・アルバニアに蔓延る男性優位な社会に生きる息苦しさを、17歳の彼女は絶望とともに感じている。エミネはある時、女性が教育を受けるのは家庭を築くためであって、能力を身に着け自立するためではないことに気づいてしまう。この状況が1980年代の話だということが信じられず、私はこの事実を何度も確認しなければならなかった。
最初の場所として私が学校に行ったのは、教育を受けていない女性はきちんとした夫と結婚できないからだというただ一つの理由を知ってしまうと、胆汁が喉の奥からせりあがってきて、食べ物の味がもう何もしなくなった。全科目で一番の成績を取らない限り、自分の人生は何の変哲もないものになるだろうと気付くと、私は吐き気をもよおし始めた。女性の政治家も、女性の教師も弁護士もこれまで一人だって聞いたことがない。私はテーブルの端をぎゅっと掴み、深い息を鼻から吐いた。私は頭を振り、夢の代わりに何が望めるだろうか考え始めた。そして私は未来の夫が私に良くしてくれることを望んだ。彼がハンサムで、誰も見たことのない一番立派で素敵な結婚式を開催してくれることを望んだ。彼の家族が、彼が私に対するのと同じように私を扱ってくれることを望んだ。そうしてこの願い事のリストを頭の中に描き終えてしまうと、キッチンに飛びこんでボウルを掴み、嘔吐した。
こうした絶望感は、自国への憎悪となって膨れ上がっていく。舗装されていない道路に悪態をつく父親に対し、彼女は「アルバニア人が作ったからでしょ」と、憎しみをにじませながら答えるのだ。
彼女は伝統的なしきたりに習って17歳で結婚することになるが、ここでもまた、アルバニア人女性を縛るマチズモが、結婚前夜の猫殺しという残酷な風習の恐ろしい描写によって不気味さを増している。
ついに母はエミネに軽い平手打ちをぴしゃりと食らわすと、あなたは自分がどんなに幸運かわかっていない、と言った。10数年前は、伝統的な結婚式では言葉にできないくらい残酷な儀式がたくさんあったんだから、と。
「例えばどんな?」と娘が訊いた。
式の一週間前、村人たちは猫を罠でとらえる。彼らは猫を閉じ込め、待つのだ。娘の母親はまるでこれが説明の必要がない細かいことでもあるかのようについでに触れたのだが、彼女は娘にどんな不測の事態にも備えてほしかったから、地域によっては婚姻の夜に新郎が猫を花嫁のもとに持っていき、妻に対する支配権を見せつけ自分を恐れるよう告げるためにそれを素手で殺すのだと教えた。
* * *
この小説の注目すべき点は、女性・男性の両面から、偏りなく男性性について語られるところだ。そこにクィアの視点が付けくわえられている。BLファンにとっても見逃せない!
フィンランドの大学に通うベキムは、ナイトクラブでCatと呼ばれる男と出会い、同棲するようになる。この男は猫として描かれており、名前は明かされず、ずっとCatと呼ばれている。かなりな美青年(というか美猫)で、その登場シーンたるやなんとも妖艶。Catに誘惑されたベキムは彼に近づくのだが、Catは「君なんか知らないよ」とつれない態度を取り、ベキムがまごつくと、彼は冗談だと言って大笑いをする。まったくニクイやつだ。こいつ、ベキムの名前を馬鹿にしたり、ベキムが移民としていつもおびえながら生きていると打ち明けると笑いを爆発させたりと、かなり失礼なヤツなのだ。そうかと思いきや、彼はベキムに「今まで誰にも話していないことを教えろよ」と言ってベキムの生い立ちを真剣に聴くこともするし、ゲイに対して偏見があるようなことを言いながらも「男は好きだがゲイは嫌いだ」と吐き捨てる場面で、以前ゲイに物のように扱われたという苦い経験があったことがわかってくる。Catは猫みたいにわがままで、そこら中散らかすし掃除はしないしベキムに対してやたらと高慢ちきな命令口調で、ちょっとジルベールみたいなのだ。
Catの移民に対する偏見は根強い。ベキムは偏見をかわすために自分の生い立ちを偽るが、それが結果的にCatによって嘘つきのレッテルを貼られてしまうのは、なんとも悲しい。憎しみの言葉が飛び交い、ときには殺意さえ抱いて互いを痛めつけながら激しい口論をする、緊張をはらんだ愛憎混じる関係が、こちらをハラハラさせずにはおかない。
この小説では猫と蛇がシンボリズムのように現れる。蛇はベキムのペットとして彼と孤独を共有している。ペットショップのじめじめした地下室の、人工的な環境のなかで人間の利益のためだけに生かされている虚ろな蛇たち―おそらく太陽の光と自然の大地を知らずに死んでいくであろう―に彼は自身の境遇を重ね、共感のまなざしを注ぐ。べキムは蛇をアパートの部屋に迎え入れ、檻のようなテラリウムから蛇を開放し、自由に部屋のなかを動けるようにしてやる。
蛇はベキムにとっては共同生活を送る仲間でもありながら、男性性の桎梏を象徴する存在でもあるように思う。
暴力的で強権的な父親からの抑圧は、蛇に襲われる悪夢となって幼少期のベキムを苦しめた。父親とは絶縁するように家を出てきたベキムは、和解なくして父の死に目に会う。父親の死さえ望んでいた彼は、父の亡き後に記憶と愛情が渦となって押し寄せ、矛盾した感情に苦悩する。ベキムの体にまといついて離れないペットの蛇を真っ二つに切り刻むのは、憎しみと怒りの囚われから自らを解放し、次に進むためのメタファーではないか。そうして彼はやっと、これまで誰にも話してこなかった父のことを、恋人に向かって語り始めるのである。
著者は、故郷への憧憬や懐かしさはいっさい語らず、一人、また一人と離散する家族の様子と過酷な現実を淡々と語る。
父親がコソヴォへ帰るための費用を捻出するため犯罪に手を染め始めると、家庭は徐々に崩壊していく。ついにはエミネも夫から離れると、一人取り残された父は絶望のなか自らの頭に弾丸を込め、孤独な死を遂げる。異国の地で引き裂かれる家族の姿が、切ない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
