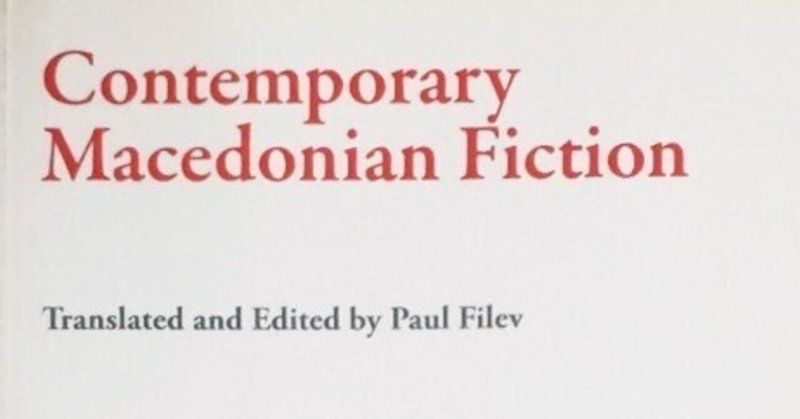
現代マケドニア短編小説 : ルメナ・ブジャロフスカ
バルカンの小村を舞台にした小説には、荒涼として黒い靄のかかったような、いわく言い難い不気味な薄暗さがあると私は感じているのだが、この作品もまたそうした印象を抱いたものの一つである。
ルメナ・ブジャロフスカの”Lilly”は、リリーという小さな女の子が不慮の事故によって亡くなり、その隠された死因によって徐々に家庭が崩壊していくさまを描いた物語である。
リリーは風変わりな外見をしていた。眉毛が眉間でほとんどつながり、肌は浅黒く、虚弱だった。お世辞にも可愛いと言えるような風貌ではなく、男の子だとよく間違えられた。歩き始めるのは遅かったが歩き方は幽霊のようで、ほとんど話さず、笑うこともなかった。
不吉ともいえるリリーの様子に死の予感を添えるのは、祖母の存在である。のちにリリーを襲う不幸を予知するかのように、病気で寝たきりになった祖母の影が死神のように彼女に付いて回る。リリーはその外見から男の子だと間違われることがあったから、母親は祖母から譲り受けたイヤリングをリリーの耳につけていた。祖母の家はいつも饐えた匂い、死のにおいが充満していた。半ば死の世界に身を横たえているような祖母を夫は気味悪がった。そのため祖母と夫は仲が悪かった。
ある日、母親はリリーを連れてアイバル(バルカン諸国の調味料で、赤パプリカをベースとした野菜のペースト)を祖母に届けに行った。(バルカン諸国では各家庭ごとにアイバルを作る習わしがあるそうだ)夫は祖母の家に行くのにいい顔はしなかったから、祖母を訪問するのは夫が仕事に出かけているときでないと駄目だった。母親は重い瓶をいくつもバッグに入れて電車に乗り込んだ。駅に着いて彼女が棚から荷物を降ろそうとすると、電車が急に動いたせいで荷物が転がり落ち、バッグから出た瓶がリリーの頭に当たってしまった。リリーは倒れ、割れた瓶からはアイバルの赤い汁がにじみ出した。意識が虚ろになったリリーを必死に抱えて祖母の家に向かうと、祖母はいびきをかいて寝ていた。
祖母に届けることがなかったらこんなことにはならなかった。早く死んでくれればいいのに。どす黒い憎悪が湧いた。母親は瓶だけをテーブルに置くと、一目散に電車に飛び乗り家路についた。半狂乱になった彼女は友人宅に行き、事の顛末を泣きながら話した。友人はリリーを病院に連れて行った方がいいと助言したが、今日の事件が夫に知られてはただでは済まないと、母親は拒否した。もし知られたら、自分は夫に殺される、と。
その夜、リリーは亡くなった。
リリーの死因が自分にあると、母親はおそらく自分を責めもしただろう。こんなに荷物を抱えて電車に乗り込まなければ、瓶が頭に当たって死ぬことはなかったかもしれない。一人で無理に行こうとしたからこうなってしまった。だが自力で誰の助けも借りずに行かなければならなかったのは、彼女だけの責任ではないだろう。
一人で行かなければならなかったのは、祖母が貧困と死の象徴でもあるかのように夫が忌み嫌い、妻が祖母のもとに行くことさえ許さなかったために、夫の協力を仰げなかったから。では彼女は友人と行けばよかったではないか?もし知り合いと行ったなら、こんな小村だからどんな小さなことでも噂になって広まり、夫の耳に入るかもしれない。だから彼女は誰も頼ることができなかったのだ。
殺伐とした行き場のなさを抱えながら真相を隠し続ける彼女の心は、次第に荒んでいく。耐え難かったのは、リリーが亡くなった後の夫の態度だ。リリーが死んだのは自分のせいだと一人で自責の念に駆られ、妻のあとを子供のようについて回り、慰めを妻に要求する。だが慰めを本当に必要としているのは彼女の方である。さらには祖母を邪険に扱ってきたことの償いをするかのように、祖母への態度をがらりと変え、しきりに褒めるようになった。リリーが亡くなる前は、妻が祖母の家に行くのを許さなかったが、リリー亡き後はしきりに祖母を訪ねてはどうかと勧めるようになった。交通費にと夫から渡される金で、彼女はまるで今までの我慢を爆発させるかのように大いに飲み食いし、買いたいものを買うことに費やす。
結局一度も祖母を訪れないまま、半年後に祖母も亡くなった。リリーの死の真相をめぐって秘密を共有している友人は、夫に打ち明けるべきだと涙ながら母親に訴える。罪悪感と憎悪のジレンマに苦しむ彼女は悪夢を見るまでに追い詰められていく。
この物語は静かな暴力性をはらんでいるように思う。母親はもしかして夫からDVを受けていたのではないかと感じるシーンがあるのだ。実際に暴力を振るわれるシーンはないのだが、祖母の家にリリーを連れて行ったことがばれると自分は殺されると叫ぶ場面で、その疑問が頭をもたげる。殺されるかもしれないなんて言葉が出てくるのは異常ではないか。その言葉は、彼女が夫から日常的に暴力を振るわれていて、家庭では絶対服従を強いられているのかもしれないと推測させる。あるいはDVを受けてはいなくても、妻は夫に従うべきだという価値観が幼少期に親から/世間から刷り込まれ、内面化してしまったことの表れなのではないか。
ルメナ・ブジャロフスカは”My Huzband”という作品で、夫から様々なDVを受ける女性たちをめぐる11の短編を著している。抑圧された女性たちの苦しみを深層部まで見通し、その透徹したまなざしによって描かれる救いのない暗い物語の奥には、痛みを共有する作者の優しさがあるように感じる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
