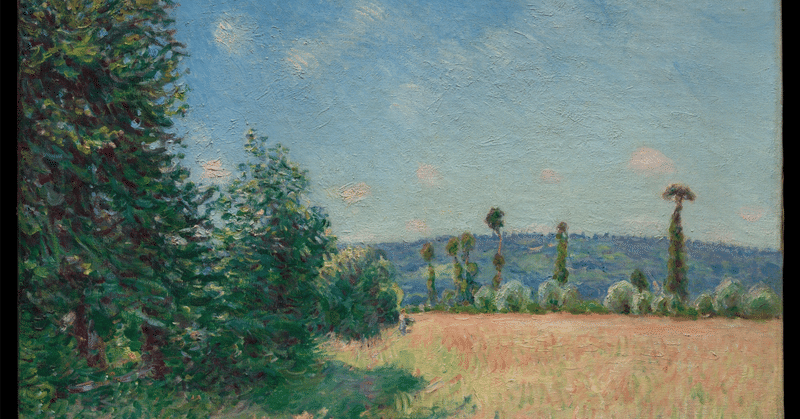
俳句の"読み"方①一物仕立てと取り合わせ
俳句の"読み"方の記事では、知っておくとより俳句が読みやすくなる基礎的な事柄をいくつかお伝えできればと思います。詠み方(作り方)で調べても同じような情報は出てきますが、こちらの記事では"読む"視点で書いておりますので、その辺りはどうぞご理解ください。(作る、のおすすめコンテンツも後半載せております)
さて、俳句の型は、シンプルに分けると、二種類あります。
俳句の初心者向けの作り方のドリルなどを見ていると必ず出てくるのがこの俳句の型の違い。まずは読んでみるという場合は、この二つの型を知っていれば大丈夫かと思います。
読み手目線の説明をしますと、俳句に詳しく無い人でも一読して何が書いてあるか理解できる型が「一物(いちぶつ)仕立て」で、その一方で「えっ?どういう意味なのかな?」となりがちな型が「取り合わせ」です。後者は、これは「型」だとあらかじめ知っておかないと「やっぱり自分には俳句よくわからない……」となってしまうかもしれん!と思うので、この記事では例句を引きながら、できるだけわかりやすく簡単に解説します。
俳句の型①一物仕立て(読んで意味がわかりやすい方)
一物仕立ては一つの季語をしっかりと描写する句の型です。俳句を読み慣れない方が一読して、意味がわかりやすいのはこちらの型かもしれません。基本的には季語を深掘りする句型なので、歳時記の例句は一物仕立ての句が多いと聞きます。以下の例句も、手持ちの複数の歳時記から引いてみました。(ちなみに歳時記とは季節ごとの季語が載っている辞典形式の本です。それぞれの季語に例句が掲載されています)
深く手を入れて紫陽花切りにけり/北島きりは
からっぽの檻を見ており遠足子/松本てふこ
レース傘レースの影をこぼしけり/辻桃子
一句目。切花にするのでしょうか、紫陽花(あじさい)の茂みの奥までぐっと手を入れています。枝はそこそこ硬いので、ぱっと手を入れてさっと切れるものでもありません。顔の近くに触れる大きな紫陽花の質感や、どこかひんやりとした温度、花と水の香り、大きな葉っぱの感触まで、伝わってきます。虫が嫌いな人だと少しぞわっともするかもしれません。
二句目。遠足の一場面を切り取った一コマ。この句の季語は「遠足(子)」で春の季語です。動物園でしょうか、遠足に来た子供たちがわらわらと、空っぽの檻を覗いている……。どこかシュールで、面白い一場面です。ちなみに井の頭自然文化園(動物園)には、中に鏡が置いてある「ヒト」という空っぽの檻があります。
三句目。レースは夏の季語です。レースの傘からこぼれた影がレースの形になっている。夏の真昼の強い日差しだからこそ、くっきりとした影が地面に描かれています。涼やかな発見です。
俳句の型②取り合わせ(読んで「?」となるかもしれない方)
二つ目は「取り合わせ」です。取り合わせは二つの事柄を組み合わせて、そこに詩情を生むという作り方の俳句です。俳句に慣れていない人が俳句をちらっと見て「何だかよくわからない」となるのは、取り合わせの句が多いのでは無いかと思っています。
マリッジブルー屋根から雪の落ちる音/神野紗希
冬すみれ人は小さき火を運ぶ/田中亜美
不眠症魚はとほい海にゐる/西東三鬼
一句目。マリッジブルーと屋根の間には、意味の断絶があります。俳句ではこの意味の断絶のことを「切れ」と言います。心の中にあるマリッジブルー、もうすぐやってくる結婚への不安と、どさりと外で雪が落ちた音。それぞれの場面が静かに響き合って効果を生んでいます。例えばこの句が「エンゲージリング屋根から雪の落ちる音」だと、元の句の、静謐でどこか寂しさと不安が混ざったような響きは生まれないと思いませんか?
二句目。もちろん「冬すみれ人」という人のことを詠んでいるのではありません。人は小さき火を運ぶ、それは光や熱量を持つ電子機器の比喩かもしれないし、誰もが胸の中に持っている小さな情熱の火種かもしれない、あるいは、それぞれの人の命の炎そのものかもしれません。作者がどのような意図で読んだか、ということはもちろんあるでしょうけども、俳句としてはそこに正解があるわけではなく、読んだ人が「冬すみれ」という小さく愛らしい命との取り合わせで、どう感じたかが優先されます。
三句目。とても有名な句です。旧仮名で書かれているため、念の為補足すると「不眠症魚は(遠)とおい海にいる」と読みます。不眠症と魚には直接の関係は無いのですが(しつこいですが、不眠症魚という魚の話ではありません)、眠れない夜の、静かな海の底にいる時のような焦燥感やそこはかとない苦しさが「魚はとほい海にゐる」という言葉と繋がるような気がしませんか?ちなみにこの句は季語がない無季の句でもあります。
まとめ
一物仕立てと、取り合わせという基本的な二つの型の紹介でした。多分、初めて読む時に最も迷うのは取り合わせの切れの部分かなと思ったので、簡単に解説してみました。型は他にも色々あるのですが、とりあえず読んでみる!という場合は、とりあえずこの二つがわかっていれば大丈夫じゃないかなと思います。
もう少し詳しく知りたい、ちゃんと知りたいという場合は、夏井先生のYoutubeの解説や、岸本尚毅先生の俳句レッスンなどもご参照ください。リンクを貼っておきます。
次回、俳句の"読み"方②では口語体/文語体、新かな/旧かなの簡単な説明をします。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
