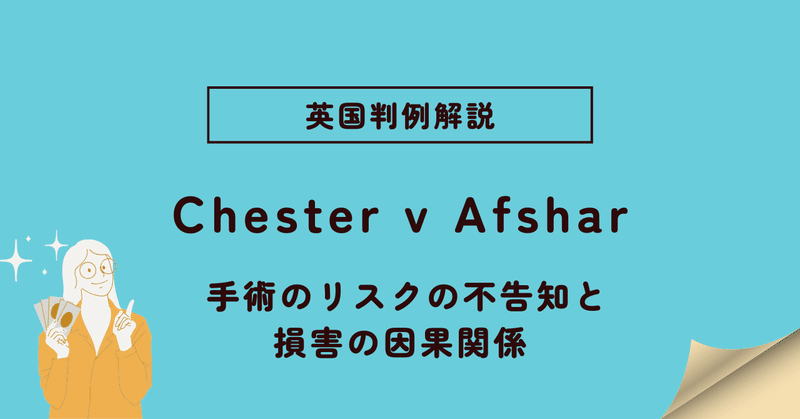
【英国判例紹介】Chester v Afshar ー手術のリスクの不告知と損害の因果関係ー
こんにちは。
お読みいただきありがとうございます。
今回ご紹介するのは、Chester v Afshar事件(*1)です。
本件は、英国の不法行為法における因果関係の判断手法である"but for"テストについて、政策的に例外を設けた事例です。
いつもの如く、日本の企業法務に従事する方が実務で参照する可能性は低いかと思いますが、とてもメジャーな判例であるため本日ご紹介します。
なお、このエントリーは、法律事務所のニューズレターなどとは異なり、分かりやすさを重視したため、正確性を犠牲しているところがあります。ご了承ください。
事案の概要
腰痛に悩む原告
Chester氏(原告)は、長年にわたり腰痛に苦しめられていました。原告の担当医は、保存的治療によるアプローチを続けていましたが、痛みが緩和することはありませんでした。
1992年、原告はMRI検査を受け、その結果、原告の腰椎の先天的な特徴によって、一部の椎間板に顕著な突出があることが判明します。1994年、担当医は、原告に手術を検討するように伝えて、医師のAfshar氏(被告)を紹介します。その際、担当医は、被告に対して、原告ができれば手術を避けたいと望んでいることを伝えていました。
医師である被告との面談
原告は、担当医からの紹介を受けて、被告と面談を行います。
この面談にて、原告は手術について承諾しますが、肝心の面談の内容については、原告と被告の間で対立があります。
被告によれば、原告との間で手術をする場合としない場合の結果について話し合い、なぜ手術が必要なのかを説明しました。また、手術には、足の麻痺を含む感覚障害のリスクがわずかにあることを説明するとともに、手術を受けなかった場合に生じるであろう問題についても、原告に伝えたと主張しています。
他方で、原告によれば、手術に関する怖い話をたくさん聞いたので、そのリスクについて知りたいと言ったが、足の麻痺のリスクを含めて、そのような説明は一切なかったといいます。また、原告の腰痛が事実上手術によってしか治らないことも知らなかったとのことです。もし、そのようなリスクを聞かされていたら、すぐに手術を承諾することはなかったと主張します。
手術の実施とまさかの事態
面談の翌週月曜日に、さっそく手術が行われます。
手術は2時間弱で終わるも、原告が意識を取り戻した際に、両足の運動と感覚に障害があることが判明します。これを受けて、被告は緊急のMRI検査を行い、その結果を踏まえて、2度目の手術を実施します。これは、椎弓切除術(laminectomy)と呼ばれるもので、原告の脊柱管全体を観察することができるようになるものでした。
2度目の手術後、被告は、運動・感覚障害が起こった原因を考察しますが、原因となりそうな事由(神経根の損傷、神経嚢の破損、体液の漏出など)は見当たりませんでした。
被告が出した結論は、馬尾症候群(cauda equina syndrome)と呼ばれる稀な合併症に見舞われたという説明しかできないというものでした。
その後の容態
原告の右足については、手術から2, 3週間でほぼ正常に戻りました。しかし、左足の回復は遅く、手術から約6年が経過しても、多くの障害が残ったままでした。
そこで、原告は、被告に対して、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起します。事件は、最高裁(当時は貴族院)まで持ち込まれます。
争点:リスクの不告知と損害の間に因果関係があるのか?
因果関係の判断にあたっての原則:"but for"テスト
日本の不法行為と同じく、英国法においても、不法行為が成立するためには、侵害行為と損害の間の因果関係の存在が必要です。これは、次のような質問を用意することで、答えが導かれます。
不注意(違反)がなければ、被害者は、被害を被ることがなかったか?
この答えがYESであれば、因果関係が認められると考えられています。このような問いかけは、しばしば、"but for"テストと表現されます。今は手元に日本の書籍が無いのですが、日本の不法行為法でも、事実的因果関係の判断手法を説明するものとして、このテストに言及されることが多かったはずです。
テストの例外(?)
このテストは、極めてシンプルかつ明確ですが、あらゆるケースで万能とは言えないのではないかという批判があります。
第一に、損害の原因が複数存在し、"but for"テストを利用して損害の原因となった不注意を突き止めることが困難又は不可能な場合です。第二に、"but for"テストの結果が不当なものになると思われる場合です。
本件は、これらの例外のうち、第二の場合に該当し得るケースです。
リスクの不告知
具体的に見ていきます。原告の主張は次のとおりでした。すなわち、本件では、原告は、被告が手術によって(手術の内容に問題がなくとも)足の感覚障害が生じるリスクを伝えておらず、もし原告がリスクを認識していれば手術の代替案について助言を求めたであろうし、手術は行われなかったであろうと主張したのです。
他方で、被告は、仮にリスクの告知怠ったとしても、手術のリスクが増加したわけではなく、どんなに注意深く手術が行われたとしても、手術に内在するリスクとして、すでに存在していたものであると主張しました。
被告の主張にしたがって“but for”テストを素直に適用すれば、因果関係なしと言えそうに思えます。
本件で被告が麻痺に関する責任を負うべきか否かは意見が分かれるところだと思いますが、被告が責任を負わないのは不当であるという考えも、極端なものではないはずです。
裁判所の判断
裁判所は、"but for"テストを修正して因果関係を認め、被告の責任を認定しました。該当部分の判決を要約すると、次のように述べられました。
手術に内在するリスクを警告する外科医の義務は、患者のリスクを最小限に抑えることを目的とし、また、患者が十分な情報を得た上で、治療を受けるかどうか、受けるとすれば誰の手で、いつ受けるかを選択できるようにすることを意図していた。被告は、原告のリスクを増大させなかったとしても、原告の選択権を侵害した。政策的な理由から、因果関係のテストは本件では満たされていた。リスクは警告義務の範囲内であったため、障害は法的な意味で警告義務の違反によって引き起こされたとみなすことができた。
考察
原告の「選択権を侵害した」とは、どういうことか?
上記の要約にあるとおり、裁判所は、伝統的な因果関係の判断手法に修正を加えた上で、原告のリスクの増大がなかったとしても、原告の選択権を侵害したものとして、因果関係が肯定されるとしました。
ここでいう選択権とは、治療を受けるか否か、受けるとして誰により、いつ受けるのかを決める権利だと思われます。そうなると、リスクの告知がなくとも、治療を受けない余地も、誰から受けるかを選ぶ余地も、いつ受けるかを選ぶ余地も無い場合には、選択権の侵害は無いと言えそうです。
実際、その後の事件(*2)では、本判例に依拠しようとする原告は、リスクが正しく告知されていれば、手術を辞退又は延期したであろうことを証明する必要が残ると判示しました。
"but for"テストでも同じ結論を導けるのでは?
最高裁は、本件の因果関係の判断に関して"but for"テストを修正しました。しかし実は、控訴審は、"but for"テストを適用しても因果関係を肯定できるという立場をとっていました。
どういうことかというと、もし、被告がリスクの不告知をしていなければ、原告は手術を受けなかったか、あるいは別の日に手術を受けたとしても、手術のリスクが顕在化する可能性はごくわずかでした。そうであれば、被告が傷害を負うことは避けられたはずであるという理屈です。
ただ、少しテクニカルに過ぎると思いますし、この理屈を突き詰めたせいで、"but for"テストの適用結果として責任を否定することが不当でない事例でも因果関係が認められる事態が生じる可能性もあり、かえって、不公平が起こったり、結局例外を設けなければいけなくなる場面に出くわすのではないかと個人的には感じています。
まとめ
いかがだったでしょうか。
本日は、不法行為の因果関係の判断に関する重要な判例を紹介しました。
本判例のほかにも、"but for"テストの適用の例外的場面がいくつかあり、またどこかでご紹介できればと思っています。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
このエントリーがどなたかのお役に立てばうれしいです。
【注釈】
*1 Chester v Afshar [2004] UKHL 41
*2 Correia v University Hospital of North Staffordshire NHS Trust [2017] EWCA Civ 356
免責事項:
このnoteは、ぼくの個人的な意見を述べるものであり、ぼくの所属先の意見を代表するものではありません。また、法律上その他のアドバイスを目的としたものでもありません。noteの作成・管理には配慮をしていますが、その内容に関する正確性および完全性については、保証いたしかねます。あらかじめご了承ください。
X(Twitter)もやっています。
こちらから、フォローお願いします!
他にも、こちらでは英国の判例を紹介しています。
よければご覧ください!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
