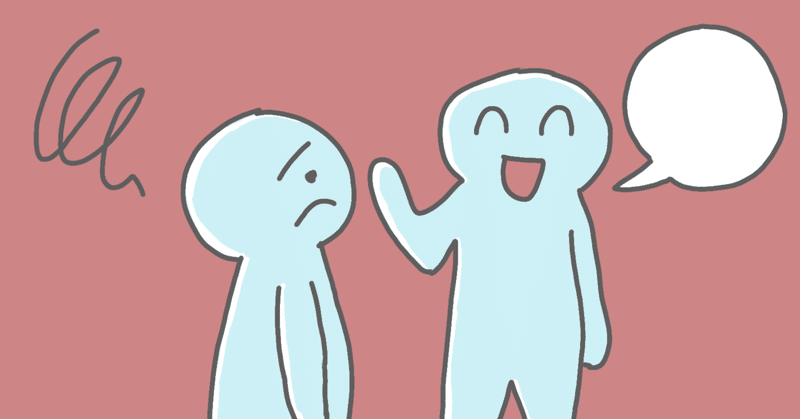
学生講師向け聞かれる話術の方法論
もともとこの記事は別の方向で書こうとストックしていた物なのですが、ちょうどこのシリーズに盛り込もうとしていたものに被っていたので、今回はマガジンの一部としてアップする事にしました。
「話し方」を研究する
大学生で塾の先生を始めた頃、僕はあまりに喋るのがヘタクソで、全く仕事にならなかった(笑)ので、一時期むちゃくちゃ喋り方の勉強をしていました。
落語、お笑い、漫才、司会、講演会etc...
とりあえずYouTubeで見られる動画を片っ端から文字起こしとタイムテーブルを作るみたいな形で書き起こし、話し方の真似をしてみたり。
そんなわけで「話し方」という話題になる、そこそこ言語化ができたりします。
「なぜこの人はこんなに面白いのだろう?」という部分や、味のある話し方みたいな所の大部分はその人の経験や環境に由来するコンテンツの部分になってしまうのでなんとも言えませんが、その面白さの技術的な部分には共通点があるように思っています。
人に伝わる話し方、人に面白いと思ったもらえる話し方は人工的に作れるというのが僕の持論です。
だれでも最低限の話し方を身につけられる「3つの型」
話しが上手い人に共通するのは以下の3点です。
①脳内で話を編集している
②相手との共通項を想定する
③ボールを受け取らない
ひとつめの脳内で話を編集しているというのは、会話の内容や尺を意識しながら話しているかというお話です。
よく、話し始めると冒頭から終わりまでを時系列にそって説明し始める人がいますが、あれをやってしまうと、相手には非常に退屈な印象を与えてしまいます。
だからダイジェストを意識しながら話すことが有効です。
例えばYouTuberの語りがそのイメージ。
彼らはおそらく、そこまで話すことが上手いわけではないので、動画にする何倍もの映像を撮った中からいい場面を切り繋いで1つのコンテンツにしています。
結果的に動画のテンポが良くなり、見やすくなっている。
会話においてもこのやり方が非常に有効です。
②の相手との共通項を意識するというのは、相手の知っている話題に合わせたり、喋りながら相手の知らない分野に関しては適宜フォローを入れるというやり方です。
友達や会社の同僚であれば話は別ですが、たいていの場合、相手と自分の共有するバックグラウンドはことなります。
自分が当たり前だと思っている言葉でも、相手は知らないということがザラにあるわけです。
そんな時に、「それって何?」と相手が聞き返してくれるのに期待するのではなく、さりげなく自分の側から前置きや解説を加える。
②の意識がある人はこれをサッとやっています。
これをする事で話の伝わり具合が格段に上がるため、聞き手にとってスムーズに内容が入ってくるわけです。
しばしば会話はキャッチボールに例えられますが、話の上手い人を見ていると、キャッチボールというより、テニスのラリーに近いやり取りをしているように感じます。
これが③のボールを受け取らないという内容です。
話しが苦手な人は、相手が投げてくれた話題を受け取ると、ずっと話し続けてしまったりします。
これをすると、相手はその間ずっと受け手になってしまうわけです。
いわばカラオケ状態。
話している側は相手にキチンと内容を伝えようとしているわけですが、聞く側は当然退屈に感じてしまいます。
そのため、振られた話題にはサッと答えて、再び相手に話題を戻してあげるという想定で話をする。
そうするとテニスのラリーのようになり、会話がテンポよく進みます。
しかもできるなら相手の打ちやすい部分に返してあげたり、時にはスマッシュを決めやすいロブを投げてあげたりする。
話し上手の人たちは、こういうゲームメイクの視点を持っているように思います。
「3つの型」を修めた人だけが使える奥義
ベテランの先生たちは話が上手いのはもちろん、どこか生徒の心を捉えて離さないような空気感を纏っていることがあります。
それは経験の成せる技だと思うのですが、若い講師の人たちでも先の3つが使えると、その空気感を擬似的に「作り出す」ことができるというのが僕の持論です。
上にあげたような「人工的な」話のうまさをもっている人は、普段意識的にこれをしているあめ、こうした3つの型をオフにして話すというカードをもっていると言えます。
そうすると、普段は整った話し方なのに急激に砕けたまとまりのない話になる。
普段からダラダラ話していると、話しが退屈な人という印象しか与えないのですが、日頃①〜③を意識している人がそれをやめると、それが人間味のように感じられるわけです。
(僕は世の中の経営者や成功している人がプライベートであったときに「いい人」という印象を与える最大の理由はここにあると思っています)
普段身内で話している場合にはそんなこと必要ありませんが、初めての人と話す場合や、大勢の前で話すという機会にはこの3つの武器(とそれを捨てるというやり方)はそれなりに有効です。
少なくとも僕が話し上手と思う先生はみんなこれをやっている。
いずれも意識した瞬間からできるようになるというものではありませんが、頭の片隅に置いておくと、少しずつ話し方が変わっていくように思います。
もし、こういった話し方の必要性に迫られている人がいたら、活用して見てください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
