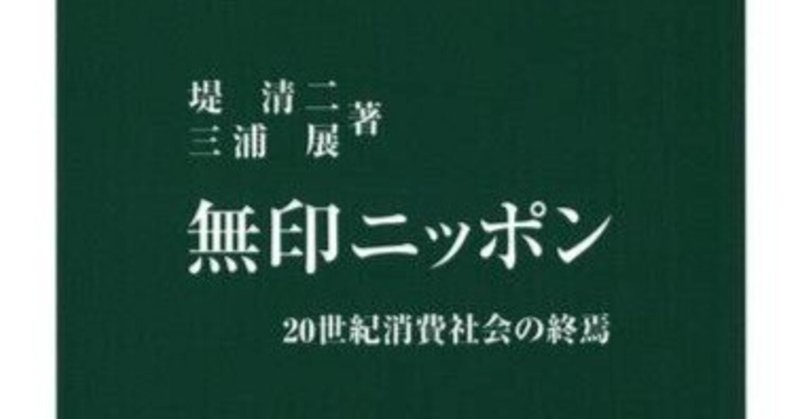
「無印良品」は消費社会打開の切り札になり得るか? 堤清二・三浦展『無印ニッポン』
~~辻井喬=堤清二を読む~~
「無印良品」は消費社会打開の切り札になり得るか?
堤清二・三浦展『無印ニッポン』
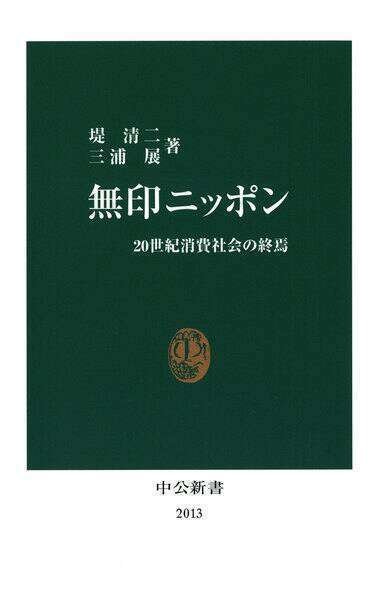
■堤清二・三浦展『無印ニッポン――20世紀消費社会の終焉』2009年7月25日・中公新書。
■対談(消費社会・現代史)。
■210頁。
■2024年5月15日読了。
■採点 ★★★☆☆。
目次
1 「無印良品」の思想
『下流社会』*[1]で洛陽の紙価を高めた三浦展(あつし)さんと、彼の元・上司(?)*[2]であった堤清二さんとの対談です。
基本的には、堤さんの年来の主張であるところの「消費社会の終焉」がそのテーマとなっています。
簡単に言えば、ブランド物などに見られるように、過剰にプラス・アルファの価値が付随された商品を高価に売買するといった消費中心の経済を考え直すべきだ、という主張のようです。
そして、堤さんのビジネスマンとしての、その反・消費社会の具体的な実践の具現化こそが、その実業家としての晩年に手がけた「無印良品」に他ならない訳です。本書の書題はそこに由来しています。
「無印良品」の思想とは何でしょうか?
対談者である三浦さんの発言によれば、以下のようになります。
堤清二最大の功績である「無印良品」のコンセプトは、シンプルな暮らしであり、「これがいい」ではなく、「これでいい」という一種無欲な商品を作ることですね。*[3]
確かに、現行の「無印良品」のホウム・ペイジを見ても、以下のように述べられています。
無印良品は衣服、生活雑貨、食品という幅広い品ぞろえからなる品質の良い商品として、1980年に日本で生まれました。無印良品とは「しるしの無い良い品」という意味です。
(中略)
たとえば、紙の原料であるパルプを漂白するプロセスを省略すると、紙はうすいベージュ色になります。
無印良品はそれをパッケージ素材やラベルなどに用いました。結果として非常にピュアで新鮮な商品群が現れたのです。
演出過剰ぎみだった一般商品と好対照をなす商品群は、日本のみならず世界に衝撃を与え、大きな共感とともに受け入れられました。
それは「これがいい」「これでなくてはいけない」というような強い嗜好性を誘う商品づくりではありません。
無印良品が目指しているのは「これがいい」ではなく「これでいい」という理性的な満足感をお客さまに持っていただくことです。
「これがいい」には微かなエゴイズムや不協和が含まれますが「これでいい」には抑制や譲歩を含んだ理性が働いています。
(中略)
無印良品の店舗は現在、全世界で1000を超え、商品アイテムも、衣服や生活雑貨、食品、そして家まで、7000アイテムを超えました。
しかしその思想の根幹は誕生当時と変わらず、北をさす方位磁石のように、生活の「基本」と「普遍」を指し続けています。*[4]
引用が長くなってしまいましたが、恐らく、この「無印」の思想の根幹に、ここにもある「誕生当時と変わらず」というように、堤さんの思想が息づいているのだと思います。
本書の中で堤さんは、「無印良品」について、幾つか散発的に述べられています。
例えば「これは反体制商品です」*[5]とか、あるいは、「無印良品は何を訴求したいかと思っていたかと言うと、それはただ一点、消費者主権なんです。(中略)ここまでは用意します。あとはあなたがご自分で好きなように使ってください、という、そういう意味での消費者主権。」*[6]という具合です。
なるほど、確かに、それは大変望ましい社会像である、と一旦は言えます。
本書冒頭に「自動車の世紀が一〇〇年で終わる」*[7]という小見出しの下に、すなわち、それは、言うなればアメリカ型の「二〇世紀の大量生産の社会が、ついに大きな転換を余儀なくされる時代にいま入った。」*[8]のだと、三浦さんは述べています。それは、企業の消費の論理に踊らされ、無駄な製品を、大量に消費し、場合によっては、大量に廃棄もする、という社会を離脱し、消費者自らが、自らの欲求や、自らの身の丈に合わせた生活や生き方を模索する時代に入った、ということを意味するかも知れません。
まさに、それこそが「無印」の思想だとも言えます。
「無印良品」の思想はともかくとして、その製品は、今や26カ国に拡がっているそうです。或る意味で、今後の世界全体の消費の考え方を占うものとなるかも知れません。
2 「ファスト風土化」
ところで、わたしは、この著で、三浦展さんを堤さんが「一読して、ここには新しい才能があると思った。」*[9]と誉めていることから、三浦さんを注目するようになりました。
『下流社会』はもとより、個人的に気になる、三浦さんの主張は「ファスト風土化」*[10]という概念です。本書から、著者自身の定義を引用するとこうなります。
ロードサイドに、大型ショッピングセンターやコンビニ、ファミレス、ファストフード店、レンタルビデオ店、カラオケボックス、パチンコ店などが建ち並び、地方から固有の地域性が消滅していることを言う。*[11]
確かに、これは、わたしたちが日常的に目にする光景です。恐らく、このままいけば、遅かれ早かれ、日本全体は、脱色化され、どこに行っても、同じような風景を眺め、同じような経験をすることになるでしょう。それは、日本全体が都会化する、というよりも*[12]、なにか人工的な模造された商空間によって占拠されることのようにも思えます。便利にはなった、でも、どこに行っても同じ、そういう日本です。
しかしながら、それは、比較的都市部に住居する者の偏った見方かも知れません。しばしば、都会に暮らす者が、田舎に行き、コンビニもないのか、とぼやきますが、田舎に暮らす方からすれば、1店のコンビニエンス・ストア、1店のスーパー・マーケットがあるだけでも、大変有難いことかも知れず、そうそう、簡単に日本全体が隅から隅へと完全に同色に塗り潰される、というのも、あるいは現実離れした、単なる妄想かも知れません。
さて、問題は何か、というと、郊外のショッピング・モールでほとんど間違いなく出店しているのが、ユニクロ、場合によっては、その下位ブランドのGUと、そして無印良品ではないでしょうか? そこにどこかの100円ショップが入る、というパターンかと思います。無印が地域の色を単色化することを助長していないでしょうか? このままだと、日本中はユニクロと無印の国になってしまうかも知れません。それは堤さんが望んだことでしょうか?
3 ノン・ブランドというブランド化
あるいは、こうも言えるかも知れません。
無印良品の最初期のキャッチコピーは「わけあって、安い。」*[13]でした。しかし、正直に言って、「無印」の製品は安いでしょうか? わたし個人はなかなか無印の製品に手が出ませんでした。安かろう、悪かろう、ということが分かっていても100円ショップの商品で済ませてしまうことが圧倒的に多かったと思います。それは結局のところ、わたしが製品に対するブランドを求めていないからだと思います。
つまり、逆に言えば、これは、しばしば言われることかも知れませんが、無印の製品を求めて買う人々は、ノン・ブランドたる無印のブランド、すなわち、ノンブランドのブランドを求めているのだと思います。つまり、今や、無印の商品は「これでいい」のではなく、無印という「これがいい」という商品になっているのではないでしょうか? だからこそ、世界的に需要があるのです。この側面はユニクロにも通底することかと思いますが、いずれにしても、これまた、そもそも堤さんが求めていたことなのでしょうか。
4 「消費」という闇
さらに、申し述べれば、堤さんや三浦さんは消費社会を批判する、と言います。確かに堤さんにはその主旨の論著もあります*[14]。
しかしながら、消費、とは何でしょうか? 門外漢のわたしには簡単には言えませんが、浪費、蕩尽も含めて、或る種の娯楽なのではないでしょうか?
個人的なことを言うと、仕事が忙しく、掃除や炊事といった生活の基本的な行動が封鎖され、生活に喜びが感じられれなくなると、食べたり飲んだりすることしか自由が利かなくなります。すると、到底、一人では飲食不可能だな、と思うぐらいの食料(主にスーパーマーケットのお惣菜であるが)を爆買いして、相方に怒られます(´;ω;`)ウッ…。
あるいは、同様に読書をする時間も無くなると、その代償行為として、古書をあり得ないぐらい買ってしまいます。恐らく、もう死ぬまで、頑張って読んでも、絶対に読み切れないぐらいの古書を買ってしまいました。自分でも「病気」ではないのか、と思うぐらいに歯止めが効きません。
これは仕事のストレス発散という側面もありますが、消費、取り分け、「過剰な消費」には、人類が抱え込んだ、或る種の闇の部分が照らし出されているのではないでしょうか。
村上春樹さんの著名な短篇小説に「トニー滝谷」*[15]という名品があります。わたしはこの作品がとても好きです。ネタバレになってしまうので詳しくは書けませんが、ミュージシャンであるトニー滝谷のパートナーの女性は、大変よくできた方だったのですが、唯一欠点がありました。それは、一生かかっても着ることのできないぐらい、片っ端から洋服を買い集めることだったのです。この場合はストレスでもなんでもなく、或る種の心の病が、彼女をして過剰な買い物に走らせていたのでしょうが、何か、ここには「消費」という人類特有の現象の、そう簡単には否定し去ることのできない、人類と消費の間の不可離性のようなものが潜んでいるような気もします。
このように様々考えてくると、堤清二さんはこの「消費」という謎に実践的な行為を通じて肉薄しようとした稀有な経営者であったのだとも言えるかも知れません。
参照文献
三浦展. (2004年). 『ファスト風土化する日本――郊外化とその病理』. 洋泉社新書y.
三浦展. (2005年). 『下流社会――新たな階層集団の出現』. 光文社新書.
村上春樹. (1996年). 「トニー滝谷」. 著: 村上春樹, 『レキシントンの幽霊』. 文藝春秋.
辻井喬. (1969年). 『彷徨の季節の中で』. 新潮社.
辻井喬. (1998年). 『本のある自伝』. 講談社.
辻井喬. (2009年). 『叙情と闘争――辻井喬+堤清二回顧録』. 中央公論新社.
堤清二. (1985年). 『変革の透視図――脱流通産業論』. トレヴィル.
堤清二. (1996年). 『消費社会批判』. 岩波書店.
堤清二, 三浦展. (2009年). 『無印ニッポン――20世紀消費社会の終焉』. 中公新書.
堤清二, 辻井喬. (2015年). 『わが記憶、わが記録――堤清二×辻井喬オーラルヒストリー』. (御厨貴, 橋本寿朗, 鷲田清一, 共同編集) 中央公論新社.
不明. (2024年). 「無印良品について」. 参照日: 2024年5月19日閲覧, 参照先: 無印良品: https://www.muji.com/jp/about/?area=footer
5,083字(13枚)
🐤
20240519 2117
*[1] [三浦, 2005年]。
*[2] 三浦さんは、西武セゾン・グループのパルコの社員でした。
*[3] [堤 三浦, 『無印ニッポン』, 2009年]11頁。傍線引用者。
*[4] [不明, 2024年]。傍線引用者。
*[5] 堤の発言[堤 三浦, 『無印ニッポン』, 2009年]97頁。傍線引用者。
*[6]堤の発言 [堤 三浦, 『無印ニッポン』, 2009年]100頁。傍線引用者。
*[7] [堤 三浦, 『無印ニッポン』, 2009年]4頁。
*[8] [堤 三浦, 『無印ニッポン』, 2009年]4頁。
*[9]堤「あとがき――楽しき対談」/ [堤 三浦, 『無印ニッポン』, 2009年]208頁。
*[10] [三浦, 『ファスト風土化する日本――郊外化とその病理』, 2004年]。
*[11] [堤 三浦, 『無印ニッポン』, 2009年]61頁。傍線引用者。
*[12] 本書でも述べられている(三浦さんの発言「東京の下町や商店街が独特の雰囲気を残している。(中略)京都でも大阪でもいいんですが、都市には風土性がやっと残っているが、地方には消えているという、不思議な状況になってる。」 [堤 三浦, 『無印ニッポン』, 2009年]70頁)ように、むしろ東京などの都心の方が、従来の伝統的な文化が残っているかも知れません。
*[13] [堤 辻井, 『わが記憶、わが記録』, 2015年]135頁。
*[14] [堤, 『変革の透視図――脱流通産業論』, 1985年]、 [堤, 『消費社会批判』, 1996年]。
*[15] [村上, 1996年]。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
