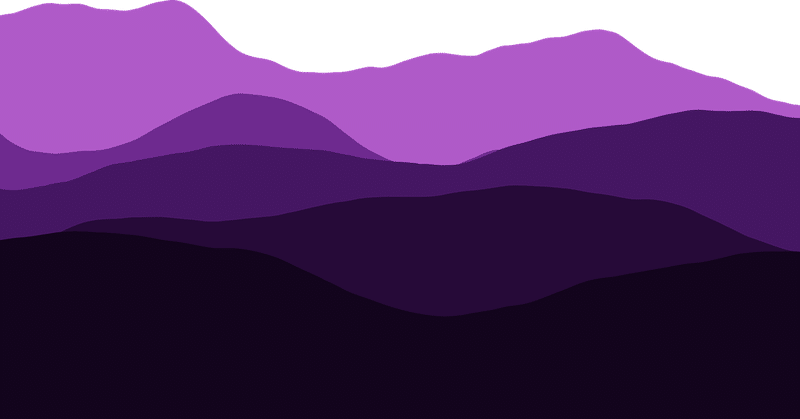
枷(かせ)【後編】
「枷(かせ)」ですか。
なんか陰惨な空気が漂いますねえ・・・。
この先、まだ行きたいですか?
こんな山道、何が出没るかわからないですよ?
真っ暗ではないですか?
「この辺はのー、よくマムシが出るけんのー、ユンベもほんれ、あすこの下駄屋のもにこ堂さんのとこの倅がやられてのー、ヒッヒッヒッヒ、くれぐれもキーつけなはれや」
って、(なぜ笑うのか不明な、まるで何かが起きることを楽しみにしてるみたいな)村の婆様に注意を受けたばかりでっしゃろ?
あんたはん、それでも行かれはりますか?
ヒッヒッヒッヒ
おっと、それとこの辺は
熊注意ですよ。
熊だけならいいですがね💦
あんたはん、「欲の道」にさらに深入りするおつもりでっか?
欲を甘く見ちゃいけませんよ、それ(←もーええっちゅうに!😅)
や、すみませんでした。
どーも、安っぽい時代劇の見過ぎのようで。
天を突き破るほどの高い目標?
さあ、前回「枷【前編】」では、「悟ったら終了」説が、なぜにそうなのかを探求いたしました。
よく言いますよね。
「それでいいと思ったらそこまで」
目標は高く、高く、天を突き抜けるほど。
天を突き抜けてさらに高く高く・・・。

いや、それはわかった。
理屈では分かった。
でも、一体天を打ち破るまでの、ロケット花火みたいなその動力源はどーすんのさ?
第一、そんな見えないような高い目標自体、どーやって持てっていうんだ。
それが出来る人物など、ごく一握りではないか?
それに、そもそもそんな高尚な精神界の探求なんて、いったいどこの暇人がやるんだ?
この現実のなか、不本意ながらも生活を守るために仕事をし、
否応なしに「低い世界」を突き付けられる。
分かってるさ、
こんな生き方が理想の生き方ではないことくらい
分かってるさ、
おそらくもっと高い世界があることくらい
いいかい?
もし仮に俺がその気高いものを追い求めるような
清い精神の人物になったとして、
女房はどうなる?
周りの友人はどーだ?
ほとんどの地べたしか見れないような連中はどーなる?
見殺しか?
現実がいくら「仮想のもの」といったって、
その現実に背を向けようとすれば、すぐさま牙をむく
その仮想世界の手ごたえと言ったら半端じゃないではないか?
それはどう説明するんだ。
その落とし前はどーやってつけるんだ
つけてくれるんだ
という地鳴りのような群衆の声が聞こえてくる。
ごもっともである。
それは「他人事」ではない。
それが「欲界」の姿だ。

しかし、
それがあってこその「色界」「無色界」・・・さらに高い世界だし、
「欲界」がなければその上の世界はない。
いや、その上の世界があるからこそ「欲界」がある。
「欲界」こそ、あらゆる家屋、ビルディング、いや摩天楼、須弥山の礎だ。
「欲界」「色界」「無色界」
それらは一直線につながっている。
欲界ほど、煩悩ほど、
つまりは、浮世ほど大事なものはまたとない。
悩み、苦悩、懊悩、矛盾、理想との葛藤ほどすばらしいものはまたとない。
それは、解決するためにあるばかりか、越えるためにあるのだ。
さらなる高みに行くための礎、
足がかりになるなるものだ。
踏み台だ。
いや、跳躍台だ。
欲界をよく見よ!
その二元性の世界をさらによく見よ!
そこがお前の目標か?
高い波がしらが、あっという間に崩れ落ちるようなこの世界に
その荒海のような世界に
「世の中は三日見ぬ間の桜かな」
のごとき世界に
その世界のどこに錨という「目標」を下ろす?
留置所行きか?
以前に、三界のうち、煩悩多き我々は残念ながら(同時に幸運なことに)、一番下の界「欲界」にいるということを学んだ(「三界に狂人住むと人の言う」)。
さらに、その欲は「カーマ」と言われる要素で構成されることも学んだ。
というより、目の前に突き付けられた。
まるで、警察で尋問された挙句、
目の前に証拠品を並べられたように・・・。
その証拠品はこれだ(再掲)
「欲望、性欲、情熱、憧れ、感覚への喜び、耽美的生き方、愛などを指し、現代的な例を挙げるなら、テレビゲームの長時間プレー、喫煙への欲求、成功への欲求などを指す」
さあ君はどーする?
留置所行きか?
絶体絶命?
(刑事に「腹減ったろ、何か食うか?」と聞かれて、うっかり「かつ丼」なんて答えるな。後できっちりその代金払わされるそうだからな)

そこはかとないうしろめたさ
な、な、なんかおかしくないですか?
何か「狂って」ませんか?
気のせいですか?
「それって、ダメなんですか?」(小声、つぶやきジロー)
ではなかったですか?
正直なところ。
いまどきですから「あー私ってダメなんだ。業が深くて、物欲サイキョーだし、典型的なダメなパターンじゃん」
なんて思われた方はいないにせよ、そこにそこはかとないうしろめたさを感じた方はゼロではないというより、多くいらしたのでは?
まあ、若いうちは特にアレですから、その「燃え盛る欲望、性欲、情熱、憧れ、感覚への喜び」がハンパないわけです。
拙者もそうでした(突然チョンマゲを付け、威儀を正す)。
カーマ(欲)がメラメラと燃え盛る
しかし、ここをあなたは見逃してませんでしたか?
カーマがどこにも「悪い」とは書いてありましぇん。
それどころか、カーマ(欲望)は、
道徳(ダルマ)や、富(アルタ)や、輪廻からの解放(モークシャ)と併せて
人生の4大目標の一つ
と、堂々と書いてあるではないか。
つまり、まとめると、こーゆーことです。
われわれは、メラメラと、あるいはギラギラした暑苦しい欲望と、飽くなき富の追求と、しかし同時に道徳をわきまえ、あわよくば輪廻を脱却することが人生の目標である!(キッパリ!)←ヒンズー教の場合ですよ
むしろ飽くことのない「欲」こそが、どこまでも私たちを高みに誘ってくれる動力源、ダイナモではないか?
インド映画はなぜ笑って踊る?
ところで、あなたは印度映画をご覧になったことがありますか?
ハリウッドの比ではなく、世界で断トツ映画製作一位、インドのその映画。
青やピンクやらの派手な衣装を着た男女が、ニコニコしながらひたすら踊る。
男は女に踊りながら距離を縮める
しかし、女は男を流し目で見つつ、
するりとかわしてじらしつつも逃げてゆく
男は大仰な驚きの表情を見せて体をくねらせる
そしてまたして獲物を捕らえに踊って走る
あー楽しい恋愛ゲーム
ニコニコしながら追っかける
そんなん、続きます。
私としても、あまりの温度差というかカルチャーショックで、
理解不能でいたわけですが、
ははー、なるほどね。
宗教的な世界観なんだなあ、とわかってくるではないか?
印度はヒンズー教の国
カーマの燃え盛る国
同じ印度で生まれた仏教が、なぜにそのインドに根付かなかったのか?
煩悩を否定し、欲界を否定したせいのか?
おそらくは、そのように(後世の学者や何ものかによって)変質されてしまったせいではないか?(とはあくまでも私の解釈)
私は、釈迦はそれら欲を「否定」はしなかったと思う。
仮に「否定」したとしても、それがそこにあるからこそ、否定という行為が成り立つ。
「(煩悩が)ある」のが前提だ。
ボンノーありきだ。
(当然ながら釈迦が生まれる前に人はいた。すでに「煩悩」があった。それを誰が否定できようか?)
私は、釈迦は、我々がそこ(煩悩)に「とらわれる」ことを否定したのだと思う。
もっというと、生々発展し続ける自分の欲(と言われる実は生命力)を「これでよし」と見限る行為を否定したのだと思う。
釈迦が煩悩の神「マーラ」に、今でいうハニトラを散々仕掛けられて、それに打ち勝ったことで、成道したという。
しかし、それがマーラを殺したり否定したことではない。
そこにとらわれないことが出来たのだと私は考える。
(とはいえ、私の場合はそのー、今、「どーしたの? なーに考えちゃってるの? ヒ・テ・イって何を?」なぞと囁く美女に近寄ってこられた日にはソリャー分かりません。悟れません。餓鬼道です。地獄変です)
「欲」ではなく、それの「枷」を否定する
いずれにせよ、仏教が、欲界にとらわれず、さらに高い涅槃の世界へと導くような「哲学」であるのに対して、
ヒンズー教では煩悩すら「神」である。
悪魔すら「神」である。
それは飽くなき「生」そして「性」の肯定である。
「欲」を否定し(と言われ)、インテリ層の好む形而上学的な世界観を持つ仏教は、その哲学の普遍性ゆえに「世界宗教」になった。
片や庶民が好む形而下学的な欲の世界を肯定し、この世の生を謳歌しようというヒンズー教はしかし、インド周辺の「民族宗教」に留まり、地理的な広がりはないものの、信者数は仏教徒を上回る。
私は本来は、いずれの宗教も「欲」を否定していないものと考える。
むしろ「欲を遮るもの」
すなわち、
枷になるものを否定したのだ、
そう考える。

欲望はもちろん、この物質界でも、本来は次々に達成するべきだろう。
好きな彼女を手に入れる(という言い方セクハラですか?)のも、
宅建の資格やFPの資格やらを取得するのも、
それが「目標」であればそれを実現すること。
そして、それに甘んじないこと。
目標(ゴール)を持つことは大事だと思います。
いや、大事というより、持たなくてはなりませんね。
目標がない旅路というものは、その船がどこに行くのか、どこで座礁するのかさえ予想つきませんからね。
目標に向かう姿勢が「意志」ですし、
それは、念ずれば叶うという願望達成の到達点ですからね。
(今の心→叶=口×10=口口口口口口口口口口)
ここで、ちょっと、整理しますね。
脱線ばかりすると、論旨があいまいになりますからね。
(といっても、別に論じるなどとエラそうなこと言ってませんが)
「欲」は否定できないばかりか、「欲」こそ、生命の根源である
それは、はるか私たちの源(涅槃)まで到達する「生命」の原動力である
「無欲」「欲」を超越した世界も、「欲」があるからこそ成り立つ
「欲」を否定することは命(生命)を否定することだ
その神聖な「欲」を否定するもの(枷)こそ否定せよ
それの一つは「沽券」
もう一つは「これでいい」と自分の限界を決めること
さらに一つはこの欲界(の誘惑)に満足すること
そう、欲は開放しなくてはならない。
では、この煩悩の世界(欲界)を超えた世界(三界でいう「色界」や、「無色界」)でそれを妨げるものはなんだ!
ですね。
なったつもりの増上慢がリミッターに
それが俗に「増上慢」と言われる奴。
いや、俗ではないですねぇ、マニアックな言葉ですねぇ。
そもそも「増上慢」という言葉、もちろん日常ではあまり聞かない。
かくいう私も「慢心して有頂天になっている状態」「天狗になる」くらいの認識でした。
しかし、改めて調べてみると、その解釈はズレていた。
それは要は、
「悟ってないのに悟ったつもりになって得々としていること」
が正解らしい。
転じて(かどうかは知らないが)、
「自己の価値をそれ以上に見ることをいう」
とある。
つまり、「中身がないのに中身が詰まっているかのように見せる」「大した器でもないのに、さも立派な人品であるかのようにふるまう」などと、まるで現代のマーケティング手法を語っているのかと見まごう程、その言葉の意味には奥行きがある。
しかも、仏教の教えでは、その「増上慢」というやつは、「慢」という煩悩の一つに数えられるもので、4つある「四慢」や七つある「七慢」の一つとも。
「え? 煩悩とはいえ、マンが四つも七つも?」
とさらに調べてみると、
「四慢」には、増上以外にも、「卑下慢」「我慢」「邪慢」があるそう。
なんでも、「自分」という幻想を中心に
それより上回っている
それと同等
それより下回っている
という煩悩が生じるということ。
まあ、今風な教訓として馴染みやすいですね?
「なるほど、過剰に自分を卑下する奴は、なんだか下心ありありでかえって高慢の裏返しに見えるし、え? 我慢も煩悩ならば、やせ我慢などはもってのほかだな」
などと、すっかり脱線している自分に気づくわけである。
ところで、これら「慢」がなぜ生ずるのかというと、
他者との比較がその原因という。
また、他者との比較ではなく生ずるものは「憍」といい、慢とはまた違うものらしい。
他者と比較せずに自惚れている状態は憍(きょう)という。サンスクリットのMānaを憍慢と翻訳する場合もあるが、憍と慢はやや異なった煩悩とされ、慢は他と比較して起す驕(おご)りで根本的な煩悩とされるが、憍は比較することとは無関係に起る。家柄や財産、地位や博識、能力や容姿などに対する驕りで付随して起す煩悩であるとされる。これを随煩悩ということもある。
まあ、よくぞここまで調べたではないか?
どーやら古代インドには、フロイドやユングやらの深層心理、精神分析学を俟つまでもなく、人間の心理の奥底を覗く学者がいたんでしょうね。
なんか、書いてるうちに慢心どころか、もう満足してしまいどーでもいいような気持になってきました。
聡明なみなさまはもうお分かりですね?
増上慢は、ケッコー気づかないうちに身近にあります。
自分でも気づかないうちにあります。
天狗になったり、有頂天になったり、増上慢になったり、
何かの拍子にそこから地べたに落とされ、目が覚めることはありがたいことです。
それに気づかないことが問題です。
その本人が周囲に嫌われることが問題なんではないですね。
魂の成長に歯止めをかけてしまうことが問題なんです。
みなさまへ
お読みいただきましてまことにありがとうございました。
本当にお疲れ様でした。
もしかして禅あたりでは言うことがあるかもしれませんが、およそ仏教らしからぬ「欲」の肯定「生」の肯定といったお話しです。
ほとんどの宗教には、「修養」や「修行」を通して、欲を去り、(血の通った人間サイドから見て)人間離れしたような存在こそが、「聖人」や「悟りを得た人」「阿羅漢」などとする「理想像」「目標」「到達点」があります。
それは、しかし人間を小さく、こじんまりとまとめて、飼いならされた羊のようにしてしまうという最大の人間性に対する攻撃、その生命に対する侮辱です。
わたしは、ここで宗教批判をしているのではありません。
また、それを信奉する「信者」を批判しているのでもありません。
なぜなら、いずれの宗教も高いところではもっともなことを言っており、その次元(観念的)では人は救われてきたからです。
私が批判・排斥しているのは、宗教に取り入り、その中身を換骨奪胎、異質なものにしてしまった勢力について言っています。
お気づきのように、その手口は「欲という生命力に対する枷」です。しかし
それこそが「真理に対する枷」をはめなさい、と言っているに等しいことに多くの人は気づかない。
これが、人間の心の自由を奪う。
せっかく良かれと思い、ひたむきに学習、修養してきたその「教え」がまさかかえって仇になっているとは気づかない。
だから、その眼には、そうでない(そんな学習も教育もない)一般庶民がむしろ楽しく自由に生きているように映る。
この辺りが「欲はなかなか捨てきれんもんじゃ、まあほどほどにしときんしゃい」くらいの、あいまいに濁したり、煮え切らない「お説」に「そうなんだー」と相槌を打ってしまう原因になっています。
とはまあ、これはあくまでも私の勝手な「意見」ですよ。
もちろん、そのあたりは、そこにあるカバヤのミルクキャラメルか、フルヤのウインターキャラメルでも舐めつつみなさまご自身でお考えくだされば幸いです。
東洋哲学に触れて40余年。すべては同じという価値観で、関心の対象が多岐にわたるため「なんだかよくわからない」人。だから「どこにものアナグラムMonikodo」です。現在、いかなる団体にも所属しない「独立個人」の爺さんです。ユーモアとアイロニーは現実とあの世の虹の架け橋。よろしく。
