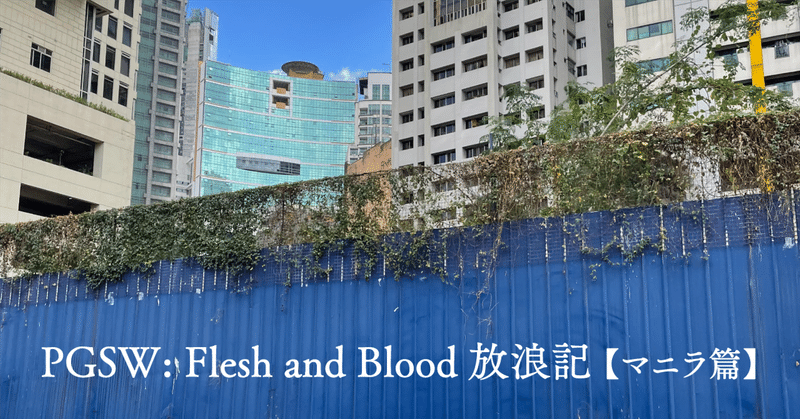
PGSW: Flesh and Blood放浪記【マニラ篇】
“Play the Game, See the World.”(ゲームをプレイし、世界を見よう)の精神を大切にしている『Flesh and Blood』というカードゲームがあります。これを題材にしつつ、海外大会への遠征にかこつけた紀行文を執筆しています。まずはマニラ篇の途中までをお届けします。
大ぶりの野人と小さな忍者
「──プレイヤーのみなさんは、所定の座席で待機してください。対戦相手が現われない場合は、近くのジャッジに声をかけて──」
運営から指示あるとおりのテーブルに向けて歩き、その間に呼吸を整える。
ここでさまざまな種類の不安を想像するのはたやすい。怪しげなくダイスをきちんと転がせるだろうか? 意図せずして不正な行為をしてしまわないだろうか? カードの持ち方はおかしくないだろうか、イカサマを疑われるような所作になっていないだろうか? デッキチェックは大丈夫だろうか、事前に大会に提出したデッキ内容と食い違いはないだろうか? カードを保護するプラスチックスリーブの角が折れ曲がっていないだろうか、特定のカードを引きやすいよう細工していると疑われないだろうか?
そんなふうに体がこわばってしまう可能性もありえた。
「ハイ。あなたはこのテーブルのひとですか」わたしが訊くと、
うむ、と先に卓についていた相手は応じる。
「日本から来ました。どうぞよろしく」握手を求める。
「ようこそ、マニラへ。わたしは地元のプレイヤーだ。今回はフィリピンでも過去一番の大きいイベントだから、あなたみたいな旅行者も来ているんだね」
そこで全体アナウンスがあり、制限時間を測る運営の時計がスタートした。こうして大会が始まったあとは不思議と、そしてすんなりと、状況を受け入れることができていた。
目的はシンプルだ。相手にまさること。

わたしが取りくんでいるFlesh and Blood(FaB)というカードゲームについて、ここで大枠を説明しておこう。
FaBとはどんなゲームかを一言で表現するなら、格闘ゲームのようなカードゲームだ。プレイできるキャラクターは、時期によって異なるにせよ、30-40名程度を数える。いや、「キャラクター」という一般的な表現は、これっきりにしておこう。FaBの用語にあわせて、ここからは「ヒーロー」と呼ぶことにする。FaBのプレイヤーとなったあなたは、まず1名のヒーローを選ぶ。その者を中心にして、数十枚のデッキを作り上げていくことになる。──しかし、こんな表現では、いかにも味気ない。
FaBのプレイヤーであるあなたは、レイスやその他の土地で名を上げた伝説上の人物(ヒーロー)になり代わる。砂漠で傭兵を率いる兵士・カッサイもいれば、鍛え上げた肉体とふた振りの小太刀で相手に連撃を浴びせかける〝忍者〟カツや、王朝の転覆を画策する〝暗殺者〟アラクニ、血の呪いに全身を蝕まれつつ相手と渡りあう〝野人〟の少女・レヴァイアもいる。各ヒーローはいずれも、それぞれの業を背負った魅力的な人物だ。ヒーローたるプレイヤーは、カードのかたちで持ち技や策略をくり出すこととなる。例えばカッサイは《戦闘中の略奪(Spoils of War)》によって得た戦略物資を駆使しながら、鮮やかな剣戟を糧に砂漠を生き抜く兵士だ。
血の呪いを受けたレヴァイアであるわたしは、いま、マニラの相手と対峙する。レヴァイアは、己の内なる怪物の力を借りて闘う、極めて大ぶりなヒーローだ。
初戦の相手は忍者タイプのヒーローだ。名前はベンジ。忍者は打たれ弱いが、そのいっぽうで、連続攻撃の爆発力に長所がある。このゲームでは、特定のカードが〈続行(Go Again)〉という能力をもっている。忍者は〈続行〉に次ぐ〈続行〉を重ねて相手を圧倒(ビート)していく。まるで格闘ゲームにおけるコンボのように、連撃をつなげていくのだ。さらにベンジは、防御しづらい攻撃を複数回重ねることができる。うかうかしていると、あっという間にこちらのライフが溶けていく。その代わり、ベンジはライフの総量がほかのヒーローよりも低い。まさに忍者タイプの典型と言っていい存在だ。
野人タイプに属するレヴァイアが、その少女の体躯からは想像もつかないほどに重たい一撃を放つ。まともに食らわせれば、ライフの3分の1をもぎ取れる程度の重たさだ。攻撃が得意なベンジであっても、流石に守って野人の殴打をやり過ごす。打点の競走(ダメージレース)だ。そうして繊細な攻防が何ターンか続けられる。
ベンジの連撃を丁寧に守ったのち、またしてもレヴァイアの攻め番。《満たされざる大食(Endless Maw)》を放つ。これはコストが重たい代わりに、超強力な一撃だ。この小ぶりな体つきの忍者から、ライフの優に2分の1を引き剥がすことができるため、ベンジは守らざるをえないだろう。レヴァイアはそう考える。しかしベンジは守らない。
一挙に忍者の身体がずたずたになる。それでもまだ、負けてはいない。ライフが尽きるまでのあいだは、まだ。
耐えて迎えた、ベンジの攻め番。まずは小太刀で斬りかかる。ゴーアゲイン。再びの小太刀。ゴーアゲイン。そして《水のように(Be Like Water)》流れる打撃をくり出す。ベンジから放たれるこの一打を、レヴァイアはブロックできない。ゴーアゲイン。ここでベンジを象徴する必殺の一撃が飛び出した──《春めく予潮(Spring Tidings)》。おいそれとは防げない一打であるにもかかわらず、これをひとたび食らわせれば、さらなる攻撃の連鎖(チェイン)を続けることができる。ゴーアゲイン、ゴーアゲイン──。
野人のライフが尽きて、勝敗が決する。わたしにとって初の海外遠征は、黒星でスタートした。

NRTーMNL
見知らぬ他人と肘が触れ合うほどに密着を強いられるエコノミークラスの狭さも、ずいぶんと久しぶりなものだ。
そんなことを思いつつ、約六時間のフライトをともにすることになる隣席の相手が座席につくのに手を貸す。と、足元に置いていた荷物が少しばかり相手の側に傾いていたから、慌てて引っこめようとする。
「おっと、すみません──」いや、日本語が通じる相手なのかどうか、見た目だけではわからない。「──ソーリー」かといって、英語が通じる確証だってあるわけじゃない、か。ひとりで苦笑いを噛み殺した。
やがて機の全体が離陸の準備に入り、5Gだか4Gだか2.4GHz(WiFi)だかの電波から遮断され、あの手持ち無沙汰な時間がやってくる。席と席のあいだから覗く斜め前の乗客は、すでにマーベル映画の新作に見入っているようだった。つられるようにして、眼の前にある10インチ程度の液晶パネルをタッチ操作でザッピングする。
そして小さな画面に世界地図が大写しになる。そのなかでは、飛行機のアイコンがA地点からB地点へ向けて、シンプルなベジェ曲線の弧を描いている。
NRT(成田)ーMNL(マニラ)。
現在時刻、18:05。目標到達時刻(ETA)、23:05。
訪れたことのないフィリピンの首都でカードゲームの大会に参加するべく、2019年から数えて4年ぶりの国際線に、わたしは乗っていた。

往路の機内では、ここ二週間ほどのあいだ行なってきた大会準備について、あらためて反芻していた。いま向かっているマニラの大会は、わたしにとって初の大舞台──いつも参加しているカジュアルなものとは異なる、競技レベルの大会だ。参加者総数は150名を超すらしい。わたしの知るかぎり、東京で100名を超す規模の競技大会が開かれたのは、2023年の一度しかない。
デッキ構築の不安だとか、人々が持ってくるデッキの予想だとか、頭のなかを渦巻く想念がさまざまありはするものの、明確に正しそうなことがひとつだけ思い浮かんだ。
準備不足。──このことだけは確からしそうに思った。そして準備不足のうちもっとも大きな部分を占めているのは、対面する相手のデッキに関する理解度であるとも自覚していた。
いまここで俎上に挙げたいのは、FaBはヒーローごとの相性がそれなりに大きいゲームであるということだ。つまり、相性が7:3程度のヒーロー同士が闘い合う可能性があるのだ。そうしたマッチアップ(彼我のヒーローの組み合わせ)に際しては、不利な側のプレイヤーが勝とうとするには、緻密な対策の知識や準備が求められる。ゲームの推移に関する適切な評価はもちろんのこと、有意な対策カードの「ここぞ」という切りどころを認識しておく必要もある。ただし、それほどの準備を積んでいたとしても、概して7:3の相性を突破するのは難しい。6:4ですらそうとうに分厚い壁に感じるものだ。そのため、不利な対面を踏んでしまった上級プレイヤーが不思議と晴れやかな表情でいるという、そんなようすはしばしば見られる。うまいこと相手と「噛み合」ったり、「上振れ」たりすることなしには、基本的には負けるものであるという、ある種の「割り切り」をもって相手に臨んでいるわけだ。
さて、わたしはこのゲームを始めていまだ半年未満のプレイヤーである。いまだ対面したことのないヒーローが、まだまだたくさんいる。どんなふうに動いてくるのか、ろくすっぽ知らないヒーローすらもいる。
そんなビギナーが競技的な大会で多少なりとも勝つためには、どんな戦略が必要だろうか? 解いてみたい問題はこれである。これについて以前、ともにFaBに取りくんでいる友人のタムラに相談してみたことがある。

ライフスタイルとプレイスタイル
「まあでも自分の側のヒーローは決まっているわけじゃない? もし仮に自分の側が浮ついてるとしたら、30×30の900通りもの可能性を検討しなきゃいけなかったわけだから、それに比べてよっぽど耐えてる」タムラはつづける。「ざっと数えて30通りの対面に備えればいい。──いや嘘か。いまのメタでプレイアブルなヒーローは20人もいない。まあせいぜい15人ってところじゃないか。つまり15通りの準備をすることだね。余裕でしょ」
いまプレイして勝てる見込みのあるヒーローは15名ほどであるからして、相手になりうるのもまたその程度の種類である。タムラが言っていることの要諦はそこにある。これを真に受ければ、たしかに、準備すべき事項の総数が減りはする。
けれども、仮に15通りだったとしても、その可能性を検討し尽くすほどの可処分時間は、自分にはなかった。家庭と仕事と趣味の両立という点でなかなか厳しく、またカードゲーム以外の趣味で制作・創作活動もしている身としても、十分に時間を取るのがむずかしい。その種のことをモゴモゴとタムラに言った。言っているうち、自分で気がついた。
「相手に付き合わなければいいんだ。対応するような構築にするんじゃなく、自分がやりたいことをやるタイプの構築にしたらいいんだ」
「同意だな。いまの条件ならば、アグロで押しつけていく──主導権を握っていくのがよさそう。そういえば結婚は来月って言ったっけ? ライフスタイルも変わるいまこそ、ミッドレンジ的な考え方を捨てるときだろうな」
TCGにおける基本的な3すくみのじゃんけんというのがある。アグレッシブに相手を攻めたてる〝アグロ〟のデッキと、相手の攻め手をすべて受けとめて守り通す〝コントロール〟デッキと、相手のスタイルに応じた柔軟な押し引きのなかで少しずつ相手にまさっていく〝ミッドレンジ〟のデッキと、3種類ある。しかしFaBにおけるミッドレンジは、初心者目線では難しすぎる。受験勉強になぞらえるなら、対策しなきゃいけない科目が多すぎるのだ。
FaB以前の自分はどうだったか──。わたしはMTGを2年半ほど遊んでいた時期がある。このときに好きだったタイプのデッキは、相手に応じて柔軟に対応できるようなものだった。相手が打ってくるかもしれぬ呪文の一覧をつねに頭に浮かべながら、こちらも呪文を唱えるのだ。MTGに打ち込んでいた頃のわたしは、まるで未熟な魔道士めいて、幾多もの呪文の名前や効果や要求リソースを諳んじられるよう訓練していた。相手も同じ魔道士ならば、目には目を、歯には歯を、呪文には対抗呪文(カウンタースペル)を、というわけだ。
とある呪文カードに付された美しいフレーバーテキストは、まさにここで引用するにうってつけのものだろう。
「現実と空想の境界は本のページのように薄く、そして破けやすい」《物語への没入》
──そんな2年半の魔道士生活を思い出していた。ついに結論が固まり、そしてわたしはタムラに同意した。
「たしかに、ミッドレンジを捨てるときだね。一夜漬けの受験勉強よりもよっぽど、見込みのありそうなデッキはあるはず」

タムラと議論したときよりもさらに、いまのわたしは立場を先鋭化させているかもしれない。最近は真正面からミッドレンジで勝ちきりたいとはほとんどいっさい思わない。どちらかと言えば〝ズルじゃん〟と苦笑いされがちな、噛み合いによって上振れて勝つようなデッキのほうに、いまでは親しみを憶える。それはハイロールなギャンブラー根性だ、と周りから言われることもある。
ギャンブラーだとしても、である。わたしは勝ちたい。少ない可処分時間という条件のなかで、勝つための方法を探りたい。だから誤解を恐れずに言ってしまおう。
なるべくなら、〝ズル〟して勝ちたい。決して〝いかさま〟でなしに。
運の絡む要素を繊細に運用することで、ハイロールな勝ちを得る。これがわたしの考える〝ズル〟の内実だ。練度が伴うとしたら、繊細な運要素の運用においてである。むかしMTGをしていたときに好んでいたプレイスタイルは、完封のために練度を積み上げる必要があった。そしてその過程がとても楽しかった。大量に時間を投じるなかで、負けながら学ぶという経験がとんでもなく楽しく思えた。
でも、ライフスタイルの変化とともに考え方が変わった。練習過程で勝ちが多いほうがいい。勝ちづらいゲームはつづけにくい。いまではそう思う。
ライフスタイルが変われば、ゲームのプレイスタイルも自ずと変わる。
「──当機は着陸態勢に入ります」
機内アナウンスを聞いて、内省を打ちきった。
高度が下がってくるとともに、徐々に身体が汗ばんでくる。ボーイング社製の鉄の外殻ごしにも、目的地の暑さが感じられてくるようだった。例のタッチパネルで情報にアクセスしてみる。
GMT+8の現地時刻で、マニラは2024年2月3日の午後23時にさしかかる頃。目的地の気温は摂氏32℃らしい。いっぽうの東京は0℃付近、天気は雪もようであると、数時間遅れで飛行機内に届いたニュースが報じている。
30℃超の気温差。
遠くの土地に来たことを、嫌でも痛感させられる。

Play the Game, See the World.
カードゲームの愉しさは他人との交流にある。そう言い切った友人がいる。カードを介して見知らぬ相手と出会い、やりとりする、その体験こそが黄金である、というわけだ。このあまりにも論争的な命題について、その当否はひとまず措かせてほしい。
もちろん、デッキ構築の楽しさを退けるつもりはない。あるいは、いままさに引いたそのカードが相手に勝る決定的な一手であった「あの瞬間」を──椅子から咄嗟に尻が浮く一瞬の価値を、否定したいわけでもない。けれど、わたしがいま盛んに取り組んでいるひとつのカードゲームのタイトルは、いささかの勇み足を感じさせもする例の命題を、その名前のうちに含みこんでしまっている。
Flesh and Blood(フレッシュ・アンド・ブラッド)──直訳すればいかにも血なまぐさい闘いを想起させるだろうこのそっけない三つ揃いの英単語は、慣用句的な用法において、ひとつのゲームを介して対面する人間同士のようすを活写したものとなる。すなわち、血の通った剥き身の(フレッシュ・アンド・ブラッド)やりとりを、である。
だからわたしもまた、先の友人に倣ってやはり、こう言ってみたい。
Flesh and Bloodの愉しさの本質は、見知らぬ他人との出会いに宿っている、のではないだろうか。
わたしはこの命題について、あなたを説得する用意がある。FaBの開発スタジオであるLegend Story Studiosのディレクター、James Whiteが折にふれて言うフレーズを引用しよう。
「ゲームをプレイし、世界を見よう(Play the Game, See the world.)」
これはもともとは『Magic: the Gathering』(以下、MTG)のカルチャーから出てきたフレーズだ。MTGは1993年に生まれた米国発のトレーディングカードゲーム(TCG)であり、そもそもTCGという概念の発祥タイトルですらある。集めたカードでデッキを構築したり、対戦したり、交換したりする。そういうゲームの老舗がMTGだ。そのいっぽう、2019年にニュージーランドで開発されたFaBは新興のTCGであり、2024年現在でようやく5年程度の歴史を歩み始めた。
そんなFaBでは、賞金制の公式大会が盛んに開催されている。ほとんど毎週末にイベントの設定があるほどの、それは頻繁さだ。週末にYouTubeを覗いてみれば、世界中の主要都市から配信される大会のもようを観戦できるだろう。2024年の1月にはシンシナティやクイーンズタウンで大会があった。2月はマニラ、ハートフォード、リヴァプール、3月にはフィラデルフィア、ダラス・フォートワース、キール、ロサンゼルスで、4月にはプーケット、アトランタ、ブィドゴシュチュ、サンフランシスコ、バレンシアで、大会が行なわれた。
配信にアクセスしてみる。すると、それぞれのタイムゾーンで、それぞれの言語で、それぞれの気候で、それぞれの文化や習俗で、いろいろな人たちが、ひとつのカードゲームに夢中になっている。見知ったカードについてスペイン語──さっぱりわからない──で話されているのを聞くのは、なんだか楽しい。配信ごしに、プーケット大会の会場で供されていたタイ料理の味を想像してみるのも、やはり小気味よい視聴体験だ。今日の献立はカオマンガイにしようか、そんな気にもなってくる。

異国との近さは、配信にはとどまらない。FaBで遊んでいると、東京に居たとしても、外国人のプレイヤーと対戦する機会はままある。わたしが新宿で出会ったベルナルドは、ポルトガル国籍の旅行者だった。
対戦中にちらっと彼の手もとに目をやると、その腕にはリストバンドが巻かれていた。フェスやイベントなどで参加者に配られるようなやつだ。目で追いかけてみるも、書かれた文字は読めない。
対戦が終わったあとで、腕のものについて水を向けてみた。
「ああ、これかい。このあいだはバルセロナに行っていたんだ」そこでにんまりと笑ったその顔が、いまでも印象に残っている。「結果は散々だったが、あの数日間は──楽しかったな」
彼は前の月に行なわれていた世界選手権大会に出ていたらしく、まるで記念品のように、イベントのリストバンドを身に着けていた。よっぽどFaBを好んでおり、また、旅を楽しんでもいるんだろう。そのことが伝わってきた。
ベルナルドとのマッチにわたしは負けたのだが、相手が世界レベルの強豪ならば仕方がないか。そう思った。
当時のわたしは、このゲームを始めてからまだ半年も経っていなかった。そう自覚して思い直す。
むしろ、強豪からは学ぶにかぎる。そう考えて、感想戦をしてもらった。ゲーム絡みの質問の合間には、いろいろと世間話もできた。東京には何日いるのかとか、三週間ほどの滞在であるという返答とか、この国で好きな食べ物は何かとか、その答えが意外にもチェーン店のカレーだったこととか、そういった話を。
やがて別れ際に、彼が問う。
「ヘイ。明日もきみはここで、店舗大会に出るのかい?」
「うーん」とわたしは応じる。「フィフティ・フィフティ、かな。あなたはどうですか(ハウアバウトユー)?」
「ふむ」と彼も応じる。「フィフティ・フィフティだな」
それ以来、彼とは会っていない。
でも、FaBをつづけていれば、いつかどこかで再会できる予感がある。それもおそらく、どこか異国の地でばったりと出くわすことになるのではないだろうか。なんとなくそんな気がする。そのときに披露するためのお土産話を、いくつももっておきたい。わたしは、強くそう思う。
おそらく再会後のやりとりは、こんな具合になるだろう──。
「きみも世界でゲームをプレイしてきたわけだね」カード越しににやりと笑う、ベルナルドの笑顔が浮かぶ。「それは、どんな旅だった?」
「うーん」とわたしは一拍置くだろう。その一拍は、これまで出会ってきたたくさんの人々を思い起こすために必要な時間だ。「どうやら長い話になりそうです」
彼に向かって話すみたいに、わたしは語ろう。
(つづく)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

