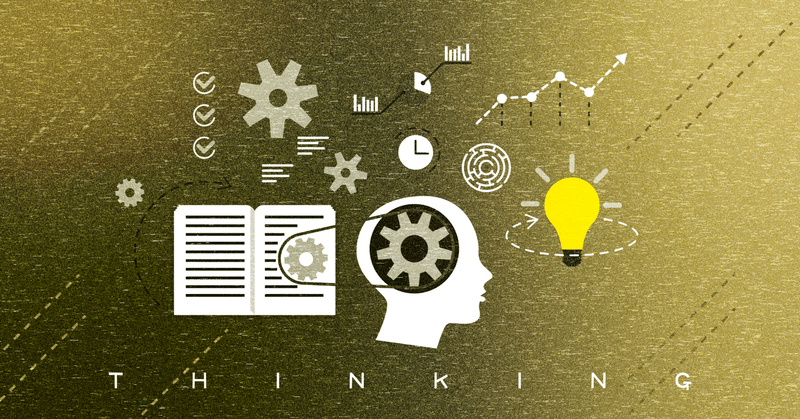
行動経済学をライフハック的に取り入れてみる
ここのところ行動経済学に興味を持って読書(積読…?)をしているのですが、行動経済学での学びを、他人の行動変容のためだけでなく、自分自身の行動変容にも活かすこともできるのではないかと思い、考えたことをメモ書きも兼ねていくつか挙げてみたいと思います。
挙げているものの中には、感覚的だったり経験則としてだったりで「そうだよね」と思えるものも多いのですが、行動経済学の中で実験等で裏付けがされているものであると理解できると、その先の対応策も真剣に講じてみようかという気持ちになりました。できないことも「気合の問題」で片づけるのではなく、そういうメカニズムなのだと知ることができると、回避行動に着実につなげられそうです。
今回参照している書籍はこちら。
ファスト&スロー(システム1とシステム2)- 朝とランチ後に考える仕事をする
人間の脳は、情報処理をする際に2つの思考モードを使い分けていて、それを「システム1 vs システム2」と呼びます。カーネマンは、システム1は直感的で瞬間的な判断であることから「ファスト」、システム2は注意深く考えたり分析したりと時間をかける判断であることから「スロー」と呼びました。
(中略)
一概にシステム2がいい、システム1が悪いというものではないが、システム1で判断してしまうことにより、間違った意思決定につながってしまうことは往々にしてあるため、意識していくべきである。
普段の仕事では、このシステム1(ファスト)で判断できることは少なく、システム2を使わなければ成果が上がらないということが多いと思います。このシステム2は思慮深い分、疲れてしまうのでずっと使い続けることはできないとされています。
より深い思考・アイデアが求められる場面ではシステム2が活性化している状態であることが望ましいのですが、それはどういった状態なのかということを把握しておいて、ある程度意図的にその環境を作り出す必要があります。
「元気な朝が良いだろう」というのは経験則としてもわかるところですが、本書では実験結果として「ランチ後」もシステム2が活発に使用されていることが証明されたと記載されています。朝だけで創造的な仕事を完了できない場合は、ランチ後にも取り組むようスケジュールを立てることで成果が上がりそうです。
また疲れてきたタイミングで休憩をとると、その後にシステム2の働きが回復することも実験から立証されています。1日を通じて成果を出せる状態を維持するために休憩時間も予定として組み込んでしまうことが必要だと思わされます。
解釈レベル理論と計画の誤謬 - 計画は定期的な見直しが不可欠
基本的に人間の意識が向くのは「今」であり、今については「現実的かつ具体的」に考えます。逆に1週間後、1か月後、1年後と考えることが先になるにつれ、思考は抽象的になっていく――。これが「解釈レベル理論」です。
「計画の誤謬(Planning Fallacy)」。「あらゆる計画は所要時間や予算を甘く見積もって計画してしまうがために失敗する」という研究で、多くの残念な実例があります。
人間には「楽観バイアス」があるので、計画を立てているときは「たぶん上手くいくだろう」と思い、さらに「解釈レベル理論」があるために、計画している先のことは抽象的にしか考えられません。
このあたりは感覚的にも頷づけるところです。計画に組み込んだバッファは大抵食い潰されますよね。
本書では対応策として挙げられているのは、全体にかかる時間を予測するのではなく、計画を細かいタスクに分けて個別に所要時間を予測することです。解釈レベル理論によって、将来のことを抽象的に考えてしまいがちなところ、タスクレベルにブレイクダウンして考えることで出来るだけ具体化しようというものです。
加えて、どんなに計画通りに進捗していたとしても、計画は定期的に見直す必要があると考えます。年間計画を組んで最初の数ヶ月は進捗通りいっていたとしても、それは時間的に近い計画が進捗通り進んだだけであって、その先の計画は元々「抽象的かつ楽観的」なものである可能性があるためです。
拡張形成理論(Broaden and Build Theory)- 淡いポジティブな感情を大切にする
前向きな気持ちで働くと効率が上がることはイメージしやすいですが、無意識レベルのポジティブな感情でも効果が上がることが立証されているとのことです。書籍内で具体的に紹介されているものですと、家族写真を仕事場のデスクに飾る、使いやすい上質なペンで契約書にサインする、温かい飲み物を飲んでホッとするなどがありました。(良い文房具を買い揃える「言い訳」になりそうですね。)
私もデスクに趣味のものを飾っていたり、コーヒーを豆から挽いて飲んだりということをしていますが、ポジティブな感情を少しでも高めるために、そうしたものに意識を受けるようにしようと思います。(始業前に好きな音楽を聴くのも効果がありそうです。なんせ無意識レベルのものでも良いわけですから。)
目標勾配効果(Goal Gradient Effect) - 「達成できそう」と思える状態を作り出す
「目標勾配効果」とは、目標に近づくにつれて、人は行動や努力を加速させるという現象を指します。スタンプ10個で景品と交換できるスタンプカードを渡して一つずつスタンプが押されていくことが目に見えてわかると、リピート率が上がっていくということです。(ポイントの数値が上がっていくよりも、目に見えて進捗が見えるスタンプの方が効果が高いようです。)
これを日々のTo-Doリストに置き換えてみると、進捗が一目でわかるように、終わったタスクをTo-Doリストから削除するのではなく、取消線で消して記載自体は残しておく方が、自分を後続の作業に駆り立てるには良いのだと思われます。
また拡張-形成理論との組み合わせで言うと、顧客には単純な10個のスタンプカードを渡すよりも、12個のスタンプが必要だけど最初から2個のスタンプが押されているカードの方が、必要なスタンプの数が々10個であっても、顧客のリピート率が上がることが分かっています。
そうであれば、To-Doリストにおいても、始めの1,2個は簡単なタスクを書いておいて、まずはそれらを完了させることでゴールに近づいている実感を得られると、次のタスクにも前向きに取り組みやすくなるのだと思います。
終わりに
ここまで行動経済学の理論をいくつか具体的なアクションに起こせそうなレベルに引き直してみましたが、他にも契約交渉に活かせるものがたくさんありそうです。(交渉手法という意味でもそうですが、自分自身が間違った意思決定をしてしまわないようにするために自分が陥るバイアスなどを把握しておくことが重要そうだなと考えています)
ですので、これからも学びを深めながら、アウトプットしていこうと思います。もし行動経済学関連でおすすめの書籍がありましたら是非教えてください。
改めて今日の本はこちらでした。最後までご覧いただきありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
