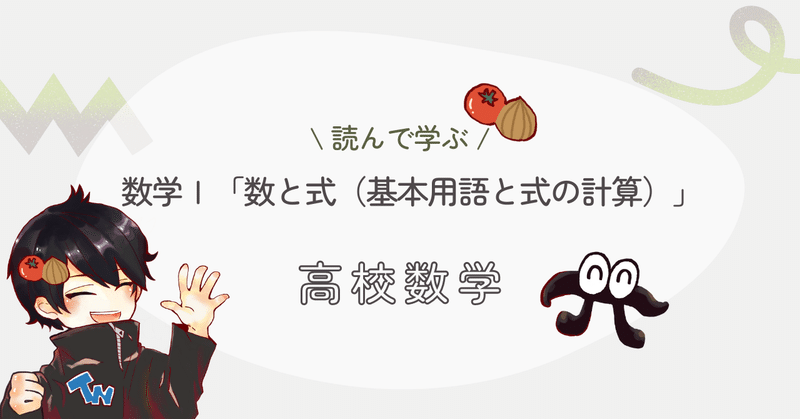
【高校数学】読んで学ぶ数学Ⅰ「数と式(基本用語と式の計算)」【苦手な人集まれ!】
こんにちは。とまねぎです。
今回の記事では、高校数学で
一番最初に学習する単元である
「数と式」について解説します。
その中でも超基本的な内容です。
ほとんどが中学校の復習です。
しかし、甘く見てはいけません。
いつの間にか
「数学が苦手だなあ」
と感じてしまう方は
こうした基本知識が
欠けているかもしれません。
平仮名が読めなかったら
絵本が読めないことと同じように
基礎知識を知らない状態で
数学の問題が解けるわけがありません。
今回の内容は中学校の復習が多いですが、
高校生がつまづく内容も含まれています。
この内容が分からないと
今後の数学の勉強が大変になるので
今のうちから基礎固めをしてください。
それでは、始めていきましょう。
今回の記事の目次は次の通りです。
1.基本用語
1-1.単項式と多項式
では基本的な用語の解説から始めます。

まずは単項式についてです。
「係数」と「次数」
という単語を紹介しました。
これらは区別しておきましょう。
係数は文字の前にいる数であり、
次数はかけ合わされている文字の個数です。

多項式は、
いくつかの単項式を足して
作られる式のことです。
ここで疑問が生まれます。
多項式はたし算だけ??
あれ??ひき算は???
例には「-」を含む
多項式が書かれています。
何故説明には
「足して」
としか書いていないのでしょうか。
それは、「マイナス」
という符号を使うことで、
これまで考えていた
どんなひき算でも
すべて「たし算」で
表現できるからです。
私たちは中学校で負の数を学習しました。
その際
「ひき算を、たし算として考える」
ということを学んでいます。
下のような感じです。

「マイナス」という符号を使って
数を表現してあげることで、
どんなひき算でも
()と「+(たす)」という
2つの記号で式を表現することができます。
だから多項式の説明では
「足して」としか書いてないのですね。
「ひき算はたし算の仲間」というわけです。
ちなみに、数学には
()と「+(たす)」という記号を
省略する習慣があります。
この2つの記号を省略すると、
数と符号(プラスとマイナス)しか
残らない状況になります。
(+2)+(-5)+(-4) が
2-5-4と表現されるということです。
※一番先頭の「プラス」も省略します。
こうなると、

単項式だけが並んでいる状態とも言えます。
多項式を分析するとき、
足し合わせている単項式のことを
単に「項」と呼びます。
このとき、各項は
数の前にある符号を含むことに注意です。
-4xや+3といった感じです。

各項の次数(文字の個数)によって、
「2次の項」や「1次の項」などと
呼び方が変わります。
特に、文字を含まない項のことを
定数項と呼ぶので注意です。

単項式と多項式を合わせて
「整式」と呼びます。
この単語は数学Ⅱになると
見かけるようになると思いますが
現段階では登場回数が控えめです。
ちなみに、単項式は
「多項式の項が1つの式」
として考えることもできるので、
「単項式は多項式の一部」
と考えることもあります。
そうなると、
整式も多項式も全く同じもの
ということになりますね。
この辺りの話は
高校では厳密に説明しないので
「へー」
程度の認識で良いです。
1-2.多項式を見やすく整理するための知識

同類項の計算は中学校でもやったので
多分大丈夫だと思います。
まとめるときは係数を計算しましょう。
1つの式に含まれる文字が少ないときは
同類項の計算は楽なのですが、
複数個の文字が登場すると、
少しややこしくなります。
これについては
「1-3」で紹介しますね。

降べきの順は超基本です。
この並べ方が式を分析する上で
一番分かりやすいのです。
一方で、昇べきの順は
ほとんど見られません。
たまーーーに使いますが、
知らない高校生が多いです。
降べきの順であれ、昇べきの順であれ
最初は多項式中の各項の次数を確認して
丁寧に並べ替えましょう。

単項式にも次数が存在したように
多項式についても次数が存在します。
単項式は多項式の一部である。
そんな話をしましたよね。
だとしたら単項式にだって
次数がないとおかしいです。
各項を確認して
一番高い次数の値が
その多項式の「次数」となります。

高校ではあまり紹介する事はありませんが、
こんなものも紹介しておきます。
多項式において、
各項どの項も同じ次数のとき、
その多項式を
「〇次の同次式」
と言います。
「何に使うのか」と聞かれると
私も困ってしまいますが、
一応、教養として紹介しますね。
1-3.着目する文字によって変化する次数と係数
1つの整式に含まれる文字の個数は
1つとは限りません。
当然、1つの式の中に
文字が複数個存在することもあります。
そのとき、私たちは
「ある文字に着目して式を分析する」
必要が出てきます。
この項目では単項式と多項式
それぞれにおいて
文字が複数個含まれている時
どのように式を見るべきなのか
お伝えできたらと思います。

まずは単項式です。
(1)はどの文字にも着目しないパターンです。
今回はxとyどちらも登場していますが、
その2つとも文字として扱います。
なので次数は3、係数は7となります。
一方で、(2)では
「xに着目」と()内に書いてありますね。
これは
「この式はxを文字として扱って、
それ以外は全て数として扱ってね」
という意味です。
x以外は全て数。
つまりyも数ということです。
よって、(2)では
次数が2、係数が2yとなります。
xに着目するなら、
2xyよりも2yxの方が正しいです。
何故なら、xが文字で、
それ以外は数として扱うからです。
このときyも数ですから、
文字であるxの前に置くというわけです。
これはyに着目しても
全く同様に考えることができます。

さて、続いて多項式です。
こちらも(1)は
特に文字に着目する指定をしていません。
なので、降べきの順に並べるときも
シンプルに次数の高い項から
順番に並べればよいです。
同じ次数の項はどの順で
並べても良いです。
(1)の場合は
定数項が+3、次数が3となります。

さて問題は
文字に着目したときです。
(2)ではxに着目しています。
基本的な考え方は同じです。
「xだけを文字として扱い、
その他は全て数として扱う」
なので、各項にxが何個いるのか
1つずつ確認して、
降べきの順に並べるとします。
降べきの順に並べることができたら
可能な範囲で同類項をまとめます。
今回(2)では
xが1次の項と2次の項が
1つしかありません。
一方でxが0次の項が
2つあります。
この2つの項は
文字であるxが存在しない項、
つまり「定数項」です。
定数項は定数項たち同士
分かりやすくまとめておきましょう。
そのために、2つの定数項を
()でまとめておきました。
()なんて無くても
定数項だと分かりやすいですが、
つけることで分かりやすく整理できます。
ちなみに、
(2)の次数は2となります。

(3)はaに着目する問題です。
着目する文字が変わると、
式の見え方は大きく変化します。
今回はaの1次の項が
合計で2個あります。
今回、これら2つの項は
同類項として扱います。
なので、同類項を()で
分かりやすくまとめましょう。
同類項の計算は
「係数部分のたし算」
で計算することができます。
同類項をまとめる際には
単に()でまとめるのではなくて、
文字(今回はa)でくくることで、
係数部分を計算しているような表現をしましょう。
定数項も分かりやすく
()でまとめておくと良いです。
今回、文字であるaの
最高次数は1なので、
多項式全体は
「aについての1次式」
となります。
2.式の計算
2-1.多項式の加法と減法
改めて、加法とはたし算
減法とはひき算のことです。

減法の場合は画像のように
「マイナス」を分配法則して
計算するやり方が一般的ですが

ひっ算のように計算する方法も
分かりやすいので紹介しておきます。
具体的にもう1つ例を紹介します。

ひっ算の形で計算するときは
同類項を縦に並べると良いです。
今回で言うと、画像のように
xの1次の項はスペースを空けましょう。
計算がグッと楽になります。
2-2.指数法則
こちらも中学校で学習する内容です。
実は数学Ⅱに入ると、
指数法則は面白くなってきます。
今回は計算法則を紹介しましょう。

まずは用語の説明を載せておきます。
注意しなければならないのは
「累乗」という単語ですね。
これは中学校では登場しないです。
累乗とは、「何かの〇乗」といった
指数を用いた表現をしている数を
まとめた呼び名です。
画像右下の図のイメージです。
画像の例で言うと、aのような
何回もかけている元となる数を
「底」と言います。
なので、累乗とは
「指数を使って表現された
底が等しい数たち」のことです。

では指数法則の説明に入ります。
上の画像にまとめた3つの法則を
順番に見ていきましょう。

まずはこちら。
よくある間違いを赤字で書きました。
指数で表現されているものは
「同じ数が何個かけられているか」
です。
その意味を冷静に考えると
きっとこの法則は
「当たり前じゃん」
と感じると思います。

一方で、1つ目に紹介した法則と
区別しておかなければならないものが
この2つ目の法則です。
ここで重要なことは
「()はまとまりを表す」
ということです。
この認識が甘いことが原因で
1つ目に紹介した法則との
区別がつかない生徒が多いです。
()に指数がついている時は
()の中身全体を何個もかけている
という認識を強く持ちましょう。

3つ目は間違える人は少ないです。
()の意味を理解していれば
そんなに難しくないと思います。
とにかく
先に紹介した1つ目と2つ目の法則を
正しく理解しておくことが大切です。
3.まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回はこれから数学を勉強するために必要な
超基本的な知識を紹介しました。
高校で新しく登場した内容は
「ある文字に着目して多項式を考える」
というものでしたね。
今後数学を勉強していく中で
1つの文字に着目して式を整えて、
計算を進めていくことが増えます。
次に投稿する記事にさっそく登場するので
「基礎知識だから」と甘く見ないで
しっかり理解を深めておきましょう。
それでは、本日はここまでとします。
お相手はとまねぎでした。
最後に本記事で使用したノートと
本記事を参考に作成した動画解説を
掲載しておきます。
動画についてはまだ作成の途中ですので、
完成次第URLを投稿します。
しばらくお待ちください(2024年5月18日現在)
ここから先は
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
