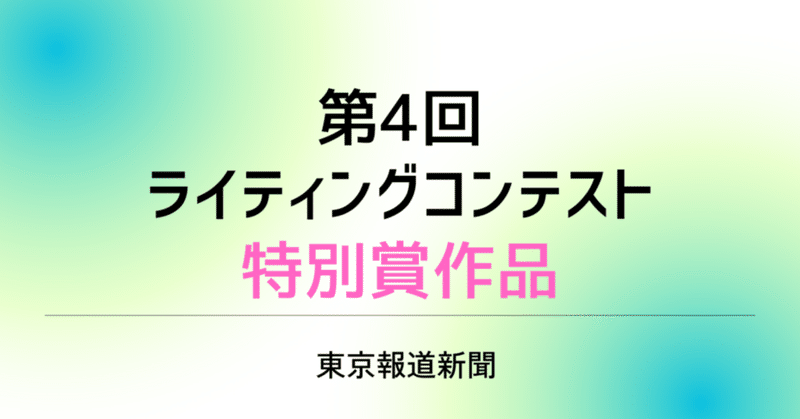
AIに負ける気がしない図書館の日常
図書館で働いていると、本当に様々な人がやってくる。老若男女、色とりどりだが、やはりご年配の方が割合に少し多い。
AIが注目され始めたとき、私はまだ学生だった。自動翻訳や画像認識、ある程度の未来予測までできるというのだから、大したものである。そんなAIに対して危惧していることと言えば、やはり人間が奪われてしまう仕事の数々だろう。
当時の国語の担任はこう言った。
「数学の教師というのは将来なくなる可能性があります。ただ、国語はなくならない」
自慢ではなく、単純に現実を教えてくれたのだろう。私も同意だった。予め答えが決まっている数学や暗記科目は人工知能でこなせるだろうが、採点者の裁量が少しでも関与する国語はやはり人の感情をもってして成り立つ分野だ。とことん文系でよかったな、と安堵したのを覚えている。
そうして大人になった私も、文系の鏡かの如く公共図書館で司書として働いているわけだが、しみじみ思うことがある。果たしてAIはレファレンスという業務をこなせるだろうか、と。
レファレンスというのは、利用者の求める答えを導き出すために資料を検索し、根拠と共に回答を与える作業のことである。わかりやすく言うと、利用者の「あれなんだっけ」を探してあげる作業だ。
一見すると、答えの決まっていることを導き出すのだからAI向きのように思われるが、相手は数式ではない、お年寄りだ。ヨロヨロとやってきたおじいちゃん(おばあちゃん)が開口一番、こう言うのだ。
「昨晩だったか今朝だったか、ラジオであの人が紹介していた本を読みたくてね」
いつ、誰が、どのラジオで紹介したどの本なのか。ヒントが皆無であるが、ここから回答を導き出さなくてはならない。
ラジオを聞いたのは寝る前だったか起きた後だったか、話していたのは男性だったか女性だったか、紹介の中で出てきたキーワードは何か無いか。利用者と会話を重ねていくことで一つ一つ、答えへの糸口を見つけていく。
そう、会話。レファレンスに必要なのは会話なのだ。相手の物忘れが激しかろうが、話し方が下手だろうが関係ない。こちらから歩み寄って、絡まった糸を少しずつ解いていく。途方もなく地味な作業である。たまに話のわからない相手が来ると本当に泣きたくなる。
しかし、それで答えにたどり着いたときの爽快感と達成感はひとしおでもある。AIには譲りたくない感覚。譲ったところで感情を持ち合わせていなければ何の意味もなさない無機物だ、「喜び」や「面白さ」なんてものは。
きっとAIで未来は効率よくなる。セルフレジが増えたように、デパートの案内係もオフィスの事務関係も、続々とAIが替わって担うようになるだろう。人件費は削減されるし、ミスによるタイムロスは減るし、万々歳だ。
しかし、この世は効率だけで回れるほど単純ではない。時には時間なんて構ってられないほど考え込んで、誰かと思いを共有して話し込んで、そうして何かが生み出されていく。これまでのクリエイティブもそうして生まれてきたはずだ。人間から「感情」や「思考」が消え失せない限り、AIが人を支配することはない。なぜなら人間は、AIが得意とする最適解だけを常に追い求めているわけではないからである。
少し重くなってきたので話を戻そう。図書館で勤めていると、様々な人が来る。基本的には、大体の人が本を求めに来ている。基本的には、ということはもちろん例外も稀にいる。
先日、フラリとやってきたご老人が眉間にシワを寄せながら自身の携帯画面を見つめ、しばらくしてカウンターにいた私にこう聞いた。
「今は何時かな」
「15時42分、ですね」
「そうかい、ありがとう」
そう言って出ていった。時間が知りたかっただけのようだ。携帯を持っていたのに。遠視で見えなかったのかな。
いや、しかし、図書館というのはそういう人のために割と目立つところに時計が設置してある。それに見向きもせず、私に聞いてきたということは、時計の針よりも私が見れるパソコンのデジタル時計のほうが彼にとっては信用に値したのかもしれない。
いやいや、しかし、彼の手首には、それはそれは立派な腕時計さえ着いていた。針が狂っていたのだろうか。それでも外さないのは息子か孫にもらったからなのかな。
謎は深まるばかりである。優秀な人工知能、AI様、貴方にこの謎が解けますか。むしろ謎なんて解けないままのほうがいいというこの面白さが、貴方にわかるのでしょうか。
ライター:皐月
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
