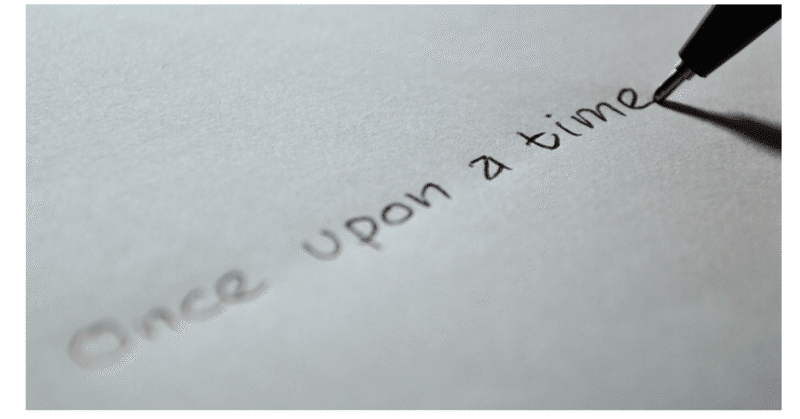
口先ひとつで生き抜いて、中国古代の恵施と「弁者12事」(1)
Ⅰ.
創造の第一条件は反抗であり、
反抗は創造の源である
結局は、暴力装置で守られた官僚制度、
学者と作家の間には近くても深い川があった
古代から、中国では教育ばかりでなく政治経済の方面にも絶大な影響を持ってきた儒教に対して、唯一対抗してきた老荘思想。
老荘思想の影響なしには文学芸術は語れないほどでも、なぜか表看板の儒教者である江戸時代や現代の教育者からあまり喜ばれなかった。
初めに政治経済と教育ありとする統治者から、生活に余裕があってからね、と老荘思想を紹介するのを控えるのが常だったし、いまでも儒教と比べて否定的に見られがちである。
でも江戸時代もそうであったように現代でも「知識人」の間では表面では儒教、内面で老荘思想を携えているのが多い。
以前、帝国主義を掲げて植民地を展開していた欧米各国に反対して、「左翼主義者」たちは表面はマルクス主義を掲げても、老荘思想と同じようにいまでも否定的に見られるアナキズムを内面に携えている知識人が多かったのに似ていた。
老荘思想と同じく「自由」を標榜するアナキズムは、20世紀になってピカソなど破壊と創造の芸術を撒き散らしていった。
このように老荘思想とアナキズムは、隠者とかニヒリズムとかマイナス言葉を与えて疎んじられ、教育者や政治家から見てもっとも知られてほしくない存在でも、文学芸術に絶大な影響を与えていた。
われわれの国の中では素直な子供や国民になってほしいのに、「変な知恵」を与えないでください、と社会を導く立派な政治家や経済人、教育者らは切に願っていた。
( この老荘思想は、統治者にすがって生きる儒教らの政治経済や教育に対するアンチテーゼとして、古代の秦の始皇帝以前、周の後期に現れた。
ちょうどその頃、地球の裏側の西洋でも同じように為政者に哲人政治や教育を説きたがるプラトンやアリストテレスに対して、アンチテーゼとしてエピキュリアンたちが、古代のアレキサンダー大王亡き後のヘレニズム時代に現れ、人生は食べて道徳を説くだけでない、いかに「幸福」に生きるかを願った。
それゆえ政治と教育を重んじる為政者から、また正しき道を説くローマ教皇から禁書扱いにされ、今でも巷では快楽主義の名でマイナスイメージがささやかれている。
誰でもが安全で幸福な生活をしたいと願い、常に世の中にあらわれて補完しあう、政治と文学、われわれと私、社会と個人。われわれの秩序ある平和な生活と満たされない私の心を埋める幸福の問題。
天からの恵みの雨と、大地の塩が対峙するような思考が生まれ、けっして茶番な言葉ではなかった。
いまも東洋や西洋では儒教やプラトン、アリストテレスたちが政治経済人や学者に支持されて、社会や学校で持てはやされるいっぽうで、そんなものに「満たされない気持ち」を抱いているのが多い文学者や芸術家たちは、老荘思想とエピキュリアンの思想に救いを求めた。むしろ東洋と西洋の文学芸術は、この老荘思想とエピキュリアンの思想なしには考えられない。
老荘思想の「自由」、エピキュリアンたちの「幸福」。
東や西に時代を同じくして孔子やソクラテスの弟子たちがあらわれ、「政治経済人及び教育者」に支持され、同様に対抗するかのように作家芸術家に支持された老子と荘子や、エピクロスとルクレティウスがあらわれたのは単なる偶然ではなかった。いつしか「権威」になってしまったものに対する「自由」の闘いでもあった。
あたかも明治維新ができ政治経済で体制を整え、教育で学者が思想固めしても、それだけでは人々は満足できやしない。
勝海舟に不満をもらしていた福沢諭吉は、学問のススメを進めても、後輩の坪内逍遥には「学者」にあるまじき小説家行為をたしなめたのは単に世代交代だけでなかった、時代が求めていた。
そんなふうに歴史の文献を読めば、東洋も西洋も古代から、偉人、エリート、才人のサイクルで回っていたようだ。偉人が国家をつくり、名門エリートが体制つくりをして、才人がほころびを立て直した。
国家ばかりでなく、「会社企業」でも苦労人が創業したら会社のブランドをあげるためにも外ヅラよく、創造性がなくても予習復習が得意なエリートを採用して、基礎固めをするのに似ていた。
中国では長い戦乱の経験から、暴力でなく、隋・唐の時代に「科挙制度」ができあがり立身出世が行われ、ヨーロッパでもフランス革命後はエリート官僚が登場し、明治維新以後の日本でもようやくハッキリ目に見えてきたように、ペーパー試験でなり上がる官僚制度が出きあがってくる。
学問を志し、孔子やプラトンを学んでエリートになっても、単なるペーパー試験の材料でしかなく、いつしか出世して楽な生活をするための手段でしかないのは、古今東西、人間の考えることは同じだった。
でも同じことを学んできても異議を唱えて、「人間解放」の復活をめざすのもまた同じ人間だった。
時は大化の改新の頃に中国で始まった、ペーパー試験の科挙という名の官僚制度。つい最近の20世紀初頭まで続いて、中国では時代の国家体制が壊れたら、また作り直されて、現在の日本においてもこれから「無人支配」という名の機構のなかで、実際を統治する官僚制度が永遠に続くんだろうか 。
そんな明治維新や、戦後すぐの焼け野原から立ちあがって、ペーパー試験で成りあがった官僚エリートも、やがて孫世代の三世の頃にでもなれば、政治家と同じように、内の人間は変わっても外見の学歴制度や官僚制は世襲化され、そのワンパターンな人物は凡庸になるのはしかたなかった )
かつてプロ野球の巨人のように、入団生え抜きの選手が活躍したのは遠い過去の夢物語で、東大「入試入学」の生え抜きの人が活躍するのも、公務員関係者以外で遠い遠い過去の夢物語になった、
初期の文芸ならまだしも、外国文学を賢く勉強して、... と言った、彼はその時、などと英文解釈みたいな、夏目漱石の小説は大いに参考になっても、現代ではどうかな。漱石先生、ごめんなさい。
また幕府の将軍家兵法指南役、柳生新陰流の初期メンバーは努力もして優れていた、けれども権威や肩書きは立派になったのに、やがて独創的で実力もある諸藩や千葉道場などの町道場に剣の道をゆずったのは、時代と分野にかぎらずどこでも見られるパターン。
そんな感じで、現在、新鮮で独創的な東大卒の後輩作家は果たしてどれだけいるのか、教師や評論家ばかりで、いても出版編集者が関の山でも、テレビ局では報道部も、芸能部と同様にセンスが必要です。
学者や科学者の間ではノーベル賞はもちろん、有名な賞の話は禁句で、それでも国からヒト百倍の大学補助金を貰って、甘やかされているのでそうもいかない、なりふり構わないで他の大学から大学院に入れたり、研究者にしたりして東大関係者にする始末。
企業のブランドを上げるために東大卒を入れても、小さい企業ならまだしも、プライドばかり高くて仕事できるとは限らないし、さっき言ったように仕事のセンスは勉強で補えないセンスが必要でもありますから、他の社員と軋轢するのが精一杯かもね。勉強するIQは高くても、創造するIQ、つまりEQを怠ったせいでしょう、お気の毒さま 。
つい、前置きがすっかり長くなってしまった。現在でも単なる口で稼ぐ教師や評論家に似ているような、弁論家やソフィストたちが昔にもいて、相前後して儒教やソクラテスがあらわれるきっかけをつくった。
その無意味ともとらえられがちな古代中国の弁論家の中に、次回紹介する荘子の友人で恵施なる男がいた。現在でもときおり展開されているような、恵施の奇妙な論理をゆっくり解説します。とてもおもしろいので読んでください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
