
Obbligato:社内報に見る「東映の支柱」⑦
「美粧係さん」(社内報『とうえい』1959年11月20日発行第23号)
前回に引き続き「東映の支柱」をお届けいたします。今回は、「美粧係さん」です。1959年の記事で、東映時代劇映画全盛期、第二東映を設立する直前、前年に誕生した京都撮影所俳優会館での取材です。



時代劇は歌舞伎にそのルーツを持っています。1908年、牧野省三が日本で初めての歴史映画『本能寺合戦』を監督して以来、講談や歌舞伎のストーリーを原作として、歌舞伎の演技演出を元にした歴史映画は旧劇と呼ばれていました。
まもなく、近代演劇や西洋映画の影響を受けた映画人たちは、歌舞伎演出様式がベースの型となっている旧劇の改革を試みます。彼らは、映画作りにリアリズムという概念を注入し、そこからよりリアルな姿と動きを表現する時代劇が誕生しました。
歌舞伎では、舞台用のかつらを結い上げ、役者の頭に乗せて整える床山と呼ばれる担当者がおり、化粧は役者自らが鏡に向かっておこなっていました。旧劇では、かつらや化粧も歌舞伎をそのまま引き継ぎます。
やがて、時代劇が誕生、クローズアップなどの技法が取り入れられるようになると顔が大きく映し出され、観客にとって歌舞伎のかつらや白粉(おしろい)白塗りの化粧のままでは不自然に感じるようになってきました。
まず始めに、時代劇化粧の改革が始まります。
新派劇や新劇などが西洋の化粧法を取り入れたこと、その後、ヘンリー小谷やトーマス栗原などアメリカ帰りの監督たちが西洋の化粧品を持ち込み、東京の現代劇映画の女優たちにドーランが一気に広がったこと、そして、関東大震災で東京から映画人が京都に移って来たことなどによって、俳優の化粧も大きな影響を受け、化粧の素材、化粧法が変わりました。すなわち、時代劇誕生とともに、俳優の化粧は、これまでの歌舞伎役者の白粉(おしろい)や砥粉(とのこ)の化粧からドーランを使った化粧に変わって行ったのです。
しかし、俳優自らが化粧を行うことは変わらず、特に大物時代劇俳優は、今でも歌舞伎役者と同様、まずは自身で化粧をしています。
脇役や大部屋の俳優たちも自分で各々勝手に化粧をしていましたが、監督の思うところと異なる化粧をすることもままあり、作品全体の化粧を統一する必要がおこりました。
そこで、監督からの要望に応えるべく、主に床山の中から、化粧専門のスタッフ、美粧担当が選ばれ、特殊な化粧や、俳優メイクの仕上げ、調整などを担当して行きます。
1926年に「山田かつら店」を設立し日活大将軍撮影所で床山として働き始めたかつら師山田順次郎は、1930年、日活太秦撮影所の溝口健二監督作品『唐人お吉』で、山本嘉一演じるハリスの、より自然に見えるひげのメイクを工夫し、シルクのチュールに植毛したひげを作りました。このリアルなひげに溝口、山本は驚き、ここから山田は俳優の化粧も徐々に手伝うようになります。1933年、山田は京都を離れ、東京のPCL撮影所、翌年日活多摩川撮影所で現代劇を中心に床山やメイクの仕事を行いました。
山田の後、メ-キャップの専門家となった二人の兄弟がいます。日活で尾上松之助主演映画を監督し、松之助の死後、所長秘書や制作総務部長を務めた小林弥六の二人の息子です。
日活太秦背景部出身の兄、小林昌典は戦後間もなく大映京都撮影所でメ-キャップの専門家として、稲垣浩監督『おかぐら兄弟』から始まり、溝口健二監督『祇園囃子』『新・平家物語』、衣笠貞之助監督『新・平家物語 義仲をめぐる三人の女』、三隈研二監督『大魔神』シリーズ、増村保造監督『華岡青洲の妻』などで活躍し、大映から宝塚映画などにも派遣されました。
日活大将軍で子役として活動していた弟、小林重夫は、旧制中学卒業後、父の意向で山田に師事しPCL、東宝映画で床山の修業を積みます。大映京都撮影所で稲垣浩監督『獨眼龍正宗』などを担当し、戦後、東横映画京都撮影所が誕生すると、そこで美粧係長に就任。その後、東横映画を離れ、東宝、新東宝、宝塚映画、松竹などで活躍しました。黒澤明監督『酔いどれ天使』『用心棒』『どん底』、高峰秀子の要請を受け、松竹で木下恵介監督『笛吹川』、松山善三監督『山河あり』などに参加、近代映画協会の新藤兼人監督『鬼婆』『薮の中の黒猫』他、様々な監督や俳優から頼られた。国際的スター三船敏郎からの信頼も厚く、最期は三船プロダクションでの仕事の最中に倒れ57歳の若さで逝去しました。
そして、関東大震災後、映画用かつらとして現在も使われている生え際がより自然なネットかつらの開発が始まります。
歌舞伎では今でも羽二重に植毛する舞台用かつらが使われていますが、新派劇用のかつらを作る「岡米」の岡田米蔵は、震災で店が被災し一念発起、そこからかつらの生え際をより自然に見せるためにネットに植毛するかつらを開発しました。そして、1930年代に入り新派のスター花柳章太郎の舞台で使用すると大変な評判を呼び、「岡米」のかつらは花嫁や芸妓のかつらに引っ張りだことなります。
同じ頃、映画界でも日活太秦の俳優久米譲がより自然なかつらの研究を進め、亀甲紗(チュール)に植毛したかつらを開発。片岡千恵蔵プロダクションで採用されると評判を呼び、1932年頃には他撮影所でもネットかつらが使われるようになりました。
また、ネットかつらにつきましては、帝劇がオペラ指導に招いたジョヴァンニ・ヴィットーリオ・ローシーが、1926年頃に連れて来たメーキャップ師がネットかつらを使っておりそれを見習ったという説もあります。
歌舞伎のかつらとは異なる映画用ネットかつらの起源はいくつかの説があり、はっきりとはしませんが、スチル写真から見ても1932年ごろには原型が普及していたようです。
こうして戦前に、現在の時代劇用ネットかつらが生まれ、戦後の時代劇ブームのなかで進化して行きました。
時代劇映画全盛の頃は色が濃かったドーランも、撮影機材の進化で画面が明るく高精細になり、時代劇でもナチュラルな化粧が求められるようになったため現代ではかなり色が薄くなっています。

かつらも自毛を生かした「七分かつら」が増えました。かつてリアルを旗印にした映像界は、より「ナチュラル」に見える創作を目指しています。
昔よりはナチュラルになったとはいえ、東映お得意の勧善懲悪の時代劇では、今でも悪役はそれとわかるように目と眉の上にアイシャドーを入れ、また、主役は目張りやアイラインを入れたり、眉を上にあげたりすることで、きりりとした顔に仕上げています。善悪のメイクは目元がポイントなのです。
昔の二枚目は化粧を落とすと素顔は全く違うことも多く、イケメンは美粧スタッフの時代劇メイクが作り上げていたとも言えます。噂では、時代劇全盛の頃、イケメンで有名な人気時代劇俳優がメイクを落とした普段着の姿で撮影所に入ろうとした時に、受付で止められたという話もまことしやかに流れています。
映画村の「時代劇扮装(ふんそう)の館」は扮装だけでなく、オプションで昔風の時代劇メイクを施しています。興味のある方は、映画村にお越しいただき、昔風のきりっとしたイケメン侍に変身してみられてはいかがでしょうか。
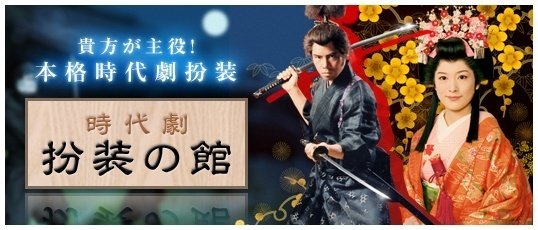
東映京都撮影所の東映俳優会館は、昨年放送の、NHKの朝の連続連続テレビ小説『カムカムエヴリバディ』にて条映映画村として画面に登場いたしました。

その1階に、二つの部屋があります。床山と化粧を施して男性の頭にかつらをのせる美粧の部屋。そして女性用のかつらを結い上げて頭にのせる結髪(けっぱつ)の部屋です。


時代劇映画の全盛期、二つの部屋の頭は林政信。結髪部屋は林の下で桜井文子を筆頭に女性スタッフが頑張っていました。
現在、二つの部屋を率いるのは東和美粧の大村弘二社長です。現在57歳の大村さんは18歳で同社に入り、林の弟子だった当時の社長・鳥居清一さんの下で修業しました。つまり林の孫弟子にあたります。
大村さんは、舞台のかつらやメイクを経験するために、およそ4年間にわたって山崎かつらに出向し、大御所たちの舞台に付くことで様々なことを学びました。
東和美粧に戻ってからも、里見浩太朗や北大路欣也などベテラン俳優との仕事を通じ、これまで京都の撮影所の先人たちが培ってきた、かつらやメイクの知識や技術を教授され、身に着けることができたそうです。
2022年、京都市は、『①映画を「見る人」の裾野を広げる。②映画を「支える人」の仕事を広く伝える。③映画を「作る人」を次世代に繋ぐ。』をコンセプトに、京都映画賞を創設しました。その栄誉ある第1回優秀スタッフ賞を大村弘二さんが受賞しました。
大村さんは、これもひとえに鳥居さん、里見さん、北大路さんなど諸先輩方の指導のおかげと語っています。
受賞、おめでとうございます!

東映俳優会館1階の二つの部屋は、125年に渡る京都の時代劇が育んできた伝統技術を使って、数多くの俳優たちを、老若男女、美人美男子から怪物にまで仕立て上げてきた「魔法の部屋」です。
