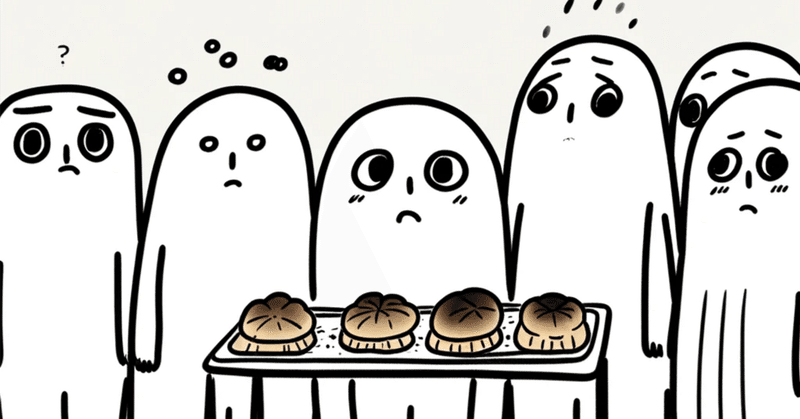
#120 フィナンシェ利用3つの批判(①ダサい②価格煽り③アート無関係)に対する一定の同意と反駁。
本コラムは、音声配信プラットフォーム・Voicyでお届けした内容をテキスト用に整形しています。AIによる編集・校正が入ってます。最後にVoicyリンクもあります。テキストでサクッと読みたい方に。
FiNANCiE(以下フィナンシェ)について、感じていることをツラツラと。
※長いです。適当に読み飛ばして下さい。
前提として、僕たちのNFTプロジェクト「ZUTTO MAMORU」もフィナンシェでのトークン発行に動いています。今週中には新しい報告ができるかも。
フィナンシェのサービス自体(トークンを使ったクラウドファンディングサービス)に対する批判は聞こえてきません。たくさんの人が素晴らしいと感じているし、僕もその一人。だからこそ、トークン発行を申し込んだわけです。
批判の矛先はプロジェクトリーダーに向けられたもので、その声は以下3つに分けられるかなと。
その①:「ダサい」
その②:「価格煽り」
その③:「アート無関係」
同意するところはありつつ、僕もフィナンシェを使おうとしている立場です。反駁(はんばく)できるところは、めちゃんこ、ある!
批判の声その①「ダサい」から順に、思うところを書いていきます。
———
<批判の声①「ダサい」について>
まず、現状把握。
イケハヤさんが「フィナンシェすげえ!」とその魅力を拡め、多くのNFTプロジェクトがフィナンシェでのトークン発行に乗り出したー、これが現状。間違いない。
一部には、イケハヤさんを先頭にフィナンシェに集まるプロジェクトを、”親ガモについていく子ガモのよう”と見る方もいるかもしれません。
イケハヤさんがフィナンシェの利用を推し進めて以降、多くのプロジェクトがこれに続いています(ずとまもも!)。この様子を見て、「ダセぇな」と感じる人がいるようです。
フィナンシェは以前から存在するサービスで、僕自身は『NFTの教科書』を読んで、初めて知りました。
また、イケハヤさんに先駆けてA.E.Bプロジェクトをフィナンシェで発行したブンさんと1年程前に”フィナンシェトーク”をさせてもらったことがありましたが、当時は「ZUTTO MAMORU」にどう組み込めるか、具体的なイメージが湧きませんでした。
フィナンシェを”スルー”してきた過去がある中で、今回イケハヤさんが火をつけて、自分もそこに乗ろうとしているので、自分でも「現金だな」って思います(笑)。
インフルエンサーに触発されて、「フィナンシェ!フィナンシェ!」ってピーチクパーチク言っている姿、僕もそうなんですけども、言っている姿が「ダセぇ」っていうのはすごく分かる。
でも分かった上で、やってるんですよ。皆さん同じだと思います。
ヘタなプライドにしがみついている余裕はなくて、本当は「ZUTTO MAMORU」もNFTだけで成り立てばと願いますが、現実問題として、NFTだけでプロジェクトの生計を立てるのはムリゲーです。(絶対、無理!!)
NFTが好きか嫌いかの問題ではなく、現実の直視です。
NFTだけでは難しいなら、他の可能性も探るべきだと。今は、そのフィナンシェに大きなチャンスがある。そのチャンスに飛び込むことは、プライドなんぞ、かなぐり捨てる意義があると考えます。
——
<批判の声②「価格煽り」について>
批判の声の2つ目は、「価格煽り」について。
トークン価格が大幅に上昇した(「する」の期待煽りも含め)という話で、人々を惹きつけるやり方。
いわば”カネで釣る”見え方に、「あらやだ、お下品ねホホ…」と嫌悪感を持つ人が少なくないようです。
この点に関しては、僕も同意見です。少々「下品」だと思います。しかし、これはイケハヤさんならではの、ある種の「職人技」だと思っています。
トークン価格が上がることは、プロジェクトサイドやホルダーさんにとって嬉しいことです。
例えば、Appleの株を持っている人で、その株価が上昇することに喜ばない人はいないでしょう。同じことだと思います。価格が上がると、基本的にみ〜んな嬉しいものです。
価格を上げるための努力は、プロジェクトリーダーにとって求められる振る舞いです(マーケットに全く無関心なトークン発行者が、信用を得られるとは考えられません)。
と同時に、特殊な「スキル」が求められるものとも思います。このスキルを持たずにヘタに価格煽りすると、大ケガをする。
僕自身は、この特殊スキルを持っていません。イケハヤさんのようには、できない。お金が絡む話なので、自分のメンタルが病られないような手法を見つけていくつもりです。
ただ、仮にもし僕がイケハヤさんのようなパワーや影響力、そしてこの特殊スキルを持っていたら、ガンガン煽りますよ(笑)。
「100倍になった!次は1000倍だ!Buy ZUTOMAMO!!」とガンガンあおる(笑)。だけど、自分にはそんなエネルギーはない。
こういった話をしていて思い出すのは、あるイソップ童話です。『とれないブドウを酸っぱいといったキツネ』の話です。
飲茶(ヤムチャ)さんが書かれた「史上最強の哲学入門」という本があって、その中でニーチェの哲学を説明するチャプターに登場します。
ニーチェは、宗教や道徳、何かにすがることを「弱者のルサンチマン」と言い放ったマッチョな哲学者です。このキツネの話は、ニーチェの哲学を説明する中で引用されています。
彼らはイソップ童話で言うところの「とれないブドウを酸っぱいと言ったキツネ」と同じである。そのキツネは本当はブドウが欲しくてたまらなかった。
ブドウが食べられるとしたら間違いなく食べた。しかし、ブドウは食べられない高さのところにあったため、彼は自分の都合でブドウの価値を貶める。
「あのブドウは酸っぱいに違いない。ああ食べなくてよかった」
このキツネがまっすぐに、人生を生きていないことは明らかである。そしてそのうち同じようなキツネが集まってきて、ブドウを欲しがらないことはいいことだといったそういう道徳や教義を打ち立て始める。
彼らは、ずっと心の中で取れないブドウへの恨み(ルサンチマン)を抱きながら、ブドウを欲しがらない無欲な自分を誇りに思うのだ。
そしてもし、そこに頑張って飛び上がりうまいことブドウを手に入れたキツネを見たら、彼らは「なんて意地汚い」と見下し、「別にブドウだけが人生じゃないのに、あんなに必死になっちゃってさ(笑)、自分ならそんなもの欲しがったりしないね(笑)」という歪んだ価値観を持ち出して、内面的に勝利することで、恨みを晴らし自分を慰めるのである。
シビレますよね…。
目が痛い人もいるんじゃないですか?
僕は痛い、「目がぁ!目がぁ!」です。
もう少し、シビレましょう。
ニーチェはこういった歪んだ人生を、ただの欺瞞に過ぎないと断言する。本当は彼らだって、ブドウを得るために必死になって、飛び上がってもよかったのだ。自分の限界を超えて戦ってもよかったのだ。だが、それをしない。
失敗が怖いからだ。
自信がないからだ。
飛び上がって取れないところを、他者に見られるのが恥ずかしいからだ。
彼らは惨めな敗北者になることが耐えられない。
だから彼らは「ブドウが欲しい」という気持ちから目を背け、「無欲は素晴らしい」という価値観にすがりつく。
しかし、もちろんそんなものは、決して自然本来の生ではない。
人生には成し遂げるべきことがある。
戦ってでも勝ち取るべきものがある。
もし勝ち取るために高い障害があるとしたら、それを乗り越える力を得るために努力すればいい。敵がいるのならば、敵を打ち倒し、己の意を貫く強さを手に入れればいい。
以上はニーチェの哲学を通じての、ヤムチャさんの言葉という感じですけども、中々シビれるでしょう(笑)。ここの一節、好きなんですよね!
話題を元に戻します。
自分にはできないことを実現している人や、特定のスキルを持っている人を見ると、僕もルサンチマンを感じることがあります。
今回のトークンの価格煽りも、その一例かもしれません。結局のところ、できるならやるだろうと。
自分がやらないことを正当化するために、”歪んだ価値観”を持ち出して「価格で煽るなんて下品だ」と言い、自分を守る。このようなルサンチマンが、価格煽りを下品だと批判する声の背後にあるのではないかと思います。
しかし、フィナンシェでトークン価格を上げることが唯一の正しい方法だと盲信するのも、また危険だとも思います。”トラの威を借るキツネ”(きょうはキツネの例えが多いw)のように、他者の力を自分のものと勘違いし、価格を煽って幻想の価値を生み出すことは、結局自分の精神を害する可能性があります。
そして、いずれ来るであろう盛り上がりの終わりに、自分が精神的に健康でいられるように、慎重に設計していきたいとも思うわけです。
「コミュニティ立ち上げ→トークンローンチ」に、長い時間を取りたいと考えています。最初はこの盛り上がってる時にトークンを発行するのが良いかなーと思っていましたが、トークンの価値の源泉は「コミュニティにある」と考えます。
そのため、コミュニティの文化や秩序、規範作りが先かなと。基盤を整えた上でトークンローンチを行うことで、お互いの長期的な視点でのコミュニケーションにつながると信じています。
急がずじっくりとコミュニティの温度を上げていく、そんな、湯たんぽみたいな設計を組みたいと思っています。
————
<批判の声③「アート関係なくね!」について>
最後、3番目の批判、「アートと無関係だ」という声について触れます。こんなポストが先日、目に飛び込んできました。
「フィナンシェで『トークン、トークン』と言っている人が、クリエイターが生み出すイラストやアートに興味がなかったということを、NFTクリエイターたちは自覚する必要があるんじゃないかな」
といった意見。この見方は面白いですが、物事を単純化しすぎている気がします。
トークンに関心を持ったからといって、NFTへの興味が失われるわけではありませんし、これらはトレードオフの関係にあるわけではない。
NFTに興味があるからトークンに興味がなくなる、またはその逆というわけではなく、実際には共存できます。
僕がフィナンシェでのトークン発行に向けて動いている中で、NFTとフィナンシェのトークンは明確にリンクし、結びつくものと考えています。これらは決して分断されるものではないのです。
僕の頭の中には、トークンを利用したコミュニティ作りの関係組織図が明確に描かれています。これは切り離されたものではありません。
僕たちのプロジェクト「ZUTTO MAMORU」は、イラストレーターのmamoruさんのクリエイティブを全面に押し出し、彼の作品や世界観を広げることを一貫して目指しています。このビジョンは100万回、強調してきたことです。
今回のフィナンシェでのトークン発行も、そのビジョンに向かうための一つのツールに過ぎません。
NFTクリエイターの中には、「トークン、トークン」と言ってアートと結びつかないトークンの発行、つまりNFTの「N」をはじいたファンジブルトークン(FT)の盛り上がりに寂しさを感じる人もいるかもしれません。そういった声も実際によく見かけます。
ただ、これらは本当に切り離して考えるべきで、例えば、僕が「カフェオレ、カフェオレ」といっているのに、NFTへの興味が薄れたわけではないのと同じです(笑)。なんでもかんでも二分すると極論に行き着きます。
フィナンシェのトークンに興味を持ったからといって、NFTへの関心がなくなるわけではなく、そう言う声は極論を超えた「暴論」です。
フィナンシェでトークン発行を進めているNFTプロジェクトには、クリエイターがファウンダーとして活動しているケースが数多くあります。
これらの方々がクリエイティブへの興味を失ったのかと言われたら、「んな、わけねぇ!」ですよね。
僕だって「mamoruさんの作品への興味がなくなったのか?と問われれば、全力否定マンです。
もちろん、このトークン発行の動きはイラストレーター・mamoruさんにも共有しており、その了解のもと進めています。
ですから、「アートと無関係じゃん!」という批判は、感情的には分かりますが、的🎯がズレてんなー、が正直なところです。
———
フィナンシェ活用に関して、批判の声を見かけることが多いので、僕なりに思うところを書きました。
「ZUTTO MAMORU」も今週、フィナンシェに関する何らかの話題を提供できるかもしれません。その準備のための打ち合わせが始まっています。
「ZUTTO MAMORU」に期待を持ってもらえたら、嬉しいです。僕なりにフィナンシェで発行する”ずっとークン(仮)”の活用法をしっかりと考え、進めていきます。
その際には、ぜひご支援をよろしくお願いしまも🙇
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
