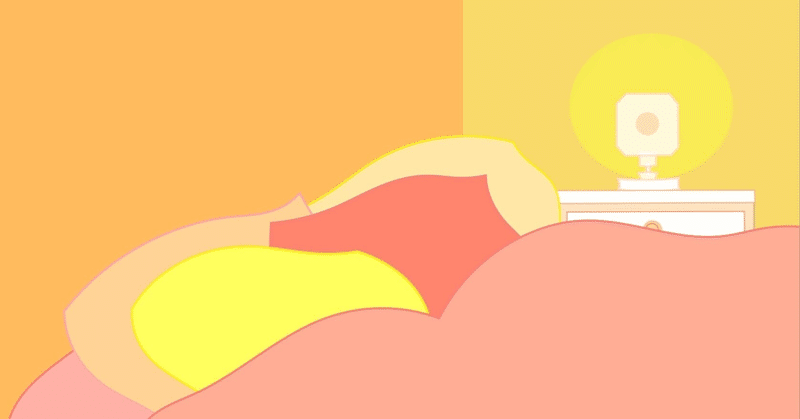
桃源枕 ② Bの話
「松阪牛が食べたいんですぅ」
テレビの向こう、アイドルの頂点に立つモモコが誕生日の花束を受け取りながらインタビューに答えていた。
松阪牛、いや、松阪と言わず、神戸でもひたちでも、今となってはどれも食べられるものではない。一部、富裕層がありえない値段を払って口にするというのは聞いたことがあるが、それはもはや都市伝説ではないかと思っている。
ちなみに僕の親世代は、当時も高級食材ではあったが、焼肉に行ったら牛肉にありつけた世代なので、モモコの発言を耳にしたことで「いやぁ懐かしいなぁ」とヨダレを啜った。
いや、それよりモモコだ。
その絶対的存在感、頂点まで上り詰める美貌、抜群のスタイルを持ちながらの親近感、どことなく憂いて見える瞳にも関わらず、天真爛漫さも隠さない、歌って踊って演技もこなす超人気アイドルモモコ。
彼女は今、僕の部屋の押し入れに住んでいる。
某有名キャラクターのごとく、押し入れに布団を敷き、時々僕にお茶菓子を要求して。
もちろん、4次元ポケット的なものは持っておらず、引き出しから未来に帰っていくこともなく、しかし玄関を使わず、常に窓から出入りしているが、竹トンボ的なものを頭につけているわけでもない。
まぁ、彼女の存在そのものが、4次元ポケットから出てきそうなキャラクターではあるが。
そもそも彼女は隣に住む同級生の幼馴染だった。
幼い頃は、そこそこの可愛らしさだったのだが、中学生の夏休み、丸っと4週間ほど不在になった後、劇的な美少女になって帰ってきた。
もちろん、夏休み明けの中学校では「ついに卒業できたの!?」という騒ぎになった。ついに何を卒業できたかといえば超有名美容整形外科なのだが、そこは『美』の資質が備わっていないと受け付けてももらえないところで、猛烈な試験やレッスンをクリアしないとそもそも手術をしてもらえない。クリアしたところで、骨格やスタイル、持って生まれたあらゆる身体(スタイル・肌質・腸内環境・DNAに至るまで)の検査を受けて、少しでも基準を外れると、通常の、それでもハイレベルな美容整形外科を紹介される流れになるらしい。
そして、その門をくぐれたものは、パーフェクト・ヒューマンである認定がされたも同様、あらゆる美の世界での活躍を約束されるとのことで、最近のタレント、そして俳優、女優、歌手、モデルに至るまで同じような顔面が出揃っていて、ちょっと気持ちが悪い。
その同じような顔面が出揃う中でも、モモコは特別な何かを持っていた。
どんな群衆に紛れていようと、いや、それがアイドルの群衆であってもなお目を引く。
これは、単に僕の身内贔屓ということではなく、モモコを取り巻く誰もが同じような感想を口にしていたし、実際、彼女はどこへ行くことも出来なくなっていた。どうやら彼女自身に発光してしまう何か、ウミホタルとかホタルイカ的な遺伝子があるのかもしれない。
ある日彼女は、どこへも行けない自分を嘆くために、自分の部屋の窓から、僕の部屋の窓へ飛び移ってきた。
19歳浪人生の春である。
正直なところ、中学生の時、とびきりの美少女になった時点で、僕との距離は広まる一方。淡い恋心を抱くこともバカらしくなるほど彼女は取り巻きに囲まれていたし、一家の稼ぎ頭となった彼女は、早々に都心のマンションに引っ越して行ったから、隣からヌッと彼女が現れた時は、単純に悲鳴を上げた。
「な、な、おま、なんで、ここ、え!?」
驚くと、人間こんなにも話せなくなるのだということを知ったのち、彼女のあまりの美貌もその時改めて思い知らされたと言える。多分僕の瞳孔は完全に開ききっていたし、呼吸も止まったので、医者がその場にいたら、とりあえず生存の確認をする流れになったのではないだろうか。
彼女は「うわー懐かしい」と、僕の様子は知ったことではないというふうにキョロキョロした後、「ここに住まわせてもらうわ」とそう言った。
超有名アイドルが家に、僕の部屋に住み込むとは。これはもう『あなたは18歳以上ですか?』の確認が必要な世界線に違いない。そして僕は19歳。0.5秒であらゆる可能性と煩悩が駆け巡り、もう一度瞳孔が開きかけた。
「あ、そういう期待に応えられるかどうかは、今後の恋愛ストーリー次第ってことで」
彼女は、僕の思考を読み取ったらしく、そう言ってから押し入れを開けて「うーふーふーふーふー」と、某有名キャラクターの声色で笑った。
どうやらモモコは、元の自分に戻りたいらしい。
あまりにも注目される世界と、憧れ続けた世界には、強烈な溝があった。
その辺は想像出来るのだが、それがなぜ僕の家に住まうことになるのか問うと、元の自分はそもそもここにあるからだという。
隣の彼女の家は、売りに出されたわけではなく、そのまま彼女の家として置いてあるので、そこに住めばいいと思うのだが、長年使われていないのと「だって淋しいじゃん」というそれだけの理由で19歳、生物学的絶賛発情期な僕のテリトリーに侵入してくるとは、超アイドルの危機管理、一体どうなっているのだろう。
「じゃあアイドルを引退すればいいのではないか?」という提案をしてみたら、あの超有名美容外科を経てのアイドルであることに問題があるらしい。
あらゆるレッスン、試験、身体の検査、そして美容手術、それらはこの先の輝く未来を約束する代わり、本人の意思に関係なく、その美が消耗され尽くすまで表舞台を引退することは認められない契約ということだった。
もし仮に契約違反をした場合、莫大な違約金が発生する。なるほど、大人の闇がふんだんに隠されていると、そういうことだ。
「こんなことなら、普通の美容外科に行けばよかったぁ。それでもアイドルにはなれたと思うのよ、私、かなり努力家だし」
と彼女は言う。普通の美容外科は今や美容院と同じ感覚で誰もが行ける。果たしてそれで、彼女が今の地位まで上り詰めることが出来たのか、正直それはわからないし、今の活躍があるからこそ、過去の世界に想いを馳せているわけで、普通のアイドルになったとして別の苦難が付きまとうだろうことは容易に想像できたが、それ以上何かを提案するのはやめた。
かくして、超アイドルモモコは僕の押し入れに住むことになった。
トイレも風呂も、両親がいない間にちゃっかり使う。共働きの両親は、週末以外はいないし、週末になると今度は彼女が出かけて行く。
あれだけ人気がありながら、週末の活動だけで超アイドルを維持できるそのカラクリがよく分からない。
働き方改革はアイドル界に革命を起こしているのだろうか?働き者の両親が不憫である。
彼女が普段、僕の部屋で何をしているかというと、小学校の卒業アルバムを見てはしゃいだり、中学校からの勉強をやり直したりと、発光遺伝子を封印し、本気で中学からやり直そうとしているようだった。
そんな日々が3週間ほど続いた。
思いのほか平穏に過ごせていることと、僕の煩悩が爆発していないことに驚きを隠せない。
何せ、瞳孔が開き切るほどの美貌の持ち主が、押し入れを開けたら無防備に寝ているのだから、「好きでもない相手」とか「相手への配慮」とか、そういった常識を並べたとて、かなり辛い毎日が待っている気がしていたのだ。ある意味、健全たる男子であることに自信を失いそうにさえなる。
ところがだ。
「松阪牛を食べたいんですぅ」
いつの間に仕事をしているかわからない、僕の家に住む超アイドルがそうインタビューに答えていたその1週間後。
モモコは相変わらず押し入れにいたのだけれど、僕に「あのね、局から松阪牛もらえたの」と報告すると、妙にピッタリと僕に寄り添ってきた。
「え、牛ってまだ生きてるの?」そう答えながら突然上がった心拍数を悟られないようにする。
「うん、いるらしいよ。ほんの少しらしいけど。ここで一緒に食べよう」
まだ食べたことのない松阪牛にヨダレが出ているのか、ピッタリと寄り添う彼女の胸の膨らみにヨダレが出ているのかいまいちわからない。
いや、3週間、押入れの襖という隔たりがあるにせよ、半径3m圏内で同じ空気を吸っているのだ、すでに彼女は僕の特別な人と言う思考回路も仕上がってきている。
恋か、恋ではないかと問われたら、少なくとも初恋相手だったと暴露したのち「あれから一途にずっと好きでした!」と嘘をつけるほどにはなっていた。ごめん初カノであり元カノのシホちゃん。
そうしてホットプレートを持ち込んだ僕の部屋で焼肉は行われた。平日の昼間、19歳男子の部屋ではあり得ない超贅沢ランチである。もらってきた松阪牛は、うやうやしく桐の箱に入っており、金箔でもってその名前を堂々と掲げていた。
生唾もので蓋を開けると、向こうが透けて見える美しい羽衣の如く、薄い肉が2枚、守られるようにシートに1枚ずつ入っていて、それぞれが強烈なオーラを放っていた。
これが…牛の肉…。
僕たちは、「牛肉の美味しい食べ方」を満遍なく声に出して3回読んだのち、まるでそれを金箔職人のように丁寧にホットプレートに敷いた。思えばそこがピークだった焼肉は、体感二秒で焼き終わった。
「ねぇ、本当はこれが全部夢だったらどうする?私も、松阪牛も」
溢れ出る肉汁というのを喉に流し込みながら、肉本体は勿体無くてしばらく咀嚼を続けていると、モモコはまたしてもピッタリ寄り添ってきて言った。
そもそも、超アイドルが押し入れに住んでいること自体現実ばなれしているのだ。これが夢オチであったとしても納得はいく。随分長い夢だけど。
「あのね、3大欲求を全てコントロールしようとしている研究があるの。あなたその実験台になってる。もちろん真実を伝えた上であなたに拒否権はあるんだけど。今、幸せか、それを問いたい」
モモコは、どういうわけか、さらにピッタリと体を寄せ、耳元に吐息を吹き込んだ上で、触れるか触れないか程度にその完璧な形の唇を僕の頬に近づけた。さっき食べた肉の香りが彼女の口から漏れていて、初めて彼女が本物の人間だと認識したような気がした。
「僕が今夢の中にいるというなら、僕の答えは簡単だ。君を押し入れから連れ出し、君が自由になることを叶え、時々、そうだな、1年に一度ぐらいは松阪牛を食べれれるだけの生活をしつつ、末長く君と幸せに暮らしたい」
まるで、台本を読むように、僕の口からスルリと言葉が溢れる。
するとモモコは映画のワンシーンのような計算され尽くした笑顔で言った。
「やっと告白されたー!長かった、3日で告白してくると思ったのに!」
その後、クルンと目を回し、今度はアイドル特有の可愛らしさ全開のむくれ顔になる。
「いやこれって告白っていうの?好きって言ってなくない?このモモコ様が、ここまで密着しているというのに、失礼なやつだわ。私はね、幼稚園の頃からあんたが好きだったの。もちろん、芸能活動して目移りしなかったと言えば嘘になるけどさ。小学生の時、仲良くここで昼寝してたあの頃が、今思えば一番自由で愛しい時間だったんだ」
心臓が鳴る。
ここで昼寝をしていたあの頃。君はまだ未完成だったけど、僕にとってはそれが完璧だった。例えば汗の匂いや小さな掻き傷、つい猫背で読みあう漫画、腕のホクロに長い毛が生えているのを発見して爆笑しあったあの日。
今その完膚なきまでの美しさを纏う君を、あの日のささやかな幸せのもとに戻してあげたい。
生まれて初めて松阪牛を食べた夜、モモコは僕を自分の膝に転がせながら僕の髪を愛おしそうに撫でた。
日本、いや世界中の君のファンが発狂するようなスタイルでもって僕は考える。
松阪牛を食べ、君の膝を枕にし、超アイドルの秘密を誰にも知られることなく優越感に浸る日々を。
これが夢でなくて一体なんだというのだ。
むしろ、現実に帰る日がくると思うとゾッとする。
何かの間違いで目覚めてしまうというのなら、後生だからもう一度松阪牛を食べさせてほしいと思いながら、君がいる現実を確認するため、そっとそのつるりと美しい膝小僧を撫でる。
Cの話へ続く
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
