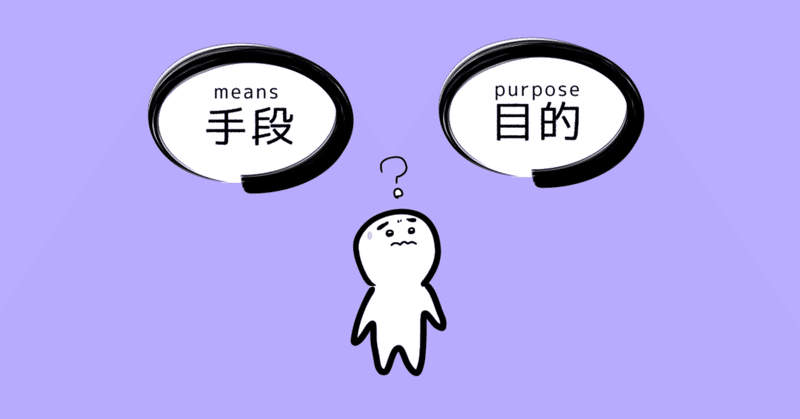
「ここにいますよ」認知症母の重い一言 介護の日々伝える本を出版・・・という記事の紹介です。
静子さんの認知症が始まったのは2005年ごろ、88歳の時だった。自宅で足を骨折し、入院したことがきっかけだった。外出の意欲が衰え、症状は徐々に悪化。風呂に入れようとすると大声を上げて抵抗し、1日に100回以上もトイレに行くようになった。
何かのきっかけで失敗や出来ない事が増えてしまうと、ただでさえ喪失感や精神的に不安な状態の高齢者にとって、認知機能の低下に繋がるトリガーになってしまう事が多いと思っていて、様々なケースがあるとは思うんですが、こういう入院やショートステイというイベントの前後で変化が大きく出るのはよくある事なんですよね。
なので、そうなる前の段階から支援が入ってるのがベストとは思うのですが、現場の制度や一般的な常識はそうではなくて、何か困った事が出てから対策する仕組みになっているので、今のままだと永遠に介護予防の取り組みは困難だと思います。
09年4月1日からデイサービスを利用するようになった。「わたし ここにいますよ」の記述はこの日から始まる。ショートステイ、特別養護老人ホームでの最期の日々まで母の話した言葉や食事の様子、施設の職員とのやり取りや他の入所者の人間模様などを31章に分けてつづった。
記述は日々、紙にメモした記録が基になっている。デイサービスを利用する前はそのメモをする余裕すらなかった。
興味深い内容なのでちゃんと読んでみたいですね。
デイサービスを利用するまでは、メモを残す余裕すらなかった、というのが家族の介護がいかに過酷なのかわかりやすいですね。
本の題名は静子さん自身の言葉からとった。老人ホームでスタッフを呼んだのに、みな忙しく誰も返事をくれなかった時に発した一言だ。「認知症の人はみな自分を見て欲しいと思っている。母の言葉の中でも重いものだった」。本が介護現場の改善につながることも願っている。
介護の仕事って本当になんなんでしょうね。
利用者さん、何らかの助けが必要な方が助けを求めてその道の専門家を呼んでいるのに、誰も返事すらしてくれなかった・・・。
忙しい、人手が足りない、それで仕方ないね、で済ませて良いのだろうかと思いますし、もともとそんな声に対応したくて介護の仕事を選んで入職した職員さんが、平気でそんな対応が続けられる訳もなく、そこに心を病んで介護の仕事を続けられなくなったり、燃え尽きたり、そんな環境自体が介護職不足を招いているのではないかと思うのですよ。
ここを変えない限りは変わらないかなぁと思ったり。
ただ、一対一で対応できる訪問介護の職員も同じように足りない状況で、その深刻さは業界内でもトップクラスの深刻さなので、それだけではない原因はあるとは思ってますが、少なくとも訪問介護の現場では、呼ばれて対応出来ない事はないのですが、あ、そっか、介護保険じゃ出来ない事が多すぎて、対応したくても出来なくて断らざるを得ない状況は、もしかすると結構心理的にしんどくなるのかもしれません。
「認知症の人はみな自分を見て欲しいと思っている。母の言葉の中でも重いものだった」
もう10年以上前から認知症の方本人の言葉に耳を傾けましょう、って認知症のケアでは常識になってたと思うんですけど実際はそうもなってないですもんね。
介護職は、介護される人が主人公であるその方の人生をより良くするための脇役ですから、そこをきちんと理解してその専門職として技量を日々磨いていきたいな、と改めて思いました。
しかし、ケアを提供するその本人のことを見向きもせずに(いろんな意味で)仕事をしたとして、そこに専門性はあるのかなぁ、と大きな疑問も持つ内容でした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
