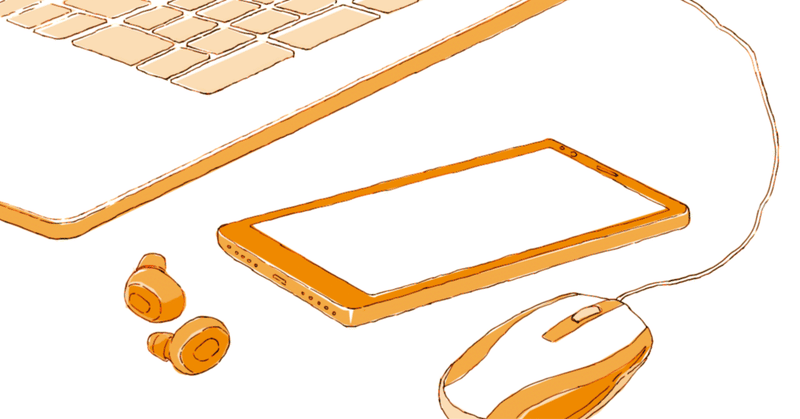
【エッセイ】微笑を読み上げられるまで
Audible 2ヶ月無料キャンペーン中との報を受けてから、加入すべきか否か悩んでいる。
これは以前Twitter で聞いた話なのだが、文章を読む時、脳内で声が再生される人とそうでない人がいるらしい。高倉は後者で、活字は活字の形をしたまま脳内で処理され、音声に変換されることはない。そもそも活字(ここでは音声になる前提で書かれていない小説やエッセイを想定する)は活字として読まれるに最適な文体で記されている筈で、音読に適した形にはなっていないと信じている。そうならば、脳内で音声に変換するメリットが感じられない。活字は無音で並ぶものだ。
なので、Audibleで音読される本と、活字の本は、例え同じ文字列を扱っていたとしても、全く別物であるように思われてしまう。Audibleで本を一冊聞いたとして、それは読書体験と呼んでいいのだろうか。
活字、とくに物語を音声にするということに、若干の恨み節がある。
小学生の頃、国語の授業ではよく音読をさせられた。席順に一人一文ずつ(或いは一段落ずつ)音読してゆく、あの時間が高倉はとても嫌いだった。活字で紡ぎあげられた一本の糸が、読み手が入れ替わり立ち代ることでぶづんぶづんとちぎられていくようだった。加えて、高倉は小学生の頃から口下手で、折角の文章を上手に読み上げられないことも情けなくて悔しかった。こんなの黙読でいいだろと思っていたし、今もそう思っている。黙読でいいだろ。音読させるなよ。図書室では静かにしろって言うくせに。
Audibleで本を読み上げるのはプロの声優さんや俳優さんらしい。音声表現のプロだ。小学生の音読と違って、糸がちぎれることは無いだろう。
台詞には高倉の貧弱な想像力では到達できないほどの感情が乗るだろうし、高倉がうっかり読み飛ばしてしまう地の文も明朗に読み上げてくださることだろう。それでも、活字と高倉の間に他の人間というフィルターが挟まることは、やはり純粋に読書とは言い難いのではないか。
と悶々と考えていたところで、阿刀田高のエッセイ集「ミステリー主義」に収録されたエッセイ「朗読のアウトサイダー」に出会った。奥様が日本点字図書館の朗読員を務めている、というエピソードからはじまり、朗読がいかに高度で難しい技能であるかについて言及している。朗読者は朗読前に済ませるべき下準備が山ほどある。例えば、ルビのない「渡辺」を「わたなべ」と読むか「わたべ」と読むか。単語のアクセントをどこに置くか。登場人物の心をどう表現するか。その後の展開を織り込んで、どのように緩急をつけるか。全てを決定してからでないと、朗読に臨めないという。
一人の男が大変な不幸に逢い、ふと仏像の微笑を見て初めて仏の恵みを知り仏門に入る、という小説があった。
「この微笑、ミショウと読むのかしら」
「仏門ではそう読むよな」
「でも、この主人公、このとき初めて仏の恵みを感じたんでしょ?仏門に入るのは、そのあとでしょ。彼の見たのはビショウであってミショウじゃないと思うの」
ここまで立ち入ったら朗読は真実むつかしいだろう。
恐ろしい世界だ、と舌を巻いた。朗読、まさかこんな高度なことをしていたとは。小学生の音読とはわけが違う。腐った恨み節で敬遠してはいけなかった。
朗読者こそ小説を一等深く読みこんだ人なのかもしれない。だとしたら、そんな人が音声にする小説を聞くことは、より深い理解につながるのではないだろうか。無音の活字で得られない理解が、もしや朗読の中にある。
無音の活字を愛しているし、やはり活字を目で追うことこそ読書だという信仰は捨て難いが、それはそれとして、朗読の世界も悪くないのかもしれない。Audible 2ヶ月無料キャンペーンの〆切は 5/9、つまり明日までだ。どうしよう、どうしようかな、と、申し込みボタンの上でカーソルを遊ばせている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
