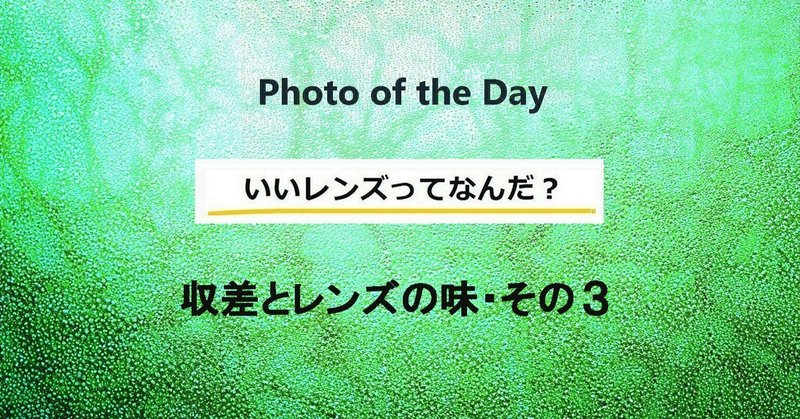
色収差と、偽色とモアレ
前回は、色のない光(モノクローム)で発生する5つの収差(ザイデルの5収差) ━━ 「球面収差」「コマ収差」「非点収差」「像面湾曲収差」「歪曲収差」 ━━ について解説をした。
今回はその続きだが、その前に余計なひと言を。
多少の収差があるからといって、それが欠陥レンズだとか、だめなレンズだと断定できないぞ、ということ。レンズに収差が残っていたとしても、過度に神経質にならずにそのレンズを使いこなしてみることだと思う。
収差のまったくないレンズなどはこの世の中に存在しないし、仮に、収差のきわめて少ないレンズがあったとしてもその写りは(たぶん)無味乾燥で味わいもナニもないだろう。そのへんのことはレンズ設計者もじゅぶんに承知していることだ。一部の収差を意図的に残すことで(残存収差により)わざと「味のある」描写を狙っていることもある。
それらのことを〝覚悟〟して、収差が残っていることをおもしろがってレンズ描写を楽しんでもいいのではないかと思う。
軸上色収差と倍率色収差
さて、前回に述べた5つの収差は白黒画像で出てくる現象だ。モノクロ写真時代のレンズ描写に悪影響を及ぼしていた。ところがカラー写真の時代になって5収差以外の収差が目立つようになった。それが「色収差」である。
光(自然光)は波長の異なった色の光線が混じり合っていて、それぞれ光の波長ごとに屈折率が異なる。そのためレンズを通った光線(波長)がピントを結ぶ位置で色ずれを発生する。被写体の輪郭部に赤や緑、青などの色が浮き出てきたり像がぼやけたりする。この現象が色収差である。
色収差には、軸上色収差と倍率色収差の2つがある。
軸上色収差は光軸上で色がずれる現象。大口径レンズや望遠レンズではわずかな光の波長の屈折率が異なっても焦点を結ぶ位置が異なり目立ちやすくなる。ピントの合った部分の輪郭に色の滲みが出て鮮鋭感が乏しくなる。
倍率色収差は焦点面上で色がずれる現象。軸上色収差と同じように光の波長が異なることによる色ずれ現象で、とくに広角レンズなどを使ったときに画面周辺部で目立つことが多い。

軸上色収差と倍率色収差のおおまかな違いは、上の概念図を見てもらえばわかるように、軸上色収差は光軸上の色ずれ、倍率色収差は焦点面上での色ずれである。
軸上色収差
軸上色収差は焦点距離の長い望遠系レンズやF値の明るい大口径レンズで目立ちやすい。ただしこれは、やや旧型のレンズでの話であって、最近のレンズでは、超低分散ガラスや蛍石レンズなどの特殊光学ガラスレンズの採用や、光学設計技術の進化などで効果的に補正できるようになったため、以前よりも目立たなくなってきている。とはいうものの、ときどき軸上色収差が出ているレンズを見かけることもある。
軸上色収差は絞り込むことで、少しだけ補正の効果は期待できるが、これも像面湾曲収差と同じように被写界深度に頼るだけにすぎない。倍率色収差は画像処理である程度の補正は可能だが、軸上色収差は画像処理などによって目立たなくすることは大変に難しい。
下の(図・1)は軸上色収差の「典型的な例」で、開放F値がF1.2という大口径レンズを使ってF1.2開放絞り値のまま、ピント位置をほんの少し前ピンと後ピンにして撮り比べたものだ。少しグリーン(左)とマゼンタ(右)の「色滲み」が出ているのがわかると思う。ピント位置からわずかにずれただけで画面中央部あたりで色滲みが目立つ、典型的な軸上色収差だ。
たとえば開放絞りで、ある部分に正確にピントを合わせて写すと、軸上色収差の影響でその前後のぼけ部分にグリーンやマゼンタの色づきが出てくる、そんなレンズもある。

やや旧式の望遠ズームレンズを使って撮影したら、画面中央付近のエッジ部に軸上色収差が(わずかだけど)出ていたのが下の(図・2)で、その赤枠部分を拡大したのが(図・3)である。

部分拡大した(図・3)では、明るい空を背景にした建物のエッジ部分にマゼンタ色の滲みがよく見える。これが軸上色収差である。

倍率色収差
倍率色収差は、広角レンズや大口径レンズを使ったとき画面周辺部に色ずれとして目立つ。これをパープルフリンジ現象と言う人もいる。
軸上色収差が像面の前後方向(光軸方向)に色ずれが発生するのに対して、倍率色収差は像面上の上下左右方向(円周方向)に色ずれが発生する。
ズームレンズや広角レンズで発生して目立つ傾向がある。広角系レンズの倍率色収差を目立たなく光学設計することはレンズ設計者がもっとも苦労することの1つと言ってもいい。
ところが近年、デジタル画像処理の技術が進化してきて、カメラ内で自動的に補正してくれるカメラも多くなってきたのでレンズ光学設計者としてはだいぶ楽になったのではないだろうか(ただし完全に補正することは現在の技術ではまだ難しいところもあるようだ)。
高倍率ズームレンズで撮影した写真だが、(図・4)の画面の四隅(左上)に倍率色収差が見られる。赤枠で囲った部分。対して画面中央部の赤枠部分には色収差がほとんど見られない。
(図・5)は、それぞれ左上と画面中央部を拡大して比較したものだ。これを見比べると、倍率色収差が画面端だけに発生していることがよくわかるだろう(画面中央部で軸上色収差はほとんど出ていない)。


倍率色収差の光学的な補正方法で一般的なのは凹凸レンズの組み合わせだ。さらに効果的な補正は光が屈折分散する幅を小さくする低分散ガラスなどの特殊光学レンズや、精度の優れた非球面レンズの採用である。
ところで、収差の中には、撮影時に絞り込むことで補正が可能なもの、絞り込んでもまったく補正効果のないもの(別掲の表を参考にしてもらいたい)、デジタル画像処理で補正が可能なものなどある。
下の(図・6)は、レンズを絞り込むことで収差などが目立たなく補正できるかを一覧にしたものだ。なお、フレア/ゴーストと周辺光量不足は収差ではないが、絞りによる抑制効果のあり/なしの例として加えておいた。

色収差と偽色/モアレ
色収差(とくに軸上色収差)と間違われやすい色ずれ現象が偽色(ぎしょく、にせいろ)である。 偽色は被写体に本来ない色が細い木々の枝や黒い髪のエッジ部に軸上色収差のような「色むら」が現れてくる現象である。フィルムカメラではまったく経験することがなく、デジタルカメラになってから俄然注目されるようになった。
偽色とよく似た現象にモアレと呼ばれるものもあって、これもまた収差とは関係のない現象である。
モアレは干渉縞ともいい、規則正しく繰り返しの細かな模様を写したときに、ごくわずかな周期のズレが原因で発生する色縞模様のこと。水面に小石を投げ込んだときに広がっていく波紋状の模様のようなもの。
偽色もモアレもイメージセンサー(の構造)と画像処理(の方法)によって目立ってくるもので、本来は存在しない「色」や「模様」が出してしまう現象である。
偽色は収差のようにレンズ光学的な原因で発生するのでない。レンズ側にはまったく〝責任〟はなくおこる。イメージセンサー(ベイヤー方式)とその画像処理(デモザイキング)が原因で発生してしまう現象である。
それを防ぐために、多くのデジタルカメラではイメージセンサーの前面にローパスフィルターを設けて「意図的に解像力を落とす」ことで偽色やモアレの発生を「隠して」いる。
ただし、ローパスフィルターをなくしてしまえば画像の解像力は大幅に向上する。それを承知の上で、偽色やモアレの発生を避けるためにやむなく使用しているというわけだ。
下の(図・7)と(図・8)はローパスフィルターを使っているカメラと、ローパスフィルターを省略したカメラを使って、同じレンズで同じシーンを撮影したものだ。

(図・7)の赤枠部分を拡大比較したのが(図・8)である。左の写真がローパスフィルターあり、右の写真はローパスフィルターなし、である。
(図・8)をクリックすると画像拡大するのでよく見比べてほしいのだが、右写真には細い枝部分に赤色系の色滲みが目立つが、いっぽう左写真はそうした色滲みはなくすっきりした色調になっている。
いっけんすると軸上色収差と見まちがいそうになるが、使用しているレンズや画像をよく見れば「違い」が判別できるはず(結像性能の優れたレンズでは軸上色収差は起こりにくく、ローパスフィルターなしのカメラで偽色が発生しやすい傾向がある)。

下の(図・9)も偽色の例である。黒髪に強い光があたってハイコントラストになると、このように黒髪部分に偽色が目立つ(赤色や緑色の混じった色むらがある)。いちおう断っておくが、この写真は優れた描写性能のレンズとローパスフィルターを省略したデジタルカメラを使って撮影したもの。

こちら(図・10)はモアレが出ている写真だ。左の画面の赤枠で囲ったところを拡大したのが右の写真。
その右側の写真の光があたった壁面に色縞模様が出ているのがわかると思う。これがモアレだ。

高い解像力を第一目的にして、ローパスフィルターを使用しないカメラも出てきている。そうしたカメラを使ったときには、撮影シーンによっては偽色やモアレを覚悟しなくてはならない。
ところが最新の画像処理やメカニズム技術を利用することで〝ある程度は〟偽色やモアレを抑える(目立たなく)できるようにもなった。そうした機能を利用すれば、被写体やシーンによっては偽色もモアレもあまり目立たない画像が得られるようにもなった。
たとえばPENTAXのKシリーズのカメラなどには「ローパスセレクター」の機能をカメラに内蔵していて、撮影前にその機能を選んでおけば(完全とは言い難いが)ある程度は偽色やモアレの発生を抑えることができる。
(図・11)はPENTAX K-3 MkIIIの使用説明書の「モアレ低減機能」を解説したページ。このカメラはより優れた解像描写力を求めてローパスフィルターを省略しているのだが、イメージセンサーを微細に高速移動させることで偽色やモアレを目立たなくする機能「ローパスセレクター」を開発しそれを搭載している。なお、ローパスセレクター機能を使うと偽色やモアレは目立たなくなるが解像描写性は低下する。逆に機能をオフにすると解像描写力は向上するが撮影シーンによっては偽色やモアレが目立つこともある。ユーザーがどちらでも自在に選べるようにしている。

キヤノンには撮影後にPCなどを使って処理する方法だが「Neural network Image Processing Tool」という専用ソフト(有償)を使えば、偽色やモアレをある程度は目立たなく処理できるようだ。
他のメーカーにも、こうしたカメラ内やPCなどを使って画像処理するツールがあるし、今後は、偽色やモアレの低減処理だけでなく収差なども最適に補正できるようになるだろう。ミラーレスカメラになって、さまざまな「レンズ補正」がカメラ内で自動的におこなわれるようにもなった。そうしたカメラ内画像処理機能については、あらためて別編を設けて解説するようにしたい。
なお、ローパスフィルターを使用しないカメラで偽色やモアレが目立つことの、もう1つの原因は、レンズの結像性能が大幅に向上して細かな部分まで解像できるようになったこともある。
言い換えれば解像描写力の劣るレンズでは偽色やモアレが発生することはめったにない、と言ってもいいだろう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
