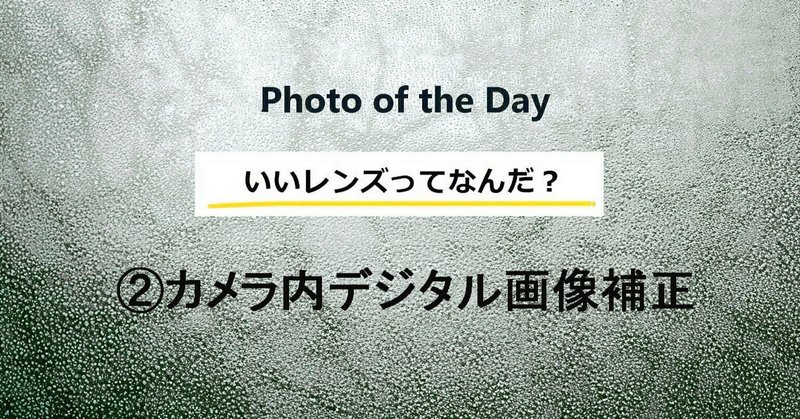
レンズ性能向上の方法や技術・その2
前回のつづき。
各メーカーのカメラ内デジタル画像処理のいろいろと、超解像画像処理、そして今後、デジタル画像処理がレンズ設計や製造、そしてレンズ性能にどのような変化をもたらしていくだろうか、そんな内容を取り上げ解説していきたい。
今回は少し話が長くなりそう。
というわけで、ここでまず、各カメラメーカーの「カメラ内での画像補正(レンズ補正)」の状況をざっと調べてみた。
ただし、言い訳をしておくが、同じメーカーカメラでも機種ごとに設定内容が異なる場合もあるし、実際にカメラを手にしてメニューなどをチェックしたわけではない。明日にでも(予想外の)新しい処理技術が搭載されたカメラが出てくるかもしれない。そして全カメラメーカーの機種をチェックしていないので「洩れ」もあるかもしれず、それらの点についてはご了承を。
なおカメラ内補正とは撮影と同時に補正処理がおこなわれることで、「カメラ内RAW現像」で補正するという意味ではない。さらにメーカー専用ソフトを使ってPCなどで処理できる補正については除外している。
■ CANON
キヤノンのカメラにはメニューに「レンズ光学補正」の項目がある。そこでは周辺光量補正、歪曲収差補正、色収差補正(明記してないが倍率色収差だろう)、そして回折補正の4種のデジタル補正が可能。現在のところ一眼レフカメラもミラーレスカメラも、ほぼ同等の処理ができる。その他にレンズ内蔵の補正データとリンクして自動補正をするデジタルレンズオプティマイザの機能も備えている。
■ Nikon
ニコンのミラーレスカメラは「静止画撮影」メニューの項がある。そこで一眼レフカメラはヴィネットコントロールと自動ゆがみ補正の2種を、ミラーレスカメラではヴィネットコントロールと自動ゆがみ補正に回折補正が加わって3種の補正が可能。ヴィネットコントロールとは周辺光量不足補正、自動ゆがみ補正は歪曲収差補正のこと。倍率色収差には対応していないようだ(未確認)。
■ SONY
ソニーは「レンズ補正」メニューがある。静止画撮影では周辺光量、倍率色収差、歪曲収差の3種の補正が可能で、動画撮影では加えてブリージング補正が選べる。撮影中にピント位置によって画角が変化する現象がブリージングなのだが、その画角変化の現象を補正できるようだ(どのような結果になるのか未確認)。すべての補正機能はON/OFFの選択ができる。
■ OMDS(旧OLYMPUS)
OMシステムではメニュー内「基本設定/画質」の項でシェーディング補正の1種ができるのみ。シェーディングとはヴィネッティングと同じく周辺光量不足の現象のことと考えてよい。歪曲や倍率色収差の補正などはメニュー内には設定項目がない。M.ZUIKO DIGITALレンズを使用すれば「完全自動」で補正できるのだろう(未確認)。
■ FUJIFILM
富士フイルム・Xシリーズのカメラメニューには点像復元処理の設定項目だけで、他のレンズ補正については見あたらない。なので(たぶん)歪曲や周辺光量などは完全自動補正してくれるのだろう。点像復元とは簡単に言えば回折現象の低減をして鮮鋭度を高める機能。なお、メニューには「マウントアダプター設定」という項目があって、そこでは他社レンズをマウントアダプターで使用するとき限定で歪曲収差、色シェーディング、周辺光量不足などの補正の設定が選べる。
■ PANASONIC
パナソニックのカメラでは回折補正(回折現象の低減)と周辺光量の2種の補正ができる。なお、フルサイズ判のSシリーズカメラでは周辺光量補正の名称だが、マイクロフォーサーズ判のGシリーズカメラではシェーディング補正と名称を変えている(理由は不明)。歪曲や色収差の補正は自動でおこなうのだろうか。
■ RICOH
ペンタックスのカメラではディストーション(歪曲収差)補正、周辺光量補正、倍率色収差補正、回折補正の4種が設定できる(ON/OFF切り替え可能)。さらに、レンズの収差補正ではないがローパスセレクターの設定をすることでモアレ(と偽色)の現象を低減できる機能も備えている。
■ SIGMA
シグマのfp/fp Lのカメラでは歪曲収差、倍率色収差、回折補正、周辺光量補正、そしてカラーシェーディング補正の5種のデジタル補正が可能。カラーシェーディングとはやや古い広角系の一部のレンズを使ったときに画面周辺部に色かぶりが出る現象のこと。富士フイルムの色シェーディングとほぼ同じ機能だろう。
以上、おもなカメラメーカーについて、レンズ光学に起因する収差やモアレ/偽色、回折などの現象をカメラ内で自動デジタル補正する機能について簡単に説明をしてきた。ついでにと言ってはなんだけど、つぎにレンズ描写性能(結像性能)を向上させるデジタル画像処理について少し解説をしておきたい。今後、飛躍的に機能向上して、将来カメラに内蔵されるだろうと思われる処理技術だ。
超解像画像処理
レンズやイメージセンサーのもともとの「解像力」を画像処理を施して見かけ上の解像力を向上する、いわゆる超解像画像処理技術というものがある。
さまざまな技術方法があるようだが、その中の一例として、ボディ内手ぶれ補正を利用するという方法がある。撮影中にセンサーを微細にずらして複数枚を高速撮影し、それらの画像を重ね合わせて処理(コンポジット処理)することで画素数を大幅に増やし、解像度の高い拡大画像を作り上げる画像処理技術だ。
大別すると、RAWファイルで撮影記録した複数枚の画像をPCなどと専用ソフトを使って超解像画像処理するタイプと、撮影するとほぼ自動的にカメラ内で処理して超解像画像に仕上げるタイプがある。
利点は高解像力の拡大画像が容易に得られ見かけ上の解像力がアップする。欠点は撮影時に(現状では)あれこれ制限があること、画像処理に時間がかかることなどなどだ。
ペンタックスの「リアル・レゾリューション・システム」、OMシステムの「ハイレゾショット」などは、機能モードを選んで撮影すれば自動的に超解像画像に仕上がる。
いっぽう、ソニーの「ピクセルシフトマルチ」、富士フイルムの「ピクセルシフトマルチショット」などの超解像画像は、カメラ内で処理するのではなくPCと専用ソフトを使って処理するものである。

上の(図・1)はOMシステム・OM-5のハイレゾショット機能のメーカー解説。2つのハイレゾショット・モードがあって、「手持ちハイレゾショット」は手持ち連続撮影中にごくわずかに発生するフレーミングずれを利用して12枚の撮影画像から合成処理して超解像画像に仕上げるもの。もう1つの「三脚ハイレゾショット」は撮影では三脚使用必須で、8枚の連続撮影をして得られた画像を合成処理して超解像画像にしあげるというもの。手持ちハイレゾショットは手持ち撮影で手軽に超解像が得られるメリットはある。三脚ハイレゾショットは三脚使用がややめんどうだが仕上がる超解像画像のクオリティは高い利点がある。

(図・2)はソニーのピクセルシフトマルチ撮影モードのメーカーによる機能解説。α7R IIIが一般的な複数枚(4枚)撮影した画像を合成をして超解像に仕上げる方法だったが、その後継機種のα7R IVではピクセルシフトマルチ機能が進化して計16枚の画像を連続撮影し、それらの画像をコンポジット処理して約2億4080万画素(19008×12672ピクセル)の大きなファイルサイズの超解像画像に仕上げる機能を持たせた。ただし、α7R IIIもα7R IVもカメラ内では処理できず、PCと専用ソフトを使って超解像の画像に仕上げる方式である。
これらの超解像画像生成とは別に、回折現象による解像力低下をデジタル処理(シャープネスとコントラストを微調整)をして、見かけ上の解像力を向上させる処理技術を採用しているカメラもある。
たとえば富士フイルムの「点像復元処理」やキヤノンの「デジタルレンズオプティマイザ」などの処理技術を使った機能がそれにあたる。
こうした超解像の技術を利用すれば、ほんらいのレンズ描写性能の実力が最大限に発揮され、または実力以上の解像感のある画像に仕上げることもできる。

(図・3)富士フイルムのXシリーズには「点像復元処理」のモードが備わっている。設定を選んでONにすると、レンズごとの焦点距離、絞り値、画面中心から周辺までのデ ー タなどをもとにして処理する。絞り込み時に影響の出てくる回折現象によるぼけや、レンズ周辺部のわずかなぼけも最適に補正する。〝擬似的にフレアーを除去=復元〟する画像処理技術である。メーカーによると、この点像復元処理をすることで回折現象の影響は約2絞りぶん改善されるそうだ。


上の(図・4)と(図・5)の画像は富士フイルムXシリーズのカメラとレンズを使って点像復元処理の実力を試してみたものだ。
(図・4)の画面右上の赤枠で囲った部分を拡大して比較したのが(図・5)である。左が点像復元処理・OFF、右が点像復元処理・ONにして撮影。小さな画像ではわかりにくいので、画像をクリックして拡大して見比べてほしい。画像右の点像復元処理・ONのほうがくっきりとして鮮鋭感、解像感が向上しているのがわかると思う。
こうした超解像処理は、カメラ内蔵のセンサー本来の画素数から得られる画像サイズを数倍に拡大したり、回折などの影響を抑え込んだりすることでレンズの結像性能の良さが出てくるいっぽうで、同時に悪い部分も目立ってくる心配もある。
もともと性能の劣るレンズで撮影したりすれば、期待するような高解像力の効果が得られない。かえって撮影レンズにとっては厳しい画像処理技術だと言えなくもない。
ところがいっぽうで、ここ数年のあいだに、レンズ性能もデジタル画像処理技術も飛躍的に向上し、さらにセンサーもAPS-C判から35mm判に大型化したり高画素化したため、あえて超解像の処理をおこなっても以前のように明確な優位性がなくなってきた。そのためだろうか、機能の搭載を控えるメーカーも出てきている。
デジタル画像処理と将来
カメラ内の画像処理によるレンズ補正技術は、とくに最近になって飛躍的な進歩をとげている。機種がモデルチェンジされるたびに、新しい収差補正の機能が追加されてきているほどだ。こうしたデジタル処理による収差補正技術は、コンピュテーショナル・フォトグラフィ(Computational Photography)やAI技術の進歩とともに今後もっともっと進んでいくことは間違いない。
将来のことになるが、コンポジット(画像合成)処理技術がさらに進化すれば、像面湾曲収差や非点収差の補正、さらにはピントの補正(修正)さえも不可能ではないともいわれている。
いま現在でも、画像合成処理でピント範囲(被写界深度)を自動的に広げる処理を搭載しているカメラもある。マクロレンズを使った近接撮影では絞り込んでもピント範囲が狭いままだが、たとえばOMシステムのカメラには「深度合成」という機能があり自動的にピント範囲を広げた画像に仕上げてくれる。
デジタル画像処理による補正はレンズの情報 ━━ 光学的な情報のほかリアルタイムの撮影距離、絞り値、ズームレンズなら焦点距離など ━━ の詳細なデータをカメラや画像処理ソフトが受け取ることで、より適正で確実にスピーディーな画像処理がおこなえる。
しかし、こうした詳細なレンズデータの取得と処理の方法は各メーカーとも非公開が原則でブラックボックス化されている。つまりカメラメーカーが作っている専用レンズについては、カメラボディとレンズとの密接な連携が確保できるため最適なレンズ補正も可能だ。
交換レンズ専門メーカーのレンズは、そのレンズの情報をカメラ側が受け付けてくれない限りは最適なデジタル画像処理をすることができない。デジタル画像処理によるレンズ補正がもっと進化していけば、いわゆるレンズ専門メーカーのレンズとカメラメーカー純正レンズとの格差がますます広がるかもしれない。
ではレンズ専門メーカーは今後どうすればいいのか。デジタル画像処理に頼らずオーソドックスな純粋レンズ作りの技術を向上させていくか(これには難題も多いが)、あるいはカメラメーカーと契約を結んでカメラボディとレンズとのデジタル処理インターフェース(マウント情報)を教えてもらって対応するという方法がある。
ミラーレスカメラでは、ソニーや富士フイルムなどは契約をしてマウント情報を開示しているが、キヤノンやニコンは非公開を続けている(ごく最近、ニコンは一部のレンズメーカーに限って特別な契約をしたうえで情報を開示しているようだ)。
画像処理による収差補正技術が進化していけば(いま、まさにそうだが)、レンズ設計やレンズ作りにかけるパワーをセーブできる。そこそこのレンズ設計と製造さえできれば、そのレンズ性能の足らざるところや欠点はデジタル画像処理で補えばいい、ということにもなりかねない。結果的に収差の少ない(目立たない)レンズが得られればそれでいいではないかという考え方もなくもないが、しかしデジタル処理に全面的に頼るのではなく、やはりレンズの設計と製造は光学的努力を尽くすべきではないか。それでも及ばざるところは部分的にデジタル画像処理の助けを受ける、という方向に進んでいってほしいものだ。
いずれにしても、光学的な補正努力をせずにデジタル処理に頼り切ってレンズが作られることはないと思われる(希望的な予想として)。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
