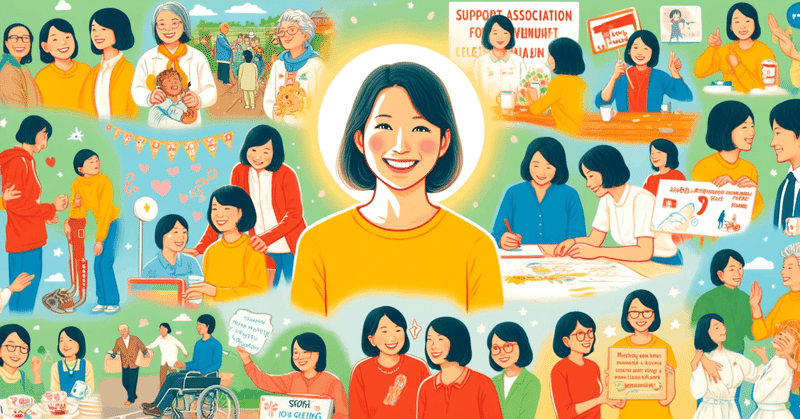
【こころ #41】大人の発達障害当事者の声を届ける
嘉津山 具子さん
内閣府による障害者差別解消法についての関係者ヒアリング。それを傍聴する機会を得たことが、嘉津山さんが金子磨矢子さんとともに『発達障害当事者協会』を創設するきっかけだった。
そのヒアリングでは、車いす利用者、酸素マスクを装着した難病患者、手話を使う聴覚障害者など様々な障害のある当事者自身が、それぞれの障害への“合理的配慮”を求める状況を説明していた。しかし、発達障害だけが「なぜか当事者ではなく大学の研究者が説明をしていた」ことに疑問をもった。
発達障害の世界にはもともと、全国及び地方の障害者団体や親の会、学会・研究会、職能団体などを含めた幅広いネットワークである『一般社団法人日本発達障害ネットワークJDDnet』が存在したが、「大人の当事者の声を集める受け皿的な団体がなかった」ことが、前述の背景だった。
金子さんや嘉津山さん自身も、大人の当事者同士がいつでも実際に会って話せる場所として有名な「Neccoカフェ(ネッコカフェ)」を開店・運営していたが、そこからさらに「当事者の声を集めて届けるまではできていなかった」と気付いた。
大人の当事者の声を集める受け皿団体を、研究者から是非作ってほしいと言われ、自分たちも作りたいと思い、2015年に「ダメ元で作ってみた」のが、『発達障害当事者協会』だった。
発足した翌年には、厚生労働省から、全国47都道府県の地域の発達障害当事者会やその活動に関する調査を受託。さらにその翌年には、調査結果をもとに『発達障害当事者会フォーラム』を開催する。全国から当事者会が集まり、厚生労働省や研究者とも議論する機会を設けたことで、双方にとって学ぶ機会になったことはもちろん、当事者にも「自分の声を発信できるんだ」という驚きをもたらした。
こうした活動を広げていく中で、意外なところから声がかかる。看護師さんなどが「いつでも/どこでも、書ける/思い出せる」ことで使うリストバンド型メモ「wemo」を開発するコスモテック社。発達障害者は、「忘れ物が多かったり、マルチタスクが苦手だったりするため、メモを持ち歩いている」と知った同社から何か利用方法はないか相談があった。
それを協会内で話すと、援助や配慮を必要とする方が支援を得やすくするためにつくられた『ヘルプマーク』と一緒であれば広まるというアイデアが出る。協会から東京都にも働きかけたことで併用が認められ、『ヘルプマーク付きwemo』が誕生する。お試しのクラウドファンディングが成功し、今後は災害避難時の利用にも期待が高まるなど、今後の広がりが期待されている。
嘉津山さんは、当事者の声を拾って発信することで留まらず、形ある成果として社会実装までつなげた。
一方で、そんな嘉津山さんでも、大人の発達障害を取り巻く環境は、まだまだ変わっていないと感じている。発達障害については、子供時代の早期発見に主眼が置かれている関係で、「業界団体の声が親と支援者で占められている」のではないか。
確かに大人の発達障害向けのデイケアも整備され、医療行為に対する保険点数もつくようになったが、「発達障害に取り組む病院がまだまだ増えておらず、就労支援施設も発達障害については手探り状態だ」とも感じている。
そうした背景から、今後は「全国的な意見集約団体をつくっていきたい」。全国にある当事者会も、「おおっぴらに開催すれば町中に知られてしまうので秘密裏にやっている」地方から「宣伝ツールなどを駆使しないと人が集まらない」大都市まで、多種多様だ。前述の「発達障害当事者会フォーラム」は地域の団体と協力し「地域の声を拾っていく土台作りだったが、これからはそれをより集約していく組織づくり」に取り組んでいきたい。
児童に限らず発達障害のある人への適切な支援を推進する『発達障害者支援法』が制定されたのは、2004年。今年で20年になる。その間、支援はどう変わっていったか、そして今後の展望はどうか。嘉津山さんは、厚生労働省で発達障害を担当してきた歴代の担当者にも集まってもらって、今年9月22日に『発達障害当事者会フォーラム』を国立オリンピック記念青少年センターで開催予定だ。それは、嘉津山さんの次なる取り組みへの大きなステップになる。
発達障害に限らず、それぞれの障害の分野で全国に当事者会があったりなかったり、あっても運営するスタイルが違ったり、それらをOne Voiceにまとめることは容易ではない。一方で、One Voiceにならなければマイノリティのまま埋没してしまい、声は届かない。
そこを乗り越えることに挑戦し、声を届けるだけではなく、そこからプロダクトも開発し、さらに社会環境整備に貢献する更に大きな声を作ろうとしている嘉津山さんの経験や取り組みは、きっと他の障害分野にとっても大きな財産になるはずだ。
▷ 発達障害当事者協会
⭐ ファン登録のお願い ⭐
Inclusive Hubの取り組みにご共感いただけましたら、ぜひファン登録をいただけますと幸いです。
このような障害のある方やご家族、その課題解決に既に取り組んでいる研究開発者にインタビューし記事を配信する「メディア」から始まり、実際に当事者やご家族とその課題解決に取り組む研究開発者が知り合う「ミートアップ」の実施や、継続して共に考える「コミュニティ」の内容報告などの情報提供をさせていただきます。
Inclusive Hub とは
▷ 公式ライン
▷ X (Twitter)
▷ Inclusive Hub
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
