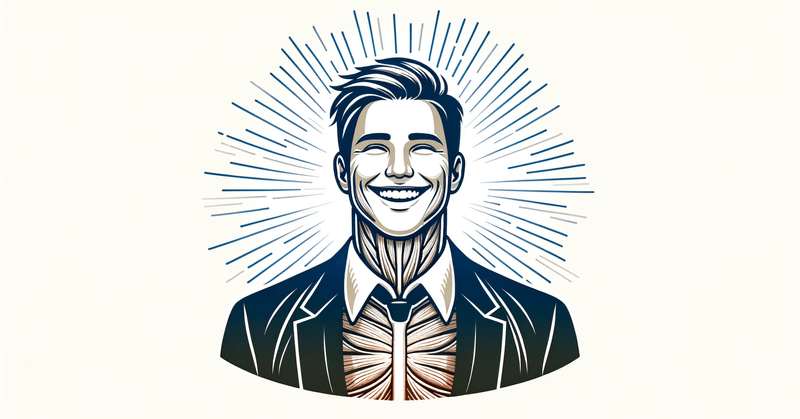
【め #14】「課題は教育」
前田 茂伸さん(後編)
(前編から続く)
障害は本人ではなく社会環境によってつくられるとする『障害の社会モデル』という考え方に基づくと、社会環境側から障害を無くすものは商品開発やテクノロジーの利用に留まらない。
前田さんは「課題は教育」とおっしゃった。
障害のある人の人権や自由を守ることを定めた『障害者権利条約』。日本は2014年に批准し、政府がどのような取り組みをしてきたのか、国連の権利委員会による初めての審査が2022年8月に行われた。
その改善勧告の一つが、「障害のある子どもの分離された特別教育が永続している」というものだった。即ち、通常学級と隔てるのではなく、「すべての子がそれぞれに合わせた必要な支援を受けつつ共に関わり合いながら一緒に学ぶ」インクルーシブ教育の推進を求めたのだ。
ちなみに、現在、国内で通常学級と隔てた特別支援教育を受ける子どもの数は、2021年度で約57万人にも及ぶとされ、10年前の2倍に増えている。それだけの子どもが通常学級とは別の場所で学んでいる。
前述したとおり海外留学経験がある前田さんが、カナダにおける視覚障害者教育の例を教えてくれた。カナダ国内に一カ所だけ点字を教える組織はあるが、基本的に全盲の子は通常学級に通いながら点字を学ぶ。または視覚障害のある子も通常学級に通いながら必要な支援を受けながら学ぶ。どんな子も「他の障害も含めて多様な人を小さい頃から見ていく国」なのだそうだ。
前田さんには、忘れられない子どもとの対話がある。
以前、一般の小学校4年生を対象にした福祉の総合学習のゲストとして前田さんが招かれたときのこと。何か失礼なことを生徒が質問しないか先生が心配しているのを横目に、悪ガキっぽい生徒が質問してきた。
生徒
「海で泳いだ時に、どうやって陸に戻るのか?」
前田さん
「波の音や太陽の方向を確認する。友達も手を叩くなど誘導してくれる。」
生徒
「友達が違う方向で手を叩いたらどうするのか?」
前田さん
「そんな友達はもっていないよ。」
もしその生徒さんが小さい頃から同じ教室に障害のある友達がいて、外に一緒に遊びに行き、そんな日常が普通だったら、質問はどう変わっただろうか?いや、福祉の総合学習自体をやる必要がなくなっただろうか?
教育現場も「インクルーシブだと言われてきてはいるが、もっともっと進んで行けば社会は変わる」。前田さんは力強くおっしゃった。
⭐ コミュニティメンバー大募集 ⭐
Inclusive Hubでは高齢・障害分野の課題を正しく捉え、その課題解決に取り組むための当事者及び研究者や開発者などの支援者、取り組みにご共感いただいた応援者からなるコミュニティを運営しており、ご参加いただける方を募集しています。
Inclusive Hub とは
▷ 公式ライン
▷ X (Twitter)
▷ Inclusive Hub
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
