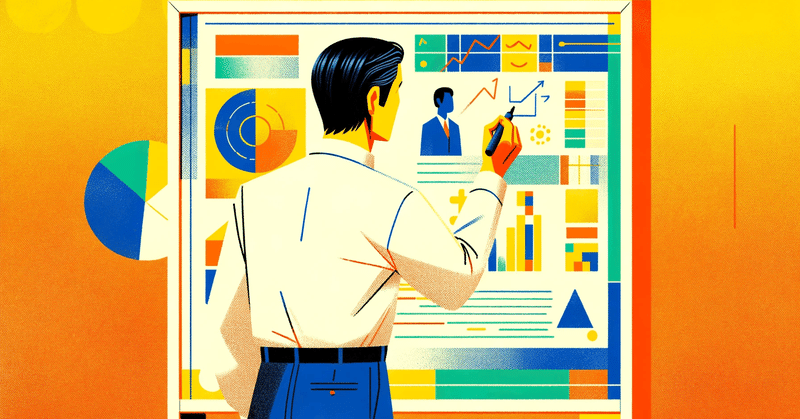
【こえ #43】“取り戻した声”に理解がない世間の目
佐藤 秀紀さん
令和2年。その前年の末に中国で確認された原因不明のウィルスは、日本において2月には『指定感染症』に指定され、感染が一気に広がる中、4月には『緊急事態宣言』が発出された。その年は、初動対応の遅れなども批判された『コロナ“禍”』の始まりだった。
同じ頃、佐藤さんの喉(のど)には、別の“禍(わざわい)”が一気に広がっていた。『緊急事態宣言』の頃からか、喉が「最初はもじょもじょという感じが、どんどん痛くなっていった」。7月8月には「(鎮痛剤の)ロキソニンが足りなくなるぐらい」までに痛みが猛威を振るう。近くの病院に駆け込むも、カメラを入れるなどの検査をしてもらえないままに単なる『咽頭炎』と診断された。しかし9月になっても痛みは治まらない。10月に入り、もう耐えきれずに「いい加減カメラをいれてほしい!」と訴えて初めて大きな病院を紹介してくれ、その結果、「『下咽頭がん』と診断された。もうステージ4だった」。
単身赴任先の兵庫県での出来事だったが、今後のことも考えて地元の愛知県での処置を望み、11月に手術に踏み切った。喉に違和感をもってから、わずか7カ月。「他に治療の余地がなく、待っていると命が危ないと言われ」、声帯も含めて摘出した。「死ぬよりはいいかと思って決めた」。
佐藤さんは、当時57歳。定年までまだ3年ある。すぐに声を出せるよう、電気の振動を発生させる器具を喉に当て、口の中にその振動を響かせ、口(舌や唇、歯など)を動かすことで言葉にする『電気式人工喉頭(EL)』を購入して練習した。職場ではホワイトボードも駆使するなど、できるだけ仕事に支障をきたさないよう、一生懸命コミュニケーションに務めた。
しかし、『電気式人工喉頭(EL)』はどうしても振動の雑音が漏れてしまう。“『電気式人工喉頭(EL)』を通じた声”が出やすくなる音程や音量、それを当てる喉の場所など試行錯誤を繰り返してきた結果、「今でこそ上手く喋れるが、最初の頃は雑音なども多かった」。
佐藤さんは、声が出ない又は聞き取りづらかったことが理由ではないと信じたいが、職場で異動の憂き目に合い、部門が変われば、「声が聞こえない」なんて理解がない態度を取られたり、発言の都合のいいところだけを切り取られるなど、「結構つらかった」。職場の外でも「あんた、その声何?」なんて言葉を投げかけられたこともある。一番嫌なことは、何より「理解がない世間の目」だった。
『電気式人工喉頭(EL)』を使うと、器具を喉に押し当てる作業が発生するため、緊急事態が発生した時に「危ない!」などとっさに声が出せない。そのため、昨年末、地元の愛知県で声帯を摘出し声を失った人に対して発声訓練を通じて社会復帰を支援する『愛友会』に入会し、「食道」に空気を取り込み、食道入口部の粘膜を新たな声帯として振動させ発声する『食道発声』の訓練にも取り組んでいる。
世の中には、声帯を摘出して声を失った人がいる、その声を取り戻しいつでも発することができるよう奮闘する人がいる。その存在を知るだけで、努力の過程を想像できるだけで、少なくとも傷つけない態度をとれるはず。対面する佐藤さんの目が、そう教えてくれる。
▷ 愛友会
⭐ ファン登録のお願い ⭐
Inclusive Hubの取り組みにご共感いただけましたら、ぜひファン登録をいただけますと幸いです。
このような障害のある方やご家族、その課題解決に既に取り組んでいる研究開発者にインタビューし記事を配信する「メディア」から始まり、実際に当事者やご家族とその課題解決に取り組む研究開発者が知り合う「ミートアップ」の実施や、継続して共に考える「コミュニティ」の内容報告などの情報提供をさせていただきます。
Inclusive Hub とは
▷ 公式ライン
▷ X (Twitter)
▷ Inclusive Hub
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
