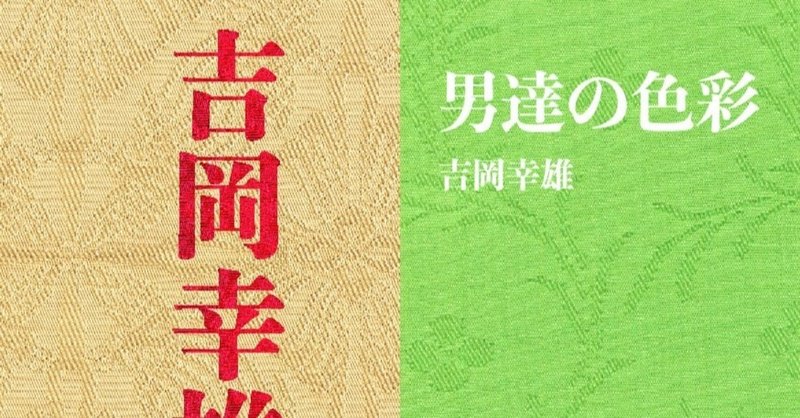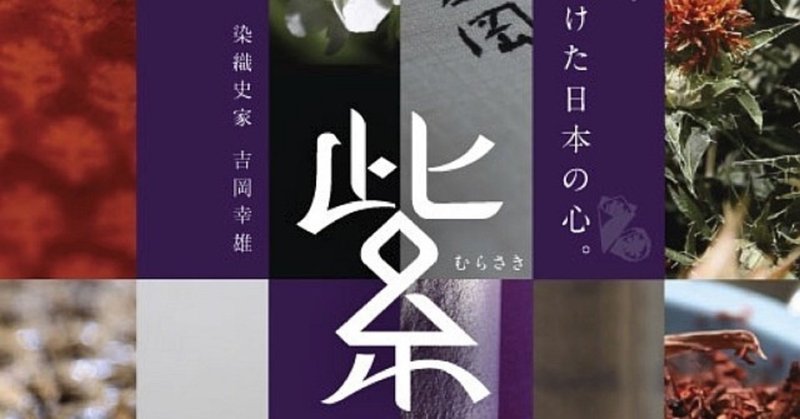最近の記事

英国V&A博物館 吉岡幸雄作品展 「In Search of Forgotten Colours 失われた色を求めて」 2020年11月15日まで会期延長決定
2017年、イギリスのヴィクトリア&アルバート博物館(V&A)からの依頼で吉岡幸雄が製作した永久保存用の「植物染めのシルク」が当博物館に収蔵されました。 それを記念し、当初2018年6月2日(土) 〜2019年1月までの予定で特別展示が行われていましたが、2020年11月15日 (日)まで延長されることになりました。 イベント名:英国V&A博物館 吉岡幸雄作品展「In Search of Forgotten Colours 失われた色を求めて」 会場:Victoria