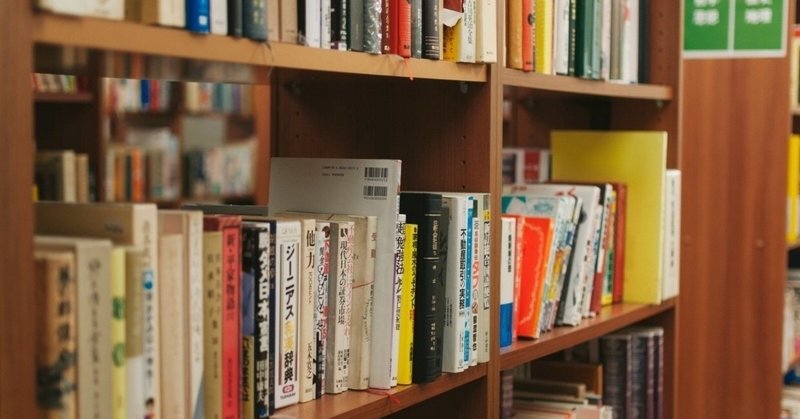
子供は何に興味を持ったのか?
子供に本を買うタイミング
皆さんはどのようなタイミングで子供に本を買い与えているだろうか?
我が家にはユニークな決まりごとがある。
「興味が生まれたら、できるかぎりすぐに本を買う」
すごくシンプルだけど、1番子供に刺さる。ただし何でもかんでも買うわけではない。
小学生の子供が本を手に入れるときは、以下の4点が主流
1、小遣いで本を買う
2、図書館で借りる
3、親にねだる
4、親や知り合いが勝手に買い与える
これをマーテケィングのAIDMAの法則で見てみよう。
<blockquote>AIDMA(アイドマ)の法則とは、Attention(注意)→ Interest(関心)→ Desire(欲求)→ Memory(記憶)→ Action(行動)の頭文字を取ったもので、アメリカのローランド・ホールが提唱した「消費行動」の仮説である。商売の基本で消費者の心理的プロセス・モデルです。<cite>via:<a href="http://www.medi-graph.com/contents/essay/manual/004.html" target="_blank">AIDMAの法則(アイドマの法則/AIDMAモデル)</a></cite></blockquote>
1、小遣いで本を買う(AIDMA)
2、図書館で借りる(AIDMA)
3、親にねだる(AIDMA)
4、親や知り合いが勝手に買い与える(A?)
AIDMAを満たしているのは1から3まで。4は購入後に興味がわいてくれるかもしれない。プロダクトアウト形式だ。
また、AIDMAを満たしていてもすぐに満足へ直結しないのが1から3
1は「資本力」が足りず購入頻度を上げるのが難しい。
2は「無い」場合が多く、満足度を100%満たせる確約がない。
3は「営業力」がなければ大人パワーに粉砕される。
そんな可哀想な状況にも光を与えるのが我が家のルール
子供からこんな質問が来たらチャンス。
「中国ってどんな国?」
「なんで台風が来るの」
「英語ってどうやって話すの?」
「どうして血が赤いの?」
「なんで飛行機は飛ぶの?」
など、「WHY」については喜んで本屋に行き網羅的に粒度の高い本をまず買う。国の本なら中国についてではなく、世界の国についての本。他の国にも興味を促すのが目的。そこからさらに掘り下げたい国が出てきたら粒度を下げてもう一段詳しい本を買う。
1回読んで終わりの本ではなく、もう一度見返したくなる知識の書籍は「興味」タイミングで買ってあげるのがとても喜ばれる。
なぜ図書館じゃダメなのか?という意見もあるが、何度も何度も読み返し好きな時に手に取れる。そして書き込みもオッケー。とにかくいい意味で本を汚してほしい。これができるのは所有物のみ。
ということで、AIDMAのAを子供の起点として、それ以降IDMAを親とともに一気通貫する。このスピーディーな取り組みだからこそ子供にも刺さるのだと思う。
子供の些細な「WHY」を聞き逃さず、「ATTENTIONキターっ!」と喜びます前のめりで一緒に「WHY」を考えてみよう。大人が知らないこと、忘れてしまったことが山ほどあることにいつも気づかされること間違いなしだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
