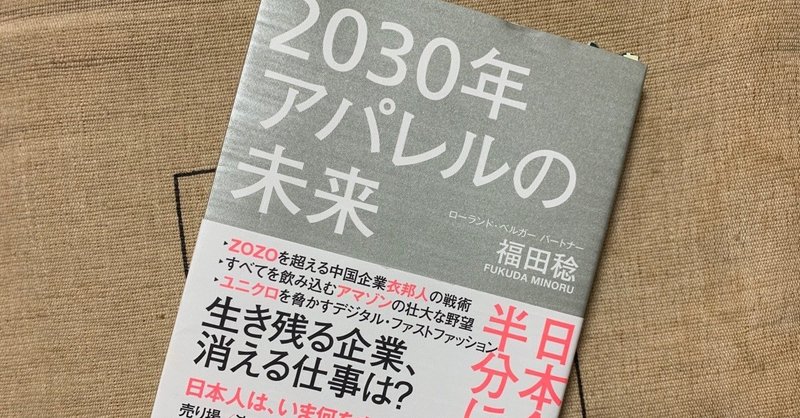
ファッションテックとエシカルの未来。『2030年アパレルの未来』福田稔(エシカル100考、37/100)
エシカルファッションとテクノロジーは相性がいい。
多様な身体や嗜好にカスタマイズして受注をとり、ダイレクトに顔の見える作り手とつないで、データベースから伝統などの技法を参照しつつ、ゴミや廃棄が少ない生産をして、輸送のエネルギーロスを抑えて配送し、リペアやリユースの循環にもすぐつなげられて、、という、エシカルファッションとして必要と思える要素の多くは、テクノロジーによって実現できるはず。
最新のテクノロジーと、グローバルな人と物とのつながりとに基づきながら、懐かしい未来を作っていこうというのがこれからのエシカルだ。
エシカルファッションって、ふんわりナチュラルじゃないのよ。エシカルはアーミッシュじゃないのよ。
だからエシカルファッションに興味を持つ人は、ファッションテックに貪欲にならないと。
『2030年アパレルの未来』は、ローランド・ベルガーのコンサルの方がファッションテックにより変わりつつあるアパレル業界の情勢を伝えつつ、日本のアパレル市場の現状と課題、未来予測と警鐘を書いた本。まとまり良く、勉強になる。
先に不満点を挙げると、素材のことは書いていない。
生産・流通・販売・マーケット・人事など広くカバーしつつも、廃棄プラスチックからできる再生ポリエステルやオレンジから作られるOrange Fiberやという、これからの技術進歩により出てくるであろう素材については触れられていない。ひるがえってオーガニックコットン等の自然素材についても言及はない。
その不満点に連動するのか、サーキュラーエコノミーについても書いていない。
服だけでなく、生活用品(消費財ってやつ)市場のこれからを考える上でサーキュラーエコノミーへのシフトは外せないと思うけど、ぼんやりと示唆されているくらい。ただシェアやサブスクリプションについては当然しっかり書かれている。
まあ、アクセンチュアの絡みがあるサーキュラーエコノミーについて、ローランド・ベルガーの人が書くわけにいかないのだろうけど。。
エシカルについては、ちょこっと単語が出てくる。
第2章「アパレル業界で進む、デジタル化がもたらす10の本質的変化」が面白い。
1は、ファッション情報をブランドが独占する時代は終わり、情報の非対称性がなくなることにより、能動的な消費者が発信者となる変化。
2は、逆に受動的な消費者はとりあえず流行のものを買うのではなく、自分に合うもののレコメンドをさらに求める。ビッグデータが活躍する場面。
3はDtoC、自社企画商品の消費者への直販。DtoCはニッチ・コアなファンをしっかり握りそこへものを届ける、痒い所に手が届くビジネス。小さく初めて確実に勝てそうなモデルとして書かれている。
胸の大きな方向けのoverEさんや、小柄女性向けのCOHINAさんや、体形の悩みに応えるブランドが成功しているのはこれに当たるのかな?和田さんとこ(overEさん)、あんまりデジタルって気がしないけど(失礼・・)。
高身長女性向けだとATEYAKAさんもあるし、男性も着られるジェンダーフリーな女性服のblurorangeさんなどもあり、この領域は楽しい。
MODALAVAさんもいるし。
4はファッションの情報格差がなくなって、双方向型へ。
5は大事。画像解析やデータ解析により在庫リスクなく、需要予測できるとある。
実際の採寸と画像解析をからめて人の身体データをとっておいて、アバターで試着して服を買えば在庫いらないでしょ、みたいな話しもあるよね。
で、そこらへんを上手く活用した「デジタル・ファストファッション」というのが台頭しているんですね。これは面白いしすごく可能性あると思った。
6はちょっと素材の話。ウェアラブルデバイス繊維の服みたいのできるかもということ。
あれか?、スパイダーマンのスーツ(スーツ自体がAIで、しゃべる)とか、攻殻機動隊の草薙素子の服(光学迷彩とかいろいろ)みたいなもんか?
7も大事で、服作りのリードタイムの短縮。パターンに起こすとかがなくなり、デザインを描くだけでさくっと製造工程ができちゃう。3Dプリンターの服版みたいな感じかな。
同時に、H&Mが投資している研究でみたけど、どう布をカットすれば余り布(ゴミ)を最小にできるかとかも計測できるようになったりするのかなと。
8は、服作り工場の効率化。遠いバングラデシュのラナプラザに人を缶詰にするんじゃなく、東京とかの最終消費地の近く(商品を早く届けられる場所)に省人化された小規模工場ができるのでは、ということ。
小さな縫製工場などの効率的な活用が進み、地産地消の服作りなんかができるようになるのかな、と思う。一方で(いいか悪いかは別として)いわゆる途上国などで工場で働く人には影響出るのかもと思う。
9も大事、マス・カスタマイゼーション。ZOZOスーツの例が出ているけど、画像解析&データ分析などで個々にカスタマイズされた服を受注生産することを、マスに向けてやれるようになる。
「受注生産」&「大量生産」の両立っていうのは、一つの答えな気がする(ここでいう大量生産とは、一つの商品を大量に生産するのではなく、たくさんの人に向けて生産するという意味の大量)。
10は人事管理について。アパレルの世界の人事って超古いよねってこと。うん、古いよね。
この第2章はいろいろ考えさせられた。
第4章で先進企業の事例紹介があるけど、サステナビリティ徹底重視の「リフォーメーション」さんというところ、恥ずかしながら知らなかった。要チェック。日本でも買える。
後半は日本の市場分析とアパレル企業はどう生き残りをはかるべきか、が書かれている。
なるほどと思ったのは、日本の市場は以前はフォロワー層(TV見てキムタクが着てた服を買う層?)が大部分だったけど、いまやその層が分裂、細分化しているという話し。
分裂して、1ライフスタイル追及層、2消費志向層、3伝統重視・保守層、4人間・家族重視層、5社会志向層、6先進・革新志向層、7快楽主義層、8件約志向層に分かれるとある。
細かい解説はさておき、エシカルファッションだと、当然、5の社会志向層が対象になる。
だけど社会志向層だけでなく、ライフスタイル追及や伝統重視や家族重視や先進志向なんかにも、エシカルは親しまれると思うなあ。
サーファーが環境配慮のブランド立ち上げたりとかって、ライフスタイル系な気がするし、サステナブルな先端素材とかって先進志向だと思うし。
社会志向層に途上国の雇用が云々いってストーリーで売ろうとし続けるのではなく、他の層にもしっかりアピールしていくことがエシカルファッションとしては大事ですね。
いずれにせよ、2030年にはエシカルファッションに興味関心が強い(教科書でフェアトレードって習っている)Z世代が生産人口の4人に1人になる。社会課題などに関心を持ちやすいミレニアル世代をいれると全体の65%になる。
それまでに、しっかり社会志向層を育てつつ他の層にもアプローチしながらブランドを成長させられるか、が各エシカルファッションブランドの課題かなあ、、と。あと10年頑張れってことになりますけど。。。
アパレルの近未来は、サーキュラーエコノミーのモデルを組み込んだ、マス・カスタマイゼーションに対応しているデジタル・ファストファッションなんだろうなあ、、と思うので(カタカナばっかだな)、そこにどう乗っかってくのかも考えないとね。。
最後に、この本で好感をもてたのが、とはいえ日本のアパレルが最初にやることとして、人のことを挙げていること。
デザイナーさんと販売員さんが報われていない。もっと報酬をだしていかないと、そこが競争の源泉なんだからという意見には大賛成です。
『2030年アパレルの未来: 日本企業が半分になる日』福田稔(東洋経済新報社)。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
