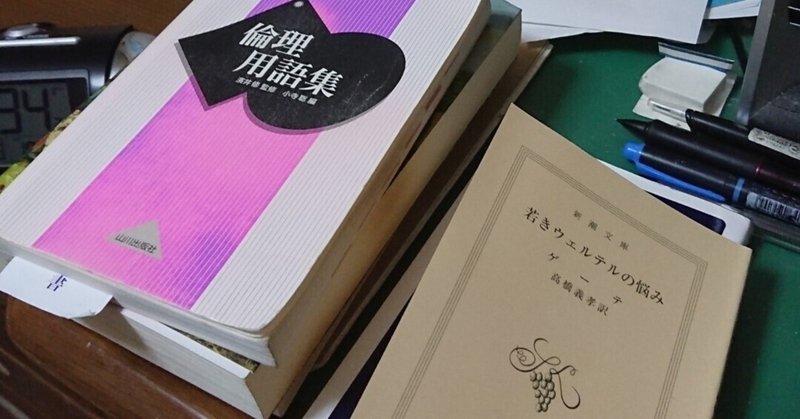
他者論に関する私小説的考察
「人口が密集すると倫理が生起する」とは、哲学者河本英夫の言葉であるが、ここで言う「倫理」とは、未だ田舎に残存するような自他の区別なく熱い良心をありがた迷惑のように注ぐ道徳心のことではなく、また、やはり田舎の上層に残存する封建道徳的倫理ではなく、やはり都市人の「他者論」的ふるまいの様式のことであろう。語義的に「倫-理」には、漢字の字面から直感的に理解できるように、秩序と欲望の関係において、けじめをつけることによって欲望を制約するような秩序的含意がある。だから、「高校倫理」のような生易しい雰囲気のものではない。高校倫理からきたした大きな誤解から哲学や思想を志す人も観測するかぎり少なくないが、そうした層の学徒はもはや我々の癒しである。そうして私は、先の河本のこうした意見に底知れぬ安堵を覚えるのである。いわばそれは、田舎から都市に漂ってきた根無し草の、いつでも帰れる故郷を再発見するときのその感覚かもしれない。例えば三鷹出身で横浜育ちの批評家東浩紀は、近著である『訂正可能性の哲学』で殊更「家族」ということを説いているが、私にはそうしたアクチュアリティはないのである。一方で青森の田舎ブルジョア育ちで文豪に憧れて東京に出てきた太宰治は、晩年の『人間失格』のほとんど最後の方で、致死量の睡眠薬を飲んだ後の描写として、
三昼夜、自分は死んだようになっていたそうです。医者は過失と見なして、警察にとどけるのを猶予してくれたそうです。覚醒しかけて、一ばんさきに呟いたうわごとは、うちへ帰る、という言葉だったそうです。うちとは、どこの事を差して言ったのか、当の自分にも、よくわかりませんが、とにかく、そう言って、ひどく泣いたそうです。
と書いている。私のような半ば故郷喪失者は、この「うちへ帰る」に、涙を禁じ得ないのである。太宰は乳母との愛着関係を形成して育ったのだが、その乳母がある日突如再婚のため去り、そして再会したときにはよそよそしい他所の母親になっていた、ということは、『津軽』に内面描写されている。すなわち、「母」が「他者」になったのである。一時期太宰治の黒歴史ノートが公開され、ネットでも笑い者にされていたが、あそこでノートの端に尊敬し同一化していたであろう「芥川龍之介」の名前をあれだけ書いていることを晒し上げられたことについては、死者の尊厳に関連して否定的な声が上がったが、実際には本人はそういう目に遭って内心で喜ぶような人だったのではないかと思わないでもない。
晩年の芥川龍之介の話ですが、時々芥川の家へやってくる農民作家――この人は自身が本当の水呑百姓の生活をしている人なのですが、あるとき原稿を持ってきました。芥川が読んでみると、ある百姓が子供をもうけましたが、貧乏で、もし育てれば、親子共倒れの状態になるばかりなので、むしろ育たないことが皆のためにも自分のためにも幸福であろうという考えで、生れた子供を殺して、石油罐だかに入れて埋めてしまうという話が書いてありました。
芥川は話があまり暗くて、やりきれない気持になったのですが、彼の現実の生活からは割りだしてみようのない話ですし、いったい、こんな事が本当にあるのかね、と訊ねたのです。
すると、農民作家は、ぶっきらぼうに、それは俺がしたのだがね、と言い、芥川があまりの事にぼんやりしていると、あんたは、悪いことだと思うかね、と重ねてぶっきらぼうに質問しました。
芥川はその質問に返事することができませんでした。何事にまれ言葉が用意されているような多才な彼が、返事ができなかったということ、それは晩年の彼が始めて誠実な生き方と文学との歩調を合せたことを物語るように思われます。
さて、農民作家はこの動かしがたい「事実」を残して、芥川の書斎から立去ったのですが、この客が立去ると、彼は突然突き放されたような気がしました。たった一人、置き残されてしまったような気がしたのです。彼はふと、二階へ上り、なぜともなく門の方を見たそうですが、もう、農民作家の姿は見えなくて、初夏の青葉がギラギラしていたばかりだという話であります。
これは、モラルとアモラルということをテーマにした坂口安吾の『文学のふるさと』の一場面であるが、この「晩年の芥川」が「突き放され」る描写には、私は戦慄を覚えるものである。普段我々は「他者」と言っても、本当の「他者」に出会っていないのであるが、こうしたときの、他者性の不気味さ、或いは「事実がただある」というこの「ただ世界があった」というこの「アモラル」の感じは、我々各々の「他者」感覚の原点である。安吾は殊更「天皇制」ということを問題にして取り上げるが、考古学的にも神話的にも、我々のやまとの原点は母権制なのである。それらの一群の論考で安吾の述べる「冷たい氷」のような感覚とは、或いは彼がいくつかの作品で展開した母性社会日本の欺瞞の暴露だったのだろうと思う。
世紀末的な哲学を残したマルティン・ハイデッガーはその存在論で「何となく不安」ということを実存的死の議論に立てたのであるが、彼は「存在としての存在」に対して、ニーチェの「力への意志」或いは「権力への意志」を「最後の形而上学」と断罪した。「権力への意志」はニーチェの妹エリーザベトの影響でナチスに利用されるのであるが、そうした諸々のことからハイデッガーがナチスに接近したことには当然視する声と疑問視する声が入り混じるのである。ただ、私のこの議論の運びからいくと、明らかにハイデッガーの世紀末的不安の哲学は、ナチス、或いはヒトラー哲学に救済を求めざるを得なかったのだろうと思う。
「他者論」の代表的人物であるユダヤ系哲学者エマニュエル・レヴィナスは、30年代の早い段階で「ヒトラー主義哲学に関する若干の考察」という論文を出しており、その危険性を告発している。レヴィナスは東欧からパリに移住する際に母親を伴うほどの人物であった。私は来歴からも文豪たちやヒトラーに同一化するほうの者であるし、ナチスやハイデガーには安心感を抱くのであるが、その安心は、だから、家庭における母性愛的な安心ではなく、故郷意識に根差した共同体的な母性の安心感なのである。だからハイデガーは「民族の生起」を語ったし、日本の平和趣味的なリベラリストは「江戸時代の村落共同体」を語るのだろう。リベラルは「疎外」や「排除」に敏感だから、家庭を居場所とする言説がいかに残酷なものであるかをよく知っているのである。というのは、「他者論」には付帯的に家族の一体性がある。むしろ、「親の顔が見てみたい」ということほど暴力的で残酷な言葉はないと思うが、レヴィナスはあくまでもラビにトーラーの解釈を学んだユダヤの学者である。ユダヤ人の大義名分は選民思想であるが、それはすなわち「包摂と排除」の社会学の如く、身内に対して「厳しくも優しい<父>」と、異邦人への容赦のなさがあるのである。事実レヴィナスも一貫してイスラエルとシオニズムを擁護する主張を繰り返している。そこでユダヤ人哲学者たちにおいては「有限責任」などという生易しいことにはならず、どこまでも「無限責任」論が展開されるのであるが、その場合、例えばパレスチナ人の血の報いは未来永劫子子孫孫背負うものなのである。これははっきりとしているが、新約聖書中の福音書では、ユダヤ人の群衆がイエスを十字架につける要求をする際、その血の報いは我々とその子孫が担うということを言っている。この、無限の血の報いという、そうした伝統がユダヤにはある。だから、十字架の血潮が和解の徴などという気楽な考え方はないのである。そこから「異邦人」=「他者」論が読み解いていけるのであるが、おわかりのように異邦人の血も大地の叫びとなるのであり、その責任を被らなければならない点で、まさにそこにこそこの「倫理」の要点があるのである。
地獄とは他人のことだ
レヴィナスはサルトルを評価しているのだが、「地獄」を勝手に読み替えると、「他者」=神に対して自己を無限に低くすることの換喩とも言える。レヴィナスの場合、反ユダヤ主義者でもあったドストエフスキーから多大なる影響を受けており、その思想を高く評価しよく引用もしているのであるが、そうしたところからも、この代表的他者論にキリスト教の影響が入っていることは否めない。すなわち、「自分を低くする者は高められる」というものである。ちなみにニーチェはこの聖句についてのアフォリズムで、「自分を低くする者は高められたいと思っている」という趣旨のことを述べて皮肉っている。
多分、だから、この他者論は、ドストエフスキーの描いたイワン、或いはニーチェや文豪たちのあの自我意識過剰な主知主義の「治療」には大きな効果があると思う。既にしてドストエフスキーが『カラマーゾフの兄弟』でキリストに生きる「信」の人アリョーシャを、評論家で「知」を代表するれいのイワンの「治療者」として描いている。愛の受容体は余りあるのに、つねに渇いていることが問題なのだ。
ところで昨今岡田尊司を中心に話題の「愛着障害」であるが、言っておくと私は近々「発達障害」と「愛着障害」に焦点を当てていわば「新しい転向論」を書きたいと思っている。私は、神経科学的基盤をもつ発達障害を受容し、ボウルビィのアタッチメント理論やフロイト、ユングを嫌厭していた時期が長かった。それはあまりにも家庭主義的だから。私はプリミティヴに戦後日本の公教育のカント主義を、或いはあの平等で平和な「幻想空間」を信じ切っていた。むしろ今もそれがこのような私の基本的信頼の源泉となって生かしめているようなところがある。
さて、岡田の理論では、愛着障害には大別して「不安型」と「回避型」があるが、まず「回避型」とは生育歴によりオキシトシン受容体がそもそも少なく、積極的な愛着行動を示すこともない型のことである。一方の「不安型」とは、生後の期間で多くの愛情は注がれたためオキシトシン受容体は多いのだが、愛着関係に中断が生じたため不安が刷り込まれて「分離不安」をきたすような類型のことである。
ここで愛着障害を取り上げたのは、この類型が使いやすく、また愛がいつも他者を必要とすることからである。私がかつて「オキシトシン自足論」を書いたのも、また、代替案としてマッサージや散髪を提示するのも、恐らくオキシトシンの分泌に関しての提案に幻滅している人が多いだろうということを考えてのことである。というのは、結局いつも言われることは「スキンシップ」など他者依存的なことだから。欧米ならともかく、この日本文化でそれを提示してあまり意味あることだとは思えない。もはやスキンシップできる相手がいる人ならばそんな記事に用はないのである。
このように、私が『コンビニ人間』の書評でも書いたように、現代は確かに内向きの他者危害原則が尊ばれる時代である。社会の主力はむしろ動作性であるが、同時に、現代社会に適応的なのも不安型ではなく回避型であろうと思う。愛情よりも、人情よりも、むしろ子供を傷つけず支配もしない教育が叫ばれるこんにちにおいて、みんな傷つきたくないのである。しかしそうであれ人間であるかぎり愛情が必要である。そこで「家庭」や「コミュニティ」といった「うち」に閉じこもるのであろうという仮説を立てている。愛情が欲しいのに傷つきたくないのなら、気心の知れた人だけでほどほどの距離感で長く付き合ったほうがよいことは明らかなのだから、これは当然の成り行きである。
「愛撫」しようとすれば、すなわち近づけば近づくほど恋人は離れていく、という「エロスの現象学」と呼ばれる議論がある。
私の事例を述べると、2013年末の母の帰還において、母が私の部屋に猫を連れてきた。捨てるわけにもいかないから、私に押し付けたかたちだろう。最初は非常に戸惑ったが、すぐに打ち解けて、私は猫に対して太母的な甘やかしを行い、猫はそれに応えていつも私に体を寄せて甘えてきた。この経験が私に入り込んだがために、或いはイエスのように、母なる存在は友であらねばならず、友なる者は母であらねばならないという規定に支配されることになったように思う。人間関係の秘訣は距離感で、神関係もまた同様である。日本では見られていないからと言い酒を飲むムスリムのように、いかに信仰が体験的に入り込んでいてもほどよさが秘訣なのだ。しかし結局、これはなにか付かず離れずのような「倫理」に近いところがあり、中学になっても親に触れながらしか眠れず、またその後も猫と一緒の布団で寝ていたような私には相性が悪い。なにかその「エロス」とやらを後生の一大事のように語られてもあまりピンと来るところがないものである。
他者論では、他者に対して自己が無限に低くなるので、そのことから「他者は神」ということが言われる場合があるのだが、私にとってその意味での「神」の原体験は案外物心つく前から刷り込まれている絶対超越でありもするから、ユダヤ的経験は恐らく入り込んでいるようなところがある。
三島由紀夫は生後まもなくより祖母に育てられ、両親から取り上げられているのだが、この祖母が、三島の語るところによると「生長の家」の信徒だったということである。
谷口雅春師の著書『生命の実相』は私の幼時、つねに病める祖母の枕頭に並んでゐた。
燦然たる光明の下に生命の芽の芽生えるその象徴的デザインは、幼い私の脳裏に刻まれてゐた。
私の家庭は複雑で、父方の祖母の実家のすぐ隣であり、その祖母の実家が地方名望家的な明治的大家族だったのだが、かつてその敷地内に一家で信仰していた生長の家の道場があり、誌友や講師を招き地元の拠点として機能していたようである。私の生まれる頃になると勢力も衰えていたのであるが、やはり私の初正月は長崎の龍宮住吉本宮という生長の家総本山であったし、祖母が健在であったので、私の母はその指示で生長の家の「母親教室」を受講していたようである。そうして私が小学2年生の時、私が生長の家の練成会に押し込まれ非常な分離不安を感じている間に、母親は失踪した。この宗教右派による母性剥奪という経験は、青年期にアイデンティティに目覚める際に爆発的に陰謀論に傾倒する契機となったし、やはり同様に生長の家およびその原理主義グループ日本会議などと共闘的な関係にあった統一教会による母性剥奪という事態には、私は同情を禁じ得ない。
旧約聖書で神が「光あれ」と言うように、私は幼時より額縁に掲げられていた「人間 神の子 光の子…」という文言を祖母に唱えさせられていた。教義的には、ある意味で、その「神」は超越をも超越しているのである。だからその意味で、「無限の二重化」の議論はよくわかるところがある。すなわち、他者は否定態として現象するが、他者による否定→否定→否定…、或いは脱構築して解釈が定まればそこで脱構築し…というように、ユダヤ的な父殺しはギリシアのような一回限りのものではないのである。先に述べたような経験から、私はだから、「忠に孝に」というような軍国儒教の教育勅語は一貫して嫌厭しているのであるが、ユダヤも儒教も生長の家のように親を敬えという教義が最も色濃い。それらの宗教が親切なのは、明確にテクストとして言語化して諭しているところである。日本やギリシアのような巫女を中心とした教義なき多神教や、キリスト教のような柔和さといった話にはならない。イエスは、安息日のために人があるのではなく、人のために安息日があると教えるような男であり、また、随所で家族の論理を否定する青年の友であるから、あのニーチェがイエスを高く評価していたのも頷けることである。
太宰治に戻ると、彼の佳作に『トカトントン』というものがある。ある男が、軍で終戦の詔勅を受けた際に、上官が涙ながらに抗戦を訴えるが、遠くから「トカトントン」という、工事の音、或いは「再建」の音が聞こえてきて、途端に馬鹿らしくなって荷物をまとめて実家に帰っていったのだが、それ以来その男は何に際してもこの「トカトントン」の幻聴が止まなくなり、この音が聞こえて来るや否や急に萎えてしまうというものである。その悩みを「某作家」が受け取る。
この奇異なる手紙を受け取った某作家は、むざんにも無学無思想の男であったが、次の如き返答を与えた。
拝復。気取った苦悩ですね。僕は、あまり同情してはいないんですよ。十指の指差すところ、十目の見るところの、いかなる弁明も成立しない醜態を、君はまだ避けているようですね。真の思想は、叡智よりも勇気を必要とするものです。マタイ十章、二八、「身を殺して霊魂をころし得ぬ者どもを懼るな、身と霊魂とをゲヘナにて滅し得る者をおそれよ」この場合の「懼る」は、「畏敬」の意にちかいようです。このイエスの言に、霹靂を感ずる事が出来たら、君の幻聴は止む筈です。不尽。
この「畏敬」と「ゲヘナ」の末路があの心中だったと思うと筋を通しているとも言えるが、随所で生きようとしていた太宰が結局は死なねばならなかったということは、なにか引っかかるところがある。
また、芥川龍之介の最末期の作品は『続西方の人』という、イエスをテーマにしたものなのであるが、彼が死に際して枕元に『聖書』を置いていたことは記憶に留めておいてよい。
クリストは彼の弟子たちに「わたしは誰か?」と問いかけている。この問に答えることは困難ではない。彼はジャアナリストであると共にジャアナリズムの中の人物――或は「譬喩」と呼ばれている短篇小説の作者だったと
共に「新約全書」と呼ばれている小説的伝記の主人公だったのである。我々は大勢のクリストたちの中にもこう云う事実を発見するであろう。クリストも彼の一生を彼の作品の索引につけずにはいられない一人だった。
この「大勢のクリスト」、或いは大勢の「短篇小説の作者」は、これらの事実を少なからず考えてみたほうがよいのではないかと思っている。
無限の否定は一見すると無限の自己否定であるが、論理的に二重否定は肯定となる。なぜ「解釈のみ」という神の死後の哲学が「存在」でなければならなかったのか、或いは「他者」であらねばならなかったのか、そして「批評」でなければならなかったのか、ということは無視せずに考えたほうがよいことである。
ニーチェの非力さは救いようがない。
2024年1月23日
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
