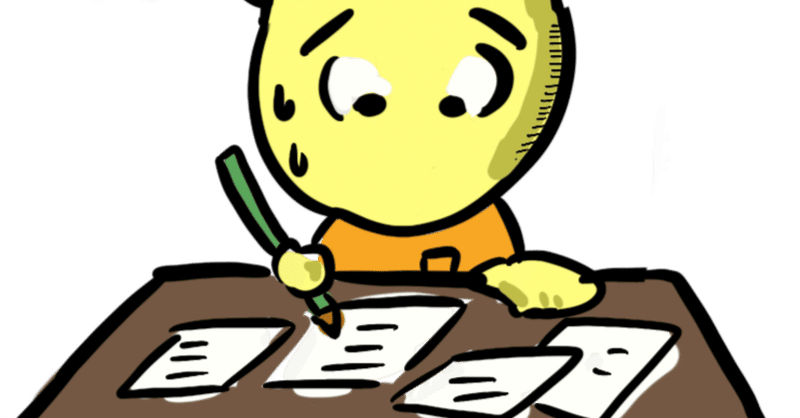
Photo by
algo2020
#1734 宿題を「やらせる」という愚行
現代の教師は、「宿題」という名の課題を子供たちに課す。
恥ずかしいことに、未だに私もその一人である。
宿題が「できる」子供は、きちんとやってくる。
一方で、宿題が「できない」子供は、「忘れました」と言い訳を言い、やってこない。
これを教師は見逃さず、「休み時間にしなさい」とその子供を叱りつける。
子供は完全に「受け身状態」となっている。
そして、教師に「やりなさい」と言われた子供は、休み時間を奪われ、宿題を「こなす」ことになる。
教師も、宿題をただ「やらせる」構図となる。
この構図となってしまった場合、教師にとっても、子供にとっても、「宿題を終わらせる」ことが自己目的化してしまう。
本来、宿題の目的は、「基礎基本の習得」のはずである。
それが「終わっていないから、終わらせる」ことが目的となってしまうのだ。
これでは、本末転倒である。
確かに「きちんと宿題をやってくる子供がいる中で、宿題をやらない子供がいる」という事実は、教師として気持ちが悪く、違和感を感じるだろう。
しかし、それを我慢し、「無目的にやらせる」という道を選ばないことが重要となるのだ。
宿題の中味である「学習内容の基礎基本」というものは、一定の間隔を開けて、反復学習をすることが有効となる。
なので、翌日の休み時間に無目的にやらせるのではなく、期間に余裕をもって進めさせることが重要なのだ。
「終わらせる」「こなす」のではなく、覚えるため、理解を確かめるため、基礎基本を定着させるために学習させるのである。
よって、期間に余裕をもって、何日かけて学習してもよいはずなのである。
それが脳科学的にも有効なのである。
本質・目的を見失わないようにしたい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
