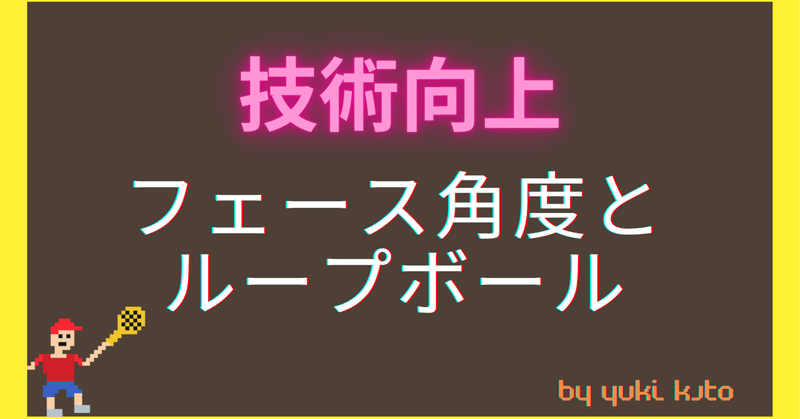
【テニス】振り遅れ?を減らす意外だった観点(ループボール)
皆さんこんにちは。加藤です。
ストロークの安定とは何だろうと考えている今日この頃です。
それについて相方Aの話が意外な観点だったので、覚えている範囲で書いていきます。
相方Aは、最近振り遅れのような当たりが何回かあり、相手の球がすごく速いわけでもなく、動作が遅れている訳でもなく、なんでだろうと考えていた結果、一つの発見があったとのこと。
それは、シンプルに面が横に開いてインパクトに向かっていたことです。
長いこと全然気づかず、トップスピンをかけているからそこはないだろうと思っていたのが盲点でした。
振り遅れたら、打点を前にするとか、準備を早くするなどの方向に頭が行きがちで、そこを意識しても直らなかったので、なんでだろうとずっと気になっていたそうです。
なので、ラケット自体を打点より少し下から出すようにしたら解消したとのこと。
皆さんもありませんか?
打点も前で準備の早さも良い感じなのにたまに出る「振り遅れ感」
もしかしたら相方Aと同じ原因かもしれません。

そして、話は「ストロークの安定」につながります。
テニスというスポーツのルール上「ネットを越えて、相手コートのラインを越えない球」を打たなければなりません。
必然的に図のようなループボールを打つ必要があります。
弾道が高ければネットしにくい、ボールの飛距離が短くなればアウトしづらい。
そんなボールを打つことが、安定してコートに入りやすいストロークと考えます。
高くて短くできる球…そうトップスピンです。
ストロークの上達の過程で、ボールスピードを上げていきたい方は同時進行で覚えて欲しいのがこのトップスピンです。
ボールのスピードが上がるほど、飛距離は伸びていきます。
この伸びた飛距離を短くするためにはトップスピンをかける事がはずせません。
ボールの飛距離は
・弾速
・弾道
・スピンコントロール
で決まります。(気圧の差などは一旦置いといて)
仮にトップスピンをかけない場合、弾速と弾道でコントロールすることになります。速いボールを打つ場合、弾道を低くしなければならないため、ネットにかかるリスクが高くなります。
フラットやスライスがメインの方は、力加減と弾道で飛距離コントロールを行うことが多くなります。

もちろん重力や空気抵抗がありますので、フラットのボールが全く落ちないと言うわけでもありません。
同じスピードで飛んでいった場合、トップスピンの方が短くなるということです。

また、フェース面をイメージ通りの角度に調整しようとしても、多少はズレるものです。
上の図は大袈裟ですが、角度が上下どちらに多少ズレても上方向にボールを飛ばせるようなフェース面で、スイング軌道に対してフェース面が少しでも下を向いていればトップスピンでループボールが打てます。

上の図をボールが高弾道になるように図を回転させていくとわかりやすいかと思います。
トップスピンの原理については、以下の記事を読んでいただけると理解しやすいと思います。
有料ですが、興味があればぜひ
私の考えでは、
ループボール→高スピン高弾道
アタック→低スピン低弾道
であり、ループボールがトップスピン、アタックがフラットという2種類ではなく、どちらもトップスピンです。
スピン量と弾道を変えて、ループボールとアタックを使い分けます。
相方Aもフラット気味に打とうとしたときに振り遅れが生じたとのこと。
アタックボールもトップスピンと同じような感覚で、弾道だけ低くしたらいい感じになったらしいです。
ストロークのロングラリーなどでは、いきなり理想のボールを打とうとせず、少しだけ弾道高めから始めていって、リズムが整うのとともに理想のスピードと高さに近づけていくのが良いと思います。
ではでは。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
