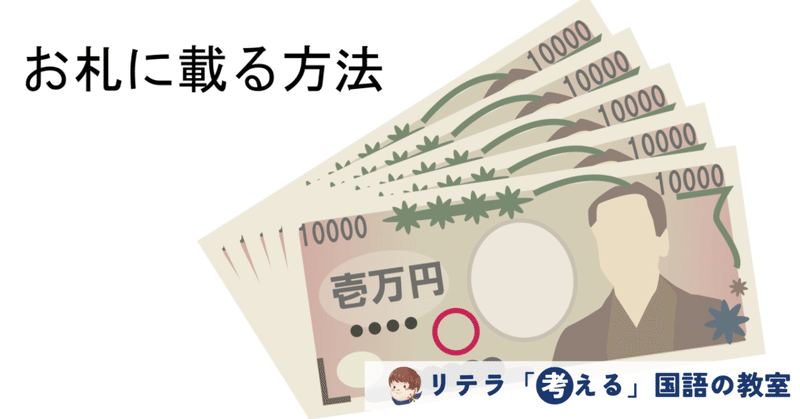
『お札に載る方法』~お金の顔になりたい!~リテラ探求学習研究レポート
有名になってお札に載りたいという夢を持っているTくん。
では、どうすればお札に載ることができるのか、歴史上の人物たちの功績をついて学びました。
この研究をしたのは新中学2年生のD・Tくんです。
■プレゼンテーション動画
■リテラの先生からのコメント
昔のお札には載っていた偉人たちを調べることは、日本の歴史をたどることに似ていていましたね。
そして、最近のお札には文化面で活躍した人が多いというのも良い気づきでした。
D君が将来の自分を考え、取り組むことが、お札に載るための一歩なのですね。
D君の肖像が載ったお札で買い物をする日を楽しみにしています。
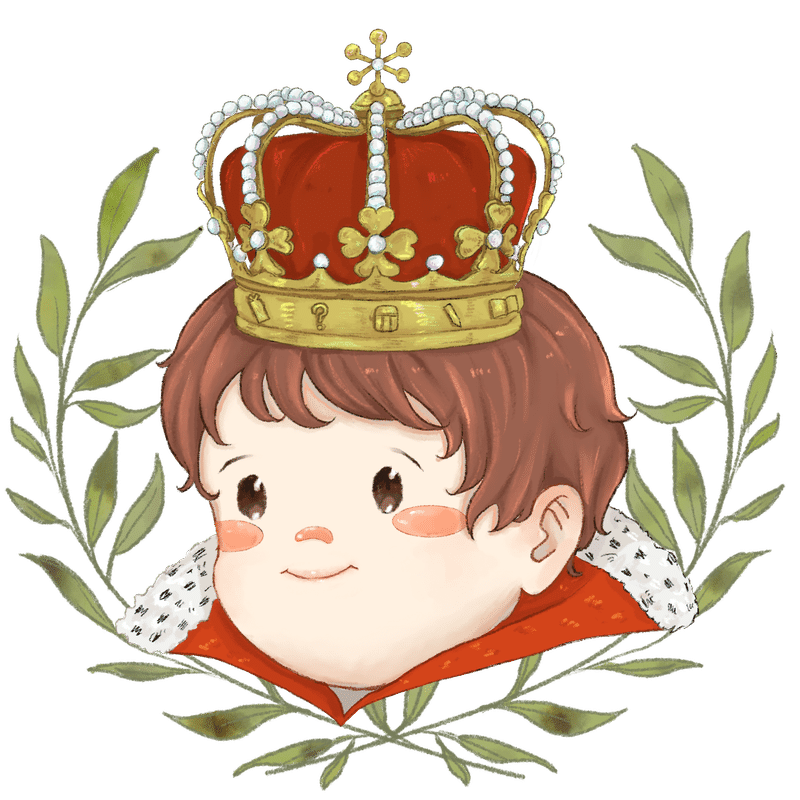
■テキスト資料
僕はお札に載る方法について研究しました。
なぜなら、ぼくは、有名になりたいからです。
お札に載っている人物達は、ほとんどの人が知っている有名な人達です。
そのため、お札に載っている人について調べたいと思いました。

ぼくは、過去に発行された様々なお札に載った人達の業績について調べました。
すると、政治方面で活躍した人物と文化方面で活躍した人物の二つに分けられました。

では、まず政治方面で活躍した人物のなかでもかなり有名な人を三人紹介します。
特にお札の発行された年などを見ていただけると幸いです

一人目は、中臣鎌足です。
1900年にお札になりました。
この人は645年に大化の改新を行った人の一人です。
この人は中大兄皇子につかえており、大化の改新後、藤原の苗字を貰っています。
平安時代で活躍する藤原家は、この人から始まりました。

二人目は、聖徳太子です。
聖徳太子が初めて発行された百円券は、1946年に流通しました。
この人は、推古天皇の摂政を務めており、十七条の憲法や冠位十二階を作りました。
また、遣隋使の派遣も行いました。

三人目は、板垣退助です。
1954年にお札になりました。
この人は自由民権運動の先頭に立った人です。
また自由党の総理にもなりました

つづいて、文化方面で活躍した人を三人紹介します。

一人目は、夏目漱石です。1984年にお札になりました。
この人は、とても有名な文豪です。
代表作は、『ぼっちゃん』や『吾輩は猫である』など、教科書にも載るような作品を書きました。

二人目は、樋口一葉です。
2004年にお札になりました。
この人は、小説家・歌人で、『たけくらべ』や『にごりえ』を書き、文学界で有名になりました。

最後は、北里柴三郎です。
2024年の7月4日からお札になります。
この人は、細菌学者であり、ペスト菌を発見しました。
ペストは世界中で大流行した致死率の高い病気でした。

気付いたことは、お札を発行した年が現代に近づくにつれて政治方面で活躍した人よりも、文化方面で活躍した偉人が増えていることです。
つまり、現代では、政治で有名になるより、文化で有名になる方がお札に載りやすいことが分かります。
では、文化で有名になるとはどういうことでしょうか。
文化では、たとえば、スポーツや、食文化、学問を追究したり、新しい技術を開発したりすることなどが考えられます。
北里柴三郎のように医学者になって、治せないと言われた病気を治すようなことをすればお札に載れるかもしれません。
または、大谷選手のように世界的に有名になれば、可能性は見えてきます。
このように考えるお札に載るために大切なことは、自分の将来について考え、その将来に向けて取り組んでいくことだと思います。
だから、僕は、将来の夢から決めたいと思います。
そして、いつかお札に載りたいです。
これで発表を終わります。
聴いてくださり、ありがとうございました。

■研究の振り返り
◇これはどのような作品ですか?
お札に載る方法について考察した作品です
◇どうしてこの作品をつくりたかったのですか?
お札に載り有名になりたかったから
◇作品づくりで楽しかったことは何ですか?
昔のお札は、政治で有名になった人で、今のお札は、文化で有名になった人ばかりだったから
◇作品作りを通して学んだことは何ですか?
自分の将来について考え、その将来に向けた取り組みをすること
◇次に活かしたいことや、気をつけたいことはありますか?
もう少しゆっくり喋りたい
◇来年、研究したいことはありますか?
学歴社会について
◇この作品を読んでくれた人に一言
お札に載れるように精進します
この記事を書いた生徒さん

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
