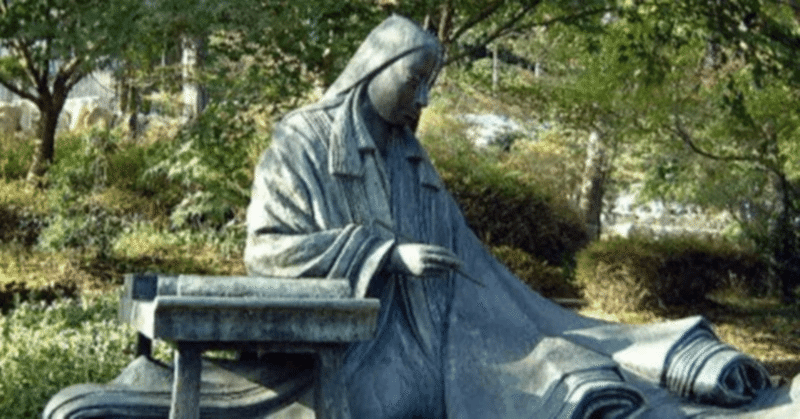
「光る君へ」第19回 「放たれた矢」 政の現実を進む道長と政に夢を抱くまひろとの相違
はじめに
道長の政は好調な滑り出しを見せました。それは、帝の信頼を得、適切な人材登用を行い、陣定の議論を重視しながらも果断な判断はしたことにあります。つまり、政に関わる者たちの意向を無視することなく、総意としてまとめあげるのが、道長の政権運営の基本ということです。
とはいえ、道長政権のスタートダッシュは、前政権への溜まりに溜まった反発を利用したご祝儀相場。だからこそ、道長は道隆の専横が招いた失策の数々を反面教師にして、慎重に堅実に物事を進めています。最初から理想の大風呂敷を広げることはせず、情報収集や政治工作といった現実主義的な面にも余念がありません。その意味では、兼家の政治手法を正しく継承しているのです。
全てがうまく噛み合うその政は、世の中が未だ民が疫病に苦しむなど苦境の世にある中でも希望を抱かせる爽快さがありました。ようやく、道長は、まひろとの約束「民を救う」政を現実のものとして始めるのだと、視聴者にも印象づける効果にもなっていますね。
一方、まひろは、宣孝の宋の話、白楽天の新楽府から、政への新たな夢を抱き始めます。身分の壁を越えた政…それは平安期においては途方もない夢です。基本的人権、法のもとの平等が明文化された現在さえ身分の壁は打破されたとは言い難い…それほどに難しいもの。
ただ、ふとした偶然から、その願いは一条帝の耳に届き、まひろの胸をさらに熱くさせます(やや暴走気味に)。またその思いは、刺激を受けた帝から道長にも伝わりました。それが、為時の昇進へとつながるときが、道長が始めた政とまひろの新たな願いの臨界点でした。
しかし、政治の表舞台に立ち、全責任を追いながら現実を生きる道長と、その道長よりも先んじた夢を抱くまひろ、その二つは今回のように交わり化学反応を起こすこともあるでしょうが、逆に生きている世界の違いから決定的にすれ違い、道を違える可能性も暗示しているようにも思われます。
そこで今回は、道長の政が目指すところとまひろの新たな夢、その二つを比べながらその行方について考えてみましょう。
1.帝の信を得、その意を汲むこと
(1)帝との対面
冒頭は、右大臣になった道長が一条帝に就任の挨拶をする場面です。太政大臣、左大臣はなく右大臣となった道長こそが人臣の頂点。実質、太政官の長となった彼に「朕の力になってくれ」と頼む帝の言葉は切実です。そもそも、道長に内覧右大臣を任じたことは帝の本意ではありません。
彼自身は、既に内大臣であった伊周を関白に据えることを決めており、幼い頃、東三条殿で遊んでもらった記憶ぐらいしかない道長をその座につけることは埒外でした。それを曲げたのは、母詮子の涙ながらの訴えに配慮したからです。おそらく、その訴えにあった道隆の専横を伊周が継ぐという文言は、彼を揺らがせたと思われます。一条帝は道隆に対する公卿らの不評を秘かに見聞きしていましたからね。
結果、自身の本意と母の懇願の折衷案として、道長を内覧右大臣止まりとして、関白にまではしない宣旨を出しました。勿論、定子が「帝の私へのお心遣い」(第18回)と言うとおり、その宣旨には寵愛する中宮への配慮も含まれており、彼の葛藤と苦渋の決断です。それだけに自身の意を曲げたこの選択が正しかったのか、今なお自信が持てないでいるのです。普段、政に口を挟まないであろう定子が、「お上をよろしく頼みます」とわざわざ口を添えるのは、そんな帝の苦悩を察しての愛情でしょう。
二人の頼みに「神明を賭してお仕えいたす所存にございます」と道長は真摯に答えますが、帝にしてみれば、言葉自体は儀礼的、型通りのものでしかない以上、道長の本心は窺い知れません。御簾の奥、帝は迷いと戸惑いの表情を隠しきれません。この期に及んでも道長を公卿の主座に据えたことに不安がよぎるのです。
それは、よく知らない道長が、道隆の専横の二の舞を演じることを恐れてのことでしょう。母の意向を押し切ってまで伊周を選べなかったことも、結局は道隆の専横を継承する可能性を憂慮したからです。
苦悩する若き帝は、逡巡しながらも「一つ聞きたいことがある」と意を決すると、「そなたはこの先、関白になりたいのか、なりたくはないのか」と問い質します。なりたいと言えば、ならせるものではありませんし、御簾越しで帝の表情が窺えない以上、ここは「お上のお心のままと存じます」という無難な答えをするのが妥当でしょう。勿論、一条帝はそんなおためごかしを聞きたいわけではありませんが、そんな答えが返ってくるとしても聞かずにはおれなかったのだろうことは、その暗い表情から察せられます。
すると道長は「なりたくはございません」と即答。意外な答えに一条帝が理由を問うと、「関白は陣定(じんのさだめ)に出ることができません。私はお上の政のお考えについて陣定で公卿たちが意見を述べ、論じ合うことに加わりとうございます」と明快な答えを淀みなく述べます。
前回のnote記事で、道長が関白職を要らないと言った理由については、俊賢と明子の会話から、現場主義と自らの政治基盤を太政官に求めたことが主だと推察しましたが、まさにそのことが道長自身の口から説明されましたね。
それでもなお「関白も後で報告を聞くが?」と問う帝には、道長の言葉が真か否かを探る意図がありますね。睡眠を削ってしまうほど政に悩む一条帝の思慮深さは、こうしたちょっとした言動にも表れます。その問いにも、道長は「後で聞くのではなく、意見を述べる者の顔を見、声を聞き、共に考えとうございます。彼らの思い、彼らの思惑を見抜くことができねば、お上の補佐役は務まりませぬ」と迷いなく応じます。
道長の返答の裏には、苦い経験があります。例えば、相手は公卿ではありませんが、直秀の助命を頼むため検非違使の看督長に賄賂を渡したことがありました。しかし、彼らの思考の仕方を知らず、思い込みで行ったそれは、結局、直秀を死に追いやりました。また、参議になったばかりの頃、陣定の空気を読めず、青臭い理想論が通じなかったこともありました。そして、道隆の専横がいかなる公卿の不満を招いたかも直接聞いています。
これらの経験は、政は一人で行うものではなく、相手の思惑を見極めなければ、自分の意向を叶えることはできないことを知らしめたでしょう。謙虚に話に耳を傾けることが大切なのです。道長自身は、「何もできていない」と忸怩たる思いを抱いたこともありましたが、結局は彼の血肉となり、帝への決意の言葉となっているのですね。
そして、この返答の末尾、「お上の補佐役は務まりませぬ」という言葉が効いていますね。道長は、帝に代わって自身が政務を行うとは言わず、自身は「補佐役」だと明言しました。あくまで政の主体は帝であり、その意向を尊重するという立場を明確にしたのです。「朕の力になってくれ」という帝の思いに応えたと言えるでしょう。
この回答に「これまでの関白とは随分と異なるのだな」と軽く驚く一条帝の顔は、みるみる明るいものへと変わっていきます。先にも述べましたが、彼は秘かに公卿らの本音を盗み聞いています。その忌憚ない言葉は、時に彼を傷つけ、悩ませますが、それでも彼らの意向を十分考慮した上で裁可をくだしています(あまり報われていませんが)。
皆の意見を広く聞きたいと願う彼にとって、道長の「意見を述べる者の顔を見、声を聞き、共に考えとうございます。彼らの思い、彼らの思惑を見抜くことができねば、お上の補佐役は務まりませぬ」という政治姿勢は、まさに、我が意を得たり!との思いだったことでしょう。道長は、帝と同じ方向を向いているのです。ようやく帝は、道長を公卿らの主座とするこの度の判断が、間違っていないと確信を持てたからこそ、晴れやかな表情になったのです。
その言葉に、「異なる道を歩みとうございます!」と気を引き締めたキリっとした顔のクローズアップで、この場面は終わります。いよいよ、道長政権の到来を高らかに宣言したと印象付けるアバンタイトルになっています。
ところで、本作の道長は、内覧は別として右大臣になることは既定路線でした。関白が決まった道兼は生前、道長を右大臣にすることを明言していました。このときは、左大臣源重信も存命でした。また、道兼は、内大臣に就いた伊周の民を軽んずる言動を、「そのような考えで内大臣が務まるとは思えんが…」(第16回)と窘めていますから、伊周に政治的資質がないことも知っていました。ですから、道長を右大臣に起用することは、伊周を内大臣に据え置くという腹づもりであったと察せられます。
つまり、この度の一条帝の宣旨は、期せずして、道兼が関白になったときの政治体制と同じ形になったのです。おそらく、関白道兼の後ろ盾のもと、道長は陣定を活用して現場主義の実務を行うというのが、兄弟の志だったことでしょう。道長は、自らの政権の中で道兼との約束も実現しようとしているのだと思われます。前回note記事で深読みしたように、やはり道長の心には、未だ亡き道兼が関白を務めているのかもしれませんね。
(2)帝の補佐役とは?
さて、右大臣になってすぐ、道長は、蔵人頭である俊賢から「伯耆国と石見国の申し出を受け入れ、租税を1/4免除しては?とのご叡慮にございます」と帝から減税の提案を受けます。それを聞く道長は「さすが、帝であられる」と微笑みます。好意的な道長の反応に「同意されるのでしょうか」と確認する俊賢に「無論、同意だ。帝は民を思う御心があってこそ…帝足り得る」と応じます。
道長は、「聖君の基本は徳である」…このことを帝が理解していることに感心したのです。また、それでいながらも、25%という具体的な数字を明示してきたあたりに、彼が訴状を知り、よくよく考えて道長に提案していることも窺えます。自己顕示欲、自己満足による横暴でもない点が、花山帝の減免策と違う点です。
俊賢と同じ蔵人頭の斉信は「陣定は大荒れになりますぞ」と、道長の政権運営を憂慮して反対しますが、道長は意に介しません。「帝は民を思う御心があってこそ…帝足り得る」との言葉は、帝が政の徳を体現者として守り、さまざまな批判や抵抗の矢面に立ち、実務を担当するという道長自身の内覧右大臣としての覚悟も示しています。それは、公卿らの反対に合うだけではなく、逆にその意向に反対し、帝からの叱責に耐えることも含まれるでしょう。彼は自らが人に恨まれる汚れ役を引き受けることを厭わないのです。
帝の意向を受けた陣定では、公任、道綱、実資、顕光ら6名が、帝の意向に賛同し、隆家以下2名が「わかりませぬ」と態度を不鮮明にし、様子伺い。大勢は帝に優位なのですが、ここで伊周だけが「よろしからず」と明確な反対意見を述べます。議論を主とする陣定、反対意見が出ることは正常で、また少数意見であっても尊重されるべきです。大切なのは、その意見の理由、あるいは根拠です。
伊周は「二国の税を免じれば、他も黙っていない。そのようなことで朝廷の財を減らして良いのか」と述べると、そうだろうと言わんばかりに一同を見回します。そして「甘やかせばつけあがるのが民。施しは要らぬと存ずる」と、帝の民を思う御心自体を言下に否定します。自身の理屈が、周りが同意すると信じ切った自信満々の物言いと振る舞いです。
伊周は、疫病についても「貧しい者がうつる病ですゆえ…我々は心配ないかと存じます」(第16回)と述べるなど、根本的に民を軽んずる傾向がありますが、今回の理屈は、以前、国司の横暴を富裕農民らが上訴した「国司苛政上訴」を退けたときの道隆の「強く申せば通ると思えば、民は一々文句を言うことになりましょう。他の国の民も国司の小さな傷を言い立てるようになることは阻まねばなりません」(第13回)とまったく同じものです。
あのときは、「国司苛政上訴」が富裕農民層の私利私欲の側面があり一定の正当性もありました。また、受領国司の横暴の実態を知らない公卿らも私欲を優先したため、道隆の意見が多数派となりました。ただ、「民の声には切実な思いがあるに違いありません」という道長の意見は無視され、道隆の意見が内包する、現状維持しか考えない保守性、民を侮蔑する意識といった問題点はかき消されてしまいました。
そして、その後、摂政、関白となった道隆の執政では、終始、現状維持しか考えない保守性、民を侮蔑する意識が徹底され、結局、疫病は蔓延し、世は乱れることになりました。いくら自らの利権を守ることに煩い公卿たちも、この現状を変えること、それを生み出した道隆の失策は断つというのが共通認識でしょう。また、あのときと違い、今回は民を救いたいという帝の強い意向もあります。ですから、公卿らの大半が、減免案に賛同したのです。
こうした状況の変化とそれに対する公卿の思惑がまったく理解しないまま、伊周は道隆と同じ論法で反対意見を述べています。伊周は、またも自らの底の浅さ、志の低さを露呈してしまいました。道隆任せで権勢だけを指向する彼は、やはり道隆の劣化コピー以上になり得ないのでしょう。陣定の主役になることはできません。
逆に道長は、帝の意向に対して公卿らの反発が薄いことを見極めたうえで「未だ疫病に苦しむ民を救うは、上に立つ者の使命と存ずる」と正論を述べます。この言葉は、これまでの道長の主張そのものであり、その発言には信念が宿りますが、それを殊更強調せず、淡々と語ることで賛成派全体の意向のようにまとめてみせたのが上手いですね。青臭いだけだった青年は、公卿たちの意見と顔色をよくよく確かめ、効果的な物言いをするようになったのでしょう。
道綱のにこりとした笑い、かの日の道長の発言にただ一人目を見張った実資の頷きなど、陣定の空気は道長への賛同へ流れていきます。公任は、道長が議論の空気を上手く支配していく手管に感心しきりの表情です。こうして、陣定は無事、道長と帝の思惑どおりの形で終わります。
一人、この展開が面白くないのは、道長に正論をもって否定され、周りがそれに同調することに驚愕していた伊周です。彼には何故、公卿らが自分の意見になびかなかったかが理解できないのです。公卿の心を見ようとしない傲慢さ、民を軽んじるだけの了見の狭さなど、自身が抱えている問題にまったく思い至らない。自分自身の能力不足、人望の無さを省みることが彼にはできないのですね。ですから、この事態も、ただただ、道長に中関白家の権勢を奪われた結果と思い込み、道長への恨みを募らせます。
それが頂点に達したのか、伊周は公卿の大半が去ったところで、「父上と道兼の叔父を呪詛したのは、右大臣どのか」と苦し紛れの八つ当たりをし始めます。あまりのバカバカしさに「ありえぬ」と一言だけ返し、去ろうとする道長を「待て!」と声を荒げる伊周は、上司に対する礼儀も、叔父に対する敬意も完全に失しています。慇懃無礼だった彼ですが、最早、慇懃な態度すらできないほど余裕がありません。
権勢を奪われた口惜しさだけを剥きだしにすると「自分の姉である女院さまを動かして、帝を誑かしたのも右大臣どのであろう。女院さまを使って中宮さまに無理強いするのをやめろ!」と一方的に激高、つかみかかります。これを道長が鮮やかにかわしたため、伊周は無様に転がります。
伊周の言い草で笑ってしまうのは「中宮さまに無理強いするのをやめろ」の部分ですね。前回、関白になれなかった腹いせに、定子に「皇子を産め」と繰り返した伊周自身が、もっとも妹に無理を強いているのです。それを棚にあげて…いや、自身が無理強いをしているという自覚すらまったくないことが、この発言からは窺えます。
権勢を失ったことは道長の策略と皇子を産まない定子の不甲斐なさと信じ、自らを省みない伊周は、今回の中盤、久々に登華殿にて一条帝に拝謁した際も、恐れ多くも帝に「中宮さまには皇子をお産みいただかねばなりませぬゆえ」「中宮さまに皇子をお授けくださいませ」と繰り返し、「伊周はそれしか申さぬのだな」と帝を憂鬱にさせます。
かつて、花山帝の腹心だった義懐が、皇子を設けられませと側室を勧めすぎて信を失いましたが、それと同じことが伊周にも起きています。一条帝は心情的には、気心が知れた伊周に好感を抱き、今もいずれは公卿の主座に起用してもよいと思っています。だからこそ、再び参内するようになったことに安堵したのですが、伊周はそんな帝の気遣いも察することなく慇懃無礼な態度を取るばかりです。自ら帝の信用を失っているのです。
帝の「もうよい。今日は疲れた…下がれ」にはうんざりした響きがあります。それもそのはず、伊周が来る前に日中であるにもかかわらず、二人は睦み合ったばかり。努力なぞ散々しているのです。一条帝の憂いを横目で確かめた定子は、これまた沈鬱な表情をすると目を閉じ、押し黙ります。定子は、既に声望が高い道長の高潔さと兄とを比較して、その器の違いに呆れ果てているのでしょう。それが自分の後ろ盾となるべき兄であることが、彼女の気持ちを暗くします。
すごすごと退散した伊周は、愛人の三の君に、こうした定子らの様子について「中宮さまのお心がわからぬ」と愚痴っていますが、すべては自分の傲慢さの結果です。
このように、帝の意を汲み、陣定を重視する道長と、己を省みることなく自身のプライドだけを重視する伊周との間は、比較にならぬほどの差がつきました。政でも、物語上においても、伊周は既に蚊帳の外にいます。
2.道長を支える者たち
(1)縁故ではなく能力を優先した人事
陣定を終え、土御門殿で悩む道長のもとに同居する詮子が「何よ、難しい顔をして」と冷やかし半分の言葉をかけてきます。この姉が弟をわがままで振り回し、からかうのは、昔からのことです。道長は詮子の揶揄に目くじらも立てず、「除目の案を考えておりました」と返します。何気ないやり取りだけで、姉弟の変わらぬ仲の良さが窺えますね。
そして、人事に悩んでいると答えたばかりの弟に「この人を入れておいて」と加えてほしい人材をぶっこんでややこしくする姉の強引さも相変わらずです。しかし縁故による人事をすまし顔でしてくる詮子に対して、道長は「知らぬ者を入れるわけにはいきません」とあっさり突き返します。自分の思う政を成すためには、どういう人材をどこに配置するかを考える道長にすれば、人柄も能力もわからない人材は信用に足りません。
正論を返す道長に「伊周一派を封じるためには、私の知り合いを増やしておいたほうがよいと思うけど」と、政権の運営には派閥の形成と反対派に対する対策が重要である旨を説きます。一応、「よいと思うけど?」と伺う言い方をしているのは道長の存念を確かめる、試すといった意図もあると思われます。
果たして道長は派閥作りには関心なさげに「道隆の兄上のようなことはできませんね」と、書類に目を向けたまま返します。道長は、道隆の失策の誤りは身の周りをイエスマンで固め、他者の意見や思いに耳を傾けなかったことにあることを実感しています。道長自身が道隆に何度も献策を一蹴されていましたし、公卿らの不満も直に聞いています。だから陣定による議論を重視する方針に改めたのです。反対派を封じては意味がありませんし、また政に必要な公正性が保たれません。
道長の優等生極まりない「そうよね」と一応、賛意を示す詮子ですが「でもあたしにも色々な付き合いがあるのよね」と今度は泣き落としにかかります(笑)この妙な甘えも、この姉弟には茶飯事ですから、道長は今度は彼女の目を見て「できませぬ」ときっぱり。
素直に「はい」と引き下がる詮子は、政治家としては彼女らしくありませんが、ここは姉の顔になっているところがミソですね。
詮子が投げかけた「融通の効かないところが素晴らしいわ」と嫌みだか誉め言葉だかわからない言い様には、呆れと諦めだけではなく、兄たちとは違う誠実さを確認した満足があります。彼女が政治的になる理由は、円融帝と自身の一粒種である一条帝とその血統を守ることです。帝に道長推挙に際して述べた「お上に寄り添う」臣下ということは、実際、彼女が道長に期待していることと見るべきでしょう。
したがって、道長が権力の座についたことで私利私欲に走り、姉に阿る人間へと変貌しなかったこと自体は喜ぶべきことでもあると思われます。「(帝の信頼に答えて)お気張りなさい」との言葉も彼女なりの励ましでしょう。
ただ、その代わり、謀略の相談相手にはならないという面白みの無さもあり、からかい半分の誉め言葉になります。道長の清廉潔白は信頼という点では強みですが、一方で政治は綺麗事ではすみません。多数派工作は不可欠ですし、力がなければ相手は駆け引きにすら応じないものです。父兼家に煮え湯を飲まされてきている彼女は、その事実にも自覚的です。
ですから、ねじ込もうとした人事案を諦めることはなく「これは帝にお頼みするから」と息子へのゴリ押しを宣言、「え…えー?!」と理解の追いつかない道長を尻目に去っていきます。
しかし、これは道長を困らせたいのではありません。道長にはその公明正大さを体現することで帝との信頼関係を維持させ、派閥作りなどの裏工作は自分が担うという覚悟でしょう。帝を守る道長の志を汚さないよう、詮子が汚れ役を引き受ける。道長の姿勢を見た詮子は、そのことを改めて決めたのでしょう。因みに詮子がたびたび、帝や道長にゴリ押し、ねじ込みを行ったことは、史実とされますが、その裏には母の情、姉の情があるというのが「光る君へ」における解釈のようです。
それでは公正な除目を目指す道長の人事の基準はどこにあるのでしょうか。それが端的に表れたのが、久々の道長、公任、斉信、行成という4人の酒宴です。同期らしく遠慮のない物言いができるこの席で、蔵人頭の斉信が「俺もそろそろ参議にしてほしいなぁ」とあつかましい願いをします。この言葉には、縁故を頼る甘えと、自分を公卿にしてくれればお前のために働くという道長への迎合かあります。気心が知れた斉信が公卿になれば、陣定は道長にとってやり易くなるでしょう。
しかし、道長は「あー、すまぬ。今回はない」と多少申し訳なさそうに、でもあっさりと否定します。まさか友人に断られると思っていなかったばかりか、次の除目で参議になるのが同輩の蔵人頭、源俊賢を参議と聞いては、斉信の顔がこわばるのも無理はありません。言葉を失う斉信に変わって、公任が気を効かせて「同じ蔵人頭なのに、何故、斉信ではなく俊賢なのだ?」とその理由を問います。
道長は「俊賢は亡き源高明どのの息子だ。されど、目指すもののためには、その誇りを捨てることができる。今の俺には無くてはならない男だと思っている」と答えます。安和の変で高明が理不尽な失脚をして以降、俊賢&明子兄妹が相当な苦渋を舐めたことは、明子の兼家への恨みの強さからも察せられます。それでも、生きていくため、膝を屈して藤原の風下に立つ忍従を選択したのが俊賢です。その割り切りについては、俊賢自身も「生きていくなら力のあるものに逆らわぬがよい」(第13回)と語っています。
そういう時勢に阿るような俊賢のあり方を、気の強い明子は「情けない」「誉めることがない」とバッサリですが、逆に道長はその裏にある芯の強さを見抜き、政治的資質を見出だしているのが面白いですね。蔵人頭としての実直ぶり、帝と関白と公卿の間に立ち粛々と実務をこなす様から、それを読み取ったのでしょう。
明子からの口添えも少なからずあったかもしれませんが、「今の俺には無くてはならない男」という口ぶりからすれば、妻の兄という縁故ではなく、有能さを買ったことのが大きい理由とわかりますね。摂政家の三男である道長は基本的にボンボン。優しく甘っちょろい性格です。そのせいで取り返しのつかない失敗をしています。
苦境に対する経験値の少ない道長では、気づかないこと、甘い見通しはこれからもあるはずで、それは一朝一夕でどうにかなるものではありません。俊賢のような苦労人の経験とそれを乗り切る手管は得難いものとなるのです。自分の不十分さを補える人材の必要性を道長は説くのです。さらに特に今は政権の事始め、余計に注意深い人事が肝要です。
このように自分自身の欠点を捉え、必要なものが何かを見極める。そして、必ずしも自分に迎合するとは限らないとしても起用する。それは、自分をも政の一部として客観的に見られているということです。その冷静さと謙虚さが、今の道長の公正さを支えているようです。この点が、自信過剰の傲岸不遜、伊周に決定的に欠けているものです。彼は俊賢のような存在を負け犬としか思いませんから。俊賢は、そのように舐めてかかることを逆手に取るのですが、それは後述します。
因みに道長の、有能な人間を適材適所に起用する方針は、実資の権中納言昇進にも見えます。実資は実務において有能、かつ権力者に対しても苦言を呈することができる筋の通った性情、その二つを認めての起用と思われます(任じられた実資が嬉しそうにドヤ顔しているのが笑えますね)。
実資は道長に不審を抱けば物申しますし、俊賢は道長に陰りあれば見切るでしょう。道長がそこまで考えているかはわかりませんが、彼らを側に置いておくことは、道長政権が正しく機能しているかどうかのバロメーターにもなるでしょう。
(2)かつてのライバルたちが味方に
ところで、この席で、公任が除目について「俺のことは忘れておいてくれ」と出世争いから撤退宣言をしたことも興味深いですね。「父が関白であった頃は、俺も関白にならねばならぬと思っておったが、今はもうどうでもよい」という言葉からは、自身の権勢欲は本心ではなかったことが窺えます。おそらく、小野宮流藤原家としてのプライド、上流貴族の上昇志向に当てられていたため、出世にムキになったのでしょう。
また父の死により後ろ楯を失って以降は、時勢を読み違えて道兼に居座られる、道隆政権では参議になるものの冷遇されました。こうした状況に抗うことも、阿ることもできなかった公任は、今は疲れてしまったのかもしれません。時勢は自分の力だけではどうにもならず、人の思いもままならないもの、それを思い知ったのでしょう。
こうした中で公卿の主座となった道長の政治力に素直に感心したのです。「陣定を見ていても、道長は見事なものだ。道長と競い合う気にはなれない」との言葉には、揶揄も阿る意図もありません。
「漢詩や和歌や読書や管弦を楽しみながら、この先は生きていきたい」との言葉どおり、公任はこの後、芸術全般で名声を残すことになりますが、一方で「参議のままでよい」という彼は、積極的ではないだけで政から引退するわけではありません。道長を支えるのも悪くないと思えたのでしょう。
ですから、除目に悩む道長に「適切な除目を行うには各々が抱えた事情を知っておいたほうがよいと思うのだ」と適切なアドバイスをすることを忘れません。勘のよい道長は「貴族たちの裏の顔か?」と、その情報収集の重要性をすぐに理解します。
頷く公任は、貴族らの裏をつかむには行成が役立つと助言すると「行成は字が上手い。おなごたちは皆、行成の字を欲しがる。ゆえに行成は意外にもおなごたちと密なつながりを持っている」と皆が注目してこなかった行成の特性を、その理由としてあげます。
公任の言葉はそのとおりで、実際、「三蹟」とされる行成の字を女性たちは競って求めたのです。「枕草子」には、清少納言と行成との親しい交遊が描かれていますが、彼女も行成の書を入手するとその一つを定子に献上しています。いかに行成の字が尊ばれたかが、窺われますね。行成の字が手に入るとなれば、女性たちは嬉しさに口が軽くなるだろうというわけです。
そして、公任が女性たちの噂話に注目するのは「おんなたちは男どもとの睦言から、あいつらが知られたくない話を仕入れる」からです。女性が美しいものに高揚し気を許すとすれば、男性は情事に口が軽くなるということです(苦笑)斉信のききょうへの言動を見てもわかりますが、一旦深い関係になった女性を自分の持ち物と思う愚かな男性は少なくありません。こうなると、自分の女への警戒心が解け、あっさり秘事や本音を漏らしてしまうのですね。傲岸不遜な伊周すら、愛人の三の君には本音の愚痴を漏らしていましたね。
まったく男とは度しがたい。公任は、そういう男女の情事の本質に漬け込む策を道長に進呈します。恋愛に長けた公任ならではのアイデアで、まひろ一筋の不器用な道長では思いつかないものです。本作では公任のプレイボーイぶりは若い頃から描かれ、町田啓太くんの麗しさが説得力を持っていましたが、それがこういう形で道長の政に関わるとは予想外でしたね(笑)
おそらく、公任は自分が関白になった暁には、こうして行成に協力を仰ぐ算段があったと思われます。言わば、秘中の秘を道長に授けたわけで、公任の道長への期待の大きさが見えますね。
そして、これを聞いた大の道長贔屓の行成は「私で、力になれるならやります」と快諾します。
民を思う帝の意を汲み、公卿らとの議論を重視する政治理念。有能な人材を尊ぶ公正さ。これらは、かつてライバルでもあった友人たちの進んでの協力も取りつけます。前回note記事で触れたとおり、人をその気にさせることこそ道長の人望と言えそうです。
勿論、道長は彼らの心情をありがたく思い、長い付き合いの友人らへの情もあります。杓子定規に理屈にこだわるものではありません。今回は割を食う友人への情も斉信へ「その先に必ず考えるゆえこの度は許してくれ」と慰めることを忘れません。
(3)道長の謀臣たちの誕生の是非
ある日、小麻呂(二代目ですかね?)を追ってきた倫子は、机の上に広げられた和綴じ本に目が止まります。そこには、日付と日常的な漢文がか書かれています。漢詩は読めずとも、その程度なら読めるのか、それとも読めずとも何を書きつけているのかわかるのか、倫子は「ふうん」と言葉を漏らし、夫が日記を始めたのだということに気づきます。所謂、今日にも残る「御堂関白記」は、道長が政権を握った頃から書かれたとされています。
それにしても、その私的な記録が広げっぱなしというのは、道長はかなり無防備ですね。倫子が道長の心に住む女性の存在に気づいていることすら気づかない道長は、女心には鈍感なため、気にしていないのかもしれません。しかし、倫子に文箱の漢詩も見つかっていますし、今回にしても見ようとしなくても見えてしまう状態というのは、一般的には不注意でしょう。
それでもこうなってしまうのは、道長の生来の大らかさだけではなく、道長にとって倫子と土御門殿ではなんだかんだで安心できる場所になっているということではないでしょうか。ここには彼の娘も息子もいる、家庭が存在するからです。
今回、穆子は、娘の倫子に「大臣の妻としての心得」として、「丈夫であること」(健康)と「子どものことで心配をかけないこと」の二つを伝授しますが、これらは家庭だけは平和な場にしておくことが、政に疲弊した夫にとっての癒しになるという趣旨です。穆子曰く「何も考えずに内裏に通っていただけ」の雅信すらしばしば円形脱毛症に悩まされたようで、その経験からの助言です。しかし、倫子は、子どもの不安については散々話してしまっているものの、日記の無防備さから見て、どうやら穆子が言うほどに配慮せずとも、既に道長にとっての癒しの空間を提供できているように思われます。
ただ、それは倫子に無理を強いていることかもしれません。例えば、彼女は、道長の心の中に住む女のことも、明子のことで嫉妬心を露わにすることもしません。また、夫の志に快く、資産を提供もしています。家庭内の不和は結局、婿である夫の居場所がなくなるだけで、道長が自分から離れてしまう最悪の事態を招く。倫子はそれがわかっているだけかもしれません。その意味では、道長は随分と倫子に甘えているようにも見えますね。
それにしても、あんなに内裏の動向に右往左往して頑張っていた雅信について、妻の穆子の評価が「何も考えずに内裏に通っていただけ」というのはちょっと気の毒ですね。おそらく穆子は、雅信の人の好さから、政に向いていない性格かつ政治的センスはないと思っていたのでしょう。相手は兼家ですから尚更です。彼女が平穏を望み、娘を入内させることに反対したのも、雅信のためであったと思われます。
その一方で、穆子は、倫子との婚姻を後押しした道長については、政のつらさを見せないところが立派であると褒めています(夫を褒められ高らかに笑ってしまう倫子がかわいいですね)。彼女は、道長の見た目以上の芯の強さと強運を見抜いているようです。彼女は「家」に相応しい男を見抜く力を娘共々持っていたのでしょう。そして、道長の政を生き抜く強さを信じるゆえに老婆心ながら倫子に助言したのだと思われます。とはいえ、亡夫のハゲを笑い話にするのは、やめてあげてください(笑)それこそ、あの世で雅信「不承知不承知」と嘆いていますよ。
さて、話を「御堂関白記」に戻します。自宅とはいえ広げっぱなしにしているのが無防備だというのは、本作における書き始めたきっかけが政のためだからです。
公任の助言もあり、道長は早速、行成に貴族たちの情報を探るよう依頼します。道長推しの行成は「右大臣さまの御ため」と、自身の筆の才を遣って迅速に情報収集にあたり、その報告書を道長に献上します。道長も「早いな」と感心しきりです。報告書に綴られた情報のなかには、藤原朝経が酒乱であるなどかなりプライベートなところに踏み込んだものもありました。この朝経は、疫病で亡くなった大納言の一人朝光の息子ですが、一条帝の時代の前半にはあまり出世の栄誉に預かっていません。
もしも、報告書から酒乱と知られたことで出世が遅れたということであれば、貴族の秘密を握った行成の報告書は重宝されたということになります。行成の行き届いた仕事ぶりは、道長に情報収集の重要性を改めて気づかせたと言えそうです。
それだけに、そこに記された秘事は門外不出です。いかな行成の達筆で書かれた書とはいえ「お読みになったらすぐ焼き捨ててください」と行成が言上するのは道理でしょう。しかし、「一度読んだだけでは覚えられぬ」と渋る道長に行成は「お心に止まったことだけ御自身で記録をつけては」と日記をつけることを提案します。行成は「私は毎朝、昨日のことを書き記します。そのことで覚える力も鍛えられます」と述べ、その効用についても語っていますが、これは「権記」のことですね。実資の「小右記」と共に一級史料とされています。
それにしても、道長が政権の頂点に上ったころには書き始めていたという「御堂関白記」が、行成が収集した情報を覚えておくために始めたという解釈になるとは。実際は物品の出納記録が主であったとされますが、「光る君へ」はそれだけではないということなのでしょう。
道長が日記に記しておくような情報を幅広く集め、提供する行成の役割は、政と道長自身のプライベートとその公私に踏み込む形で重要度が増していきそうです。
ところで、もう一人。道長に欠かせない人材になるのが、道長自身がそう言及し、参議へと昇進させた俊賢です。道長は早速、彼を呼び出すと、無様に転がった日以来、参内してこない伊周&隆家兄弟を陣定に引きずり出すことを依頼します。
道長が公卿の主座に就いたことを内心は面白くないと思う者は、伊周一派に限らず存在します。そうした人々がすることと言えば、道長の瑕を探しだし、上げへつらうことです。現状、その瑕となる可能性となるのが、参内しない内大臣伊周です。彼らが参内しないことを放置し、政を進めれば内大臣をないがしろにして、専横を始めているとの噂を立てられかねません。道隆との違いを出すことが道長の政の生命線です。同じだと言われることだけは避けなければなりません。
しかし、プライドの高い彼ら二人を宥めすかすのは難儀なことです。とくに同じく気位の高い貴族をぶつけては喧嘩になるだけです。ここは、彼らの前に平気でへりくだり、なおかつ揺るがない人物が必要。そこで、俊賢に白羽の矢を立てたのです。
一方、俊賢は明子にだけは、風見鶏を止め、道長に期待をかけ、彼一本で忠勤に励む決意をしています。彼も道長の目指す新しい政に自分の才覚を活かしたいという志に燃えているのですね。明子にはあさましく、口添えを頼んでいますが、根にあるのは卑しさだけではないようです。そんな俊賢が今、欲しいのは、道長に自分の有用性を理解してもらうチャンスです。ですから、道長の依頼は渡りに船というもの。両者の利害は一致し、俊賢は早速、中関白家へ訪問します。
「内大臣さま中納言さまにはご機嫌うるわしく心よりお喜び申し上げます」と型通りの挨拶をする俊賢を、伊周も隆家も最初から信用していません。気性の荒い隆家は「ご機嫌うるわしいわけがなかろうが!なんだお前は!」と語気を荒げますが、俊賢はどこ吹く風、源俊賢だと名乗り、惚けています。「そんなことはわかっている!」といきり立つ隆家を横に伊周は「右大臣どのに言われて様子を探りにきおったか」と警戒心を露わにします。
伊周自身は相手の痛いところをついて、先制攻撃をしたくらいに思っていますが、最初から構えてあたるのは腹芸としてはあまり上手くありませんね。「さて、その俊賢どのが何用かな?」とすっとぼけて笑顔で迎えるくらいでいいのです。最初から上から目線の冷笑を浴びせるだけという伊周のいつもの手はワンパターンというもの。詮子にも、道兼にも、この遣り方による恫喝でしたからねぇ。
いつもの伊周の反応に「とんでもないことでございます」と心外であるという表情を浮かべる俊賢に「お前の妹は右大臣どのの妻であろう」と核心を突く一言を突きつけます。しかし、俊賢が道長の依頼を受けた時点で、伊周のこの指摘は俊賢にとって予想の範疇でしかありません。慌てることなく、「左様でございますが、私は源の再興のために右大臣さまに近づいているだけで、道長さまに忠義立てしているわけではございません」と悪びれることなく答えます。
この俊賢の返答が上手いのは、真実と嘘の匙加減が巧妙な点です。人を信用させるためには、完全な嘘はすぐバレ、ほどほどに本当のことを混ぜるべきとはよく言われますが、俊賢のこの弁の場合、前半の「源の再興の」は決して嘘ではありません。最終的にはそうなることを望んでいます。しかし、当面は貴族として生きのびる確かな状況を確保することが第一義です。ですから、「源の再興」は嘘と真実は半々といったところでしょう。
後半の「道長さまに忠義立てしているわけではございません」については、前回の「これからは右大臣さま一本でいく」との言葉からすれば嘘ですね。そして、彼がそう決めたのは、「これほどの心意気の方とは思わなかった」と道長の志の高さに感動したからです。勿論、道長が俊賢の期待に添わない人物であった場合は見捨てるでしょうが、現時点ではあり得ないわけです。俊賢は、誰もが知る自分の「家」の苦境を持ち出すことで、自身の嘘をもっともらしく見せているわけですね。
勿論、「内大臣さまのほうが、深くご聡明でいずれは高みに上られましょう」と誉めそやすことも忘れません。そして「今宵は先々のために、種を撒いておこうと参じましてございます」と言うことで、我が「家」のことしか考えない没落貴族らしい卑しさを演出します。道長が見立てたとおり、目的のために誇りを捨てられる人間であることが窺えます。
私利私欲に凝り固まった人間というのは、伊周にとって扱いやすい人間ですが、いつでも裏切る信用のできない輩でもあります。伊周は表情を変えませんが、隆家は「図々しい奴だなぁ、お前」と言うと、俊賢の目の前に座り込むと彼に顔を近づけ、その目を値踏みするように見据えます。騙されないという恫喝と俊賢という人間の心を見ようとする隆家は、若いながら正直、伊周よりも駆け引きのできる人間と見ます。
隆家は今回、長徳の変を引き起こしてしまいます。その行為自体は無鉄砲という他ありませんが、その裏にあるのは冷ややかに物事を見る眼差しとそれゆえに物怖じしないという豪胆さです。定子に八つ当たり、道長に言いがかり、三の君に振られたと思い込み落胆…など何かと感情的な伊周とは対照的な人物と言えるでしょう。第16回note記事でも触れましたが、彼は香炉峰の雪にも中関白家の栄華にも一歩引いています。長徳の変の弓矢も、情けない兄のために一肌脱ぐの感覚が始まりです。そういう彼だからこそ、俊賢を脅し、見極めようとするのですね。
しかし、これまで人知れず多くの苦労を重ねて、ようやく参議にまでなった俊賢は、甘やかされて育っただけの傲慢な兄弟に臆することも怯むこともありません。それどころか、ここでようやく「帝も内大臣さまのことを案じておられました」と伝家の宝刀を抜きます。案の定、それまで胡乱な顔をしていた伊周の顔色が変わります。そもそも彼が、道長への内覧宣旨でひねくれたのは、帝が自分の味方ではないと疑ったからです。それは裏を返せば、帝の後ろ盾を誰よりも期待しているということ。俊賢は、その見え見えの心情を上手く刺激したのですね。
自身の言葉で顔色を変える伊周の様子を確かめると、俊賢は薄く笑うと「右大臣さまに対抗する力がなければ、内裏も陣定も偏りなく働かぬ…と帝はお考えなのではありますまいか」と更に言葉を連ね、彼の自尊心を散々にくすぐります。伊周が願うこと、それは帝の必要とされている、認められているという確証です。道長に対抗するために力を貸してほしいとは、伊周が待っている言葉です。
俊賢には、伊周の心が透けて見えるようでしょう。帝が伊周に参内してほしいと思っていることは事実でしょうが、そこまでのことを期待しているかと言えば、その点は現状、100%嘘でしょう。しかし、伊周が望みに添うその言葉にに帝の考えと推測する文言を加えてやれば、簡単に心は動きます。人は自分の信じたいものを信じる生き物ですから。
「帝がそう仰せになったのか?」と聞く伊周に「そのようにお見受けいたしました」と、決して帝が発言したとの言質を取らせないあたりも俊賢の巧さですね。あくまで俊賢の推論でしかないとした上で「つい前ごろまで蔵人頭として帝の側でお仕えしてきましたので。私の目に狂いはございません」といい、信用させます。このあたりも、直前まで伊周を関白にしようとしていた帝を知っていますから、あながち嘘だけになっていませんね。
そして「内大臣さま、中納言さまのおわさぬ陣定などあってはならぬと存じます」とのトドメの一言も素晴らしいですね。この文言は字面どおり、まったく嘘がありません。ただし、伊周たちに参内してほしいのは彼らのためではありません。
あくまで、右大臣が内大臣をないがしろにしている噂を立てられたくない道長のためです。つまり、言葉は真実でも、それが誰のためなのかは嘘というわけです。つくづく、俊賢の調略における虚実皮膜は絶妙だったと言わざるを得ませんね。
因みにこの一連のやり取りでは、俊賢が主導権を握る後半から、BGMがコミカルなものになっていきます。愚かな伊周が完全に俊賢に手玉に取られていることをBGMも表現しているのです。
こうして伊周たちの調略に成功した俊賢は、道長の報告において「必ず参内されましょう」と自信を覗かせるだけでなく「ダメであれば第二の手を打ちます」と腹案を持っていることを仄めかしてもいます。俊賢は、道長の謀略の臣として、密やかに、そして印象深くデビューしました。
今回、道長のために活躍した行成、俊賢は、公任、斉信と共に四納言と呼ばれる、道長を支える公卿となるのですが、その中でも行成が情報取集、俊賢が調略で力を発揮したという描かれ方をしたのが興味深いですね。道長は、表では陣定の議論を重視した政の王道を目指しています。また、その政も民を救うという徳治を目的としています。
しかし、その一方で貴族の裏情報を収集し、また調略で伊周たちは半ば騙すやり方で表舞台へと引きずり出しました。これは、あくまで公明正大な政、有能な人材を起用する公正な人事のために行われた大前提ゆえに、今回は気持ちのよい展開になっています。
しかし、道長自身が「まーだ始まったばかりだ」と公任に言ったように、今はただ道隆政権の過ちに対する反動もあって、帝も公卿も自分も上手く噛み合って、一体化し上手く進んでいるに過ぎません。この先、経験の少ない道長の政を、海千山千の公卿たちがあの手この手と邪魔してくることは目に見えています。
実際、「御堂関白記」には「雨下 可有定陣 而納皆不参 仍畄了」(意訳:雨が降った。陣定が行われるはずだったが大納言、中納言らが全員出席せず、取りやめになった)というものがあり、かなり軽んじられた扱いも受けていますから。
どんな政も上手くいっているときはよいのです。しかし、思うように政が進まなくなったとき、権力者が持っている力に抑制的になれるかどうかは難しいのです。道長の政が行き詰ったとき、それまでは正道を支えるために情報収集と調略が、表へと大きく顔を覗かせてくるかもしれません。政が綺麗ごとでない以上、そこに頼ることは避けられませんが、それだけに頼るとき、道長の政は自然と歪んでくることになるでしょう。
思えば、清濁を併せ呑み下した兼家は安倍晴明という謀臣を抱え、調略を巧みに使いながら政権を維持し、政を行ってきました。今、道長も同じく謀略の臣下、しかも晴明のように油断ならぬ者ではなく、道長に心酔する謀臣たちです。
つまり、道長は兼家の手法を最も確かな形で継承し、その気になれば、兼家以上に上手く政を意のままにできる力を握りつつあるのです。実はその政権を支える体制が、兼家、道隆以上に独裁向きになっているのですね。爽やかにして鮮やかな道長の手腕の裏に潜むものまでが描かれたことは見逃せないでしょう。道長の正しさが、どこまでも道長を正しく導くとは限りません。
3.まひろの新しい政の夢の行方
(1)まひろ、帝に意見する
道長の政の手腕は、ききょうによってまひろの元にも届けられます。ききょうがたびたび、まひろの元を訪れているのは、定子に仕える喜びは何ものにも替え難い一方で、陰湿で心無いいじめが横行し、それにやりきれなくなるときがあるからでしょう。
後半、まひろを連れて後宮に上がった際、鋲を撒かれ、そのいじめの一端が描写されます。その際、ききょうは、意地悪な女房たちに聞こえるようわざと声を張り上げ「私も三日に一度くらいは何か踏みますので、足の裏は傷だらけです。でもそんなこと、私は平気です!中宮さまが楽しそうにお笑いになるのを見ると、嫌なことはみーんな吹き飛んでしまいますゆえ」と笑みまで称えながら、高らかに宣言しています。まひろは、ききょうの強気に呆気に取られながらも感心しきりですが、このくらい気を張っていないとやっていけない世界だということです。
ときにそれに疲れ果て、唯一の友であるまひろの元へ息抜きに来たくなるのも宜なるかなでしょう。いつの時代も同性だけの世界とは生きづらいものですね。
さて、まひろの元に来たききょうの顔は穏やかですが、その口は饒舌です。
「新しい右大臣さまに望みは持てぬと思っておりましたが、それが案外頑張っておられますの」という言葉を洗濯を干しながら背中で聞くまひろは「へー」とちょっとほっとした表情です。何せ前回は「人気がない」と聞かされていましたからね。
続く、「疫病に苦しむ民のために租税を免除されたりして」という政策には、はっとした表情になります。まひろは、悲田院での道長との出会いについて、「民を救う」という自分との約束を覚えていたからではないかと推察していたましたが、それが事実であったことを確信できたのです。間違いなく、民を救う政を始めている道長に薄く笑みがこぼれますが、その表情はききょうに悟られないようにして「そうですか」とあっさり目の答えをしています。前回、笑いが止まらずききょうに怪しまれてしまったのを反省してのことでしょう。
また、伊周たちが久々に参内した際の陣定で話題となった若狭に上陸した70名の宋人についても、小国の若狭ではなく受け入れる館のある越前に送るよう道長が帝に奏上したとの話もでてきました。陣定で話題が訴状にあがった際、公卿らは動揺した様子でしたが、どうやら道長は果断な判断をくだしたようですね。意見を聞きつつも決めるときは決める…主座らしさも見せているようです。
ところで道長の件を語るときのききょう、「帝に申し上げ、そうなったのですぅ」「素早いご決断に皆、感嘆しておりましたぁ」と語尾が伸びていて、ちょっとうっとりしているのがよいですね。実は清少納言は、道長に対しては当初かなり好意的でそれを定子にからかわれているくらいでした。そうしたことを踏まえてのことでしょう。しかし、前回は散々だったのに、変わるものです。そして、ききょうまでもが好意的に語る今、道長の政が概ね、順調であることも窺えます
しかし、想い人の活躍よりも、まひろの関心を強く引いたのは、宋人たちが今、越前にいるという事実です。勢い余ったまひろは「宋人とはどんな人たちなのでしょう?」と聞いて、道長の武勇伝にうっとりしていたききょうを戸惑わてしまうほどです。まひろが、宋人の興味を抱いたのは、宣孝から聞いた科挙の存在です。
彼女は身分が低い者は政に関われないと信じ込んでいました。それが常識だったからです。それゆえ、あの夜、涙ながらに高貴な身分の道長に自分の思いを託したのですね。それは、苦しく哀しい選択でした。それだけに、異国には、身分に関係なく、政に関わる機会がわずかながらに開かれているという事実には、驚くしかありませんでした。直秀の死以来、どこかで自分が男ならば、世の中を変えて見せるのに…とずっと思ってきた彼女にとって、それは夢そのものです。
その科挙の話に対する憧れを、さらに加速させたのが、「白楽天が民にかわって政を批判している」という白楽天「新楽府」です。この中でも、身分の貴賤で、有能さは決まらないとの一節があります。白楽天自身も科挙で道が開けた人物ですから、こうした発言をするのは当然でしょう。冒頭、惟規から借りた「新楽府」を必死で写すまひろが、白楽天の言葉に感銘を受けていることは間違いありません。
しかし、こうした感動は乳母のいとにはわかってもらえません。「政のあるべき形が書かれているから」ためになるのだと説いても、「そういうことは若様にお任せになって」と婿取りを祈るために清水寺詣でをしようとしか返してくれず、まひろはうんざりしています。
だから、漢籍にも通じ、教養もあるききょうに「宋の国では身分の低い者でも試験がよければ政に関わることができるのです。我が国では考えられないことです」と熱く語りますが、「そうですわね」というききょうの答えはあまり気乗りしていないことが丸わかりです。しかし、熱くなっているまひろは、それには構わず「私は身分の壁を越えることのできる宋の国のような制度を是非、帝と右大臣さまに作っていただきとうございます」と大それた話をぶち上げ、「あ…まひろさまってすごいことをお考えなのね」と、あのききょうをして驚かせます。
しかし、ききょうほどの教養人をもってしても「そんなこと殿方に任せておけばよろしいじゃありませんか」としか返してはくれません。無学な乳母いとにせよ、漢籍がわかる教養人ききょうにしても、この世の理不尽を当たり前のものとして受け入れています。そして、政は男のものであるのが道理で、考えること自体が意味のないことだと言うのですね。それは、賢い倫子も同じでしょう。本作で政治的な女性と言えば、詮子や貴子や定子がそれにあたりますが、それでも内裏内での権力闘争のレベルの話。まひろと道長の志、「民を救う」という観点に立つものではありません
ただ、ききょうはまひろの熱い思いに応えられないことをオタクとして申し訳なく思うらしく、「私はただ中宮さまのお側にいられれば、それで幸せですので」と自分のあり様を正直に答え、笑ってくださってよいのよというように笑います。
勿論、ききょう大事に思うまひろにそんな気はありません。寧ろ「ききょうさまがそれほど魅せられる中宮さまに私もお目にかかってみたいものです」と、素直な関心を寄せます。その言葉に「中宮さまの後宮にお出でになりたいの?!」と俄然、盛り上がるききょうの表情が素晴らしいですね。自分の推しを布教するのは、オタクの誉れでしょう。まひろの要望を積極的に受け入れ、あれよあれよといううちにまひろは、定子の御前へ謁見する機会を得ます。
迎える定子も「少納言が心酔する友」が来るということで、楽しみしてくれていたのか、御簾を下げず、気さくにまひろと対面することにします。「和歌や漢文だけでなく政にもお考えがあるようです」と面白がるききょうの言葉に、驚き興を引かれた定子は、まひろに意見を促しますが、ここで一条帝がお渡りになり、中断してしまいます。
帝と中宮の「重いお務め」の後、帝と中宮の両方を前にまひろは、その意見を披露することになります。流石に躊躇したまひろですが、定子同様、気さくな帝は「ここは表ではない。思うたままを申してみよ」と促します。
そして意を決すると「恐れながら、私には夢がございます。宋の国には、科挙という制度があり低い身分の者もその試験に受かれば、官職を得ることができ、政に加われると聞きました。全ての人が身分の壁を越える機会がある国は素晴らしいと存じます。我が国もそのような仕組みが整えばといつも夢見ておりました」と一気に語り切ります。
日頃抱えた想い、誰にも語ることができず、まして共有することなどあり得なかった、まひろの政に対する新しい夢…淀みない語りには、ふつふつと考え続けたことが窺えます。おそらく、まひろ自身も政に関わりたいという本心も隠されているでしょう。
定子は、まひろの大胆な物言いを静かに聞き、一条帝の反応を窺うのですが、彼は「その方は新楽府を読んだのか?」と目を輝かせ、興味津々です。問われたまひろは、迷いながらも自身の思いの根拠となる一節「高者未だ必ずしも賢ならず、下者未だ必ずしも愚ならず(意訳:高貴な身分の者が愚かで、卑しい身分の者が賢いことは珍しくない)」と答えます。
帝が目を輝かせたのは、勿論、「新楽府」を読んでいるからです。まひろの引用に「身分の高い低いでは、賢者か愚者かは計れぬな」と軽く苦笑いします。まひろの引用は、結果的には、貴族だけで政を行う一条帝の親政に対する批判にもなっていますし、彼自身、有能な者を起用し続けているとは言えませんから。
その帝の微妙な表情の変化よりも、帝が「新楽府」を読んでいて、話が通じるということにテンションが上がってしまったまひろは、我を忘れて「はい。下々が望みを持って学べば、世の中は活気づき、国もまた活気づきましょう。高貴な方々も、政をあだおろそかにはなさらなくなるでしょう」とこ久々にオタク度全開で「新楽府」の講釈をしてしまいます。
このまひろの講釈がなかなか興味深いのは、すべての民が学問と知性を身に着けることで国と国民全体が底上げされるという教養主義の発想が織り込まれているということですね。そして、民の知性が政治家の愚かな行為、不正を監視するというのは、理想的な民主主義のあり方です。皮肉にも、現在の日本人が忘れかけていることですね。
帝への批判も含むまひろの言葉に目を見張った定子は、思わず帝の顔を窺いますが、帝は面白がる顔です。定子は、二人の間にわずかに通った共鳴を認めると「言葉が過ぎる」と釘を刺し、まひろの発言遮ってしまいました。それと気づかぬまひろは、我に返り恐縮するだけですが、帝は「そなたの夢、覚えておこう」と優しい言葉をかけてくれました。初めて女性から仕掛けられた政治問答にいたく感銘を受けたのですね。
ここで定子がまひろを危険視したと思われるのは見逃せないところです。定子は漢籍に通じていますが、彼女に寵愛されているききょうの様子を見る限り、彼女もまた帝に政に関して口を挟むようなことはしていないでしょう。そもそも、入内当初は内裏の政治闘争にも関心が薄く、帝と仲良くしていればよいぐらいにしか思っていませんでした。成長し、帝が政に苦しむ姿を見ても、ただただ心を痛めて見守り、傷ついた彼をお慰めしてきたと思われます。
しかし、まひろは帝の政の悩み自体にその学識と豊かな思考で話し合うことが可能な女性でした。それは、政の話ができない定子にとって、かつてない脅威だったのでしょう。ききょうの目論見とは違い、まひろは定子に危険視されてしまったのではないでしょうか。
もっとも、まひろは定子のそんな思いには気づいていないでしょう。大人になり、他人を慮り、相手の気持ち合わせる大人になったまひろですが、政への新しい夢に目覚めた今の彼女はやや暴走気味で、昔の空気の読めない子に戻ってしまっている感があります(面白いですが)。初めて体験する後宮の空気に至っては、尚更わからないでしょう。
ですから、帝と話が通じ、優しい言葉をかけてもらったことで、自身の夢が少しは意味のあることに思え始めたことに熱くなっています。今の彼女自身には何もできませんから、父にその望みをかけます。それは、除目の申し文です。彼女は、自身の宋人への関心から「越前守をお望みになったらよろしいのではないでしょうか?」などと言い出すと「越前には宋人が大勢来ております。父上なら宋の国の言葉もお話になれますし、他の誰よりもお国のために役に立ちまする」と仕切りに 挑戦を勧めます。
「途方もないことを申すな。大国の国司は五位でなければなれぬ」と現実を見ろと返す父に「いっそ千尋の谷に飛び込むつもりで大胆不敵の望みをお書きなさいませ。乗るか反るか身分の壁を乗り越えるのです」などと無茶苦茶を言う始末です。熱い気持ちになっている今、何かをせずにはいられないのでしょう。勿論、何の力もないまひろにできることはないのですが…それでも、今回だけはまひろの大胆さが奇跡を呼びます。
(2)まひろの夢と道長の政が交錯する瞬間
ある日、道長は、謁見の場で帝から「世の中には政のことを考えるおなごがおるのだな」と感心しきった言葉を聞きます。帝に関わる女性で政治的、あるいはそうした教養を持ち合わせるとすれば限られます。「中宮さまも女院さまも左様にございますか?」と無難に聞き返しますが、「左様な高貴なものではない」と答えた帝の口から出たのは「まひろと申しておった」です。
宮中で絶対聞くはずのない名に、道長の目は驚きに見開き、言葉を失います。どこでどうやって帝にまひろが謁見する機会があったのか、想像もできませんが、「朕に向かって下々の中にいる優秀な者を登用すべきと申した」との恐れを知らぬ物言いは、道長の知るまひろ以外にありません。
いつも唐突に、思いも寄らぬところで道長を先回りするように現れるまひろ。道長がわかりやすく思考停止してしまい、驚きの表情を隠せないのも仕方のないところ。寧ろ、帝の「いかがいたした?」の問いに「お上に対し奉りまして、恐れ多いことを申すものだと思いまして」と答えられたことを褒めるべきでしょう(苦笑)それに対する、帝の返答はあの者が男であったら、登用してみたいと思った」と嬉しそうなものでした。まひろの思いは、帝の心すら動かしたのです。
謁見後、道長の心は千々に乱れます。ようやく、「民を救う政」に着手したばかりだというのに、まひろはさらに先んじて身分を越えていくことを考えています。その上、男であれば「登用してみたい」と帝にまで言わしめる才覚…彼女は発想と思考において、常に道長の先を歩いています。あの月夜のときと同じく。彼は未だにまひろにたどり着けていないことを思い知らされたと言えるでしょう。
しかし、彼は平安期の常識の中であるとはいえ、比較的男だから、女だからという考え方をするタイプではありません。まひろが自分の先へ進み、帝の心を動かしたことはささやかな感動もあるのではないしょうか。また、まひろとの約束を胸に政の道を進んできた道長にとって、自分が能力重視で公正な除目を行おうとしていることとがまひろの思いと合致していると確かめられたことも納得できるでしょう。
そんなまひろの思いに応えること。それは、埋もれてしまっていた為時の才能に気づくことでした。それゆえに彼は為時の申し文を探し出したのです。まひろを登用することはできませんが、まひろをあのような考えになるべく教えた為時の才覚は買えます。また、上の空で参加したとはいえ、兄と兄嫁が漢詩の会に呼ぶほど漢籍に優れた人物です。
加えて、ここも重要であると思われますが、夜通しまひろの看病をした翌朝、為時は、娘を心配する気持ちを抑え、道長に大納言としての役目を果たすよう諭しました。権力者に阿ることなく、筋を通し、言うべきことが言える、その実直な人柄にも道長は触れているのです。詮子が推挙した人材のような「知らぬ者」でもなく、埋もれてよい人材ではない。だからこそ、淡路守を希望していることを見て、まず受領国司になるために必要な従五位下の官位を与えることにしたのです。
まひろの夢に帝が動かされ、回り回って道長を動かし、為時は従五位下を与えられます。物語が、わざわざ回りくどい経緯を経て、為時が昇進するという展開であるのは、為時の昇進、その先の受領国司登用が、好きな女の父の面倒を見てやったというような安っぽい縁故採用でないことを強調するためでしょう。
きっかけこそまひろの言葉ですが、彼が為時の採用を決めたのは、自身が能力重視の公正な除目を目指していたこと、まひろの考えがそれと合致したことがまずあるでしょう。あの夜、志で深く結ばれた二人は凡百の恋愛感情ではない次元で共振し合ったのです。そして、為時がその条件に見合う教養と人柄を身に着けていることを道長が知っていたからこそ、昇進に至るのです。つまり、昇進と登用自体は、為時の実力によるものなのです。
為時は最終的に淡路守ではなく、越前守へ任じられますが、それは越前にいる多くの宋人たちに対応するため、会話ができるほど漢籍に通じた者が必要となったことが理由だと言われます。こうした史実を踏まえても、道長の判断は、為時自身を見てのものと思われるでしょう。
突然の昇進に為時もまひろも驚愕します。まひろにしても、いくら道長が自分への思いを今を抱いているからといって、それで為時を登用するとは思っていないのですね。伝達の使者は、この昇進が「右大臣さまからのご推挙でございます」と道長への意向であることも合わせて教えてくれます。従五位下、これで名実ともに貴族の仲間入り、しかも国司受領の資格を得ましたから、まひろも「国司にしてくださるということでしょうか」と色めき立ちます。まあ、そこで為時に窘められた越前守の話を蒸し返してしまうのは、夢に暴走気味なまひろの愛嬌としておきましょう。
任官から離れすぎて、為時は従五位下の赤の束帯を持っていないことを、いとに指摘され、まひろは早速、宣孝に借りに行くことにします。その準備の最中、まひろは自室で道長に思いを馳せ、喜びを噛みしめます。それは、やはり恋する女性の顔ではありません。あの道長が為政者として、父の才覚をきちんと見てくれたということへの感謝なのでしょう。魂で結びつくまひろは、道長の思考を直感的に正確に読み取っているのですね。
ただ、そんな深い事情を知らない為時といとは、この昇進は、道長とまひろが深い男女の仲にあるからとしか思えません。まあ、安易ですが、これは仕方のないところですね。二人のつながりが生んだ奇跡と思う為時は、昇進に関する感謝を道長に述べる際に「悲田院でお助けいただいた娘もおかげさまで息災にしております」と一言添えます。
わざわざ為時があさましくもそれを口にしたのは、二人が深い仲であるのなら、道長がまひろを世話してくれないだろうかという思いがあるからでしょう。それは、右大臣と昵懇になりたいからではなく、ただ娘が好きな男性と幸せになってくれたら妾でもいいという親心からでしょう。
道長はまひろの現状を聞くとき、思わず微笑を浮かべています。やはり、まひろのことを聞けるのは嬉しいという本心が見えますが、挨拶が終わると真顔に戻ると優し気にただ「お上の御ためなさに尽力されよ。ご苦労であった」と、あくまで政務のために頑張ってほしい。政務での成果を期待する旨を伝えます。この昇進、その先の登用があくまで為時の能力を買ってのものであり、極端なことを言えば、人事そのものはまひろには関係のないことだからです。男女関係に落としてしまうことは、道長にとっても、まひろにとっても本意ではないのですね。
熱く燃えるまひろの新たな政への夢は、遂に政の頂点に立ち「民を救う」政を担わんとする道長の現実は、為時の有能さを通して交錯することになりました。それは二人の想いが持つ可能性ですが、一方で完全に同じ方向を向いているわけでなないことも暗示しています。
おわりに
第19回は、道長とまひろ、それぞれが中心に描かれ、その呼応が為時の昇進へと結実していく構成でした。前回まで道長の政敵だった伊周は、無様な振る舞いも含めて、その存在感を大きく減じていたと言えるでしょう。にもかかわらず、隆家が花山法皇に弓を引き、矢を放ち、長徳の変が始まったところで幕引きとなりました。これは、何を意味しているのでしょうか。
ラストで矢を放った相手が花山法皇であることに、伊周と隆家は初めて気づきます。それは取り返しのつかないとんでもないこととなって、中関白家に厄災をもたらします。そう、一度「放たれた矢」は戻らない。修正が効かないのです。
そして、それは、いよいよ始まった道長政権も同じです。これまで道長は、大きな壁、あるいは後ろ盾の中で政に関わってきました。ですから、最終的な責任は彼が負うものではない場合が多くあったと言えるでしょう。しかし、政の頂点に立った道長は、あらゆる現実に直面し、自ら判断し、決断しなければなりません。関白につかないこと、陣定を重視し、太政官を政治基盤にしようよいう方針、行成と俊賢に調略を担わせること、すべてはまひろとの約束「民を救う」政のためですが、これが吉と出るか凶と出るか、どちらになっても道長は責任を負わなければなりません。
また、自分のしたことから生じた他人のしたことへの責任も取らざるを得なくなる局面もあるでしょう。つまり。自分の起こしたアクションの清濁を併せ吞み下す・・・兼家がやってきたことを今度は、道長がすることになります。政の現実に生きるということは、「放たれた矢」の責任を取り続けることなのかもしれません。道長は後戻りできない道を進み始めたのですね。
今回は順調だったから、大きな問題は起きませんでしたが、隆家の矢から始まる長徳の変は、一般には道長がそれを利用して伊周一派を徹底的に排除する政争であると知られています。政敵の完全排除は強引なものになることが多く、それは反発を生み、あるいは専横の始まりとなる可能性を孕んでいます。今回見たように、道長は調略に長けた腹心二人を得たことでいつでも独裁的になってしまう危険性も秘めています。
隆家の矢という不可抗力は、道長にとっても放たれた矢となり、早速、道長は綺麗ごとでは済まない政権運営を余儀なくされます。その中で変質するのか、しないのか、早々に道長は試されます。
一方、まひろの政への新しい夢は、身分の壁を乗り越えるという実現不可能な夢です。そして、その発想は貴族社会の頂点に立つ道長政権とどこかで齟齬を起こすでしょう。道長政権はどこまで貴族社会の代表者ですし、また男性が政を行うその象徴になってしまいますから。
また、まひろは理想論を追うだけですが、道長は政の現実に生き、理想論では何ともならない苦境に直面します。その点でも、二人はいずれズレていくしかないのかもしれません。「民を救う」目的は同じでも、理想と夢、方法論などで二人は道を違えていくしかないのかもしれません。
となると、為時の昇進を媒介にした、二人の今の思いがプラスに作用しあった今回の臨界点は貴重なものになるでしょう。
ところで後年、紫式部は、中宮彰子の教育に白楽天「新楽府」を使っています。紫式部自身は政に直接関わることはできませんでしたが、中宮彰子には政の理念を徹底的に学ばせているのは興味深いですね。中宮彰子は後々、父道長と対立し、溝を深めていくことになりますが、その裏には紫式部の教育があったかもしれません。そう考えていくと、本作のまひろと道長の関係というのも、思った以上に波乱万丈のものになるのかもしれませんね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
