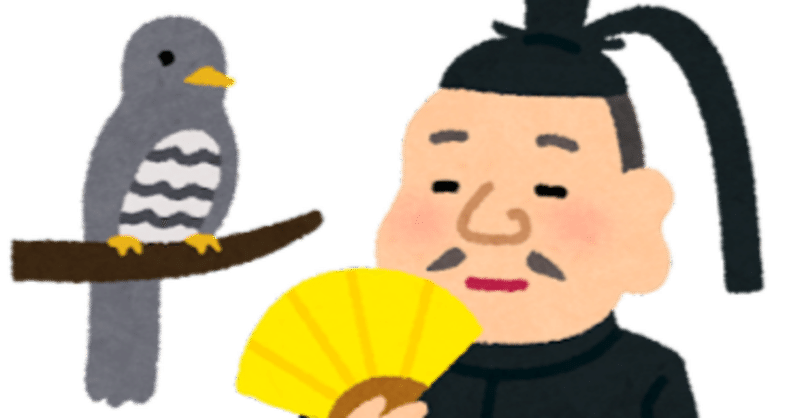
「どうする家康」第25回「はるかに遠い夢」 守るべきものたちに生かされた家康、泣き虫弱虫洟垂れの終焉へ
はじめに
とうとう、その日が来てしまいました。
この記事を読んでいる方々の中には、見たくはないと思いつつ覚悟を決めてご覧になった方もいらっしゃるでしょう。え?それとも、怖いからまだ観られず、先にこの記事を読んでいますか?それはそれでありかもしれませんね(笑)
ところで劇中、瀬名と信康の死を要求した人物がいたでしょうか?
家康や家臣団は当然、二人を生かすため最善を尽くしましたし、裏切られた信長も深く暑苦しい家康愛ゆえに家康に全てを委ね、静観しました(結果は分かっていたでしょうが)。
また二人の処分の必然を説いた佐久間信盛にしても徳川が信長を裏切っていない状況を自分のために懇願しているだけですから、死そのものは言及していません。
更に自身のプライドから瀬名たちを裏切り、この事態を招いた勝頼すら、信長と家康の間に亀裂を入れることが目的であり、瀬名と信康の生死は問題ではありませんでした。寧ろ、二人への情から家康が信康から離反することを望んでいたことは「人でなしじゃな、家康は」からも読み取れます。
そう、誰一人、二人の死を望んではいないのです。それでは、何故、二人は死ななければならなかったのでしょうか?
史実だから?それも理由にはなりません。
実は瀬名には生存説があります。また、信康についても明治期に史料から生存を推定した方がいたりします(現在では否定されていますが)。何の史料を取り込み、フィクションとしてドラマを構築していくかは、その匙加減を含めて、どうとでも出来ます(後述しますが、瀬名生存説はストーリーに少し組み込んでいます)。
にもかかわらず、死ななければならなかったのは、これまでに入念に人物を造形された瀬名たちが、自身の思いと使命に殉ずることを選んだからです。
彼らは史実だから死ななければならないのではなく、自分の生き方を自ら選んだ結果が死であっただけです。自分の人生を生き抜いた、そう描かれているところに、生々しい人間性が表れてくるのですね。
そこで今回は、愛すべきキャラクターとして「どうする家康」前半を牽引してくれた瀬名への鎮魂、供養の想いも込め、瀬名と信康が自分の想いと使命に殉じた経緯と理由を探りながら、彼らの生きた証が家康にもたらすものについて考えてみましょう。
1.それぞれの決意と覚悟
(1)最初から決意を固めていた母子
冒頭の前回の振り返りでは、瀬名の謀が勝頼のプライドによって砕かれ信長にバレるまでの顛末を、畳みかけるようなショットを連ねるように表現することで急転直下の徳川家の危機が強調されます。
しかし、その直後は俯瞰の視点から茶が点てられる二つの椀のショットです。望月千代女に痛いところを突かれた瀬名が茶を服することで息を整えた場面にも見られるように、お茶を振る舞うというのは、茶を点て、一服することで心を落ち着かせる行為です(既に村田珠光が唱えたとされる禅と茶を結び付けたわび茶はあります)。ですから、前回、信康が築山へ謀の瓦解を告げに来たことを引き受け、事態に対して落ち着こうというわけです。冒頭の畳みかける有り様とは対照的に築山の夏は、穏やかです。同時に映される瀬名と信康の背中がそれに呼応しています。
そして、勧めた茶を飲む信康に瀬名は「信康、そなたは…」と言いかけて口をつぐみます。この言葉の後に続くのは「(そなたは)生き延びよ。全てはこの母が引き受ける」であったのは、前回の「全ての責任は私が負います」からも明らかでしょう。勝頼の裏切りは予測出来なかった瀬名ですが、信長に謀がバレた場合のこと自体は想定内です。後は巻き込んでしまった息子を引き離すだけです。しかし、この緊急事態にゆっくりと茶を飲む信康の様子から、瀬名は信康の覚悟を悟ってしまいます。
このとき、くすりとした笑みが瀬名の複雑な心境を表していますね。慈愛の国の謀の最初期からの同志である似た者母子だからこそ、根が優し過ぎる信康の一本気が分かってしまいます。母だけを死なせはしないという気負い、そして自らの命で徳川家を守ろうとする思いに彼の成長が見えてきます。
そして、若き君主に相応しいまでに成長した信康だからこそ、彼に彼の人生を選ばせるしかなく、親はそれを見守る以外にないのです。彼の成長と思いやりへの喜ばしさ、そしてその成長ゆえに死に向かおうとする彼を止められない哀しさと寂しさ、それらが同居する一種の諦観が入り混じり、微笑むしかなかったのでしょう。彼女は、父に「忘れるな」と言われたその微笑みでいつも困難に立ち向かってきましたから。瀬名の笑みには、単純ではないものがありますが、その繊細なニュアンスを演じ分ける有村架純さんのお芝居は今回も光っていますね。
そして、こうした瀬名自身の覚悟と息子の決意を受け入れるもう一つの覚悟による静かな笑顔があるからこそ、その視線の先にある信康もおそらく静かで穏やかな顔でいるであろうことも窺えます(カメラは瀬名にフォーカスしているため、彼の表情はボヤけていますが、彼を見つめる瀬名の表情だけで説明できています)。
このシーンの時点で母子はそれぞれに自分たちのここからの生き方を選び取っており、それに邁進する揺るぎない決意を固めています。したがって、その後の家康とその意を受けた家臣や同志(於大や氏真)たちの思いとは裏腹に、第24回の結末はこのシーンで決まってしまっているのです。後はその幕引きを見届ける以外にないのが、視聴者にとっては忸怩たるところですね。
(2)家康に判断を委ねた信長の胸中
さて、母子が静かな覚悟を決める中、別の覚悟をもって豪雨の中、信長との密会に応じるのが家康です。彼は、佐久間信盛が言い募る築山・信康ら岡崎衆の謀反、そしてそれに家康も加担しているという噂に対して、一言の弁明もなく、無言のまま、雨に濡れるにまかせ、ただただ信長の前で地面に跪くだけです。
二人の対峙(信盛はオマケなので無視)はロングショットで捉えられており、家康と信長の間には距離があります。瀬名の謀に乗った家康と裏切られた信長の心理的な距離になっていますね。
とはいえ、家康の態度は、まずは主君である信長の沙汰を待つといった体です。彼は彼で自分の命だけで済ませる腹づもりがあったのでしょうね。雨の中のその表情はうなだれてはいるものの怯えた様子もなく静かです。まつ毛から滴り落ちる雨しずくが、その表情を引き立てていますね。
主君が主君たる所以は、いざというときに臣下をかばい、詰め腹を切り責任を取ることにあります。奇しくも、家康も瀬名も信康もそうした主君の器を持っていることが示されています。下の者に責任転嫁し逃げ回り言い訳ばかりする現在の日本の政治家や経営者とは真逆ですね。
対する信長の表情ははっきりとは見えません。カメラは彼をロングショットでもクローズアップでも背中越しにしか捉えません。そうすることで、信長の複雑な胸中が表現されているのですね。そして、家康を一瞥することもなく「お前の家中で起きたことだ。俺は何もせぬ。お前の家で処理しろ」とだけ言い渡します。
信長がこの件について家康の判断に委ねたというのは、近年の説に乗っ取ったものです。山岡荘八「徳川家康」は「三河物語」の逸話に合わせて信長の命による殺害で描かれていますが、近年では「当代記」にある「家康存分次第(家康の思う通りにせよ)」との記述や家康の書簡などから信康の切腹は家康の判断によるとされています。
ただ、この「当代記」の素っ気ない信長の返答に、家康への複雑な思いを重ねるのが「どうする家康」です。水野信元誅殺を使い、鷹狩に誘い念押しまでして、家中に気を配るよう家康に警告はしたものの疑り深い信長のことです。内心は彼が翻意したのではないかと気が気でなかったはずです。その苛立ちは、前回、佐久間信盛への罵倒となって表れています。
心配が最悪の形となって報告された挙句、それに対して必死に弁明するでもなく、ただただ跪く家康の姿に家康の加担すら事実と悟ったのではないでしょうか。そして、なおも妻子を庇おうとする家康の姿にも思うところはあったでしょう。
そして、ここまで弟分の家康を追い詰めたのは、信長自身です。裏切らせないため、臣下にまでしたことが裏目に出た形です。自身を含めた様々へのやり場のない憤り、期待を裏切った家康への落胆など様々な想いが、胸中を吹き抜けたことでしょう。
にもかかわらず、それらを押し隠し、謀叛を詳らかにせず、同盟を破棄することもなく、内々で落着させようという温情措置がなされました。この措置の理由の一つは、信長自身への家康への情の深さでしょう。彼は実弟を討ち、また義弟も討ちました。この上、お気に入りの幼馴染の弟分をこうした形で安易に失うことは、極力避けたいということはあるでしょう。
また、今や臣下である家康に妻子の処分を命じることは簡単なはずです。しかし、それを家康に任せ、信長ならば、その果断さで死を与えるであろうその処分について、今回は「よーく考えてな」といったヒントすら出しませんでした。これは、その処分が、過酷で心に大きな傷を残すことが分かり切っているからです。
まして、家康の妻子への情の深さについては、今回のみならず、清須同盟を結ぶ際、金平糖探しの件などで信長も知るところです。それだけに、信長自身から口に出すことは憚られたというのもあるかもしれません。
しかし、処分を家康に委ねたのは、そうした直接的な感傷だけではありません。自身もかつて経験した身内を処分しなければならない状況を、家康が君主としてどう切り抜けるか、それを試そうともしているようにも思われます。
例えば、家康には、妻子への温情措置の可能性も担保されています。例えば、瀬名は離縁し尼寺へ、信康は廃嫡及び幽閉という形です。しかし、この場合は、家康自身が謀反に加担した疑いを完全払拭できませんから、禍根を残すことになります。また、そのまま信長と袂を分かち、一戦を交えるという判断も残されていますが、これが徳川家を滅ぼす判断であることは設楽原の戦いで示されています。信長からすれば、徳川家を滅ぼさない最善策は一つしかありませんが、家康ならば別のことを思いつくかもしれません。
どのみち、これらは主君が判断することであり、その判断の責めと後悔を延々と抱えて生きるより他ないのです。君主の責任は他の誰も負えません。臣下に負わせたときから、君主は臣下を恨むだけの人間に成り果て、その治世が歪むのは明白ですから。誰にも変わってもらえない君主としての判断と責任とはなにか、信長は、家康にそれを学ぶことを要求しているのではないでしょうか。
信長としてはこの判断はリスキーです。信長にとっての最善の判断をしたとき、可愛い弟分が身も心もボロボロになるのは目に見えています。家康が妻子を許せば、彼への疑念を持ち続けなければなりません。そして、滅びを覚悟して袂を分かつ判断をしてきたときは、心ならずも全力で彼を叩き潰さなければなりません。
また、どの判断であっても、結局はそこまで追い詰めたのは信長自身ですから、家康の恨みは買うかもしれません。ある意味では、ここで徳川家を滅ぼしてしまうことのほうが、楽なのかもしれないのです。
それでもなお、彼のあらゆる判断結果を受け入れようと見守る覚悟を決めたところに、彼の本当の家康愛が見えてきます。家康にとって信長はPTSDを起こすほどの最悪の人物なのは間違いありません。
しかし、善きにせよ悪しきにせよ、信長は家康に試練を与え続け、見守るべきときは見守り、その成長を待ち続けているのですよね。自分と肩を並べる真の兄弟分になるのをずっと先で待っているとでも言いましょうか。結果的に、信長は家康に取り、兄でもあり師でもあるのでしょう。
因みに佐久間信盛は「どうすべきか分かっておられますな」と念を押しています。前回のお叱りからすれば、家康に謀叛でも起こされたら今度こそ自身の死活問題だからです。ですから、「処分が決まったら」と肝心の判断はやはり他人事です。君主同士の会話の中で、どこまでも自己保身で家康を案じてしまう小者感が哀れですね(苦笑)
(3)家族を守りたい~家康と五徳の愛情~
さて、信長との密会を終えた家康は力なく、瀬名と信康×五徳夫妻が待つ築山へと現れます。五徳の「父は?」の問いにも答えられないのは、どうすべきか逡巡があるからです。その上で出した答えが、信長と袂を分かち戦うであるのは安易すぎますが。流石に信康も呆れ「武田が裏切った今、織田と戦えば徳川は滅ぶ」と苦言を呈します。そして、それゆえに信康は、秘めていた自分の切腹で事を収める提案をします。しかし、息子を犠牲にできないと家康は激昂します、家族が犠牲になる、そのことに過剰に敏感になる家康は冷静な判断が下せていません。
そんな家康を尻目に、瀬名も「存分のご処置を」と自身の死を覚悟し、自分たちが汚名を一手に被るため、信長へ悪口雑言を書き立てた書状(通説でいう「十二ヶ条の訴状」)を五徳に送るよう頼みます。こうして罪の全てを被ることで、家康と徳川家から自分たちを切り離し、彼らを守ろうというまさしく苦肉の策です。勿論、これには信長の娘である五徳を守ることが含まれています。
しかし、最早、織田の娘ではなく、徳川の、岡崎のおなごとなった五徳は承服できません。慕う信康のことは勿論のこと、胸襟を開き謀の一端を担うことになった五徳は義母である瀬名もまた本当の意味での母になっています。思えば、彼女は9歳で嫁いできていますから、多感な時期を過ごした岡崎での日々のほうが余程に大切です。素直になった今の五徳にとって、この家族はようやく確かなものとなった幸せです。分かたれることなどあり得ません。「謀の仲間と思われぬためにも…」という瀬名の気遣いにも「仲間でございます!」と即言い返し、静かに再度、その言葉を繰り返し瀬名ににじり寄る五徳は健気です。
そんな彼女を、瀬名は「そなたには二人の娘を育てる務めがあろう!」と叱ります。この言葉、第6回で関口夫妻に追いすがろうとする瀬名を思い止まらせた巴の「そなたにも守るべきものがあろう」に呼応していますね。よくよく考えれば、瀬名は38歳ですが既に祖母、あのときの母、巴と同じ立場にいるわけです。あのときの巴の思いに瀬名のこれまでの苦難が重ねられて発せられたその言葉には、五徳を押し黙らせるのに十分な重さがあります。
やり取りを聞きながら家康は決意し、瀬名と信康を呼び寄せ「わしは決めたぞ、そなたらには責めを追ってもらう」と諭します。この言葉に安堵を見せ、覚悟を新たにした二人に、それは表向きであり、死を偽装することを提案します。そして、表向き二人に責めを負わせて死んでもらうため、改めて五徳に瀬名が言った書状をしたためるよう指図します。家康も事態の打開の最善策が、二人の死であることはよくよく分かっているのです。
それでも、愛する妻と大切な息子を死なせたくない、だから、それを両立させようとします。そのとき発した「信長を…世を欺く」の言葉に、家康の覚悟が見えます。今の家康たちにとって、信長とは天下人と言える人物、世の中そのものです。その彼を欺くことは、世界を敵に回すことそのものです。世界を敵に回してでも、自分の家族を守りたいのです。家康のこの想いの裏にあるものは、後半改めて語られます。
因みに家康が瀬名と信康を逃そうとするこのくだりは、瀬名の首を討った野中重政に家康が「おなごの事なれば計らひ方もあるべきを」と述べ、命を助けなかったことを責めたという「実紀」(徳川実紀)の記述を受けてのものであると思われます。史料を踏まえ、そこから瀬名を助けたかった家康の気持ちを読み解いて、掬い上げているのが巧いですね。
また、五徳が、築山殿の不義、信康の乱行などを書き連ねられた「十二ヶ条の訴状」は、結果的に築山・信康事変のきっかけとされた信長への書状です。信長に呼び出された酒井忠次が、書状の内容を認めたために処分が決定します。浅はかな五徳の愚痴が、二人を死に追いやり、結局、彼女自身も終生、孤独なままになったという自業自得のように扱われます。また、家康が、書状の内容を認めた酒井忠次を終生恨んだ旨の逸話も残されています(政治的には重用されていますが)。
しかし、近年では後年の加筆修正の疑いも持たれていますので、今回の信康を慕う五徳ならば書かない可能性もありましたが、寧ろ積極的に採用されましたね。ただし、瀬名が家康と徳川家を守るために五徳に書かせた書状であり、また酒井忠次の一件もその書状を利用した二人の死の偽装計画の一環とされました。あくまで、家康と五徳と家臣団は一致団結して、瀬名と信康を守ろうとした。「一つの家」である「どうする家康」の徳川軍団の絆ならではの展開と言えます。
こうして事態は、瀬名と信康を表向き死なせるシナリオと同時に裏では身代わりを立て、死を偽装する計画の二つが進められていくことになります。
この展開は、五徳自身をも、通説の哀れな女性という立場から救っています。計画は順調に進み、信康が岡崎城から退去することになります。一時的なこととは言え、五徳は信康と長い別れを経験することになる予定です。裏事情を知らぬ山田八蔵以下、岡崎衆は泣いていますが、計画の一端を担う五徳の顔は穏やかです。
達者でいろという信康の心遣いに、五徳は「一つお願いがございます。これからもずっと、どこに行こうと、私は岡崎殿と呼ばれとうございます。お許しくださいますか?」とおねだりをします。前回の一家団欒での心からの笑顔、これまで描かれた信康を慕う気持ちからすれば、五徳の申し出はとても自然です。勿論、信康は破顔一笑、快諾します。
実は、既に信康は自決の覚悟を決めていて、五徳との終生の別れを告げているのですが、それを知らぬ五徳は満足そうに穏やかで静かな笑顔を見せます。信康を慕い続けていたい、添い遂げたい、これが五徳の純情の全てです。信長のごとき猛々しい男を理想とした彼女が、強さはあるものの心根が優しい父とは正反対の信康を愛したとき、彼女は親離れし、一人の成熟した女性になったのかもしれません。
因みに五徳は、築山・信康事変の後の多くを京都で過ごすことになりますが、終生、岡崎殿と呼ばれます。その史実を自ら望んだことにした先の台詞によって、当時、二十歳の五徳がその後、再嫁しなかった理由も、後年、家康の四男より2000石近い化粧料が間接的に与えられ大切に扱われたことも、信康への一途な想いを貫いた結果であると説明されました。
信康自害という結末が彼女を悲嘆に暮れさせたことは、中盤描かれたとおりです。しかし、その人生までは哀れにしない。五徳は一生分の恋をしたのでしょう、そしてそれに支えられ長い余生を送ったのです。それが不幸か否かは、他人の決めることではありません。彼女は、自身の選択を後悔していない…そのようにして「どうする家康」は歴史に埋もれた人々の思いを浮かび上がらせていきます。
それにしても、常に攻撃的で、高慢を絵に描いたような振る舞いしか出来なかった五徳から、彼女本来の優しさと笑顔が引き出されることになるとは…病み切った信康の心と孤独で冷たく固く閉ざされていた五徳の心、二人の若夫婦に一時でも夢見させ、その心を解放した…それだけでも、瀬名の慈愛の国構想は意味があったのかもしれませんね。
2.瀬名と信康の生きざまが、家康に遺したもの
(1)家康の計画を認められない瀬名
さて、家康たちが進める、瀬名と信康を表向き死なせるシナリオと身代わりを立て、死を偽装する裏計画の同時進行作戦、一見、巧くいっているようですが、家康は二人を守ることに盲目的になる余りに色々と見落としているように思われます。
一つは、大局を見失っているということです。二人を生き延びさせ、その後どうするのか、そのビジョンは明確ではありません。それに「世を欺くこと」は容易いことではなく、一度は隠しおおせても秘密はいつか暴かれ、その瞬間、それは致命傷になります。隠していた分、その被害は想像以上になるのは明白です。徳川家臣団の主要メンバーのほとんど巻き込んでの計画ですから、間違いなく徳川家は滅亡の道を進むでしょう。
そして、そもそも、そのような隠し事をし、世を欺く君主を領民は何と思うでしょうか。「世を欺く」とは、天下人を欺くだけでなく、民をも欺くことなのです。その本質的な問題に、「慈愛の国」という真っ直ぐな理想を思い描いた瀬名が思い当たらないはずがありません。
そして、もう一点は至極単純な話で、このシナリオには二人の身代わりという何の罪もない人間の死が前提化されていることです。この身代わりの策は、瀬名の生存説を取り入れたものです。生存説では、川井某の娘を身代わりにして生き延びた瀬名は尼となり、人々の菩提を弔ったとされます。
しかし、本作の瀬名は、民が楽しげに過ごす本證寺を「あんなにいいところ」と称し、民に開かれた築山で民の話を多く聞き、民の言葉や思いに心を砕く人です。彼らの想いを家康に届けようとすらした彼女だからこそ、民の貧しさをなくす東国一円貿易圏構想が立ち上がったことを忘れてはいけません。
そんな、彼女が自分の命と引き換えに無辜(むこ)の命が失われることを是とするでしょうか。瀬名にしてみれば、どう考えても、自分が謀反人の悪女として死ぬ以外、事を収める方法がないことがはっきりわかるだけなのです。
そして、あのお母さん子である賢い信康が、瀬名のそんな思いを察しないわけがありません。それ故に、彼は家康の支持どおりに手配した寺へは入らず、裏計画の実行役である服部半蔵らを困らせます。その後、二俣城に移されてなお、彼は動こうとはしません。彼の一言は「母上がお逃げになってからじゃ」…瀬名がこのような穴だらけの策に身を任せるかどうかを案じています。おそらく彼は母が死ねば追い腹を切り、死なずばそれに安堵した上で母に代わって謀叛の責任を取るつもりだったろうと思われます。
さて、話は前後してしまいますが、信康が岡崎城を退去した後は、瀬名が築山を去る番です。その前に、謀の同志だった久松×於大夫妻と氏真×糸夫妻が来ています。致し方ない事情を前に於大は「そなたを誇りに思うぞ。立派にお役目を果たされよ」と精一杯の誠意を伝えます。於大はかつて人質になっている彼女らを見捨てよと家康に進言した人ですし、また側室問題で心無いことを瀬名に言ったり、振り回したりもしてきました。しかし、於大の側には悪意はなく、ただただ瀬名と楽しくやってきたつもりでしょう。だから、他意なく心からの労いがそこにあります。
そして瀬名が彼らを呼び寄せたのは今生の別れを覚悟してのこと、ですから築山の「草花をお持ちくだされ」と形見分けのようなことを言います。瀬名が去れば、彼女の夢が詰まった美しき築山は失われ、さびれます。せめて、同じ夢を抱いた人々にその思いを忘れないでいるよう願うしか瀬名にはやれることがないのですね。巻き込まないため事情を知らされていない於大が、それでも「家康があの二人を死なせようか」と一縷の望みを託しているのが切ないですね。
こうした瀬名は、彼女の生きる世界の中心に据えられ、武田との交渉も見守ってくれた、家康の弱さと優しさの象徴である木彫りの白兎を袂に入れ、築山を去ります。付き従うは鳥居元忠と侍女に扮した大鼠です。身代わりに死んでもらうという汚い仕事を服部党が一手に引き受けているのですね。冨塚につき、大鼠は身代わりと入れ替わるため着替えをするよう伝えますが、それよりも「信康は逃げたのか」と聞きます。冒頭の茶のシーンで瀬名は、信康の覚悟を悟っていますから、彼がどうするのか半ば分かった上で確認しているのですね。哀しく通じ合った母子です。
そして、自身の身代わりとなる娘をわざわざ確認しに行くとその怯えた表情を見て取り「行くがよい、家にお帰り」と優しく諭し、微笑みます。このとき、死ぬとばかり思っていた娘の顔が、ぱあっと明るくなるのが良いですね。この世で瀬名が、最後に助けた命です。
この一連の様子を大鼠がずっと目で追っているカットがわざわざ挿入されるのが印象的です。彼女は、仕事だから身代わりの娘を用意し、その娘を殺します。そこに取り立てて感情はありません。あるのは生きるための日銭を稼ぐことのみです。ですから、身分のある者が最下層の者たちを直接的に間接的に犠牲にする様子を、そんなもんだと冷ややかにずっと見てきたはずです。瀬名もまたかつて彼女ら忍びの命を犠牲にして救った身分のある者です。
その瀬名が、自分のために無辜の民が死ぬことを良しとせず逃がす様は、大鼠には奇異に映りつつも、それを自己満足と見なし呆れていたかもしれません。しかし、この眼差しは一変することになります。
何故なら、瀬名は、身代わりがいなくなったことで計画が頓挫し、途方にくれる元忠に「彦、介錯を頼む」と言い、短刀を抜こうとするからです。慌てて止め、介錯を渋る元忠を前に仕方なしと悟った瀬名は、大鼠に介錯を頼みます。目を見開いた大鼠は、彼女の顔をまじまじと見つめます。そして、その真意と覚悟を見て取った彼女はそくざに太刀を振りかざし、彼女の願いに応えようとします。「何をする!」と止めに入る元忠の慌てぶりのおかげで、ややユーモラスになっています
ね。
大鼠は、先の身代わりの娘を助ける善意が単なる自己満足ではなく、その先の自分の死を覚悟した上での信念だと瀬名の言動と表情から察したのですね。彼女が、職業軍人的なプライドを持った忍びであることは、前回の半蔵の求婚に対する「殺すぞ」でよく分かります。
そんな彼女ゆえに、彼女のように強く信念を抱き、覚悟を持っている瀬名に何か通じているものを感じ取ったのでしょうね。だから、契約にない瀬名の介錯を瞬時に行おうとしたのです。守銭奴である彼女にここまでさせるのは、余程のことでしょう。
瀬名の自害にすったもんだしているところに佐鳴湖の向こう岸から家康が舟でやってきます。この展開はご都合主義的に見えたかもしれませんが、そうではありません。
築山での終活的な様子に一人、妙な顔をしていたのが数正です。彼は、彼女がこの計画に乗り気ではないことを察したのでしょうね。だからこそ、瀬名が築山を去る際、その背中に「どうか、殿のお指図どおりに」と念押しします。それでも危惧が拭えない数正は、家康に早馬で連絡を入れたことでしょう。だから、家康は、瀬名の思いにようやく気付き、佐鳴湖畔にやってきたのです。
家康が現れたことで自決の決心は鈍り、短刀を納める瀬名の様子に、彼女の未練、家康への溢れる思いが察せられます。事態を収める最善は自身が死ぬことだと分かっている瀬名です。家康が来れば、それを止められ面倒なことになるのは目に見えています。ですから、事態を収めるだけなら家康が岸に着く前にさっさと自決してしまうべきです。しかし、愛する夫を目の前にして、面倒な事態になっても最期に言葉を交わしたい、その姿を目に焼き付けたい、そんな心情が打ち勝ってしまったのでしょう。だから、彼女は一旦、自決を中止するのです。
彼女の本心は、ずっとずっと家康を側で見ていたいなのですから。
(2)徳川家嫡男としてできる唯一のこと
その後の家康と瀬名のやり取りは一先ず置かれて、秋を迎えた二俣城へ場面は移ります。瀬名の死よりも先に信康のことを描きます。築山・信康事変を「三河物語」に準拠して描いた山岡荘八「徳川家康」は、信康を死なせなければならなかった家康の苦渋の選択に比重が置かれますが、「どうする家康」は第1回から第25回まで、ずっと家康と表裏をなすように物語を牽引してきた裏主人公、瀬名に物語の比重があります。
信康の髭とやつれに時間経過が見て取れますが、信康の意思は変わらず「「母上がお逃げになってからじゃ」」です。たまらず、半蔵は逃げて無事だと言いますが、夕陽の影がわずかに射したため訝しんだような表情になった信康の顔は、それを嘘と見抜いている様子が見えますね。「忍のくせに嘘が下手じゃな」と力なく言う信康に流石の半蔵も「私は忍びでは…」とは返せません。心を隠せないから忍びにはなれず、嘘も下手、しかし、信康を助けたいという半蔵の人間性が垣間見えます。
本作では三河一向一揆の頃、半蔵が竹千代時代の信康と遊ぶシーンが挿入されているのを覚えているでしょうか。幼少時に遊んでやった子どもを救いたいと思うのは、当然でしょう。因みに、半蔵は信康が憐れすぎて介錯できなかったという逸話も残っています。
さて、母の死を知り、信康は説得に応じる振りをします。ようやく動いてくれた信康に安堵の表情を浮かべ肩を貸す傅役に平岩親吉の隙をつき、彼の腰刀にて信康は切腹を果たします。傅役として影となり日向となり信康を支えてきた姿が描かれてきただけに、絶叫し、助からぬと分かっていても助けようとする親吉が可哀想ですね。彼は通説では、信康の切腹について、責任を自分が被ろうとしたが防げず謹慎したと伝えられます。そんな彼の思いを反映した描写です。
切腹で苦しむ信康を介錯せんとする半蔵、半狂乱になり「ならん、半蔵」と信康を抱え込む親吉、信康を苦しませないため親吉を引きはがす大久保忠世(二俣城城主)、三者三様の思いの交錯が、信康の哀しい最期を引き立てます。
意を決した半蔵の刀が振り下ろされる瞬間、信康の命が燃え尽きた瞬間、夕焼けの中、真っ赤に萌えあがる紅葉が背景に映り込みます。信康の死は、旧暦9月の半ば(10月初め)ですから、業平の「ちはやふる~」より萌え盛る紅葉はちょっと早過ぎます。しかし、徳川を守りきるほどに成長した彼の散華を象徴する情景として、敢えてのその風景としたのでしょう。ここには、介錯せざるを得ずプロフェッショナルに徹した半蔵、死なせてしまった親吉、見届けるしかなかった忠世たちの哀しみもその情景には託されているかもしれませんね。
ところで、信康の末期の絶叫「わしが徳川を守ったんじゃ。見事役目を果たしたんじゃ。父上にそう伝えてくれ。」は心に刺さります。信康は、20代の若者です。徳川家の嫡男として然るべく育てられてきました。そんな彼が、何の役に立つこともなく、徳川家の足を引っ張り、ただただ生きながらえることは苦痛でしかなかったのでしょう。また、「もう人を殺したくない」彼にとって、慈愛の国構想が壊されたことも大きな挫折であったに違いありません。彼に出来ることは、自分に仕えてくれた家臣を、敬愛する父を守り、徳川家を託すことしかない、そう思い詰めていたと察せられます。そして、言葉どおり、信康の死によって、家康の潔白は証明され、徳川家を守られ、織田との同盟も維持されます。
そして、信康の死は、於愛の笛を聞きながらぼんやり過ごす家康の元へ届けられます。大きな広間の縁側でぽつねんと家康が座るという遠景のショットに、家康の現在の無情感が表れています。於愛の笛が心なしか聞けるレベルになっているのは、傷心の彼を癒したい於愛の真心なのでしょう。万千代の「ご自害なさいました」の一言に対し、家康の表情はショックを受けるでなく、全く動きません。もうこうなることが分かっていた、そういう諦めと放心と呆然が入り混じった無表情。今回の松本潤くんの芝居の白眉は、心が完全に死んだこの表情でしょうね。
そして、無言のまま立ち上がり去ろうとするも、心労で倒れ伏します。
そして各所に、瀬名と信康の訃報が届けられます。
築山の草花を生けたものを見つめる於大の元に力なく書簡を手に提げて現れる長家。夫婦に会話はありません。ただただ無言の中に溢れる万感は、於大の目に涙を呼び込みます。
そして数正から報告を受け偲び泣き崩れる五徳。五徳の哀しみは当然のことながら、報告し平伏する数正の無念の表情に流れる涙が印象的です。劇中で唯一、瀬名の異変に気付きながらも、それを止めることが出来なかった数正の胸中を思うとたまりませんね。
また、劇中では描かれませんでしたが、西三河の旗頭でもある彼は信康の後見人でもありました。だから、五徳への報告は彼がしているのですが、それも合わせると彼の無念も更に分かる気がします。
そして落胆する氏真に号泣する糸…幼いころから知る知己とその息子の死、そして心躍らされた謀の無残な結末に言葉はありません。
出てはきませんでしたが、亀姫も長篠で泣いていることでしょう。
人の価値は、その人が死んだときにどれだけの人が哀しみ、涙したかであるとはよく言われますが、それは、その人の記憶が多くの人の中で生き続けるということだからです。その意味で、彼らはこれからも生き続けるのでしょう。
そして、それはかつての敵も同様です。敵として相対し、その後、夢を共有する同志となった望月千代女は、静かにこの事件の顛末を伝えます。それを聞く穴山信君にも落胆の色が混じります。そして役目を終わったとばかりに去っていく千代に穴山は「どこへ行く?」と呼び止めます。
振り返る千代は、哀しみの笑顔を見せ、軽い会釈だけをして去っていきます。ようやく胸襟を開き結ばれた女性同士の絆を打ち砕かれ、千代はどこへ行くのでしょうか…
ここでふと思うことがあります。これは戯言、余興として読んでほしいのですが、実は家康の後半生では重要な側室、阿茶局の配役が未発表なのですね。彼女は、築山事変の1579年には家康に召されているので、未だに配役が出てこないのを不思議です。で、まさかのまさか…勝頼の元を去った望月千代女が名と素性を変え、阿茶局として家康に力添えする展開とかはないでしょうかね?
阿茶局は、父親は元々、武田方の関係者です。また未亡人で子どもも失っています。なんだか、千代に符合する点が多いキャラクターだったりします。また、家康の戦場にもよく随行し、妊娠も小牧・長久手の戦いの陣中(流産しましたが)という剛の者で、交渉術にも長けた有能な外交官でもありました。更に、おそらく瀬名の慈愛の国構想の夢を最初期から最も共有していたこの人物が、瀬名の思いを事あるごとに伝えるとしたら…などと妄想してしまいます。
最も、年齢が違いすぎますので、「望月千代=阿茶局」をやるにはクリアすべき問題が大きいので、実現すればかなり強引なことになり、史実に煩い御仁から非難を浴びることになりますね(苦笑)
当たるも八卦当たらぬも八卦…もし当たったら大笑いしてください。
ただ、先にも述べたとおり、本作で、瀬名の思いを最もダイレクトに知るのが望月千代女であるのは紛れもない事実。今後も何らかの形で家康と接触し、それを伝える、あるいは家康を助けるということで再登場するだろうとは思います。
話が妄想で逸れ過ぎましたから戻しましょう。去っていく千代に一瞥もせず、「人でなしじゃな、家康は」と言ったのが勝頼です。「お前が言うな」と思った視聴者も多かったでしょうが、この言葉は、信長と家康を戦わせて漁夫の利を得るという自分の必勝の策の当てが外れ、(勝頼にとって)つまらないオチになったことへの腹いせ、子どもじみた戯言に過ぎません。
そもそも、彼の父、信玄が、長男義信を謀反の疑いで廃嫡&幽閉と今回の家康とほぼ同じことをしたことを知らぬはずもありません。寧ろ、そのような心無い言葉ゆえに、策も外れた今、更に人心が離れ、落ちぶれていくことになることが暗示されています。勝頼にその自覚は無さそうですが。
さて、瀬名たちの顛末を最後に聞くのは信長です。今回も背中越しに報告を聞いています。
そして、佐久間信盛は無事、事が収まったことだけを見て「良かった…良かった…」としみじみ言います。信盛にしてみれば、家康に何かあったら責めを負うところでしたから、その思いは本当でもそこに自己保身が混ざるのは致し方ありません。そして、その決断をした家康の心底を慮れないことも、そもそも信長の真意を汲めない鈍さゆえに仕方のない面もあります。
しかし、その無神経は、家康を思う信長の怒りを買います。憤怒の信長は「何が良かったか?」と問い質します、この直後の「ああん?」がヤンキー丸出しでかなり怖い。ですが、この「ああん?」に優しい弟分の苦しんでいるであろう心情に誰よりも共感している信長の心痛が窺えます。
それだけに信盛を許せず、「二度と顔を出すな」と事実上の失脚宣言とも取れる台詞を放ちます。訳が分からず立ち去るしかない信盛の呆気に取られた顔が印象的です。
実際の彼の追放はまだ後の話であり、理由も家康とは関係ありませんが、この件をきっかけとして信長の不信を招いていったのかもしれませんね。
信盛が去った後、遠景のショットの中、背中だけを見せる信長はただ「…家康…」と独り言ちます。彼だけは瀬名たちではなく、家康の心情に想いを馳せます。
今回の試練を与えたのは、結局のところ信長です。時には愛する者の命すら斬り捨てねばならない苦悩、その責めを終生抱え込まなければならない孤独、君主の宿命の暗黒面を実践してきた信長は、同じ心痛を同じく君主である家康に教え込みました。それは、家康に確実に大きな変化をもたらします。彼の可愛がった白兎の終焉、その果てに彼がどう変わるのか。今、その痛みに耐え続ける弟分への心配だけが彼の心を占めているのでしょう。
とはいえ、娘の五徳が伴侶を失い哀しみに暮れていることにも少しは心を砕けよ…とは思います(笑)
(2)瀬名から「はるかに遠い夢」を託された家康
さて、倒れた家康は、於愛の看護を受けていますが、その表情は硬いままです。しかし
その無表情から一筋の涙が零れ、あの日の瀬名との最期の会話が蘇ります。
湖畔に辿り着いた家康は開口一番「死んではならん」と伝えますが、瀬名は「それはできません」と突っぱねます。何故と問う家康に、この謀反を正しく収めるには「私たちは死なねばならない」とその必然と理屈を説きます。勿論、瀬名は「信康だけはどんな形でも生きていてほしいけれど」と本音も漏らしますが「あの子はそれを許さないでしょう」と彼の意思を尊重せざるを得ないことも伝えます(この言葉があるからこそ、彼は信康が死を聞いた際に諦めの気持ちがあったのです)。瀬名は、将来と大局を見て判断しています。そして、息子についても、自分の意思を貫く代わりに、人のそれを認めなければならないことも分かっているため受け入れます。
賢いゆえに哀しいくらい理屈が立ってしまうのが瀬名の独断専行の所以であり、悪い癖ですね。その理屈は正しくても、家康の瀬名への気持ちを置いてけぼりにしてしまいますから。だから、それでもお前たちを死なせなくない、嫌なんじゃと叫ぶ家康に思わず「それはワガママ」と叱ってしまいます。ただ、このお叱り、家康に向き合わず、背中越しに言っていて、本心は真逆です。そう言いすがってくる家康のことが嬉しくて愛おしい。だからこそ、家康を直視しないのです。見たら、自分の気持ちがブレてしまうから。
ここに来て、家康は「ワシは一度、そなたたちを見捨てた。」と長年抱え続けた瀬名たちへの後ろめたさをようやく口にします。岡崎に来てここで生きていくしかないと思い極めた瀬名は、決して彼をこの件で責めることはしませんでしたし、また両親の死を彼のせいにすることはありませんでした(山岡荘八「徳川家康」の築山殿は内心、恨んでいましたが)。瀬名の賢さゆえに、清州同盟により一旦は彼女たちを見捨てることになった件は、話題にされずに流されてきました。その件をここに来て回収しにきたのは、流石ですね。
そして、その後悔があるからこそ、氏真から取り戻したあのときに二度と家族を見捨てず「そなたたちを守っていくと」と誓ったのです。清州同盟の際、彼は人知れず泣き崩れ、それを見たお市が婚姻を破棄したことを思い出しますね。あの時の涙を家康は忘れていなかったのです。
瀬名の真意を汲めない夫でしたし、良き父親にもなれなかった家康ですが、「世を欺」いてまで、世界を敵に回して家族を守ろうとしたのは、一人抱え続けた後悔も大きく作用していました。だから、盲目的な策を講じてしまったのであれば、一概に彼を愚かと責めることはできません。そして、「お前たちを守る」ではなく「守らせてくれ」と懇願します。
しかし、瀬名は、その優しさに寄り添いたい気持ちを押し隠し、哀しい顔をしながら、それでも毅然として「あなたが守るべきは国でしょ」と自分たちが共に見た夢で諭そうとします。自分の心からの思いに応えようとしない瀬名に家康が「国なぞどうでもいいんじゃ」とブチ切れて返すのも仕方のないところですが、家康が自分だけの伴侶ではないことを知っているからこそ、それを敢えて言わなければならない瀬名の心情もまた切ないところです。
家康にしても本当に「国なぞどうでもいい」と思っているわけではありません。ずっとずっとそのためだけに悩み続けましたから。そして、瀬名は優しさゆえに悩み続ける彼を支えたいと思ってきましたから。
家康が「瀬名奪還作戦」「続・瀬名奪還作戦」で自分の家族を守りたいという原点に返る中、瀬名もまたその日が自分の原点であったと語るあたりが、家康との綺麗な対比になっていますね。その原点とは、以前のnote記事でも採り上げた巴の遺言です。
瀬名、強くおなり。
我らおなごはな、大切なものを守るために命を懸けるんです。
そなたにも守らねばならぬものがあろう。
そなたが命を懸けるべき時は、いずれ必ず来る。
実は巴の発言は「大切なもの」「守らねばならぬもの」が明確ではありません(彼女自身は家族のつもりだったと思いますが)。それゆえに、その言葉を考え続けた瀬名は、家康の守りたいものが、「家族」であったことに対して、瀬名のそれは家族から家康がまとめていく「国」になり、更にはその先の「戦のない世の中」にまで成長し、あの謀につながっていきました。
二人が目指すのは「厭離穢土 欣求浄土」ですが、家康のそれはミニマムな自身の家族を守りきったその先にあり、瀬名は「戦の無い世」というマクロの実現によって自身の家族を守ろうという発想でした。
そして、君主という家康の立場に必要な視点は、瀬名の側の見方であるのは明白です。家康が彼女の謀に圧倒され、無謀でもあってその策に乗ったのも、彼自身が瀬名の見方に正しさを見たからでしょう。ですから、そのために「全てを背負わせてくださいませ」と懇願する彼女を止める術がありません。
ただ、こうなると瀬名たちを助けるために打った全ての手が、反転し永遠に彼らに汚名をかぶせるだけになります。家康は瀬名と肩を並べ「世の者共は悪辣な妻と語り継がれるぞ」と語ります。しかし瀬名は「平気でございます。本当の私の心は殿の中にございます。」と慰めます。多くを求めず「足るを知る」瀬名は、家康の心の中にだけ生きていたらそれで幸せなのだというのです。
以前の記事でも話しましたが、瀬名は自分のしてきたことが家康に守られているから出来たと自覚しています。家康を信じ、甘えることで自由に学び考えたのだと。そのことを忘れないため、そして家康に守られている安心感を得るため、彼女は白兎を手放さず、いつも自分を見守る一に据えていました。その信頼が、この台詞を言わせているということも押さえておきたいところです。瀬名は、本当に家康がただただ好きな人だったのです。
そして、二人は抱きしめ合います。このシーンはロングショットで、竹やぶの竹がクロスしている部分をナメて抱き合う二人を捉えています。こうすることで二人の信頼関係、今生の別れとなる最後のハグを強調しています。そして、このハグの中で瀬名は、初陣のときに語った「二人でどこかにこっそり落ち延び、誰も知らない土地で小さな畑をこさえて暮らしたい」という発言を覚えているかと語りかけます。そして、一言「あれが瀬名のたった一つの夢でした」と言い、更に「ずっとずっとはるかに遠い夢でございましたなぁ」と付け加えます。ただただ穏やかに愛する人と過ごしたい、そんな単純なことが叶わぬ世の無情に思いを馳せます。
この初陣の台詞は、以前のnote記事でも瀬名の変わらぬ初心として、そして素朴でシンプルなその願いに全ての理想があるとして、二度ほど採り上げました。そして瀬名のキャラクター造形が1話から入念になされていると説明しましたが、まさにその通りだったようです。そして、これが家康に託される願いとしていく今回の脚本は秀逸です。瀬名の理想と夢が、家康が後々、天下一統を果たすための軸になる。だからこそ、彼女は第1回から第25話をかけて、ずっと本作の裏主人公で居続けたのですね。
そして、瀬名は、自分が家康と共には果たせぬその夢を、家康と共に叶えて見届けるよう平八郎(忠勝)と小平太(康政)に託し、家康には死にゆく自分には最早、不要な木彫りの白兎を返します。家康の弱く優しい心の象徴であるそれを手渡し、自身の原点であるその心を大切にするよう「いいですか、兎は強うございます。狼よりずっとずっと強うございます。」と力強く励まします。
こう言えるのは、瀬名が白兎の元で大胆なことをして見せたからですし、また瀬名のあり方そのものもまた武勇などの外見上の強さではなく、しなやかで折れない強かな芯の強さにあります。それが出来るのは、自分の弱さを知るからです。だからこそ、よく考えて力押しだけではない方法で巧みに物事を進めていけた。家康もそうなると瀬名は思うのですね。だから「厭離穢土 欣求浄土」も「貴方なら出来ます、必ず」とも伝えます。
三河一向一揆編のときは「なんとなく」だったそれを「必ず」と断言したのは、家康を信じ続けてきた瀬名の強い思いなればこそですが、一方で自分が叶えたかった「はるかに遠い夢」を家康に叶えさせる、ある種の呪いの言葉でもあります。そして、三方ヶ原合戦で散った夏目広次の「大丈夫」の言葉とも響き合います。家康は、またも守りたいものたちに生かされ、救われ、励まされ、願いを託されて生き延びるのです。彼らの願いは、彼らの生きた証として、家康に刻まれます。それはとても重いはずです。だから、願いでもあり呪いでもあると言えるでしょう。
そして、瀬名はそこに更に「瀬名はずっと見守っております」と添え、家康の行くべき道筋を決め打ちします。瀬名が、悪女だとするなら、家康に平和な世の中を築くよう願いを託したことかもしれませんね。この先、瀬名のいない世界で歩む彼の道は過酷ですから。
こうして、家康は小舟に乗り、佐鳴湖へこぎ出します。去っていく家康を万感の思いをもって見つめる瀬名は笑顔です。徐々に遠ざかる彼女の姿ですが、ここで美しく終われないのが家康です。「嫌じゃー」と叫び、止める平八郎、小平太をコントみたく湖に突き落とし、飛び出します。このとき、家康は「嫌じゃ」という感情の吐露だけではなく「こんなの間違っている」と冷静な判断も口にしている点は見逃せません。
そう、瀬名と信康が死ななければならないことは間違っています。彼らは、ただ人々が安寧に穏やかに暮らしていくことを願ったに過ぎません。誰かの心を傷つけるようなことは何もしていません。また、誰も彼らの死を願っていません。にもかかわらず、誰もが願う幸せなひと時を願っただけで、死なねばならないのはどこかがおかしいのです。その気づきが家康にあったこと、それは大きな喪失と後悔として家康の胸に刻まれ、そうした多くの人々の幸せを願うことで死ななければならない乱世をどう解決していくのか、それを考えさせることになるでしょう。
さて、そんな泣きじゃくりこちらへと戻ろうとする「泣き虫弱虫洟垂れ」の家康を瀬名はどこまでも微笑ましく見つつ、自決を覚悟します。自身の目の前で自決されることは、家康にとっては大きな傷になるでしょう。彼の絶叫で暗転した今回の幕引きがそれを象徴していますし、またあの無表情にもそれが表れています。
しかし、瀬名のほうはどうでしょうか。彼女が、断末魔に見るのは自分が愛した「泣き虫弱虫洟垂れ」の家康です。その姿を目に焼き付けつつ「ああ、もう仕方のない人なんだから」とある種の幸福感を持ちつつ亡くなっていけるのだとしたら、せめてもの手向けとなったかもしれません。刃を首にあてる彼女の瞬間に悲壮感が薄いのはそのせいでしょうか。
そしてくず折れる瀬名を今度こそ楽にすべく、一撃で介錯、トドメを刺しにいくのは大鼠です。トドメを刺した後、彼女が瀬名にひれ伏し、土下座をするところに彼女の最大限の敬意が見えますね。出来る女が出来る女を理解し、それゆえに看取る。「どうする家康」で度々、描かれた女性たちのシスターフッドな関係が、瀬名の最後にも見られました。このことは、瀬名が女性たちをつなぐ扇の要であったことを示しています。その要を失った女性たちの思いと、そのつながりはどうなるのか、家康の今後の動向と共に気になるところです。
おわりに
江戸時代から現代に至るまで、築山殿は悪女と語り継がれてきました。
しかし、「どうする家康」の瀬名は、情け深く、思慮深く、女性たちの人望を集める有能な女性として描かれました。そして、賢い彼女は大いなる夢を抱き、それゆえに破れます。全ては、人の善性を信じ、人々のために尽くそうとした結果でした。
そんな自発的に動く女性は、「男ども」(お万)の都合で後世の人々に悪女にされたのではなく、悪女として残されることを選び取った。ですから、五徳の「十二ヶ条の訴状」を初め、後世語り継がれる悪評も瀬名自らの申し出たことであり、そう語られることが、徳川を、家康を守った証でもあるという彼女の意思を際立たせるように構成されました。
あくまで、女性たちの選択を尊重するその描き方は、正史に埋もれ、切り捨てられていった弱者の意思を掬いあげ、救おうとする「どうする家康」ならではの誠意が窺えますね。
それにしても、第1回から第25回まで入念に組み上げられ、誰もが予想だにしなかった東国一円貿易圏を背景にした慈愛の国構想をぶち上げ、そして散華していった瀬名とは何だったのでしょうか。女性を含めた弱者への眼差しの集大成であるのは勿論です。しかし、彼女を支えたのは、どこまでも「泣き虫弱虫洟垂れ」の家康を愛したという一点に尽きます。
ここで第二章の目論見を考えてみましょう。第13回で信長がぶち上げた天下一統を始め、家康に新たに要求されたのは、将来、全国、世界といった大局的な視点と視野の広さです。ですから、家康なりの大局的な視点を得ることが、第二章の家康の課題となると述べてきました。
それを象徴するように、金ヶ崎、姉川、三方ヶ原と大局的な視点に立っての判断を絶えず求められました。家康を鍛え上げたのは、兄貴分の信長の過酷な試練であり、そして大敵、信玄の存在でした。しかし、家康は彼らと同じ視点に立つことはついぞ出来ませんでした。家康にどんな国を作りたいか、明確なビジョンがなかったからです。そして、信長や信玄のような覇道も家康には共感し難いものでした。
覇道とは違う徳治による王道の政治、それを見出し、家康に提示したのが、彼の裏で彼の知らない領民や女性たちといった弱者の声を見聞きし、学び考えてきた瀬名だったのです。彼女はもう一人の家康として、彼の合わせ鏡として、物語を牽引してきました。そして、家康に進むべき道を示し、その実現の過酷さも身をもって示し、消えていきました。第二章の目論見、将来を見据えた大局的な視点は、他ならぬ瀬名によって与えられたのです。言い換えるなら、それこそが彼女の作品上の役割だったと言えるでしょう。
一方で、家康は愛すべきものを多く失ったのが第二章の特徴です。
三河一向一揆で彼は、家族を、家臣を、領民を守ると誓いました。しかし、結果は三方ヶ原合戦にて、自分が守るべき多くの家臣によって彼は生かされました。そして、築山・信康事変では、遂に最も守りたかった妻子に彼は守られ、生かされることになりました。哀しいことの連続の果てにあった妻子が命をかけて自分を守った現実。信康の死の際に見せた諦めと放心と呆然が入り混じった無表情は、全ての感情を一度失ってしまったかのようでもあります。
そう考えていくと家康の優しさと弱さの象徴たる木彫りの白兎こそは、瀬名の願いと共に託されましたが、瀬名だけが知る「泣き虫弱虫洟垂れ」という家康の一部は彼女が引きつれて永遠に彼岸へ旅立ったかもしれません。とりあえず、今の彼には必要のないものとして。だとすれば、築山で言った瀬名の「いつか必ず取りにきてください」が叶うのは、家康が「戦のない世」を実現できたそのとき、謂わば彼が彼岸に旅立つときかもしれません。
また、築山・信康事変による処断により、彼は君主の孤独と過酷さも身に沁みました。そして、生かされ生き延びる君主ならではの苦悩も更に増しましたね。ですから、これからの家康は、大局的な視点を持ち、それを叶えるため、君主の孤独と過酷さに耐え忍びながら、邁進することになるのでしょう。
オーソドックスな家康が描かれた大河ドラマと言えば「葵 徳川三代」の津川雅彦さんが演じた家康が有名ですが、この家康は「人に上に立つ者は心に鬼を住まわせねばならない」と君主の心得を説いています。今、まさにそれを「どうする家康」の家康もそれを身に着けようとしているのかもしれませんね。
「泣き虫弱虫洟垂れ」という長い長い青春期は終わり、新しい家康の時代が次回から始まることになるのでしょう。第26回予告編の打って変わってバカなほど明るく振る舞う家康には、既に腹芸の出来る複雑な人物像への転身という片鱗が見えます。平たく言えば、遂に家康の俗説評「たぬき親父」への道が開かれたようです。こういう家康になれば、光と影の演じ分けも重要になります。松本潤くんの芝居の真骨頂はこれからでしょうね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
