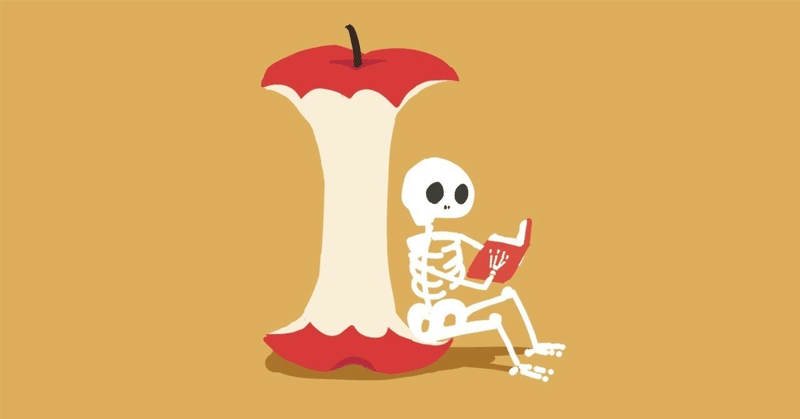
14歳までの読書と41歳からの読書
もう十年以上の前のことになったが、日本に帰国した際に、懐かしさから自分が小学校入学時に通った通学路を辿ってみたことがあった。初めて大人たちの監視の下を脱した解放感からか、わずか一学期足らずのことなのに、思い出がたくさんつまってる道である。
ところが、子どものときには一時間くらいに思われた道のりであったものが、大人の足では20分足らずで、いささか拍子抜けした。子どもの視点からは神秘的で謎に満ちていたような場所が、大人の眼からはすべてが光によって照らされている。なんの謎も秘密もありそうもない。隠された危険もなければ、まだ見つけていない冒険の可能性もない。
たとえば、寺の墓地から谷へ下ったところに、舗装のない細い道の両側に高い杉のような木びっしりが並んでるようなところがあった。枝が重なってアーチみたいになっているから、昼でもちょっとうす暗い。通るたびに、ちょっと薄気味悪かった。それが大人の眼からは、わずか十数メートルの貧弱な並木道だ。早起きしてカブトムシやクワガタを採りに行った鬱蒼としたクヌギ林であったものも、木々が規則正しく並んだはなはだ人工的な公園でしかなかった。
若隠居を強いられて暇になったとき、やっぱり懐かしさから、自分は子どもの頃好きであった児童文学書なんかを手にとってみた。それ以前は、本は仕事で読まされていたから、仕事じゃないときにもう読書なんかする気が起きない。物語や小説なんかからは長いこと遠ざかっていた。
ところがやっぱり、読んでも懐かしさを覚えるだけで、昔のような気分の昂揚がない。なんでこんなものを神秘的で魅力的だと感じたのだろう、と不思議になった。同じ人格であっても、子どもの視点と大人の視点では世界はこれほど異なって見える。そういうことを改めて感じさせられた。
はっきりとは思い出せないが、子ども、そして青年になってからもしばらくは、まだ知らない世界への憧れとか不安を抱いて本に向かっていたような気がする。だから、わくわくどきどきしながら読んでたし、わくわくどきどきするために本に手を出した。まあ、他の人であったら映画なんかをに見に行くような感覚に近いと思う。自分はあんまり映画に親しんでいなかったので、退屈すると本を手にとるような少年・青年であった。
それで、手を出す本も創作文学がほとんどだった。子どもの頃に読んだもので思い出せるいちばん古いものは、サンタさんがくれたスティーヴンソンの『宝島』と『アーサー王と円卓の騎士』、兄弟がサンタからもらったドリトル先生シリーズ、『海底二万マイル』などだ。
男の子だからかやはり冒険ものが多い(もちろん、少年マンガも盛んに読んでた)。だが、このほかに児童文学の古典みたいなものも好んで読んでいた。いまタイトルが思い出せるのは『長くつ下のピッピ』とか『トムは真夜中の庭で』くらいだが、舶来ものか、あるいは『魔女の宅急便』みたいな舶来ものっぽいお話がお気に入りだった。まだ都会化しきっていない西洋の小さな町や田舎を舞台としたファンタジーものが多い。
なぜなら、西洋世界の日常自体が、一つ未知の世界だった。とくに、自分が普段見慣れているのとはちがう食べものとか飲みものとか、微笑ましい恋愛感情・表現などが、子どもらしい好奇心を直接に刺激した。だけども、物語の設定や構造自体にも魅力があって、その日常に幻想の世界が食い込んでいるような話が多い。狭い世界しか知らない子どもにとっては、二重の意味で未知の世界に感じられた。
であるから、学校と家庭を往復するような退屈な生活では感じられないような、心をゆり動かすなにか、今であったら「エモさ」とでも呼ばれそうなものが、本の世界には感じられた。かつての通学路のように、書物というものはちょっと神秘的なもの、闇を含んだものであって、そこには子どもが近寄るべきではない多くの危険が潜んでる。それが不安をかき立てるが、冒険を通じて獲得されるなんらかのお宝(とくにお姫さまだ)も秘められてる。そういうイメージだった。それが子どもをして本に手を延ばさせた。
自分のような子どもが、宇宙の神秘にかかわるような事件に巻き込まれて、散文的な日常から放り出される。そうやって、謎を解くための冒険が始まる。さまざまな試練を勇気と知恵でくぐりぬけて、最後にお宝をゲットする。そのときは意識してなかったけども、そういう物語がとくに好きであったようだ。
「わくわくどきどき」を動機で読んでいたから、いい本に出会ったりすると、自分の周囲で起きてることなんかそっちのけにして、本の世界に浸ってることも多かったように思う。今ではオタクというとちょっと老けた連中が想像されるようになったが、マンガにかぎらず本好きの子どもはだいたいオタクなところがあるから、それがそのまま大人になるだけの話じゃないだろうか。だから、読書に親しむ子ども増やせば、試験の成績も上がるかもしれんが、オタクも増える。そういう計算になる。自分などもそういうオタクの第一、第二世代かもしれない。
ついでに言うと、自分が一連のジブリ映画を見るようになったのはずっと大人になってからだが、子どもに見せながら自分も楽しんでしまったのは、なんだか懐かしい気分にさせられたからだ。子どものころに親しんだ児童文学に近い感触があった。だから、こんなものを創る人たちは、きっと自分が愛したような本を愛する人たちだと決めつけて、なんだか親近感を抱かされた。
ところが、だんだん年をとるにつれて、マンガや児童文学のわくわくどきどきからは遠ざかっていった。なんてことはない、子どもの生きる狭い世界から世間に出るにつれて、謎に包まれていた世界から未知のものが減っていく。闇が光に照らされていくんだが、そうやって明かされた現実世界や人間は、本に登場する世界や人間たちと比べてあまりにも卑小でつまらなく見えた。だからまだ知らぬものへの不安や憧れも相対的に減じていく。
なあんだ、外から見るのとはちがって、現実の世界はこんなものかという幻滅もあったが、その代わりにもっと現実的なあこがれや不安の対象がいっぱい用意されてる。冒険がなくても市場における競争や権力闘争があるし、お宝やお姫様がなくてもカネで買えるものや生身のガールフレンドがいる。だから、そちらに忙しくなって、もう本の世界などに浸かるのが時間の無駄に感じられるようになった。
要するに、もう少し現実的な人間になり、本は何かを学ぶため、楽しいからじゃなくて役に立つから読むものになった。書物は趣味娯楽、人生の道草というよりは仕事道具みたいになっていった。悪くすると、他人に感心してもらいたいがために、たいして面白いとも思わないものを読むような場合さえある。「わくわくどきどき」は、もうどこか別のところに行ってしまった。
寂しい話だが、それで読書が楽しくなくなったわけでもない。こうやって暇を得て児童文学書を読んでみても、やっぱり得るところはある。ある意味では子どものときよりも、より楽しめるところもある。エンデの『モモ』が典型だが、子どものときには大して印象に残っていなかったのに、大人になって読んだときにようやくその面白さを理解したという例さえある。
だから、どうやら子どもの頃には想像もつかなかった別の読書の楽しみがありそうだ。昔のように、まだ自分のよく知らぬ世界をこわごわのぞき見る窓(この窓のガラスには子どもの無知と偏見に合わせた色が塗られてる)としてではなく、同じ世界に生きる人間の仕事/作品として読むようになった。ジブリ作品鑑賞が一例だけど、その作品世界に浸るというよりは、こんなものを作った人たちはどんな人たちなんだろうと考えながら、鑑賞するようになったらしい。
むろん、まだ未知の世界をのぞく窓という機能も、完全には失われたわけではない。たとえば、海外の小説に対する欲求には、いまだに未知の部分が多い世界に対する好奇心というものが働いてる。古い小説、自分が知ってる時代と異なる時代に書かれたものなんかも、そういう一面がある。
だけども、その世界においてだって、やはり自分の知ってる世界とおなじ自然法則が働いているということが想定されてる。森の中で魔女の集会が開かれたり、魑魅魍魎がうろうろしてたりしない。夜中に時計の鐘が鳴るとタイム・スリップできるような場所があるとは、もう思ってない。
まあ、音楽なんかと同じで、たくさんの音楽体験を経ると耳が肥えるが、その分、エモい経験はめったなことではしなくなる。評論家的な態度で作品を鑑賞するようになったということで、それによって失われたものも多い。もちろん、それでも時たま泣いたり笑ったりさせられるが、その泣いたり笑ったりという経験が、もう宇宙との交感という何やら神秘的な秘儀という性格を失ってる。心理学的な分析の対象にまでおとしめられてる。子どもらしい素朴な楽しみは、もう失われた。だが、そうであれば、いったい何が読書の楽しみとして残ったか。
この本の読み方の変化を促したのは、おそらく自分で物を書くようになったことである。だから、「物書く人」として他の「物書く人」たちの作品を見てる。どっちも現実世界の住人であって、おとぎ話の登場人物ではない。この現実世界の住人が現実に感じている不安や憧れと向き合う一様式として、「書く」という行為がある。単に文字を書くだけではなくて、物語や考えを文章という形で創作するという広い意味でである。
言ってみれば、「書かれたもの」に対する関心が、「書いた人」への関心と切り離されずに結びついている。自分が書こうなんて思いもしなかったことを書いた人間は、いったいどういう人なのか。なぜ書いたのか。どうやって書いたのか。あるいは、彼らを自分を映し出す鏡として見て、逆の問い方もできる。なぜ自分はこれを書かなかったのか。これを書かない自分とはどういう人間であるか。どうすれば書けるようになるか。そんなことを考えながら読んでる。
そして、書かれたものは誰かに読まれる。読んだ人が、そこから何かをとり出して、また何かを書く。そうやって「書く」と「読む」と「書く」というのが無限にくり返されていく。そのあいだに、伝言ゲームみたいに、内容が変化していく。最後には、最初に伝えられたものとはぜんぜんちがうものができ上がってる。自分が書くものでさえそうであって、自分が最初に予想もしなかったところに連れて行かれる。
むろん、文字文化以前の「話す」と「聞く」にも同じようなフィードバックがあるが、伝えられる内容の量、そして時間や空間を越えていく媒体としての力が格段にちがう(むろん、文字にすることによって失われてしまうものもあるから、伝えられるものの質については留保が必要だ)。
ここから先は
コーヒー一杯ごちそうしてくれれば、生きていく糧になりそうな話をしてくれる。そういう人間にわたしはなりたい。とくにコーヒー飲みたくなったときには。
