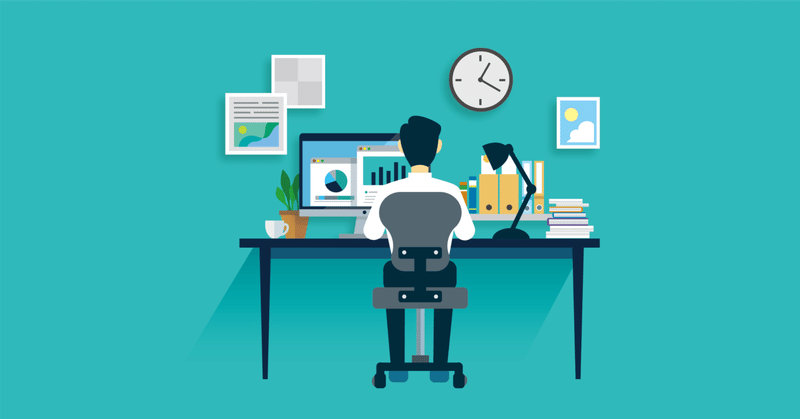
国税庁見解を受けた信託型SO発行企業の動き方を考えてみた
ここのところスタートアップ界隈は信託型SOの話題でもちきりです。
これはもちろん、2023年5月29日に国税庁が示した、税務上の取り扱いに関する見解を受けてのものです。信託型SOは行使時に給与所得課税になるよ、ということです。
信託型SOに関連する相談を弁護士の立場から複数受けていた身として、私も関心をもってウォッチしています。
今回の国税庁見解を受けて、既に信託型SOを発行している企業の動き方を考えてみました。
既に信託から従業員に交付済み、かつ従業員がSO行使済みの場合
会社に源泉所得税の納付義務があるというケースです。
この場合、以下の選択肢が考えられます。
大人しく納税する(国税庁によれば、分納も検討してほしいとのこと)
納税債務の時効完成を震えて待つ
国に納税債務の不存在確認訴訟を提起して争う
もっとも、信託型SO発行企業は、上場会社か上場準備会社(準備に入っていなくても、将来的に見据えている会社も含む)になると思いますので、2と3はコンプラ上得策ではないでしょう。
そのため、現実的には1の対応をとることになると思われます。ただ、1をとるとしても、さらに、会社が負担した分を従業員に対して求償するかという問題があります。これについては、税務メリットも込みで従業員採用に信託SOを利用していたと思われるため、従業員の反発を嫌って敢えて求償しないという会社もありそうです。逆に、SO行使者の大半が既に退職しているような会社は、従業員との関係性を考慮する必要がないので、粛々と求償するということになるでしょうか。
なお、1をとる場合、過年度決算修正も検討が必要になり得るように思いますので、監査法人とも相談する必要があるでしょう。
また、もし付与対象者に役員が含まれる場合、報酬決議を取っていないケースもあるかもしれません(時価発行なので有償SOと同じという理解がこれまでなされていたと思われます)。その場合、理論的には会社法361条違反となりますので、株主からの責任追求もあり得るかもしれません。
既に信託から従業員に交付済みだが、従業員においてSO未行使の場合
この場合、未だ税務リスクは顕在化はしていないことになりますが、はたして交付済みのSOをどうするかという問題があります。
なお、下記の通り未交付の場合は税制適格SOへの移行可能性が残されていますが、交付済みの場合はその可能性はないと思います(付与時の割当契約で一定の税制適格要件を満たす必要があるため)。
現在のところ、行使すれば1のとおり給与所得課税となるため、行使を控える従業員が多いものと予想されます。この場合、手元のSOをどうするかということになりますが、大きくは、以下のようなところでしょうか。
SOを放棄してもらう
SOを会社に買い取ってもらう
給与所得課税を受け入れてそのまま維持する
現状では、1のとおり放棄してもらい、税制適格SOとして付与し直すということを検討している会社が多い印象はあります(さすがに放棄してもらって終わりでは従業員が納得しないでしょう)。実際、国税庁から同時に発表された、新株価算定ルールの下では、権利行使価格をかなり抑えられる可能性があります。
なお、役員が付与対象に含まれるのに報酬決議をしていない場合、SO行使済みのケースと同様の問題が起こりうると考えられます。
まだ信託から従業員への交付がなされていない場合
この場合、国税庁の説明によれば、税制適格SOと取り扱うことができないか検討中とのことです。
これについては、従業員への交付時の割当契約で、税制適格SOの要件を網羅すれば、対応できそうにも思いますが、そもそも、管理委託契約を締結してくれる証券会社等がいるのかという疑問があります。ただでさえ、非上場企業の管理委託を引き受けてくれる証券会社は少ない(アイザワ証券は有名ですが)のに、今回のような経緯で引き受けてくれるところはなおさら少ないのではという予感がします。
したがって、このステータスにある会社は、今後の国税庁の発表を待って、いったん交付はステイするのが穏当ではないでしょうか。
以上、信託型SO発行済企業の動き方を考えてみました。まだ流動的なところもあるので、引き続き動向を注視する必要があるとともに、これまでのSO実務とは違うイレギュラーな処理も出てくるので、専門家によく相談する必要があると思われます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
