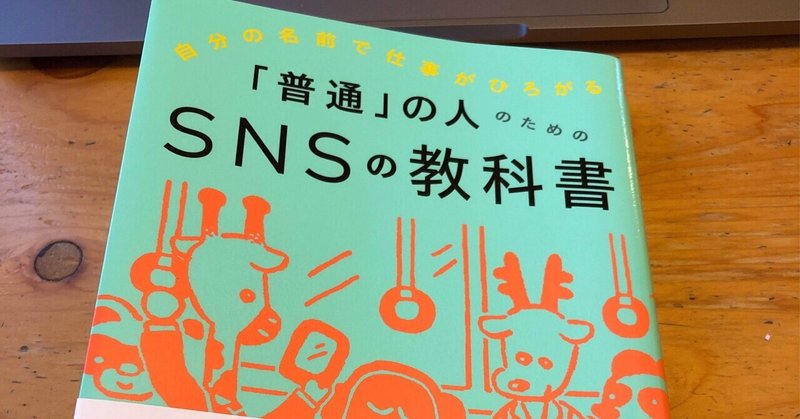
TwitterやブログなどのSNS発信について一歩踏み出せない人にお勧め
「「普通」の人のためのSNSの教科書」は、noteプロデューサーの徳力基彦氏が書いた書籍です。
「バスらなくていいし、ビビらなくていい」という書き出しに惹かれました。TwitterなどのSNS発信を行うときはバズらなくてはならない,、誰も知らない有益な情報を発信しなければならないという先入観が自分の中にありました。しかしこの書籍には、SNS発信は「自分のためのメモ」であると考えることで、発信のハードルを下げることが可能になると書かれています。
さらに「自分のためのメモ」と考えるとTwitterでもツイートしやすいと思いました。SNSをしているとフォロワーを増やさないといけないと考えてしまいがちですし、プレッシャーに思ってしまうことが多いです。しかし「自分のためのメモ」という認識に変えると、自分のために残したい内容をTwitterやブログに蓄積することができるということです。自分のために残すものという認識になれば、SNS発信を積極的にできそうと思えるようになりました。Twitterも義務感をもって発信するのではなく、最低限のルールを決めて、自分のペースで更新していこうと気楽に考えられるようになりました。
「アウトプットが「思考訓練」になる」というところにも納得できました。情報をインプットして記憶にとどめておきたいとき、インプットした情報に対して、どのように考えたか、意見を持ったかをアウトプットしておくことで、必要なときに情報を引き出しやすいと記載されています。確かに、ある考えや情報について、自分はどのような意見を持ったかを考えることで、自分の思考力を鍛えることに繋がりそうだと思いました。普段からこのような習慣を身に付けられると、仕事中や会議中に意見を求められたときでも、すぐに考えや意見を言えるようになれるのではないかと考えます。思考力を鍛えることで、仕事にも良い影響を与えてくれそうです。
私は文章を書くのが得意ではないですが、「自分のメモ」としてこれから読んだ本や興味を持ったニュースなどアウトプットしていこうと思います。書籍を読んだ後は、いつもなら本棚にしまっていました。しかしアウトプットのために、noteを書こう、Twitterでツイートしようと思えたこと、このような考え方に変わっただけでも、この書籍を読んだ価値があったと思いますし、購入して良かったと思います。
そしてSNSを用いることで自分のキャリアや仕事にも役立つということも記載されており、それぞれのライフスタイルに合わせて、考えや意見を発信していけることもメリットですね。発信の仕方に決まりはなく、自分の発信のスタイルを確立していけることもSNS発信の魅力だと言えます。どのように発信するか、どのような表現をするかでそれぞれのスタイルが構築され、その人のキャラクターも作られていくと考えられます。
感染症が流行し、ネット上でのコミュニケーションも増え、ビジネスでもSNSの重要性が高まっていっているのは確かです。集客、営業などSNSを通じて行われていることは珍しくありません。対面での会議、営業が減少し、リモートワークで家にいる時間が増えている人も多いです。このような状況の中でSNSの利用者が増加するのも自然な流れだと考えます。
例えば、Twitter利用者数は、国内だけでおよそ4,500万人が利用しており、LINEの次に利用者が多いSNSという推計です。Twitterは、ブログと比較すると短文のコミュニケーションであり、自分のためのメモとしてアウトプットするには最適だと感じます。
このような状況の中で、SNSが大切なのはわかっているけれども自分には文章力がない、役立つ情報を持っていない、SNSを始めようと思っている人は、ぜひ一度手に取って読んでみてほしい本です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
