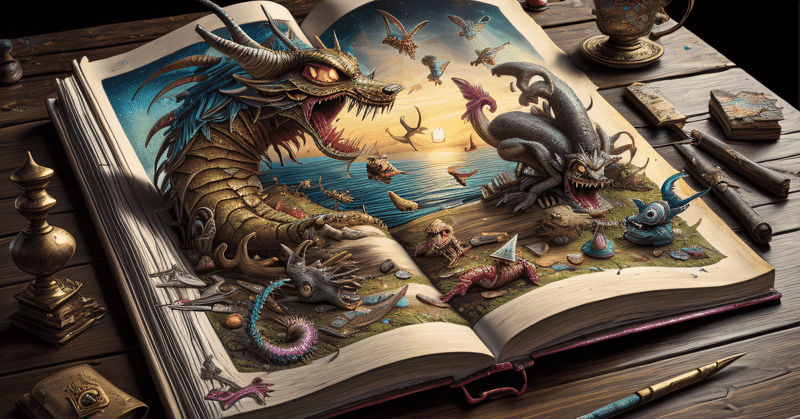
「派手な演出」「見せるデザイン」ってどうなの? WEBサイトの表現と限界
元WEBデザイナーが、WEBデザインの仕事についてつらつらと書いていきます。今回はWEBサイトの本質、WEBサイトの表現と限界についての自論を語ります。職業訓練・スクールでWEBデザインを学んでいる人、就活中の人に読んでいただければ幸いです。
WEBページの本質は「文書」、WEBサイトは「本」
HTMLを正しく理解している人ならわかると思いますが、HTMLの本質は「文書」です。故に「ハイパーテキスト」「リッチテキスト」などとも表現されます。
HTMLの構造化、セマンティックウェブも「文書としての構造を明確化」することで、内容、構造を機械的に正しく理解できるようにすることが目的です。見た目上のことはともかく、技術的、内部構造的視点ではWEBページは「文書」として定義されるべき、という設計思想が見えてきます。
WEBページの本質が「文書」であるなら、それらを複数ページ備えたWEBサイトは「本」「カタログ」「雑誌」等と本質的には同じものであると言えるでしょう。
派手なアニメーション演出って必要?
ユーザーの興味、関心を引くための演出として、派手なアニメーション演出を多用するサイトはFLASH全盛期から存在しました。アニメーション演出のあるサイトは見ていて楽しい、話題性を集める事ができるという理由で実装を希望するお客様も結構います。
一方で演出ばかりが目立って、サイトの内容が記憶に残らない、話題性はあつめるものの、ユーザー、クライアント双方の目的を達成できず、作り手の自己満足で終わってしまうことも多々あります。これはFLASH全盛期の頃から度々議論されてきたことでもあります。
また、演出の度が過ぎて、ユーザーの行動を制限、アニメーション演出を強制的に見せるサイトも存在します。ユーザーの本来の目的にそぐわない、ユーザーのWEBサイト内での自由な行動を阻害するような演出の手法は、はたしてユーザーファーストと言えるでしょうか?
伝わらないは「敗北」
派手な演出ばかりが印象に残って、本当に伝えたい内容が伝わらない、記憶に残らない、ユーザーの自由な行動を阻害する、そのような表現はWEBサイトの目的、情報伝達の方法として成功していると言えるのでしょうか?
ユーザーの目的を無視して、一方的に自分達の主張を押し付ける演出に価値があるとは思えません。ユーザーは何を目的としてWEBサイトを訪れているのかを考えたうえで、適切な表現・演出を考えるのがデザイナーの仕事ではないのでしょうか。
クライアント、ユーザーの目的を達成できず、演出ばかりが目に付くデザインを実装してしまうのは制作者の自己満足、伝わらないデザインは「敗北」であると言えるでしょう。
WEBサイトの表現の限界
インターネット普及から20年以上の歳月が流れ、WEBサイトの表現は年々リッチになってきているように見えますが、紙媒体と比べてみて視覚的な領域で全く異なるメディアに成長したかと言われると、それほど明確な差異は感じられません。
VR、ゲーム等と比べてみると、WEBサイトは平面的で没入感がなく、動画ほどの視覚的訴求力もありません。コンテンツとしてそれらを扱う事はできますが、WEBサイト自体は視覚的な表現力が豊かなメディアとは言えないのではないでしょうか。
WEBサイトの本質が「文書」である限り、どんなに技術を駆使して飾り立てても文書は文書、それは「静」のメディア、「読む」ことが主体のメディアではないかと、筆者は考えます。
「見せるデザイン」をどう解釈・調理する?
「見せるデザイン」「見栄えの良いデザイン」を考えるうえで、情報の取捨選択、掲載情報の厳選は必要な事です。また、一度に過度な情報をユーザーに与えてしまうのは良くない事ともいわれます。
ユーザーへの第一印象を良くする、ユーザーに興味を持ってもらうための入口としては、それらの手法は大事だと思います。しかし、それだけで終わってしまうと、よりよく知りたい、深堀したいというユーザーのニーズには答えられません。
流し見だけでなんとなくわかったつもりになるような「表面的な理解の量産」はいかがなものかと思いますし、それがユーザーのニーズ、クライアントの思惑に本当にマッチしているのかというと、そうではない可能性は十分に考えられます。
また、演出は派手でもコンテンツの薄いWEBサイトはGoogle先生にも評価してもらえません。(SEOを学んだことのある人はわかるはず。)
流し見でなんとなくわかる工夫も大事ですが、「続きを読ませる工夫」「最後まで興味を損なわせない工夫」「より深い理解へと導く工夫」も大事なのではないかと筆者は考えます。
一番強いのは「言葉」の力
どうあがいてもWEBサイトは「文書」の性質をもったままであるとするならば、そこで一番力を発揮するのは「言葉」ということになります。
現段階でもそうですが、検索エンジンはこれからも「言葉」主体であることは変わらないと思います。
かつてWEB上の文章は素人の手による、素人仕事にあふれていましたが、紙媒体の衰退にともない、WEBの領域に雑誌の編集者、ライター等、今まで本を作る事に携わってきた「言葉のプロ」が流れ込んできた結果、文章の内容、表現の仕方、見せ方、興味の持たせ方も高度になってきました。
WEBサイトというメディアが今後いつまで存在し続けるのかはわかりませんが、存在し続ける限り、それは「言葉」主体のメディアであり続けると、筆者は予想します。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
