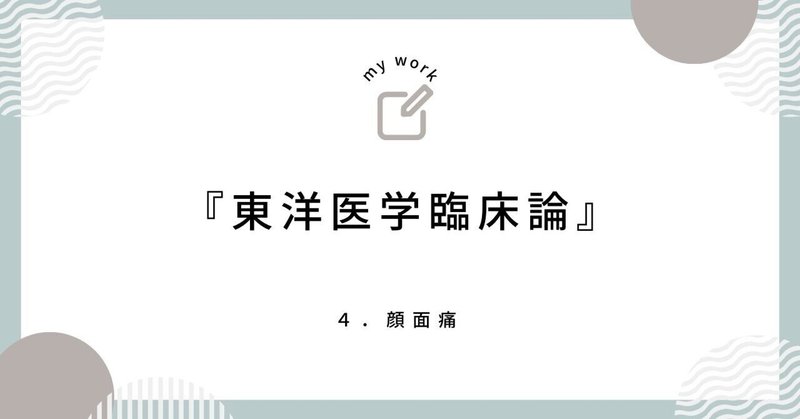
『東洋医学臨床論』4顔面痛
顔面痛は前側は頭痛でもある前頭部痛とも関係しやすいので、頭痛の分類も大きく関係していくものになります。東洋医学での考え方は、その人の証(弁証)が重要になってくるために、頭痛であっても、顔面痛であっても、弁証が同じになったり、違うこともあります。
1.概説
(1)現代医学
顔面痛は前側だと頭部とも関わるために、「国際頭痛分類(第3版)」(ICHD-3)の中の、第2部(二次性頭痛)と第3部(有痛性ニューロパチー、他の顔面痛およびその他の頭痛)に該当することになります。
さらに、この教科書では分類や評価などが詳細に述べられているので、「国際口腔顔面痛分類(第1版)」も紹介されています。

(2)東洋医学
東洋医学では「面痛」「両頷痛」と呼ばれ、前側と関係するので、経絡的には陽明経との関係が密接になります。また、顔面部は四総穴の合谷と関係が深い場所になります。
(3)注意を要するもの
・脳腫瘍(占拠性病変):三叉神経痛、舌咽神経痛
・群発頭痛、特発性片頭痛:周期性
・急性緑内障:霧視(むし、かすみ目)、嘔吐
・副鼻腔炎:鼻汁、顔面痛
・歯科疾患:う歯、歯周病
・ハント症候群:水泡、顔面神経麻痺
2.現代医学

特発性三叉神経痛は三叉神経走行なので、昔から関連する経穴が問われやすい傾向があります。PIFPは神経痛かどうかも怪しいというものなので、国家試験では治療まで含め出題されないのではないでしょうか。
顎関節症は臨床でもみられやすい疾患で、解剖学的に構造、動きを尋ねやすいので、国家試験では出題されやすいので、顔面部の筋肉・神経もしっかいと学習しておきたいところですね。
術後のアイペインは臨床でみることもあるでしょうが、圧倒的にVDT作業(パソコン、スマホなど)からのドライアイとアイペインが多いので、どうやって治療をしていくかをしっかりと考えておきたい疾患です。
※評価
・VAS:長さ10㎝の線で左が痛みなし、右が激痛として評価してもらう
・NRS:痛みがない(0)から最大の痛み(10)の11段階評価
・SF-36:QOL評価
・CMI:心理社会的評価、神経症傾向判定
・ミネソタ多面的人格目録(MMPI):心理社会的評価、人格測定検査
3.東洋医学

・局所治療:疏通経絡、止痛:前頭部(太陽、陽白、攅竹)、上顎部(四白、下関、顴髎)、下顎部(頬車、聴会)
・循経選穴:面口は合谷
・熱は炎上する性質があり、体内で発生した熱は「陽気を主る」心に影響しやすい。
・肝火上炎で発生した熱は炎上する力も強く、めまいや顔面神経麻痺を生じ、中風(ちゅうふう:脳血管障害)を引き起こすことがある。
・肝火上炎で発生した熱は炎上する力も強いためい、「心神」に影響することで、心煩、入眠困難が生じることがある。
・入眠困難は熱が関係していることが多い。
・腎陰虚は心腎不交や肝陽上亢へ移行することがある。
4.生活指導
(1)現代医学
・疼痛誘発因子を避ける
エアコン、扇風機などの風が直接当たらないようにしたり、冷やしたりしないようにする。痛みが生じやすい動作はしないようにする。
・リラックスしストレスを発散させる
ストレスがあると、睡眠中のかみしめにも影響し、顎関節症も発生してしまうので、リラックスが大切になる。
(2)東洋医学
・顔に風が当たらないようにする:風邪が気を付つける。
・身体を冷やしすぎかい:寒邪によって気血の流れが悪くなってしまう
・暴飲暴食、偏食を控える:内湿を生じないようにする
・適度な休養をとる:過労は気血を消耗するので身体を回復させる
最後まで読んで頂きありがとうございました! 頂いたサポートは、有益なコンテンツ作成に役立たせて頂きます。 無料でできる「スキ」や「シェア」でも、私へのサポートにつながります。
