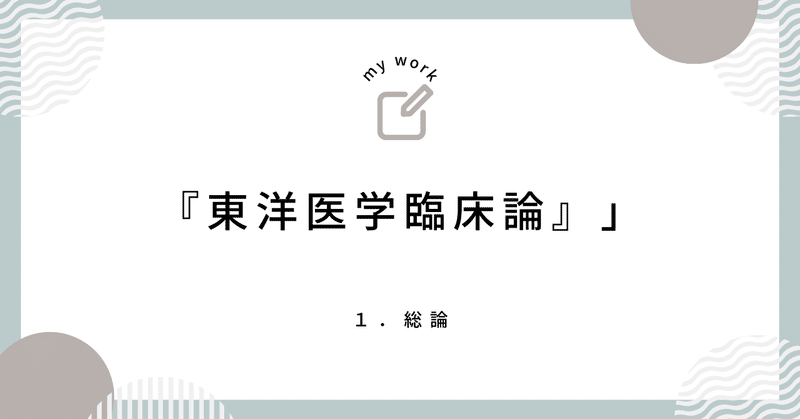
『東洋医学臨床論』1総論
「東洋医学臨床論」の教科書が改訂され、授業でも使われていますが、試験対策にもなる省略版を作ってみたいと思います。どこまでできるかは分かりませんが、試験として気を付けたいところ、臨床的に大切なところをまとめていきたいです。
1.プライマリケア
①セルフ・ケア
②プライマリ・ケア:一次医療、家庭医
③セカンダリ・ケア:二次医療、一般病院
④ターシャリ・ケア:三次医療、高度専門病院
ケアには4種類あります。4種類ということは、国家試験の洗濯しと同じなので注意しないといけないです。調子が悪くなったら、まずはセルフ・ケアですね。
プライマリ・ケアのプライマリは「第一、基礎」という意味があるので、最初のケアです。現代医学では家庭医、かかりつけ医という表現になりますが、鍼灸もプライマリ・ケアに該当します。セカンダリは「2」、ターシャリは「3」という意味です。
2.生命医学倫理の諸原則
①自律性の尊重:患者の意思決定の尊重
②無危害:患者に危害を及ぼすことの回避
③善行:患者に利益をもたらす行為
④公正:利益と負担の公平な配分
なぜこの考え方が、重要なのかといえば、医療において倫理的な問題に直面したときには、この4原則を考えることが大切だということです。
実際には、これだけではなく「臨床倫理の4分割表」(医学的適応、患者の意向、QOL、周囲の状況)の側面から多方面な視点から検討することが大切になります。ということで、問題としては内容量も多いので出題されないのではないでしょうか。
3.診察
①患者との関係
1)コンプライアンス:患者への一方的な指導関係
2)アドヒアランス:患者との相互理解がある関係
これは国家試験で出題されました。一般的な用語と、医学系の用語の違いを攻める問題ですね。一般的には、「コンプライアンス」は法令遵守(ほうれいじゅんしゅ)を意味して、「企業のコンプライアンス」ということで用いられることが多いです。
そのために、「コンプライアンス」という言葉を知っていると、「法令遵守?」となってしまい、混乱します。「コンプライアンス」は、「何かに従うこと」であり、企業であれば「法令」となります。
医療では服薬コンプライアンスという言葉もあり、医師から決められた用法・容量を遵守することになります。
②西洋医学
医療面接、理学検査などを用い、障害を確認して筋肉・神経・血管に対して施術を行っていきます。体表から内臓への刺激は体性-内臓反射となり、内臓の不調が体表に生じるのは内臓-体性反射となります。
③東洋医学
東洋医学では四診の望診(視覚)、聞診(聴覚、嗅覚)、問診(会話)、切診(触覚)を用いていくことが大切で、虚実には補瀉を行い、証には本治、症状には標治が行われます。
東洋医学の特徴は現代医学とは違い、同病異治(どうびょういち)と異病同治(いびょうどうち)になります。同病異治とは、同じ病でも弁証が違ければ治療が異なりますし、異なる病でも弁証が同じであれば治療は同じとなります。
例えば、同病異治は、めまいという病でも精虚や気虚によって生じていれば治療が変わります。異病同治は、腰膝酸軟、耳鳴りと違う症状の人でも、精虚であれば治療は同じになります。
4.治療穴とその応用
ここではいろいろなことが書かれているのですが、かなり内容も細かいので、試験での出題の可能性は非常に低いと思います。
歴史的な内容、経穴の使い方など、興味がある場所ではありますが、国家試験を受ける学生の方はそれほど注意しなくていいのではないでしょうか。
国家試験に出題されるのは、毎年のように出てくるところ、たまに出てくるところがありますが、それだけでもかなりの量になるので、出る可能性が非常に低そうなところ、新しい分野・単語は、捨ててもいいのではないでしょうか。
国家試験はもともと満点を取る試験ではないですし、満点を取ったとしても臨床能力には直結しないですしね。
最後まで読んで頂きありがとうございました! 頂いたサポートは、有益なコンテンツ作成に役立たせて頂きます。 無料でできる「スキ」や「シェア」でも、私へのサポートにつながります。
