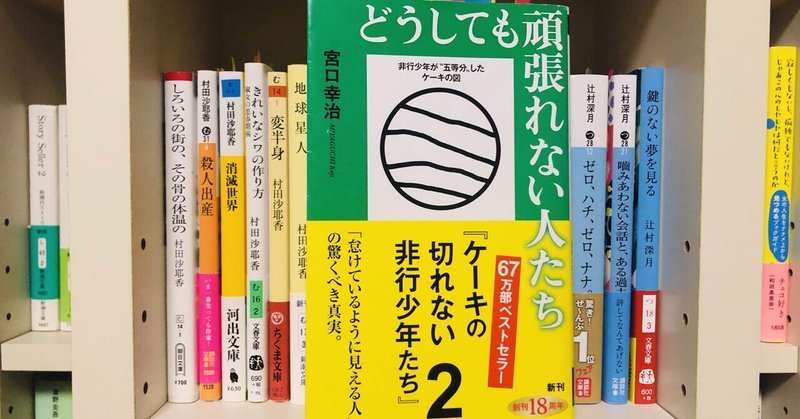
社会が人間に厳しいのか、人間が社会を舐めているのか、それとも社会は「普通」なのか 宮口幸治/どうしても頑張れない人たち
最初に伝えておくと、非常に長いです。内容がとても濃厚だったので、読了からだいぶかかってのレビューとなりました。
わたしが働く学校は、通信制高校に在籍している子たちが学ぶ学校だ。だから、基本的に自由な時間に登校できるし、平日学校に来ず、友達と遊びに行くこともできる。
必要な単位さえ取得できれば、卒業は可能だ。
枠としてはそのくらいなので、サボれる子はいくらでもサボれるし、真面目にやろうとするとキリがない。
自分自身の軸のようなものをしっかり持てていないと、どうしたらいいか分からない子はいるだろう。
一方で、精神疾患を抱えている子や、不登校だった子どもの受け皿になっていることも確かだ。
学習も行事も、全日制高校に通っている、あるいは通ったことのある人からしたら、だいぶ緩い。
わたしたちも、生徒たちには通ってほしいと思うから、どうしても甘やかしてしまう。
卒業までにこの子を、いわゆる「普通の」社会でやっていけるようにしないといけない。そんな風に思うけれど、なかなか生徒に強いことを言えない。
コロナ禍で普及したオンライン授業。生徒の学習機会を継続できるものではあるけれど、サボり癖のある子には、その癖をより助長させてしまった。
小学校や中学校に全く行ってない子もいる。
わたしの中学校生活は、なんかもう戦場そのもので、親に行きたくないと訴えたこともあった。
それでも行き続けたのは、親がそこで悲しい顔をして、休むことを許さなかったからだ。
あの時、誰かがわたしの味方になって、「休んでもいいよ」と言ってくれてたら、全く違う人生を送っていただろう。
あの過酷だった日々、もう二度と戻りたくない日々の中にあったもの。
おそらくそれは「頑張った経験」なんだろう。
一日一日を過ごすだけで、自分をただひたすら守り続けるだけの、ままならない毎日。早く終わってほしいと祈り続ける毎日。それは、あの過酷だった日々を「乗り切った」ことになる。今思うとそれは、紛れもなく「頑張った経験」だ。
それを美談にする気はない。だって中学の頃の思い出なんて、ほとんど覚えてない。その過酷さしか、わたしの中に残ってない。
今も中学校で苦しんでいる子たちはたくさんいるわけで、命がけで学校に行っている子たちだっているはずだ。そんな風に、すでに頑張りすぎてしまった子たちには、休む提案は必要だ。しかし別のフィールドで、学校生活を送る機会はあった方がいい。
本作品に、こんな言葉が出てくる。
P34「『頑張らなくてもいいよ』『もう我慢しなくていいよ』とは十分に我慢して頑張ってきた人たちへの労いの言葉であり、まだ頑張っていない人への言葉かけではありません」。
気を付けないといけないのは、背中を押さないといけない場面で誤って労ってしまうことだ。
生きてるだけで疲れる現代社会、なんでもかんでも「無理をしないで」と言いがちだ。相手のことを深く知らないと、どちらの声かけが目の前の子に相応しいのかが分からない。安易に「無理しなくていいよ」と言い過ぎている、自分の支援方法を、恥じた。
日本の学校教育は叩かれることが多い。
けれど、学校という場所は、社会に出て必要なことをそれなりに学んでいける場でもあるのではないか、ということだ。前述した「別のフィールドで、学校生活を送る機会はあった方がいい」というのは、そういうことだ。
もちろん、社会の全てを学校で学ぶことは難しい。だけど、学校生活についていけてたかどうか、って結構重要な指標なんだなと、そんな風に思う。
そして最近思うのは、社会が厳しすぎるのか、もしくは社会の厳しさは普通で、そこについていけない人たちが甘いのか、ということだ。
大人や社会を完全に舐めてる子たちに「それじゃ社会でやってけないよ」と、よく思う。でも、その子たちはその子たちなりに、きっとその社会の中でそれを学んでく。たぶん、大人がすべきは、その学ぶべきものの先取りではなく、壁にぶつかった時に諦めずに向き合っていく力をつけてあげる、ってことなんだと思う。
でもそれってどうやってやるんだ。社会に出る前、複雑な家庭環境で育っていたり、繊細すぎていたり、怒られることを極端に嫌がったりする子に、社会のハードルは高い。
よく、児童養護施設が例に出される。18歳で自立を求められ、環境面でも精神面でもまだまだ脆弱さが残るその年齢で、さらに複雑な環境を経て施設へ入所した子なら、挫折をする子は多いだろう。挫折経験は、「普通に」社会人になった子にも、大きな壁となる。大学を経て、20歳を過ぎても社会人になるのは大変だ。それを、施設を出たばかりの、たった18歳の子がこなしていかなくてはならない。
今のまま、社会に出たら怒られることだってたくさんある。
怒られた時に、逃げるのではなく、へこんでもいいから、落ち込んでもいいから、向き合ってほしい。
怒られた時、その意味がわからないということもあるかもしれない。それならば、それを相談できる人に相談して、客観的な意見をもらったらいい。だから、信頼できる大人、相談できる大人が傍にいること。結局、「自立支援」というのは、こういうことになるかもしれない。
そして、社会にいる側の大人も、「怒り方」には気を付けないといけない。この「怒り方」を間違う人がいるから、社会のハードルが高くなるのではないか、社会が厳しすぎると感じてしまうのでは、と思うのだ。
P25「支援したくないような人こそ実は支援の対象」
この「支援したくない人」の中には2種類が含まれると思っている。
「支援を求めてくる被支援者」と「支援を求めてこない被支援者」だ。
前者には支援したくなるけれど、後者にはその気持ちは起こらない。
支援する側の、接し方は異なるものになるだろう。
あと、支援を受けている時に申し訳なく思う人やお礼を言ってくる人には支援したいと思うけれど、やってもらって当然!それが仕事ですよね?みたいな尊大な態度を取られると支援したくなくなってしまう。
このような差別化が起こらないように、できるだけ公平に人を支援したいと思う。でも、支援者の状況や能力に差がある分、支援の公平性というのはとても難しいし、人がやる以上、やはり接し方に差が出てしまうのは否めない。
だからどうしても、助けてほしいと言っている子だけ、支援を求めている人にだけ支援をする、ということが起こる。
人に敬意を払い、「この人になら相談したい」と思ってくれている人。そういう人には、こちらも支援したくなる。
でもそれって結局、支援する側の自己満足だ。
その関係性なら、支援者側の言葉はどんな言葉だって響くだろう。
問題はそうじゃない関係性の時だ。
正論や常識が理解できない、人の気持ちを理解できない、そもそも人を信用していない、甘やかされ過ぎて人に何かをやってもらうのが当然だと思っている、等々。
最終的には結局それに向き合っていくって事なんだろうけど、わたしにはその勇気や力があるんだろうか。
そのような態度を取ってくる生徒に対して、怒らずに、しかし言うべきことを言うことができるだろうか。会社とお客様という枠組みと関係性の中で。
「向き合う」という言葉の中に含まれる、日常的なコミユニケーションとは一体どんなものか。その時に発された言葉への切り返しは、一体何が正しいのか。
学校へ行く意味。
来てくれたら出来ることはあるけど、来れないならできない。
でもそれでは不登校を否定することにならないか?結局、来れない=怠けてる、と思っていないか?
朝井リョウの「正欲」で思ったことでもあるけれど、結局わたしの思考は、マイノリティのふりをしたマジョリティなのだ。多くの人が頑張れるわけだから、それをしないのは怠けてる、と決めつけてるマジョリティ。
でも高校を卒業したいのであれば、やっぱり最低限のことはやるべきなんじゃないか?
でもこれは「頑張り」の押し付けであってもしかしたら「頑張れない」のかもしれない。
だとしたらその根っこはなんだ。
なぜ頑張れないのか。どうすればやれるのか。
わからない。難しい。
一体何が正しい支援なのか。
P3「頑張ったら支援します」
という考え方は、正論ではあるのだけれど、「頑張れない」を排除していることになる。でも、なぜ「頑張れない」のかを探るのは難しい。だから、「怠けてる」のか「頑張れない」のかを探るため、やはり「ここまで頑張ったら支援します」という過程はついてくることになる。結果、頑張れなかった人は、振り落とされてしまう。社会と密接に繋がった教育業界が頑張るを強要して、そこで疲れた人達が、福祉を頼ってくる。そこで癒された人たちが、再び「普通の」社会に戻ってゆく。
おそらく、現代日本では、このループが起きている。
これで、いいのか?社会ってそういうもん、で済まされるのか?
長くなりました。最後まで読んで下さり、ありがとうございます。
対人援助職の人はもちろん、すべての人に読んでもらいたい一冊。
#読書の秋2021 #読書感想文 #読書 #本 #感想 #書評 #読書日記 #小説 #レビュー #おすすめ本 #私の仕事 #子ども #子供 #生きる #学校 #教育 #学校教育 #高校 #高校生 #通信制高校 #人間 #普通 #社会 #努力 #不登校
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
