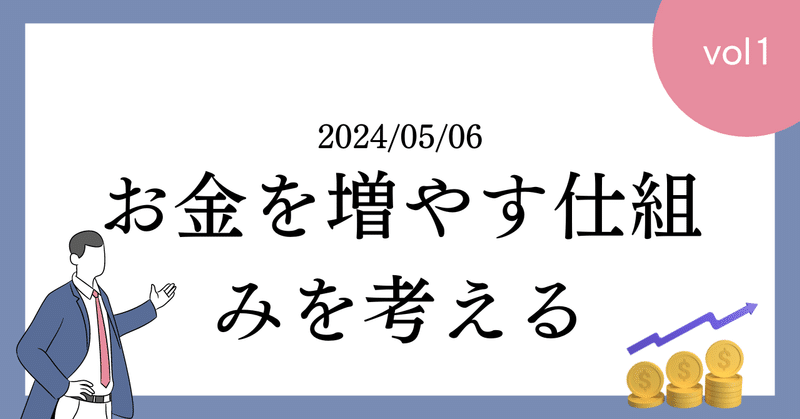
お金を増やす仕組みを考える①
1 お金を増やすためには
お金を増やすためにはどうしたら良いでしょうか?
単純にお金を稼ぐだけであれば、単発でお金を稼ぐ方法はありますが、継続的にお金を増やすためには、お金を増やす仕組みを作る必要があります。
1.1 お金を増やす仕組み サラリーマンのケース
お金を増やす仕組みは、わかりやすいのはサラリーマンでしょう。サラリーマンで言えば、会社に就職すれば、自分の時間と引き換えにお金を給与として得る事が出来ます。しかし、自分の持っている時間は有限なので、期待以上の収入を増やす事は出来ません。その代わり、首にならない限りは安定した収入を得る事が出来ます。
1.2 自分でお金を増やす仕組みを作る
では自分で、お金を増やす仕組みを作るにはどうしたら良いでしょうか?
サラリーマンの場合は、お金を増やす仕組みは会社なので、会社の経営者がそれを考えていることになりますが、それを自分でやろうとする場合は、そこを自分で考えなければなりません。
考えてみたら、お金の増やし方については、学校の勉強では教えてくれません。経済学部に行けばお金の増やし方を教えてくれるのかと言えば、そうではありません。経済学では、経済原理は教えてくれますが、稼ぎ方は教えてくれません。
幾ら成績が良くても、お金の稼ぐのが上手とは限らないのです。お金を稼ぐのは、センスも大事かもしれませんが、経験がものをいうものだと思います。そのためにはチャレンジして、失敗も含めて経験を積むことが大事だと言えます。
しかし、闇雲に突っ込んでも、成功する訳ではありません。しっかりと戦略を作る必要があります。ここではお金の増やし方、稼ぎ方について自分なりの仮説を考えてみたいと思います。
2 お金の稼ぎ方のパターン
お金の稼ぎ方はいくつかパターンがあります。これらのパターンを列挙しながら考察してみたいと思います。
(1)ジョブ型
ジョブ型の仕事で、誰かからの頼まれた仕事を熟す事で得られる報酬型のお金の稼ぎ方があります。
(2)プロダクト型
プロダクト型の仕事であれば、何かを生産して、それを売る事で、対価を得る稼ぎ方もあります。
(3)サービス型
サービス型の仕事は、何かのサービスの対価として、フィーを得る稼ぎ方もあります。ジョブ型に似ているかもしれませんが、ジョブ型は言われたことを熟す仕事で、言わば請負契約で、サービス型は、委託契約で、ある求められる性能水準のものを提供するというイメージのことを言います。
3 産業別での稼ぎ方の特徴
1次産業、2次産業、3次産業での稼ぎ方の特徴について、解説してみたいと思います。
(1)1次産業
1次産業のように、自然を相手にする場合は、インプットに対するアウトプットの不確実性が大きく、天候や自然環境の変化による変動(ボラティリティ)が大きいビジネスだと言えます。
これまでの1次産業は、大量生産、大量消費型の規格商品を大量に作り、安く提供するという思想のもとに、生産者を疲弊させてしまったがために、1次産業は儲からない、3Kと嫌われて、結果的に担い手不足となり、日本の1次産業の担い手は壊滅的な状況になっているように思います。
昨今では、そこに目をつけて、小規模多品種のニッチなマーケットを狙い、高付加価値高単価の商品の提供をしている生産者さんの成功事例をよく聞くようになりました。
(2)2次産業
2次産業の場合は、原材料と製品の需給の関係での変動リスクがあります。原材料が高騰しているのに、製品の需要が上がらず、価格に転嫁できない場合は、多くの在庫を抱えてしまう事になります。
特に、原料を海外の輸入に頼る場合は、現在の円安の状況においてはかなり苦戦を強いられる格好になります。
一方で、海外に輸出するケースではその逆も言えます。かつて日本は1ドル360円の固定だった時代は、輸出産業で経済成長をしていたことを考えると、円安時代こそ輸出産業がチャンスと言えるのかもしれません。
(3)3次産業
3次産業は、提供するものがサービスなので、人件費がメインであるため、原材料によるコスト比率が低いので、需要の高いサービスを提供できれば、利益率の良いビジネスが出来ると言えます。
近年は、産業の付加価値はほとんどが3次産業が生み出しているといっても過言ではありません。お金を稼ぐ事は、付加価値の総量と言っても過言ではありませんので、1次産業、2次産業のように、製品として既製品となっているものでは、付加価値を高めることは至難の業であります。3次産業においては、顧客のニーズを満たせれば、それがお金になるわけですから、ここの分野でこそ、付加価値をつける可能性があると言えます。
一方で、生活必需品以外での商品については、消費者のニーズを捉えているかが重要であり、そのあたりのマーケティング力が試される分野とも言えます。
(4)6次産業
1次、2次、3次産業を組み合わせたものを6次産業化と言います。個人的には、この6次産業化にはとても可能性を感じています。自分自身も6次産業化に寄与できるようなビジネス、自分自身での6次産業を目指していきたいと考えています。
4 考察
ここまでの考察を見ると、6次産業化を、1次産業側から幾ら見ても、ビジネス的には軌道に乗せていくのは非常に難しいと言えるような気がします。農水省やJAが推奨する6次産業は、地元の名士的な老舗の企業が成功した事例を取り上げているので、もともと資金力のあった会社が、2次創業を狙って投資したケースがほとんどであります。
こう考えると、1次産業スタートの6次産業とは、1次産業の成功者の2次創業であり、企業としての拡大路線に他なりません。
スタートアップとして、最初から6次産業化を目指すのはハードルが高いと言えるでしょうか?
もう少し、ステップを分けて、段階を踏んでいく必要があるように思います。次からは、もう少しそのあたりを深掘りしていきたいと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
