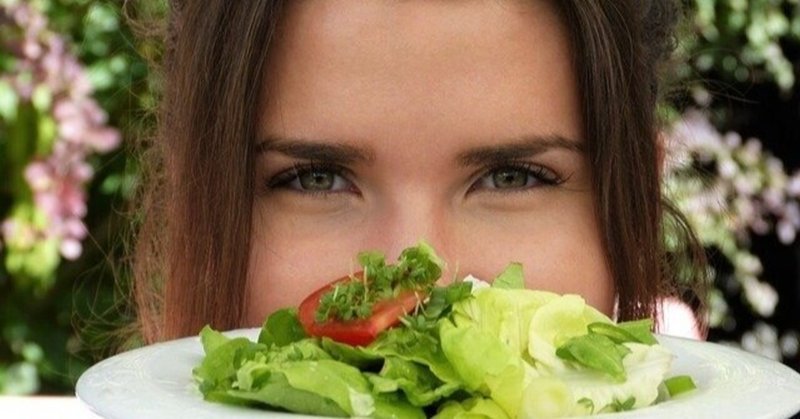
「食料システムサミット」が示すこと
column vol.440
SDGsを達成するために。
「食料システム」を持続可能なものに変えなければならないという問題意識のもと、国連が主催する初の「食料システムサミット」が9月23、24日、オンラインにて開催。
150カ国超が参加し、日本からは菅義偉首相がビデオメッセージを寄せました。
〈HUFFPOST / 2021年9月24日〉
「食料システム」とは、食料の生産から加工、輸送、消費に関わる一連の活動を指すのですが、現状のままでは、世界の食料需給バランスが維持できず、環境破壊も進んでいくという厳しい状況…。
強い危機感を背景に、ついに国連が動いたというわけです。
まず、どれぐらいの危機なのかを一旦把握したいと思います。
人口は1.3倍、食料需要は1.7倍に
農林水産省の資料によると、世界の人口は2050年には2010年比で1.3倍に増える一方、食料需要は1.7倍の約58億トンにまで増えることが予測されています。
限られた農地で、人口の増加率以上に食料の生産性を上げなければならない…。
それなのに…、「フード(食品)ロス」は世界で年間13億トン、日本では年間600万トンにも上ります…(汗)
また、環境面では、農地確保のための森林伐採の他、牛のげっぷなど家畜から排出される温室効果ガスが問題視されています。
国連食糧農業機関(FAO)によると、世界の温室効果ガスの排出量のうち、家畜(飼料含む)による排出が15%を占め、そのうち65%が牛肉と牛乳によるものとのこと。
いずれも、概要としては皆さんご存知の話だとは思いますが、数字で確認するとやはりズシンと胸にくるものがありますね…。
ちなみに、このような食料システムに対して、菅首相が語ったのは以下の3点となります。
①生産性の向上と持続可能性の両立
②自由で公正な貿易の維持・強化
③各国・地域の気候風土、食文化を踏まえたアプローチ
例えば、①についてはイノベーションやデジタル化の推進、科学技術の活用がカギになると主張。
農水省が5月に策定した「みどりの食料システム戦略」を通じて、農林水産業の脱炭素化など、「環境負荷の少ない持続可能な食料システムの構築を進めていく」と語っております。
食品ロス改善に向けたコンビニの取り組み
そんな中、民間企業もがんばっています。
「食品ロス」と「温室効果ガス排出」への改善取り組みとして、私が気になったトピックスをご紹介したいと思います。
まずは、「食品ロス」から。
コンビニ大手のローソンが弁当などの売れ残りを減らすため、AIで商品の売れ行きを店舗ごとに予測して値引きに繋げる新しいシステムを開発。実証実験を始めています。
〈NHK / 2021年6月21日〉
さらに、消費期限が迫った商品の値引き情報をスマートフォンでお客さまに通知するサービスも実用化を目指しているとのこと。
ローソンが2019年度に東京都内の500店舗で行った調査では、1店舗当たりの売れ残りによる廃棄量は、年間で2トンを超えると推計されています。
食品を廃棄する費用の大半は店側が支払う仕組みとなっているため、食品ロス改善はオーナーにとってもありがたいこと。
一石二鳥の取り組みに、小売業のマーケティングに従事する人間としては、非常に感銘を受けております。
「ビヨンドミート」の新風
続いて「温室効果ガス」について。
家畜から排出される温室効果ガスを改善するために「ビヨンドミート(代替肉)」の開発が盛んになってきていますが、この分野で最近精力的に活動しているなぁと思う企業が「グリーンカルチャー」です。
〈PRTIMES / 2021年9月27日〉
フードテックベンチャーなのですが、植物肉「Green Meat(TM)️ シリーズ」を使用した「Green 植物肉丼の具」の開発を完了し、一般向けおよび飲食店向けに発売することを先月下旬に発表したことがニュースになっていました。
ちなみに、「Green Meat(TM)️ シリーズ」といえば、最近では早稲田大学の学生を中心に構成される学生団体「Planmeet」が運営するキッチンカー事業とコラボ。
環境意識の高いZ世代の若者と一緒に新しい取り組みを行う姿勢にとても注目していました。
世間からの期待も高く、今年7月に、亀田製菓株式会社、オイシックス・ラ・大地株式会社ら計4社から総額2.5億円の資金調達を実施。
過去10年間で30万件以上の出荷実績に基づく最終消費者の嗜好に関するデータ、並びに独自の開発データベースを活用した製品開発が特徴です。
他にもさまざまなトピックスがあるのですが、続きはまたの機会に。
取り急ぎ、この秋、国連が初めて「食料システムサミット」を開催したということが個人的には1つの大きなポイントだと思いましたので、本日はこのテーマでお話しさせていただきました。
今後も食糧問題は注視していきたいと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
