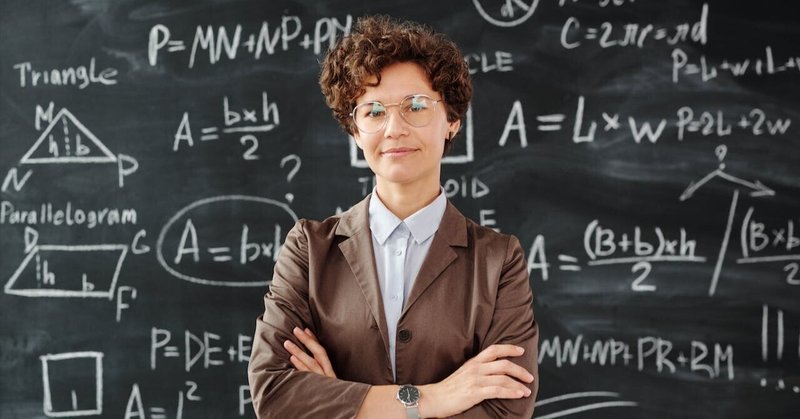
「成果」を上げる「数学」の力
column vol.1177
本日は当社の年内最終出勤日。
明日からは冬休みに入ります。
年末年始はガッツリ読書を楽しみたいと考えているのですが、学びのテーマの1つに「数学」があります。
48歳の私が今さら数学?
と、私を知る関係者だったら思うかもしれませんが、最近「数学の力でビジネスで成果を出す」といった関係の本に刺激を受けているのです。
そこで、冬休みの読書にオススメの本と併せながら、本日は数学をテーマにお話しさせていただきます。
圧倒的な利益を生み出す「数値」の力
「成果を出す」ということでいえば今、多くの方々から注目されている企業の1つが「キーエンス」でしょう。
営業利益率は脅威の55%超、社員の平均年間給与は2000万円超。
「利益率の高さ」と「給与の高さ」は圧巻です…(汗)
〈現代ビジネス / 2023年12月25日〉
…ちなみに、キーエンスの2022年度の「従業員一人当たりの売上高」は約8700万円で、「一人当たりの営業利益」は4821万円。
今、「日本企業全体の一人当たりの営業利益」の中央値は約253万円ですので、同社の社員は「日本の平均社員の約20倍の利益」を叩き出しているというわけです…(驚)
このキーエンスの成功の秘訣が「徹底した数値化」にあります。
そのノウハウをまとめたのが、元同社社員の岩田圭弘さんが執筆した『数値化の魔力』です。
キーエンスの社員は「自らの仕事」を数値化し、日々管理しています。
しかも、「売上」や「利益」といった「最終的な目標」の数値だけでなく
●電話の回数
●アポの件数
●面談の件数
●商談化の数
など、あらゆる「プロセス(行動)」をデイリーで数値化し、管理しているのです。
とはいえ、使うのは「四則演算」。
つまりは「たし算」「ひき算」「かけ算」「わり算」のみですから、誰もがすぐに始められます。
例えば、こんな感じです。
・営業……先月、受注目標を達成できなかったのは、『電話の件数』が10件足りなかったからだ
・人事……「応募数」が20件足りていないから、採用人数も目標の数字に足りていない。応募数の改善が急務だ
「目標」だけでなく、そこに至るまでの「プロセス(行動)」を数値化することで、「自分の不足点」が客観的に可視化できる。
「不足点」とは、成長の源。
「自分に足りない点」を改善するからこそ、人は成長できるというわけです。
こうした「不足点」を日々改善し、「素早い行動変容」をするからこそ、圧倒的なスピードで成長することができる。
普通は成長に10年かかるところ、同社の営業さんは1年で実力がつくのはそのためなのです。
また、数値化を自主的に行うことで、社員の自律心を育むことも大きいでしょう。
「圧倒的な数値化」をAIに頼る
…とはいえ、「数値化なんて…、本を読んでも一人でなんてできない…」と思う方もいらっしゃるでしょう。
そこで、キーエンス絡みでもう1つオススメしたいのが、『「キーエンス思考」×ChatGPT時代の付加価値仕事術』という本です。
こちらは、ChatGPTを使って今まで曖昧だったものを数値化するノウハウを学ぶことができます。
著者は、これまた元キーエンスの社員でカクシンCEOの田尻望さんです。
〈PRESIDENT Online / 2023年11月29日〉
例えば、顧客満足度調査を行ったとします。
「数値化する」ということでいえば、NPS(ネット・プロモーター・スコア)、CES(カスタマー・エフォート・スコア)などが有名です。
しかし、数値化を目的としていない感想だけのアンケートもあるでしょう。
例えば、ビールについて、このような回答があったとします。
パッケージデザインがとてもおしゃれで、友人たちとの飲み会の時に持ってくると注目されそう。
こうした感想は数値で測ることが難しいはずです…
しかし、以下のプロセスを行えば、chatGPTを通して数値化することが可能になります。
(1)「顧客の感想を数値化できる項目を10個ほど出してください」と聞く
…(「感動度:10段階評価」などサンプルを与えると、適切な回答をする可能性を高められる)
(2)感想文を読み込ませ、数値化させる。
その例として、田尻さんがビールの新商品に対する感想文をChatGPTに分析してもらい、数値化しています。

どうでしょう?
単なる感想も数値化できていますね。
人間にはバイアスがあるので、言葉だけだと、それぞれの人が都合の良いように解釈してしまう傾向にあります…
一方、数値化することにより、調査結果(評価の現在地)を社内でズレなく明確に共有することができる。
これも数値化の力によるものですね。
数字は物事の「本質」を明らかにする
数字があることで個々人の受け止め方の相違を無くす。
こうした考え方が学べる一冊が、データサイエンティストとして活躍する冨島佑允さんの著書『東大・京大生が基礎として学ぶ 世界を変えたすごい数式』です。
冨島さんは “数式読解力” という造語を使っているのですが、これは数式を通じて物事の本質を見抜く力のことを指します。
〈AERA.dot / 2023年12月5日〉
例えば、ノーベル経済学賞を受賞したプリンストン大学のアンガス・ディートン教授が、年収と幸福度の関係を調べたことによって世界が変わりました。
年収が800万円を超えると、そこからは年収が上がっても幸福度はあまり増えない。
こうした隠れた法則を見つけたことで、お金さえあれば幸せになれるという世の中の常識が変わっていったわけです。
このように、見たり聞いたりできるものの裏にある法則を発見できれば、そこから思いもよらぬ発想が生まれ、新しい何かが創造されていく。
そうした考えについて、冨島さんはこのように仰っています。
欧米企業の特にリーダー層は、たとえ自身は数学が苦手であっても、現場の人たちに数学的な説明を求め、数式から理解しようとする姿勢があります。一方、日本では、文系と理系のようにはっきり住み分けてしまいがちで、自分の担当ビジネスに人工知能・機械学習・データサイエンスがどう活かせるか発想するための理系的リテラシーを持つ文系リーダー層が少ないという課題があります。これでは、新しいビジネスチャンスを逃してしまいます。
考えてみれば、chatGPTを介してプログラミングもできる時代。
数学の知識がなくても、数式や数値化はAIがサポートしてくれます。
私個人としては、徐々に数学的リテラシーとモチベーションが高まってきたので、来年はこれを経営に活かしていきたいと考えております。
今回は数学に限定した話をいたしましたが、皆さんも、ぜひぜひ冬休みを活用して、1UPしていただければ幸いです。
本日も最後まで読んでいただき、誠にありがとうございました😊
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
