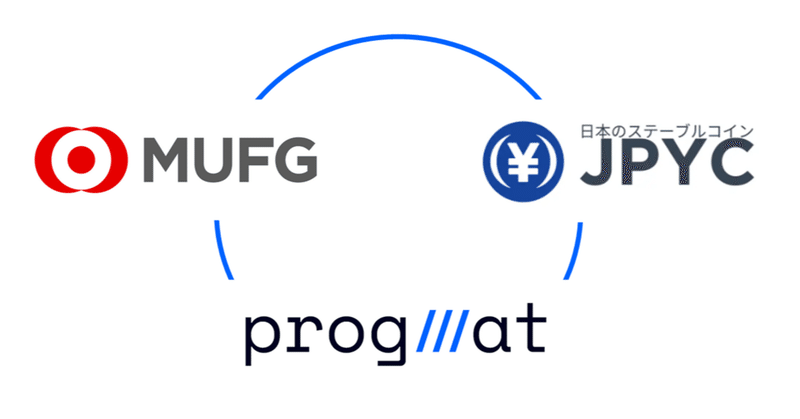
【速攻解説】ProgmatとJPYCが組むって、どゆこと?USDC等を含めて一覧化します
こんにちは、プログラマブルな信頼を共創したい、Progmat(プログマ)の齊藤です。
2023年11月28日に、プレスリリースを発信しました。
タイトルは、「三菱UFJ信託銀行とProgmatおよびJPYCの協業による、「JPYC(信託型)」および国内外ステーブルコイン間の交換に関する共同検討開始について」です。
昨日の日経電子版、今朝の日経朝刊でも報道されていた取り組みです。
プレスリリース等を実施したイベント週では、
情報解禁後いち早く正確に、背景と内容についてこちらのnoteで解説していました。
ということで、第10回目の本記事のテーマは、
「【速攻解説】ProgmatとJPYCが組むって、どゆこと?USDC等を含めて一覧化します」です。
結論、各SCをまとめるとこんな感じ
結論、これです☟

それでは、上記の全体像を頭の片隅におきつつ、各論をご説明していきます。
Progmat×JPYC協業は「2つの要素」で構成されています
今回発表した協業スキームの全体像はこちらです☟

上記スキーム全体像には、2つの要素が組み合わされています。
信託型SCスキームを用いた「JPYC」というブランド名のコインを新たに発行する(「JPYC(信託型)」)
仲介者としての「JPYC社」が、「JPYC」、その他各種「国産SC」、USDC等の「海外SC」を取り扱い、”SC⇔法定通貨”や”SC⇔他SC”間の交換チャネルとして機能する
上記「JPYC(信託型)」をはじめ、これまで発表してきた各種SCを発行/管理するために、発行体(信託銀行等)や、当該SCを取り扱う仲介者が利用する共通基盤が「Progmat Coin」システムです。(上記図表において、信託銀行及び仲介者の下に位置しています)
「Progmat Coin」システム自体は独自ブロックチェーンではなく、Ethereum等各種ブロックチェーンを利用するアプリケーション(Dapps+オフチェーンDB等)です。(上記図表において、「各利用エンティティ」と「パーミッションレスブロックチェーン(BC)」の間に位置しています)
「Progmat Coin」システムを介して発行した各種SCと、USDC等の海外SCとは、同じブロックチェーン(例えばEthereum)で繋がったトークン同士であり、スマートコントラクト等の仕様も基本的に合わせているため、相互移転/交換等の挙動を円滑に行うことが可能となります。(上記図表において、最下層の「パーミッションレスBC」で繋がっています)
このような、そもそも「Progmat Coin」システムがどこを担っているか?等の前提情報は、以下の記事にまとめていますので適宜ご参照ください。
それでは、構成要素を1つずつ解説していきます。
なぜ「JPYC(信託型)」?
まずは発行サイドの解説からです。
まず、既に発行されている現状の「JPYC」は、”SC=電子決済手段”を定義づけた資金決済法の改正前から「日本円ステーブルコイン」として発行していた、業界のパイオニアプロジェクトです。
当該「JPYC」は、資金決済法上の前払式支払手段として発行されています。前払式支払手段は、原則として金銭による払い戻しができません。
改正資金決済法に則り、電子決済手段として新たに発行する「JPYC」は、金銭による払い戻しが可能になります。

電子決済手段の類型としては、「銀行預金型」「資金移動型」「信託型」の3つの類型がありますが、最も制約のない「信託型」での発行を目指すのが「JPYC(信託型)」です。

つまり「JPYC(信託型)」は以下の特徴を備えることができます。
金銭による払い戻し(直接的な換金)が可能になる
送金金額に制約がない(100万円以上の送金も可能になる)
各種デジタルマネーとの比較や、SC=電子決済手段内の類型比較の勘所は、以下の過去記事も適宜ご参照ください。
「JPYC(信託型)」はどんな座組みで実現できる?
「JPYC(信託型)」の発行理由がクリアになったところで、実現方法の解説です。
「信託型SC」スキームは、以下のとおりでした。

【信託委託者】=●●コインを発行するための信託(以下、SC発行信託)を設定する、企画者/ビジネスオーナーです。
【信託受託者】=委託者の指図に基づき、裁量なくSC発行信託の管理を行う、法的には信託型SC発行体としての業規制を受ける主体です。
【預金取扱者】=SC発行信託でSCの裏付けとなる金銭について、預金として受け入れ運用する金融機関で、信託委託者の裁量で決定します。(必ずしも信託受託者自身とは限りません)
【仲介者】=信託委託者又は受託者からSCを調達し、SC利用希望者に対して各種交換機能(SC⇔法定通貨、SC⇔他SC、SC⇔暗号資産、等々)を提供するチャネルです。
【SC利用者】=SC発行信託の受益者(信託受益権保有者)、という位置づけになります。
「JPYC(信託型)」においては、以下のとおりです。
【信託委託者】=JPYC社
【信託受託者】=三菱UFJ信託銀行
【裏付資産】=預金(円建て)
【信託受益権銘柄名】=SCブランド名=JPYC
なお、冒頭の「結論」の一覧チャートでも明らかなとおり、【信託委託者】や【信託受益権銘柄名】はプロジェクトによって様々ですが、他の中核となる部分はプロジェクト問わず同じで、標準化/横展開可能なビジネスモデルとなっています。
ここで、各種SCを取り扱い、SC利用者との直接的な接点となる【仲介者】が登場します。
ということで、ここから構成要素の2つ目、仲介者サイドの解説です。
なぜ「JPYC社(as 仲介者)」?
先ほどの協業スキーム全体図を再掲しましょう。

「JPYC社(as 仲介者)」の立場を中心に、上記図表からポイントを抽出します。
自分たちのプロジェクトである「JPYC(信託型)」のほかに、「Progmat Coin」システムを介して発行される様々な国産SCを取り扱う
Circle等に代表される海外籍企業が発行する、USDC等に代表される海外SC(外国電子決済手段)を取り扱う
様々な国産SCや海外SCの交換機能を提供するチャネルとして、「電子決済手段等取引業者」のライセンスを取得することを前提としている
JPYC社(as 仲介者)の利用者は、自己管理ウォレット(セルフカストディウォレット/アンホステッドウォレット)での授受を前提としている
つまり、「JPYC(信託型)」という特定のSCを発行する立場のみならず、電子決済手段等取引業者=SC交換業者として、様々なSC交換のハブとなることを志向されている、といえます。
その中でも特筆すべきはUSDC等の海外SCの取扱いです。
この取り組みがうまく機能すると、日本法に従う国内居住者の皆さんも、「国産の円建て/外貨建てSC」のみならず、海外産の「ネイティブ海外SC」との相互交換が容易になります。
ということで、今度はCircle等の海外籍発行者サイドの立場に立って解説を試みます。
海外籍発行者のもつビジネス上の選択肢
Circle等の海外籍発行者からすると、ビジネスフィールドは日本市場だけではありません。むしろ、日本は”アジアのローカルマーケットの1つ”くらいでしょう、正直なところ。
そんな”ローカルマーケット”の”ローカルルール”を調査すると、既に発行済の「ネイティブ海外SC」を直接持ち込むシナリオでは、以下の事項が判明します。
方法①:そのまま持ち込む代わりに、仲介者が犠牲になる(さらに、利用シーンも選ぶ)

「ネイティブ海外SC」を取り扱ってくれる”ローカルパートナー”である【仲介者】に、顧客預りSCと同額の法定通貨を”買取準備金”として自己勘定から拠出し信託義務が課されるという、非常に重い資金保全の負担を飲んでもらう必要がある
そのような”ローカルパートナー”がいるとして、海外SCには100万円の送金上限額制約がつくため、個人/小口の取引利用に限られてしまう
ということで、”ローカルビジネス”として規模を追求するうえでは、なかなか足枷/制約がありそうです。
ただ、上記制約を受けるのはあくまで”ローカルパートナー”であって、海外籍発行者自身ではない、ともいえます。
海外籍発行者からすれば、”ローカル利用者”と「ネイティブ海外SC」との接点は多いに越したことはなく、少なくとも海外籍発行者の立場からは”ローカルパートナー”=【仲介者】を特定先に絞る積極的な理由はなさそうです。
(逆に絞って排他的にすることで、【仲介者】の汗かき分を別途バーター取引で相殺する、等の戦略的な組み方も考えられそうですが、全て齊藤の妄想です)
【仲介者】を複数確保するうえで、大きな枷である「顧客預りSCの買取資金の信託義務」を回避する方法はないのでしょうか?
それが今回「JPYC社(as 仲介者)」と発表している、「SC預りの発生しない仲介モデル」です。
方法②:SC預りの発生しない仲介モデル
仲介者が自己勘定で資金を確保する対象の残高は、「顧客から預かっている」コイン分のみです。
ということは、顧客から1円も預らなければ(”宵越しの顧客コインをもたない”)、資金を確保する必要もない、という整理も可能かもしれません。
※為念、齊藤は弁護士ではないので、法律事務所のプロフェッショナルの先生方にご相談ください
これはつまり、
仲介者として「交換機能」だけ提供することに徹し、「カストディアルウォレット(預り)」としての機能は提供しない、というモデルといえます。
このモデルにおける前提は、
各利用者は仲介者から購入した「ネイティブ海外SC」を、購入後そのまま利用者自身のウォレット(アンホステッドウォレット)で受領して管理する、ということを意味します。
方法①でも触れた「送金上限額100万円」の制限自体はそのままのため、
この方法の場合の結論として、
利用者は「アンホステッドウォレット」を使いこなせる人に限定される
利用シーンはほぼ「個人/小口取引」に限定される
といえます。
逆に言えば、
だれでも使える素敵なウォレットが存在し、個人間の少額取引で利用する分には、この方法でも必要十分ということもできます。
方法③:信託スキームを用いて「海外ブランドコイン」をつくる
ということで上記方法①②とは別の手段があるのですが、今回の発表の本筋から外れますので、気になる方は過去記事をご参照ください。
(Binance×Progmatの協業パターンはこちら)

ということで、今回のUSDCは?
「ネイティブ海外SC」であるUSDCについて、まとめると以下のようなことがいえそうですが、齊藤の私見を含みますのでご留意ください。
今回情報公開された”ローカルパートナー”=【仲介者】の一角が、「SBI VC トレード社」と「JPYC社」
いずれにせよ「送金上限額100万円」の制約がつくため、個人/小口の取引利用に限られそう
少なくとも「JPYC社」チャネル経由での取得の場合、アンホステッドウォレットを使いこなす必要がある
ということで、少なくとも初期的な想定ユーザーは、「SBI VC トレード社」又は「JPYC社」と取引のある、クリプト領域になじみのある個人中心になりそう
最後に、もう一度「一覧表」を振り返る

以上を踏まえたうえで再度「一覧表」を見返すと、様々な発見がないでしょうか?
端的には、一覧の上から順に次のような点がポイントといえます。
「銀行協業コイン」も「Binance協業コイン」も「XJPY/XUSD」も「JPYC」も、【発行企画=信託委託者】が違うだけで、後は「信託型SCスキーム」ということでほぼ同じ
”外貨建てSC”は必ずしも「USDC」に限らず、「JPYC」以外の「国産SC」は全て「円建て」と「外貨建て」をどちらも発行する
「USDC」のみ、「送金上限100万円」と「資金保全負担(又は回避するためのウォレット制約)」を前提とする必要がある
SCブランド⇔【仲介者】は必ずしも排他的な関係ではないため、様々な組み合わせがあり得る(少なくとも「JPYC社」は複数の国内外SCを取り扱う計画)
複数のSC銘柄の発行が想定されているが、少なくとも短期的な利用者や利用シーンは【信託委託者】又は【仲介者】のネームにより一定の棲み分けがなされ、”乱立/利便性欠如”といった●●Payのような状況にはなりづらい
最後の「”乱立/利便性欠如”といった●●Payのような状況」にしない!というのは、Progmat/齊藤として強く意識しています。
ビジネス的には「各SCプロジェクトの座組み/ゾーニング」を戦略的意図をもって組み立てているところです。
ただ、より重要なのは技術面(オンチェーン部分)で「グローバルスタンダードな仕様」に準拠しているか?だと考えています。
皆さまが懸念するような「ガラパゴスなビジネス」にならないよう、「海外→日本」だけでなく「日本→海外」のベクトルの話も鋭意仕込んでいます。
更に盛り上がる国内外のデジタルアセット市場に、引き続きご注目いただけると嬉しいです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
