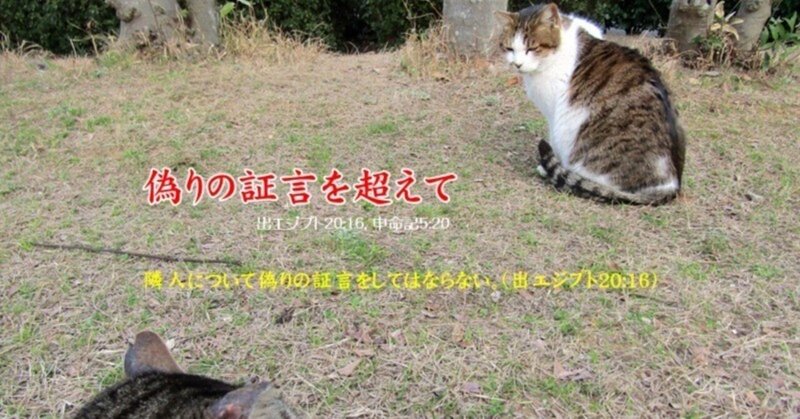
偽りの証言を超えて (出エジプト20:16, 申命記5:20)【十戒⑨】
◆偽証と嘘
隣人について偽りの証言をしてはならない。(出エジプト20:16)
出エジプト記も申命記も、殆ど変わりはありません(原語にわずかな違いはある)。「偽りの証言をしてはならない」とは、やはり裁判でのことでしょう。十戒というと、それぞれが自分にとって切実な問題であり得たものでした。神に対するものはもちろんですが、殺すな、盗むな、というように、一人ひとりの日常の倫理に関わる問題です(日常的に殺すということはないにしても、そうならないように注意しながら生活している)。
しかし、偽証というのは裁判沙汰にならない限り、また法律を職業としていない限り、日常生活ではあまり縁がありません。裁判所に足を踏み入れることのない人も、多数いるだろうと思われます。この戒めは、社会に於いては重要ですが、個人にとってはあまり切実さを感じないかもしれないように見えます。
そこで、考えました。個人に関わるとすれば、これは「嘘をついてはならない」という意味に理解することが可能です。確かに「偽りの証言」を禁じている戒めですが、しばらく「嘘をついてはならない」というところから、近づいてみようかと思います。
早速の反例ですが、私たちには「嘘も方便」という便利な言葉があります。嘘を言うことを弁護するものです。しかし、「嘘も方便」という言葉があること自体が、「嘘はいけないこと」という前提があることを証明している、とも考えられます。
今日は祝日で、「こどもの日」です。このことは来週また触れますので、こどもたちのひとつの側面をご紹介しましょう。推薦入試や、中高一貫校の入試においては、作文が課せられます。その作文で、経験したことがないために書けない話題があったどうするか、教えることがあります。それは、嘘が混じっても構わない、ということです。ありのままに正直に書く必要はなく、嘘を書いても分かりはしないのだから、まとまった筋道でさえあれば、脚色を加えても構わない、と教えるのです。もちろん、あまりにも空想的ですべてが創作、というわけにはゆきませんが、話をまとめることを優先させよ、というわけです。
でも、案外これは、子どもには難しいものです。嘘を書くということに、心のブレーキがかかることが多いようです。「嘘をつけ」と命じられると、「嘘をついてはならない」という道徳が心に引っかかり、正直に書くべきだ、と考えてしまうかのようです。
そこで私はひとつ意見を聞こうと思って、「嘘は絶対についてはならないか、それとも時と場合によっては許されるか」という課題で作文を書かせることにしました。小学生たちは、全員が、場合によっては嘘をついてもよい、という意見を支持しました。きっと、誰もが、嘘をついた経験があるのだな、と推測しました。
◆カントが許せない嘘
今年2024年で生誕300年を迎えた、ドイツの大哲学者イマヌエル・カントは、近代思想と現代社会を構築するために、絶大な影響を与えた人ですが、その論文の中に一つだけ、全く不人気で、殆どの人がその内容を否定し、カントはおかしい、と非難するものがあります。
それはよく、「嘘論文」などとも呼ばれます。「なぜ嘘をついてはならないか」を論ずるものです。カントは道徳を、人間の大切な原理としましたから、「嘘をついてはならない」と主張する、そのこと自体は、何も非難の対象にはなりません。しかし、それを言うために、カントが持ち出した例が、人々の反感を買うのでした。
友人が家に駆け込んでくる。人殺しに追われているという。友人はどこかに隠れる。そこへ、当の人殺しが家に来た。自分に害を及ぼすつもりはないらしい。奴はどこにいる。そう問われた。さて、どう答えるか。
私たちは当然、ここで嘘をつくだろう。だが、カントはここで道徳の原則を以て答える。嘘をついてはならない。嘘をつくことは、社会の信用を破壊する、などの根拠が、道徳哲学者のカントにはあるものの、さすがにこの場での「嘘をついてはならない」には、世間が怒り、また嗤った。
『人間愛から嘘をついてもよいという誤って思い込まれた権利について』というような題名の、短い論文です。晩年、カントは認知症を患っていたらしいのですが、1797年、73歳のカントは、現代とは違い、かなりしんどい思いをしていた可能性があります。が、その主張していることは、自分の中の原則に従っており、筋は通っているように思います。
但し、私たちが「嘘をついてはならない」に同意できないとき、その理由について、顧みる必要があります。私たちはここで、嘘をつかなかったために、友人は殺されてしまう、と決めつけていないでしょうか。それを当然だとしているために、なんて酷いことだ、と義憤を呈するのです。
カントは言っています。友人は、自分の知らない間に、外へ逃げたかもしれない。そのとき、もしも嘘をついていたら、人殺しと鉢合わせになり、それこそ殺されてしまうということになる。もしもそうなったら、嘘をついたことが友人を殺したことに直結し、嘘の責任を負わねばならなくなる。
もちろんこの言い訳にも、世間は納得などしませんが、私たちの前提に匹敵するものがあるような気もします。
蛇足ですが、カントを頭ごなしに嗤う人は、これが思考実験であることを考えず、実際の場面として考えているように思われます。いまでいう「トロッコ問題」へのひとつの答えだ、というふうに捉えるべきだったと思うのです。そのうえ、この非難もまた、非現実的です。実に中途半端な非難であることに、自ら気づいていないような気がしてなりません。もし実際にそういう場面に出くわしたら、私たちは、その殺人鬼から殺される、という危険性を第一に行動するはずですが、呑気に友人の逃げた先だけを議論しているからです。自分の身の安全を守ることを先ず考えるはずです。友だちは逃げました、などと、その相手と対話が成立するようには思えません。思考実験を、現実的ではない、と非難することこそ、現実的ではないわけです。
◆子どもと嘘
さて、子どもは誰も嘘をついた経験があるらしい、と先ほど申しました。そして、必要な嘘はつくことが許される、という考え方をもっている、と分かりました。家族のことにいて作文を書いたとき、親の恥ずかしい姿を吐露する小学生は、物心ついてからは、普通いないでしょう。脚色を含め、何らかの嘘を交えて書くのではないでしょうか。そして教育者は、それでいい、と言います。わざわざ親の恥を公開することはしない、それが子どもの正直な心情である、と。むしろ嘘を書くほうが、心に嘘をついていないことになる、というような解釈です。
ノアが裸で酔い潰れたとき、息子のハムは裸を見て、セムとヤフェトに知らせます。しかし二人は、父の裸を見ないように、後ろ向きに近づいて父の裸を覆いました。ノアは酔いから醒めると、ハムの家系を呪いました。創世記の、そんな話をふと思い起こします。
ただ、嘘をついたことが何か心に引っかかる、ということもあります。幼い頃についた嘘が、生涯忘れられない、ということもあり得るでしょう。特にその嘘で、何かよくないことが起こったときには、心の傷となって遺ります。
また、単に怒られたくないために嘘をつく、というのも、特に小さい子どもの場合にはよくある殊です。怒られる結果を予想し、そうならないための方法を瞬時に考えてのことですから、当人には嘘をついているという感覚がないのかもしれません。困難の回避は、いわば自分の身を守る手段ですから、嘘と真実という道徳的な観点からそうしているのではないように思います。
小学生を相手にしているときも、こうした嘘に出会います。宿題をしていないのに、机の上に置いて忘れた、という言い訳も日常的です。親が捨てた、という話も頻繁に聞きます。全部が嘘と決めつけはしませんが、大人からみれば、しらばっくれているとしか見えないものです。多分に小学生でも、当人は嘘をついている、とは思っていないような気がします。
こうした心のメカニズムを考えるゆとりが、子どもを相手にするときには必要です。教会学校で、子どもの嘘に出会ったときに、「それは神さまが赦しません」とか「罪です」とか、熱心な信者である大人は言いたくなるかもしれませんが、とんでもないことです。まさか、日常的にそう言って、信仰深い大人を演じている、などということはありませんか。
◆聖書の中の嘘
それでは、聖書の物語を繙いてみましょう。聖書の中にも、きっと嘘が犇めいています。とはいっても、それぞれあまり詳しくお聞かせする暇がありません。立て続けにご紹介することをご容赦ください。
99歳のアブラムに主が現れました。このときからアブラハムという名をもらいます。妻のサライも、サラという名をもらいます。そして主は、子孫が与えられること、しかも来年90歳のサラが男の子を産むと告げます。まさか、と驚くアブラハムに、主は、産まれた子に「笑う」という意味をもつ「イサク」という名をつけよ、と畳みかけるのでした。その後、アブラハムの許に謎の三人が現れ、重ねて今度サラに男の子が生まれている、と告げます。そこでサラはひそかに笑いました。無理、と。三人――いえ、主は言います。なぜ笑ったか、と。サラは恐ろしくなって、「笑いませんでした」と言いますが、主は「確かに笑った」と言い切ったのでした。サラが「笑いませんでした」と言ったのは、子どもが叱られないためにとっさに嘘をついたようなものでした。
そのイサクの息子ヤコブも、なかなかの巧みな者でした。狡賢いとでも言いましょうか。双子とはいえ弟の身分で、家督を継ぐ資格がありません。ヤコブを溺愛する母のリベカの指金で、危篤に近い父イサクを騙して、長子の権利をまんまと手に入れます。騙すときに、派手な嘘を演じ続けたのです。
その後ヤコブは、逃亡生活となり、リベカの兄ラバンの許で暮らします。確かにラバンに謀られたのも事実ですが、長く働いて後、ラバンの思惑を超えた知恵を以て、良質の家畜を奪い去ってゆくことになります。旧約聖書は、権謀術数の宝庫です。先週お話しした、テラフィムを盗んだラケルの件でも、ラケルは見事に嘘をついて捜索をごまかしています。
ヤコブの息子ヨセフは、その生意気さの故に、11人の兄たちに恨まれます。そして企みによって死んだものとされ、どこかに売られていなくなってしまいます。ヨセフは、エジプトに連れて行かれ、いろいろあって出世します。王ファラオに次ぐ宰相の地位で、やがて来る飢饉を知り、穀物を保管しておく政策をとり、いざ飢饉となっても平気な状態を作りました。しかしカナンの地で、父ヤコブとヨセフの兄弟たちは飢え死に寸前となります。兄たちは、穀物が豊富だと聞きつけてエジプトを訪ねますが、そこで見えた宰相がヨセフだなどとは、夢にも思いません。ヨセフにだけは、兄たちだと分かります。そこでヨセフは、様々な謀を考え、さかんに嘘をつくのでした。それは、復讐のためではありません。自分と母親が同じ弟ベニヤミンと、父ヤコブとに会いたいがためでした。しかし、最後には感情的にこらえきれなくなって、すべてが嘘だったと打ち明けるのです。
士師記の時代、イスラエルが主の目に悪と映ったため、モアブの王エグロンに仕えなければならなくなりました。イスラエルの民は主に立ち返り、救いを求めました。それで主は、エフドをも用いてイスラエルを助けることにしました。エフドはエグロンに嘘を言い、いい話があると近づいて、王を殺害しました。左利きのエフドは、多くの人と反対側に剣を隠すので、見破れなかったのです。ぶよぶよ肥った王の体に、剣は刺さったままだったそうです。
ダビデの臣下でありブレインであったアヒトフェルのことも思い起こされます。ダビデの息子アブシャロムが謀反を起こしたとき、アヒトフェルもダビデの許を去りました。ダビデが、アヒトフェルの知恵を愚かなものにしてください、と主に祈ったとき、側近のフシャイが目につきました。そこでダビデはフシャイを、敵方にスパイとして送り込みます。フシャイは、ダビデには呆れたと言い、アブシャロムの部下に潜り込みます。そして、ダビデを追い詰める知恵を募られたとき、アヒトフェルの策だとダビデが危ないと判断したフシャイは、別の尤もらしい策をアブシャロムに提言し、それが採用されます。これを悲観して、アヒトフェルは縊死します。つまり、フシャイは、巧みに嘘を語り、ダビデ王を守ったのでした。
新約聖書で目立つ嘘といえば、アナニアと妻のサフィラのことでしょうか。これは詳しく先週お話ししたので、もう詳しくは申し上げますまい。初めて教会が成り立ち、皆が助け合って信徒としての生活をしていたとき、この夫婦は、献金をごまかしたのです。ペトロは後に言います。何も、献金が少ないなどということを問題にしているのではない。土地を売って得たお金を献げたときに、実は土地代の一部分であったにも関わらず、これが全額だと偽ったことがよくないのだ。これにより二人は死という罰を受けることになりました。
◆命懸けの証言
主イエスの身近で嘘が取り沙汰されることはそうそうなかったようですが、イエスが嘘を好んだとは思えません。しかし、イエスにとって、この嘘というテーマは、重大な意味をもつものとなりました。
なによりイエスが、偽証により訴えられたということです。マルコ伝の14章を垣間見ましょう。
55:祭司長たちと最高法院の全員は、死刑にするためイエスにとって不利な証言を求めたが、得られなかった。
56:イエスに対する偽証をした者は多かったが、一致しなかったのである。
57:ついに、数人の者が立ち上がって、イエスに対する偽証をして言った。
58:「この男が、『私は人の手で造ったこの神殿を壊し、三日のうちに、手で造らない別の神殿を建ててみせる』と言うのを、私たちは聞きました。」
59:しかし、この場合も、彼らの証言は一致しなかった。
結局、この偽証そのものがイエスを有罪にすることはできませんでした。しかし、イエスは偽証に囲まれていたのです。これで憤った大祭司の問いかけに対して、イエスが、自らをメシアと名乗るような言い方をしたために、これは死刑だ、と周囲の者たちの感情がヒートアップしていったのでした。
十戒が禁じたのは、元来このような裁判における偽証でした。新約聖書でも、十戒に関係して「偽証」という話題が出てくることが殆どです。「偽証」となると、ただの嘘、あるいは偽りだけではなくて、「証言」という意味が加わってきます。証言する人を「証人」と呼びます。よく知られているように、聖書に使われている言葉においては、「証人」と訳されている語が、同時に「殉教者」を表す語となっていきました。証言をも偽ったときには死罪が待ち受けています。証言するというのは、命懸けの行為であったのです。
私たちが「イエスはキリストである。主イエスは救い主である」と語る、それが伝道となります。いまの時代ではこれを言ったからといって、命が取られるわけではありません。が、それが命懸けであった時代は、遠い土地のことでもなければ、遙か遠い昔の話でもありません。もちろん400年遡れば、拷問を受け、転ぶことを強いられ、従わなければ磔にもされました。が、ほんの数十年前においても、日本はそういう時代空気の中にあったのではないでしょうか。天皇とキリストとどちらが、などと迫られ、拷問から獄死へと至った人も、いたのです。
いまは、「イエスはキリストです」と言えば、「敬虔なクリスチャン」などと褒められることすらあります。その是非はいま話を深めないにしても、果たしてそもそも「イエスは救い主です」と、私たちの誰もが、生活の中で言えているかどうか問われれば、恥ずかしくさえなりはしないでしょうか。
◆隣人に対して
普通なら、この辺りでこのメッセージは終わっていたかもしれません。十戒の第九戒は、偽証を戒めるものでした。そもそも十戒というのは、禁止命令というよりも、「君がこのようなことをするはずがない」と諭すような口調である、とよく言われます。神が、さあ言うことを聞け、と圧力をかけるようなものではないのだというのです。だから、ここでも「偽りの証言をすることなどありえないよね」とでも言われたと思えば、パワハラを受けたような気持ちには決してならなかっただろうと思います。
隣人について偽りの証言をしてはならない。(出エジプト20:16)
ここで、ふと気づくのです。大切なことを忘れていた、と。そう、ただ偽証とか嘘とか、そういうことを議論している場合ではなかったのです。語順からすれば「答えるな。隣人に対し、偽りの証言を」というように、中央に潜んでいるのですが、「隣人に対して」とはっきり書かれています。この戒めは、対象が限定されていたのです。
「殺してはならない」が対象を明記しないでいたとき、同時に神が「殺せ」とさかんに命じている事実に、私たちは悩みました。しかし今回、「偽りの証言をしてはならない」については、「隣人について」という制限がかけられています。
やはりこれは、裁判の場を想定するべきだろうと思います。しかし、必ずしも法廷でのみこれを適用するものだ、という堅いことを言わず、もう少し場を拡げて受け止めてみましょう。隣人、つまり誰か自分と関係をもつ他人に対して、仲間に対して、偽証をするべきではない、ということです。
どんな偽りの証言でしょうか。私たちは何を証言するのでしょうか。新約聖書で「証言」という言葉が多く登場する場面があります。
祭司長たちと最高法院の全員は、死刑にするためイエスにとって不利な証言を求めたが、得られなかった。……しかし、この場合も、彼らの証言は一致しなかった。(マルコ14:55,59)
先ほども挙げました、イエスを訴える裁判の場面です。やはり証言という考え方は、裁判の場面が相応しいのでしょうか。しかし、「証言」ではなく「証人」と検索ワードを換えると、たとえばこういう使われ方に出会います。つい先般、私たちも味わったあの言葉です。
ただ、あなたがたの上に聖霊が降ると、あなたがたは力を受ける。そして、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで、私の証人となる。(使徒1:8)
この使徒言行録には、この意味での「証人」という言葉がたくさん出てきます。使徒たちは、イエス・キリストを伝えるために、様々な困難に出遭いながら、つねにキリストの救いの証人となろうとしています。いえ、その殆どの場合、「証人である」という断言となっています。「証人となりなさい」ではなく、「証人である」と宣言されているのです。イエスの弟子は、すでに、イエスがキリストであることの証人であるのです。
イエスに会った者は、イエスの言葉を語るのです。出会ったそのイエスのことを伝えるのです。イエスに会ったことがない者は、イエスの言葉を語れません。イエスの言葉を取り次ぐこともできません。オウムのように、口まねだけで何の意味も解さず、聖書の言葉や聞きかじった本に書いてあることを「かたる」だけです。日本語では、このようなときの「かたる」を「騙る」と表記します。正に、これこそ「偽証」に違いありません。
◆真実を語る
さあ、それでは私たちは、何をしましょうか。ここからどんな恵みを受けるとよいのでしょうか。それは、お聞きになる一人ひとりに、様々な形で与えられるでしょう。私が決めつけることはできません。ただ、きっかけをもたらすのは、私の役割です。私に与えられた恵みをお伝えします。
偽証をしてはならない。この言葉から、びくびくして、「嘘を言ってはならないのだ」と構えていることは、健全ではないと思うのです。先生に怒られないように、失敗しないように、びくびくしている子どもがいたら、どうしましょう。失敗を恐れないで、勇気を出して踏み出すように、声をかけたくなりませんか。
「隣人について偽りの証言をしてはならない」という言葉を、新たに踏み出す言葉として受け止めてみるのは如何でしょうか。その逆を考えます。「してはならない」ではなく、「しなさい」または「しよう」の方向でそれを言えば、どういうことになるでしょうか。そう、「隣人に、真実を語る」のです。私たちの為すべきことは、「隣人に真実を語る」ことでよいのではないでしょうか。私はそう聞きました。
「真実」は、いま新しい聖書の訳で思い切って使われ始めた箇所の多い語です。それまでは「信仰」と訳されていたところの語が、「真実」と訳し直されたところが多々あるのです。これを説明し始めると、ここからまた20分以上費やしますので、その意義はまたどこかでお話しできようかと思います。少なくともここでは、「真実を語る」という言い方が、「信仰を語る」という言葉に換えてもよいような意味である、と受け止めてくだされば幸いです。
私たちは、あるいは仲間にでもよいのですが、とくにまだキリストとの出会いを経験していない人に、自分の「信仰」を語ることがあります。いえ、積極的に語りなさい、伝えなさい、という指令をうけています。これをキリスト教世界では「証し」といいます。そう、私たちは信仰を語るというとき、証人となるのです。証言するのです。
イエスは確かにキリストである、救い主である、事実私はキリストにこのように救われた、そういう証言をします。ええ、裁判でしたら宣誓があるでしょう。私は嘘偽りをここでは語りません、と誓います。自分は確かにキリストに出会った。キリストに救われた。誰がなんと言おうと、この事実を私は否定することなどできません。命を懸けてでも証言します。イエスは私の救い主です。――こうイエスを「証し」します。
このように自分の信仰を言い表すこと、それが「真実を語ること」です。
このとき、聖書の神とあなたとの関係が問われています。つながりです。出会った確かな経験です。そのイエス・キリストのこと、十字架の救い、復活の命、それを語るのです。隣人に対して偽証してはなら「ない」という否定形ばかり見つめている必要はありません。肯定的な、積極的な、十戒のへの従い方がここにあります。
裁判など、日常生活ではあまり縁がないかもしれない。最初にそのように心配しました。でも、それは無用でした。この第九の戒めは、否定形から肯定形へと変わり、「隣人に対して真実を語る」という、キリスト者の強い生き方に変わりました。これは、日曜日だけではなく、キリスト者の日常でいつも、そしてこれから生涯ずっと、必要になり、常に伴う戒めとなるものだったのです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
