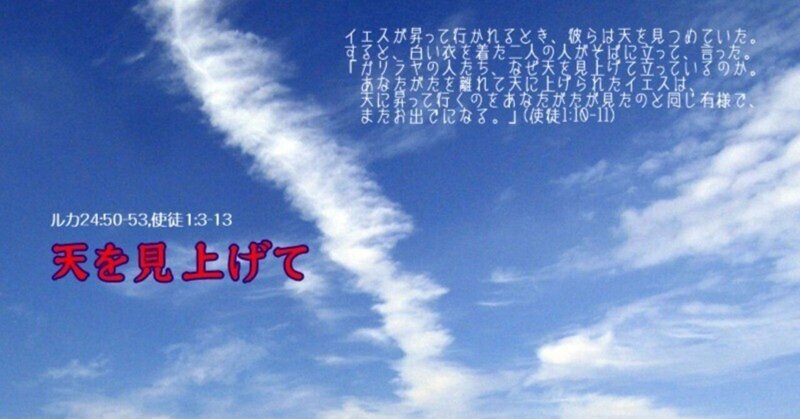
天を見上げて (ルカ24:50-53,使徒1:3-13)
◆映画の真実
特に映画ファンだというわけではありませんが、話題のものや、好みのものは観たいなと思います。いまはあまり感じませんが、昔は、アクション映画を観た後、出て行く客が、すっかりアクションスターになったような気持ちでポーズをとっている、という風景もありました。そうでなくても、映画の主人公のような、清々しい気持ちで映画館を出て行く、というのは、よくあることでした。
映画を観て、勇気を与えられたこともおありでしょう。よし、自分にも何かできる、という前向きな気持ちになる、という経験はないでしょうか。尤も、救いようのない暗い映画の終わり方だったら、うーん、と心を静めて考えることになるのかもしれませんが。
しかし、映画に共感を覚えない、というケースもあろうかと思います。なんだかストーリーに入れず、傍観者になってしまい、この映画はああだこうだ、と批判する心ばかりがある、という人です。それが職業である映画評論家ならば、そういうものなのかもしれませんが、ただの映画愛好家が、何かと映画の批評ばかり考えて観ている、というのは、気の毒な気がします。
すぐさま二人は立って、エルサレムに戻ってみると、十一人とその仲間が集まって、主は本当に復活して、シモンに現れたと言っていた。(ルカ24:33-34)
十字架から復活という過程は、この春の時季であったことが分かっています。それで私たちも、しばらくイエスの十字架を、そして復活を追いかけてきました。いまお読みしたのは、先週お開きした箇所です。エマオへの道でイエスに出会った二人がエルサレムに駆けつけると、弟子たちの間でもすでに、復活のイエスが、シモン・ペトロに現れた、という話題でもちきりでした。
「主は本当に復活」した、と互いに話しています。「本当に復活した」という言葉を、私たちはいま、どのように読むでしょうか。あなたは、どう聴きますか。実はこれが、信仰生活というものをつくる、決定的なポイントとなります。
映画の場合、それは「本当の出来事」でないことを、私たちは了解しています。一部、ドキュメンタリー・タイプの映画がないわけではないのですが、殆どの映画は、作り事です。いわば、映画は大抵は、「架空のもの」であるわけです。そのとき、その映画に感動した私たちは、映画を「作り事」だと言ってしまうでしょうか。いま正にその映画が、自分に勇気を与えてくれた、そのときに、あれは作り物だ、と言うでしょうか。私は言わないだろうと思います。
もちろん、映画に感動しなかった人にとっては、それはただの作り事であり、自分とは無関係な物語に過ぎません。自分とは別世界の「おはなし」であるに留まります。
「主は本当に復活した」という弟子たちの言葉に対しても、単に教義だから口にし、それを信じると言わなければ、楽しい教会に集う仲間に入れてもらえないから賛同するのだ、というだけであれば、結局はただの「作り事」とそれを呼ぶ立場にいることに、なりはしないかと思います。
教会に集うのは、元来、このイエスの復活が確かに現実となった人であったはずではないでしょうか。この教義を信じ込ませる、圧力や脅しがあるわけではありません。信じないと地獄に行く、という恐怖を与えるような、洗脳じみたことを言う者がたまにいますが、それはいわゆるカルト宗教に特有なあり方に過ぎません。
キリストの弟子とは、「主は本当に復活した」と、心から言える人のことを言います。それは、映画を「作り事」だとは思えない人の心理と、少しだけ、似ているような気がします。
◆イエス・キリストはいまどこに
「主は本当に復活した」と言い切るとき、では、どんなことが私の上に起こるのでしょうか。さすがに弟子たちと同じように、イエスを見たからそう言う、という情況とは違うでしょう。いまイエス・キリストを、私たちは基本的に、目で見ていません。この私たちの情況で、「主は本当に復活した」と信じることには、どのような意味があるのでしょうか。今日、復活のイエスと弟子たちとの別れの場面から、受け止めたいと願っています。
教会にお越しの皆さまがすべて、とは申しませんが、信仰をもって教会に集う人々は、基本的に、聖書のこの「主は本当に復活した」という記事を、信じていることになります。それで、復活したのだ、と信じたということを、そのままに受け容れることにしましょう。
それでは、その後に現れる、このような疑問については、どうしましょうか。それは、「いまイエス・キリストはどこにいるのか」という問題です。
主はいつも私たちと共にいるのだ、という信仰で答えることもできるでしょう。では、確かに「いま」私たちと共にいるわけです。そうですか。本当にそうだ、と迷うことなしに肯く信仰があれば、それでよいでしょう。でも、少し揺らいだ人はいませんか。そう言えばどうなんだ、と疑問に引っかかった人もいるのではありませんか。
人間は、人間の目の高さでしか、ものが見えません。想像の翼を羽ばたかせても、高くは飛べません。「いま」という言葉のもつ意味は、人間がそれと信じる意味でしかない――そんな保証は、どこにもありません。「いまイエス・キリストはどこにいるのか」の「いま」は、人間にとっての「いま」であることは間違いないのですが、本当にその意味での「いま」しかありえないのか、疑問を呈することができるのではないでしょうか。
神にとっての「いま」が、私たち人間が呼ぶ「いま」と同じかどうか、問わなければなりません。神にとっては一日は千日にもまさる(詩編84:11)のであり、千年といえども夜の一時にすぎない(詩編90:4)のです。そして、イエス・キリストはきのうも今日も変わることがない(ヘブライ13:8)のでした。
「いまイエス・キリストはどこにいるのか」という問いは、人間にとっては興味津々な問いであるかもしれませんが、神からすれば、その「いま」という人間の思う言葉が、無意味であるのかもしれません。もしそうだとすると、「いまどこに」という、人間が問うような意味は有っていないのではないでしょうか。
そうであっても、人間にはやはりまだ腑に落ちません。私たちは「いま」キリストが見えていないのです。共にいると信じることは可能であるにしても、キリストを見てはいません。ルカは、その仕組みを、ここでうまく説明してくれたのだと思います。
◆イエスの昇天
ルカは復活後のイエスを描く24章の、いよいよ福音書の最後を締め括ります。これは、マルコはもちろんのこと、マタイも描いていない記事です。その後、ヨハネもまた、これに類する記事を描いてはいません。
復活のイエスはその後どうしたのか。自分たちには見えないではないか。ルカのそばにいた信徒たち、イエスの出来事から半世紀ほどを経た弟子たちの仲間のうちの幾人かは、そうした疑問を、きっともっていたことでしょう。しかし、誰もそれを説明ができませんでした。あるいは、何か説明ができていたかもしれません。しかし、それをルカ以前に記録した人はいませんでした。いまここに、ルカが画期的な記録を残したことになります。
50:それからイエスは、彼らをベタニアまで連れて行き、手を上げて祝福された。
51:そして、祝福しながら彼らを離れ、天に上げられた。
52:彼らはイエスを伏し拝んだ後、大喜びでエルサレムに戻り、
53:絶えず神殿の境内にいて、神をほめたたえていた。
復活したイエスは、弟子たちに、確かな復活の教えを告げました。弟子たちの心の目を開いたのです。イエスは、弟子たちをベタニアに連れてきました。手を上げて弟子たちを祝福すると、天に上げられます。弟子たちはイエスを伏し拝み、喜んでエルサレムに戻ったといいます。それから神殿の境内に幾度も出入りし、神を褒め称える生活をしたのだ、とルカは記しました。
これが、いわゆるイエスの「昇天」です。このことは、ルカ伝の続編であると見なされる「使徒言行録」の最初の章とオーバーラップしています。そちらの内容は、少し後で詳しく読んでみることにします。そして、使徒言行録によれば、これは復活から40日目であったことから、キリスト教会では、その日を「昇天日」として、特別に考えることとしています。但し、さほど大きなお祭りや集会をすることはありません。
ただ、ルカ特有の視点は、ほかにも見出されます。エルサレムに戻るというのは、マルコにもマタイにも描かれませんでした。マルコではさしあたり示唆されるだけでしたが、マタイでは、はっきりと、弟子たちはガリラヤに戻って山に登り、イエスと再会しています。イエスは、世の終わりまで共にいる、と意味深いことを告げますが、昇天の様子は描いていません。そしてその言葉で福音書を閉じます。福音書が人々に告げるメッセージとして、イエスが最後に宣言したように見受けられます。
今年の春は、十字架と復活の記事を、ルカ伝に従って読みました。従って、私たちも、エルサレムに戻ることにします。ガリラヤではなく、エルサレムに戻ります。
◆何故ベタニアなのか
ところで、なにげなく読み飛ばしてしまいそうで、そしてそこに引っかかる人はあまりいないのかもしれませんけれども、私の心にブレーキをかけた地名があります。もう一度、ルカ伝の最後のところに目を向けます。
50:それからイエスは、彼らをベタニアまで連れて行き、手を上げて祝福された。
ベタニア。福音書の中でも幾度か耳にしたことのある地名です。でも、どうしてベタニアなのでしょう。イエスの昇天はベタニアに於いてでした。ベタニアとはどういう場所であったのか、立ち止まって振り返ろうと思います。
イエスが最期を迎えるエルサレムに入ろうとしたとき、入城のために子ロバを探しました。それがベトファゲあるいはベタニアであったように読めます。それらの村は、2km程度しか離れていないというので、同一視されたのかもしれません。この村については、旧約聖書にも特に言及がないようなので、これは新約聖書のメッセージの内で捉えるしかありません。
まず、ここでは共観福音書のそれぞれを横断しながら触れていきますが、イエスはどうやらエルサレム滞在というときに、ベタニアに宿泊していたようです。重い皮膚病、ないし規定の病のシモンという人の家にいたように読めます。
ベタニアは、エルサレムという神的な営みを行うイエスと弟子たちの、生活の基盤でした。イエスがエルサレムで教え、また十字架の使命を全うすることへ向かうための、生活の基盤であったのです。
しかし、これがヨハネ伝になると、だいぶ意味合いが変わってきます。同じエルサレムでの受難に近い出来事としては、ヨハネ伝でとりわけ有名な、マルタとマリアの姉妹が関係してきます。この姉妹は、ルカ伝でも10章で登場しますが、ヨハネ伝11章での出来事がなによりも印象的です。
ベタニアは、マリアとマルタの村である、としています。また、兄弟ラザロが共にいて、ラザロの復活という大きな出来事が、イエスを死に追いやるひとつの土台となりました。敵の妬みがクライマックスになってゆくからです。ラザロの復活については、いま細かく申し上げる暇はありません。人間が蘇ることと、イエスの復活とは同じではありませんが、イエスの蘇りは、再びイエスが来ることへとつながるかもしれません。
それは、私たちにとり「いま」イエスの姿は見えませんが、やがてイエスが現れて、いつかお会いできることへと、目を向けさせることにもなろうかと思います。
もうひとつ、ベタニアを登場させたのは、やはりヨハネ伝です。ルカがそれを知っていたのかどうか、それをいまは問わないこととします。ヨハネ伝の初めの、洗礼者ヨハネの登場の場面です。洗礼者ヨハネには、イスラエルを救うメシアではないか、という目が注がれていました。権力者たちは、あなたはメシアなのか、と問い尋ねに来ます。ヨハネはそうではないと答え、やがて偉大な方が来られることを宣言します。これが、ベタニアでの出来事だった、と記者ははっきり書いています。
ベタニアは、イエスこそメシアである、と証言した洗礼者ヨハネの出来事の場所だったのです。当時の教会にとり、ベタニアは、何か特別な意味のある場所だったのではないか、と推測可能であることにしておきます。
このように、イエスの体がこの世界から見えなくなる「昇天」の出来事は、イエスの十字架の指令を準備し、イエスがメシアであることを証言し、そしてやがて再びイエスが来ることを象徴するかのような、幾つかの出来事が重なる場所として、私たちにベタニアをそれに相応しい場所として示すものであるように思われます。ヨハネ伝を交えて読むことには、少し心苦しいものがありますが。
◆使徒言行録から
福音書は、イエスの救いの意義が伝えられることが中心でした。その続編としての使徒言行録では、弟子たちの働きが中心となります。そこで、その冒頭の部分では、改めてイエスから弟子たちへのバトンタッチの様子が説明されます。そこには、イエスが最後に弟子たちに言い残したことが、福音書よりも詳しく書かれていました。ここから、使徒言行録に沿って、様子を見ることにします。
3:イエスは苦難を受けた後、ご自分が生きていることを、数多くの証拠をもって使徒たちに示し、四十日にわたって彼らに現れ、神の国について話された。
4:そして、食事を共にしているとき、彼らにこう命じられた。「エルサレムを離れず、私から聞いた、父の約束されたものを待ちなさい。
5:ヨハネは水で洗礼を授けたが、あなたがたは間もなく聖霊によって洗礼を受けるからである。」
ここまでが、イエスの告げた内容です。「昇天」に直接関係のない、復活のイエスが伝えたかったことです。弟子たちの問いかけによらない、イエス自らが告げたくて告げたこと、と言ってもよいでしょう。四十日という要素が見られます。神の国のことを話した、という内容にも触れられています。それから、ガリラヤに戻れ、ではなく、エルサレムを離れるな、との指示があります。「父の約束されたもの」は、後でそれが「聖霊」であることが分かります。次の節でも、その「聖霊」の登場が明らかにされています。水の洗礼ではなく、聖霊による洗礼を君たちは受けるのだ、と言っています。
この次に、弟子たちからの問いかけと、イエスの「昇天」が描かれます。
6:さて、使徒たちは集まっていたとき、「主よ、イスラエルのために国を建て直してくださるのは、この時ですか」と尋ねた。
7:イエスは言われた。「父がご自分の権威をもってお定めになった時や時期は、あなたがたの知るところではない。
8:ただ、あなたがたの上に聖霊が降ると、あなたがたは力を受ける。そして、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで、私の証人となる。」
9:こう話し終わると、イエスは彼らが見ている前で天に上げられ、雲に覆われて見えなくなった。
弟子たちは、まだよく分かっていないようです。イスラエルの建国という、新たな王の期待がよく表れています。それは正にいまからなのか、とわくわくした問い方をしているように見えます。まだこのときには、やはり理解ができていなかったのです。しかし、これはルカの教会の中にもあった声なのかもしれません。だから、ルカは「聖霊」を予告します。
約束の「聖霊」が来るまで、エルサレムで待て。そのとき、聖霊が降る。そして、力を受ける。それは、イエスの証人となるということだ。そのようなことを、イエスは告げます。そうして、イエスは天へ上げられて、その姿が雲に覆われて見えなくなりました。
◆見えない神
10:イエスが昇って行かれるとき、彼らは天を見つめていた。すると、白い衣を着た二人の人がそばに立って、
11:言った。「ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのか。あなたがたを離れて天に上げられたイエスは、天に昇って行くのをあなたがたが見たのと同じ有様で、またお出でになる。」
さあ、ここでイエスの姿が、見えなくなりました。現代の私たちと同じく、神の姿が「見えない」時代に入ったのです。その昔、「神の姿を見た者は死ぬ」とイスラエルでは怖れられていました。しかし、神は何らかの形で現れたことが、旧約聖書にも書かれています。そして新約聖書では、イエスという形で、現れました。そのイエスが、このとき見えなくなったのです。それ以来、いまなお、イエスの肉体としての姿を、人間は見ていません。この瞬間に、いまと同じ特徴をもつ時代となったのです。
白い衣を着た二人は、ルカではイエスが復活した朝、空になった墓の中で、女たちの前に現れた二人と見てよいでしょう。二人は、神の代弁人です。新たな時代に入り、神が弟子たちにまずかけた言葉が、ここに記されています。それは「なぜ天を見上げて立っているのか」という言葉です。
これはただの疑問文ではありません。反語のようなものです。「天を見上げて突っ立っていてはいけない」と言っているに違いありません。あるいは「天を見上げてぼうっとしている場合ではない」という意味かもしれません。イエスはまた来る。いま昇天したのと同じように、ただこの次は天から降りるという逆の動きで、イエスが来るのだ、と言うのです。
ベタニアに降りてくるのかどうか、それはここからは確定できません。しかしベタニアは、この出来事を象徴する舞台として相応しい場でした。それは、再びイエスが目に見える姿を現す、ということでもありました。
見えなかった神が、いつかまた見える時が来る、そのような希望が、このメッセージを受けた者から、始まるのです。私たちがいま、それを始めようとしています。このメッセージを受けたからです。
それは、このときの弟子たちに与えられた恵みの中に、探すことができるのではないか。最後に、その点に足を踏み入れてみましょう。
◆真実の映画
イエスが天に上げられた瞬間、ルカの筆は、スポットライトを弟子たちに当てます。
12:それから、使徒たちは、「オリーブ畑」と呼ばれる山からエルサレムに戻って来た。この山はエルサレムに近く、安息日にも歩くことが許される距離の所にある。
13:彼らは都に入ると、泊まっていた家の上の階に上がった。それは、ペトロ、ヨハネ、ヤコブ、アンデレ、フィリポ、トマス、バルトロマイ、マタイ、アルファイの子ヤコブ、熱心党のシモン、ヤコブの子のユダであった。
この使徒言行録の描写は、次のようなルカ伝の最後と重なるものでした。
52:彼らはイエスを伏し拝んだ後、大喜びでエルサレムに戻り、
53:絶えず神殿の境内にいて、神をほめたたえていた。
「なぜ天を見上げて立っているのが」との声に促されて、弟子たちは、自分たちのすることへ、気持ちを向けさせられます。自分たちはここから何をしなければならないだろうか。イエスからの言葉を信じて、待つのだ。ただ待つのではない。約束の聖霊を受けたら、力強くイエスのことを伝えるのだ。イエスはこのようなお方だった、と証しするのだ。それが、弟子たちに与えられたミッションでした。
待つ場所は、ベタニアではありませんでした。ベタニアは、イエスの動きを象徴するものと私たちは捉えましたが、人間である弟子たちの歩みは、一旦エルサレムに戻ることでした。安息日に歩くことが許される距離というのは、1km弱だそうです。近いものです。泊まっていた家というのはよく分かりませんが、そこをまずは拠点として、この後十日間ほど、エルサレム神殿へ毎日出向きます。
ルカにとり、エルサレムは特別な場所でした。イエスはひたすら、エルサレムの方に顔を向け、ガリラヤから旅してきました。心は常にエルサレムに結びついていました。このルカ伝では、復活と昇天の後、弟子たちはガリラヤのスタートラインに戻るのではなくて、エルサレムで聖霊を待ちました。そして、使徒言行録に於いて、弟子たちは聖霊を受け、そのエルサレムから、全世界へ出て行くことになるのでした。それは、キリスト教の伝播する歩みを示すものとなりました。
使徒言行録では、この場面の最後を、弟子たちの名前で締め括っています。ユダを除く11人の名が連ねられています。しかし、12というひとつの完全性を表す数には1人足りません。使徒言行録では、この穴埋めをする様子が一応描かれています。けれども、そのマティアという人物は、なんだか仕方なしに登場したような印象すら与えます。何をした、とも書かれていません。
私は愉しく想像しています。ルカはここで11人の名を記しましたが、もう1人の名前を、きっと書きたかったのだろう、と。さすがにそれはルカはしませんでしたが、私たち読む方は、少しばかりに想像の翼を羽ばたかせて、もう1人の名前を、心の中で書き加えてもよいのではないか、と思うのです。
誰の名前でしょう。自分です。私の名を。あなたにとっては、あなたの名を。この映画に確かに登場するキャストの一人です。自分もこれから登場する、真実の映画が上映されるときには、エンドロールに、自分の名が、きっとあるはずです。そう思いませんか。
ただ、まだその映画はラストシーンが上映されていません。私たちの「いま」という基準においては、その映画はまだ完結していないのです。「いま」、その映画はまだ上映中です。ラストシーンは間もなくかなぁ、と期待しながら、このスペクタクルは続行中なのです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
